今日は,裁判所外での進行協議期日に立ち会いました。ですので,進行協議期日について少し。短答対策ですね。まず,条文から。進行協議期日は,法ではなく,規則です。
=引用=
(進行協議期日)
第 九十五条 裁判所は、口頭弁論の期日外において、その審理を充実させることを目的として、当事者双方が立ち会うことができる進行協議期日を指定することができる。この期日においては、裁判所及び当事者は、口頭弁論における証拠調べと争点との関係の確認その他訴訟の進行に関し必要な事項についての協議を行うものとする。
2 訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾は、進行協議期日においてもすることができる。
3 法第二百六十一条(訴えの取下げ)第四項及び第五項の規定は、前項の訴えの取下げについて準用する。
(音声の送受信による通話の方法による進行協議期日)
第 九十六条 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、進行協議期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
2 進行協議期日に出頭しないで前項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
3 進行協議期日においては、前項の当事者は、前条(進行協議期日)第二項の規定にかかわらず、訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾をすることができない。
4 第八十八条(弁論準備手続調書等)第二項の規定は、第一項の手続を行う場合について準用する。
(裁判所外における進行協議期日)
第 九十七条 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において進行協議期日における手続を行うことができる。
(受命裁判官による進行協議期日)
第 九十八条 裁判所は、受命裁判官に進行協議期日における手続を行わせることができる。
=引用,終わり=
読んで字のごとくなのですが,これは訴訟の進行を協議するためのものです。「期日外」の手続です。ですから,証拠の提出などは予定されておらず,できないと考えられています。一般的には,ラウンドテーブルの法廷で,裁判官は法服を着ずに,比較的ラフな形で行われます。
で,次なるポイントは,「裁判所外」においてもできるということです(97)。例えば,当事者に出頭願うことは不適当な場合に裁判所が出向いたり,あるいは,交通事故の現場,境界確定訴訟において境界が問題になっている地で行うこともできます。実際には,後二者の使われ方がされるようです。例えば,裁判官が事故現場や境界の現場をを見たい場合,どういった方法があるでしょうか?ぱっと思いつくのは,検証(民訴法232~)なのでしょうけれど,これは「重い」手続です。検証調書を作ったりしなくていけない。そこで,お手軽に現場を確認して心証形成の一助とするなら,裁判所外での進行協議期日として,現場を見ながら進行について協議するわけです。
では,そういうふうにして進行について協議していたら,あれよあれよという間に当事者間の話がまとまってしまった。その場で和解できるでしょうか?結論からいうと,「できない」とされています。95Ⅱが,「訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾は、進行協議期日においてもすることができる。」としていて,ここに和解は含まれていないのですね。まぁ,あくまでも期日外の手続ですから,和解まではできないのでしょう。裁判上の和解をしたいなら,別途,そのための期日を設ける必要があります。
ポイントになるのは,だいたいこんなところでしょうか。
水曜から模試を受けている方は,明日は中休みですね。かなり疲弊していると思うので,午前中はちょっとゆっくりするのがいいと思います。
<参考文献>
「民事訴訟法講義案」(司法協会)
=引用=
(進行協議期日)
第 九十五条 裁判所は、口頭弁論の期日外において、その審理を充実させることを目的として、当事者双方が立ち会うことができる進行協議期日を指定することができる。この期日においては、裁判所及び当事者は、口頭弁論における証拠調べと争点との関係の確認その他訴訟の進行に関し必要な事項についての協議を行うものとする。
2 訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾は、進行協議期日においてもすることができる。
3 法第二百六十一条(訴えの取下げ)第四項及び第五項の規定は、前項の訴えの取下げについて準用する。
(音声の送受信による通話の方法による進行協議期日)
第 九十六条 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、進行協議期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
2 進行協議期日に出頭しないで前項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
3 進行協議期日においては、前項の当事者は、前条(進行協議期日)第二項の規定にかかわらず、訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾をすることができない。
4 第八十八条(弁論準備手続調書等)第二項の規定は、第一項の手続を行う場合について準用する。
(裁判所外における進行協議期日)
第 九十七条 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において進行協議期日における手続を行うことができる。
(受命裁判官による進行協議期日)
第 九十八条 裁判所は、受命裁判官に進行協議期日における手続を行わせることができる。
=引用,終わり=
読んで字のごとくなのですが,これは訴訟の進行を協議するためのものです。「期日外」の手続です。ですから,証拠の提出などは予定されておらず,できないと考えられています。一般的には,ラウンドテーブルの法廷で,裁判官は法服を着ずに,比較的ラフな形で行われます。
で,次なるポイントは,「裁判所外」においてもできるということです(97)。例えば,当事者に出頭願うことは不適当な場合に裁判所が出向いたり,あるいは,交通事故の現場,境界確定訴訟において境界が問題になっている地で行うこともできます。実際には,後二者の使われ方がされるようです。例えば,裁判官が事故現場や境界の現場をを見たい場合,どういった方法があるでしょうか?ぱっと思いつくのは,検証(民訴法232~)なのでしょうけれど,これは「重い」手続です。検証調書を作ったりしなくていけない。そこで,お手軽に現場を確認して心証形成の一助とするなら,裁判所外での進行協議期日として,現場を見ながら進行について協議するわけです。
では,そういうふうにして進行について協議していたら,あれよあれよという間に当事者間の話がまとまってしまった。その場で和解できるでしょうか?結論からいうと,「できない」とされています。95Ⅱが,「訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾は、進行協議期日においてもすることができる。」としていて,ここに和解は含まれていないのですね。まぁ,あくまでも期日外の手続ですから,和解まではできないのでしょう。裁判上の和解をしたいなら,別途,そのための期日を設ける必要があります。
ポイントになるのは,だいたいこんなところでしょうか。
水曜から模試を受けている方は,明日は中休みですね。かなり疲弊していると思うので,午前中はちょっとゆっくりするのがいいと思います。
<参考文献>
「民事訴訟法講義案」(司法協会)











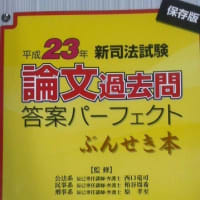
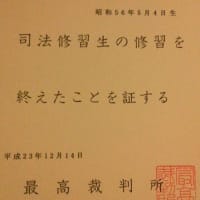
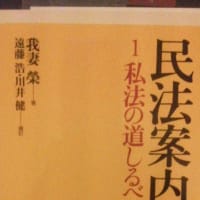






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます