今日の午後は法務局にて修習。登記・供託実務などについて講義があり,その後,実務の現場をちらっと拝見。その後,訟務検事との座談会。LS生や受験生の皆さんでもご存知ない方も多いいのではないかと思いますが,訟務検事とは,国が当事者になる事件の代理人をする人のことを言います。誰が訟務検事になるのかと言えば,裁判官や検察官です。法務省に出向というかたちで,訟務検事として執務をするそうです。いきなり訟務検事になる方はいないでしょうが,初任明け(裁判官や検事になって最初の赴任地で2~3年執務した後)で訟務検事になる方は結構いるようです。今日,座談会に出席されていた訟務検事の方もそうでした。もともと裁判官だった人が,当事者席に座るのは何とも違和感があるのだとか。訟務検事になると,かなりの高確率でいわゆる大規模著名事件に携わることができます。国が被告になった事件にどんなものがあったかを思い起こしてみればわかると思います。百選掲載判例も,結構な数がそうですよね。
さて,表題の話を。去年や今年の短答の出題を見るに,このあたりを押さえておく必要があるように思います。でも,意外と盲点なんじゃないかと。試しに,次の肢を考えてみてください。
「不法行為における因果関係の立証は,一点の疑義も許されない自然科学的な証明ではなく,特定の事実が特定の結果を発生させた相当の蓋然性を証明することであり,その判定は通常人が疑いをさしはさまない程度に真実の確信を持ちうるものであることを必要とし,かつ,それで足りる」
…こういうふうに書くと,場合によっては正しく見えてしまうかもしれませんが,いずれも×の判定になるかと。ちょっと整理します。
ベースにしたのは,ルンバール事件(最判S50.10.24)です。結果発生が,(もともと原告が患っていた)化膿性髄膜炎によるものか,あるいは,医師である被告が施したルンバール施術のショックによるものかが争われたものです。「一点の疑義許されない自然科学的証明ではなく」という部分は結構有名なのですが,問題はその後。「相当の蓋然性」ではなく,「高度の蓋然性」です。「相当の蓋然性」ではやはり不十分であることは,判例が明確に言っています(最判H12.7.18)。そのレベルまでは証明しなくてはいけない。法律の勉強を始めて間もない方は,このあたりの独特の言い回しにも注意して勉強を進められるとよいでしょう。強弱の程度としては,「高度の蓋然性」>「相当の蓋然性」です。この言い回しは,泉佐野をはじめとする著名な憲法判例にも登場します。なお,「蓋然性」という言葉は日常ではあまり使われない言葉でわかりにくい表現なのですが,これは,「可能性(ありうる)」と「必然性(必ずそうなる)」の中間くらいの概念だ,という押え方をしておけばよいでしょう。相当・高度,必然性・蓋然性・可能性,こういったあたりの言葉を使いこなせるようになると,教科書や判例を読んで行く際にも理解が進むし,締まりのいい論文が書けるようにもなるので重要です。
さて,民事の証明度に対して,刑事で要求されるそれは,「自然科学者の用いるような実験に基づくいわゆる論理的証明ではなくして,いわゆる歴史的証明である。論理的証明は『真実』そのものを目標とするのに対し,歴史的証明は『真実の高度な蓋然性』をもって満足する。言い換えれば,通常人なら誰でも疑いをさしはさまない程度に真実らしいとの確信を得ること」(最判S23.8.5)とされます。ちょっと古い判例ですが。学説上は,「合理的疑いをを超える確証」なんて表現されたりもしますね。そうすると,民事よりははやり厳格な証明度が必要だということになるでしょうか。モノの本には,「刑事は90%,民事は80%の照明度が必要」とするものもあります(田中和夫「事実上の推定について」(裁判官特別研究業績19)13頁以下)。
…と,言葉で説明するとこんなところなのですが,これはなかなか言葉で説明するに適しない点なんですよね。ですから,この先は修習に来て勉強してください。ただ,そのためにはまずは司法試験を突破するために「言葉で」理解しておかなくてはいけないのですよね。おかしな論法ですが(笑)
<参考文献>
「民事訴訟における事実認定」(法曹会)5頁以下
さて,表題の話を。去年や今年の短答の出題を見るに,このあたりを押さえておく必要があるように思います。でも,意外と盲点なんじゃないかと。試しに,次の肢を考えてみてください。
「不法行為における因果関係の立証は,一点の疑義も許されない自然科学的な証明ではなく,特定の事実が特定の結果を発生させた相当の蓋然性を証明することであり,その判定は通常人が疑いをさしはさまない程度に真実の確信を持ちうるものであることを必要とし,かつ,それで足りる」
…こういうふうに書くと,場合によっては正しく見えてしまうかもしれませんが,いずれも×の判定になるかと。ちょっと整理します。
ベースにしたのは,ルンバール事件(最判S50.10.24)です。結果発生が,(もともと原告が患っていた)化膿性髄膜炎によるものか,あるいは,医師である被告が施したルンバール施術のショックによるものかが争われたものです。「一点の疑義許されない自然科学的証明ではなく」という部分は結構有名なのですが,問題はその後。「相当の蓋然性」ではなく,「高度の蓋然性」です。「相当の蓋然性」ではやはり不十分であることは,判例が明確に言っています(最判H12.7.18)。そのレベルまでは証明しなくてはいけない。法律の勉強を始めて間もない方は,このあたりの独特の言い回しにも注意して勉強を進められるとよいでしょう。強弱の程度としては,「高度の蓋然性」>「相当の蓋然性」です。この言い回しは,泉佐野をはじめとする著名な憲法判例にも登場します。なお,「蓋然性」という言葉は日常ではあまり使われない言葉でわかりにくい表現なのですが,これは,「可能性(ありうる)」と「必然性(必ずそうなる)」の中間くらいの概念だ,という押え方をしておけばよいでしょう。相当・高度,必然性・蓋然性・可能性,こういったあたりの言葉を使いこなせるようになると,教科書や判例を読んで行く際にも理解が進むし,締まりのいい論文が書けるようにもなるので重要です。
さて,民事の証明度に対して,刑事で要求されるそれは,「自然科学者の用いるような実験に基づくいわゆる論理的証明ではなくして,いわゆる歴史的証明である。論理的証明は『真実』そのものを目標とするのに対し,歴史的証明は『真実の高度な蓋然性』をもって満足する。言い換えれば,通常人なら誰でも疑いをさしはさまない程度に真実らしいとの確信を得ること」(最判S23.8.5)とされます。ちょっと古い判例ですが。学説上は,「合理的疑いをを超える確証」なんて表現されたりもしますね。そうすると,民事よりははやり厳格な証明度が必要だということになるでしょうか。モノの本には,「刑事は90%,民事は80%の照明度が必要」とするものもあります(田中和夫「事実上の推定について」(裁判官特別研究業績19)13頁以下)。
…と,言葉で説明するとこんなところなのですが,これはなかなか言葉で説明するに適しない点なんですよね。ですから,この先は修習に来て勉強してください。ただ,そのためにはまずは司法試験を突破するために「言葉で」理解しておかなくてはいけないのですよね。おかしな論法ですが(笑)
<参考文献>
「民事訴訟における事実認定」(法曹会)5頁以下











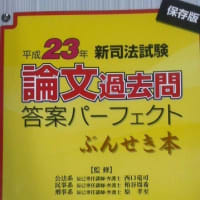

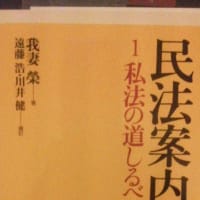






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます