今年は、2月に始まったロシアのウクライナ侵攻による戦争の一年であった。テレビの報道で爆撃で破壊されたウクライナ各都市のありさまを眼にすると誰しも無惨な気持ちになることだろう。建物だけでなく、多くの人々が死んだり負傷した。日本では、自然災害による死者や負傷者は多いが、戦争によるものは、第二次世界大戦以降、経験がない。昭和30年代、私がまだ子供のころ、大阪の天王寺公園を通ると、戦争で手足をなくした兵隊が何人かじっと立っていた。元来備わっていたはずの手足がもぎとられた姿に、子供心に何ともいたましい気分になったものだ。
ところで、話は変わるが、現在では動物を飼うときには、動物を適正に扱い、虐待しないこと、つまり動物愛護が義務付けられている。動物の命にも尊厳を払うということだ。動物保護法は1911年にイギリスで制定されたのが最初である。その後、西欧各国や北米にも広まっていった。これを聞くと「流石にキリスト教徒は、人間だけではなく、動物にまで愛情を注いでいる」と感心される方もいるだろう。しかし、現実を見ると、キリスト教徒は日本人には想像ができないほど、おぞましい動物虐待をしていた。
かつてローマでは、コロッセウムでは剣闘士同士だけでなく、人間と野獣が死ぬまで戦わされていた。当時のローマはまだキリスト教国では無かったので、野蛮であった、と言い訳はできる。しかし、17世紀のロンドンでは国王主催で行われた「牛いじめ」にはそういう言い訳は通用しない。
ミッチェルの『ロンドン庶民生活史』(みすず書房)では近世のロンドンの庶民生活が活写されているが、その中の第6章・第3節に「牛いじめと熊いじめ」という一節がある。それは、動物同士の残虐な戦いで、大きな牛や大きな熊に猛犬を襲いかからせるのであった。本文を一部抜粋する。
==================
1604年8月18日の日曜日に、 ジェイムズ1世がカスティリャの長官歓迎用にホワイトホール宮で催した宴会ともてなしは、優美にしつらえられ、身分の高いジェントルマンたちがもてなし役を勤めた。そのあと、器楽演奏とダンスがあり、ヘンリー王子 (ジェイムズ1世の長男。1612病没)も「たいそう陽気に、また、しとやかに」 ガリャード踊りを踊った。 万事まことに優雅な趣好に包まれていた。ところが、舞踏会が終るが早いか、「全員が、中庭を見下す部屋の窓に陣取った。その中庭には壇が築かれ、王の飼っている熊がグレイハウンドと戦うのを見ようと大群衆が集まっていた。これは大きな楽しみを与えた。」 そのあとで猛犬によるいじめがあり、牛は長い縄で首をつないであった。
(中略)
(熊いじめ)一般に熊は同時に数匹の犬の攻撃を受け、そのうえ歯を研ぎ減らされるという不利な条件をつけられていたので、強力な前足だけを頼りにした。牛は普通1回に、高度の訓練を受けた1匹の犬と試合をした。ドイツ人トマス=プラッターは彼が見た牛いじめの様子を書いているが、その時は大きな白牛が次から次へと犬を空中に放り上げ、それを付添人が棒で受け止めて落下を防いだ。殺さないでおいて、手当ての末元気を回復させ、またその後の牛いじめに使うためである。
==================
とても血腥い凄惨な戦いであったことは容易に想像できる。牛や熊のような大型動物と大型の猟犬の戦いはヘビー級ボクシングのようだが、フライ級のような戦いもある。それは、街中を走り回っているドブネズミを犬に噛み殺させるスポーツ(?)で「ネズミいじめ」(Rat-Killing)と呼ばれている。ヘンリー・メイヒューの『ロンドン路地裏の生活誌: ヴィクトリア時代(下)』(原書房)に「ネズミいじめ競技場での一夜」として描かれている、実に凄惨な場面だ。参考まで、英語の原文サイトを紹介しよう。
"London labour and the London poor" by Henry Mayhew,
A Night at Rat-Killing
キリスト教国のイギリスでは、長らくこのような非人情的な残忍な催し物が庶民の間だけでなく、王侯貴族によっても堂々と行われていたようだ。近代になって反省し、現代ではかつての悪癖を撲滅するだけでなく、まるっきり正反対に、声高らかに「動物愛護」を謳うようになった。

イギリス(だけでなく欧米)の手のひら返しのような処置を「他山の石」として、日本にも旧来の悪癖をひっくり返して欲しいことがある。それは、樹木の剪定だ。街中の公園や街路樹を見てみよう。どれもたいていは剪定されていて、自然の枝ぶりの美しさを完全に損なっている。美観だけの問題ではなく、樹木の生命力も削いでいる。よく見るとわかるが、切られた枝はかなりの確率で枯れる。中には、枝だけでなく樹木が丸ごと枯れ死に至るケースも少なくない。
日本では、行政が管理している樹木は、本来的には植えてから順調に生育さすべき義務があるはずだが、意図的に枯れ死に至らせていることになる。それに反し、ドイツのある都市ではコンピュータが天候に応じて自動的に公園の樹木や街路樹に、適切な時間に適切な量の水を散布することで、無駄な水やりを無くし、同時に樹木が枯れるのを防いでいる。このような事例から判断すると、日本人は自分たちは「自然を愛する」国民を考えているようだが、ドイツの樹木に対するこの思いやりを見ると、全くの虚構であることが分かる。
日本のこの残念な傾向は、何も公園や街路樹などに止まらず、樹木の自然の姿を学ばせるための施設であるはずの植物園ですら、不要な剪定をしているのを見かける。(全国的にはどうだか分からないが、少なくとも私の住む大阪市の長居植物園はそうだ。)それだけでなく「生きとし、生けるもの」に慈愛を注ぐことを理念としている仏教寺院ですら無惨な剪定の例外ではない。大阪の四天王寺は 593年に聖徳太子が建立した日本最古の官寺と誇っているが、境内の楠は本来なら高さ、幅とも10メートルにも及んでもおかしくない位の古木であるのに、毎年の剪定に継ぐ剪定で、醜い姿を呈している。聖徳太子がご覧になれば、きっと血の涙を流されることだろうと、構内を歩くつど私は胸につまされる思いがする。
ついでに個人的な感傷を述べると、母校の京都大学も残念ながらこの悪疫に罹った。私の学生時代(1973年から1980年) 、土木会館の前あたりの道路には樹木が一面鬱蒼と茂っていた。雨が降った翌日などその前を通ると、マイナスイオン一杯の森林浴に浸ることができた。それから数十年して、2008年に京都大学に奉職するようになってキャンパスを巡ると、ほとんどの樹木は惨めな姿をさらしていた。驚くのはそれだけでなく、そのような写真が恥ずかし気もなく堂々と京大のサイトに掲載されていることだ。著作権の関係でその写真をここに転載できないが、是非下記のURLをクリックして、いかに樹木が無惨な形にされたかを確認してほしい。
【写真】総合研究14号館(旧土木工学教室本館)
【写真】人文科学研究所本館
【写真】尊攘堂(夕暮れ)
ここ2、3年のコロナ禍による影響は無視すると、近年、日本を訪問する外国人は大幅に増加している。彼らは、無惨な剪定された樹木をみて、きっと「日本人は何て、品のない、無情なことをする人たちなんだろう!」といや~な、そして、気味悪い思いをしている、と私は確信している。それはあたかも、冒頭で述べたような、爆撃されたウクライナの街の様子を目のあたりにしているような気持ちに違いない。このような日本に「是非、観光に来てください」と頼めたものではない!一刻も早く、「植物愛護法」を国会で審議し、無惨な剪定を取り締まって頂きたく思う。
【参照ブログ】
惑鴻醸危:(第52回目)『あくどい整形外科医』
ところで、話は変わるが、現在では動物を飼うときには、動物を適正に扱い、虐待しないこと、つまり動物愛護が義務付けられている。動物の命にも尊厳を払うということだ。動物保護法は1911年にイギリスで制定されたのが最初である。その後、西欧各国や北米にも広まっていった。これを聞くと「流石にキリスト教徒は、人間だけではなく、動物にまで愛情を注いでいる」と感心される方もいるだろう。しかし、現実を見ると、キリスト教徒は日本人には想像ができないほど、おぞましい動物虐待をしていた。
かつてローマでは、コロッセウムでは剣闘士同士だけでなく、人間と野獣が死ぬまで戦わされていた。当時のローマはまだキリスト教国では無かったので、野蛮であった、と言い訳はできる。しかし、17世紀のロンドンでは国王主催で行われた「牛いじめ」にはそういう言い訳は通用しない。
ミッチェルの『ロンドン庶民生活史』(みすず書房)では近世のロンドンの庶民生活が活写されているが、その中の第6章・第3節に「牛いじめと熊いじめ」という一節がある。それは、動物同士の残虐な戦いで、大きな牛や大きな熊に猛犬を襲いかからせるのであった。本文を一部抜粋する。
==================
1604年8月18日の日曜日に、 ジェイムズ1世がカスティリャの長官歓迎用にホワイトホール宮で催した宴会ともてなしは、優美にしつらえられ、身分の高いジェントルマンたちがもてなし役を勤めた。そのあと、器楽演奏とダンスがあり、ヘンリー王子 (ジェイムズ1世の長男。1612病没)も「たいそう陽気に、また、しとやかに」 ガリャード踊りを踊った。 万事まことに優雅な趣好に包まれていた。ところが、舞踏会が終るが早いか、「全員が、中庭を見下す部屋の窓に陣取った。その中庭には壇が築かれ、王の飼っている熊がグレイハウンドと戦うのを見ようと大群衆が集まっていた。これは大きな楽しみを与えた。」 そのあとで猛犬によるいじめがあり、牛は長い縄で首をつないであった。
(中略)
(熊いじめ)一般に熊は同時に数匹の犬の攻撃を受け、そのうえ歯を研ぎ減らされるという不利な条件をつけられていたので、強力な前足だけを頼りにした。牛は普通1回に、高度の訓練を受けた1匹の犬と試合をした。ドイツ人トマス=プラッターは彼が見た牛いじめの様子を書いているが、その時は大きな白牛が次から次へと犬を空中に放り上げ、それを付添人が棒で受け止めて落下を防いだ。殺さないでおいて、手当ての末元気を回復させ、またその後の牛いじめに使うためである。
==================
とても血腥い凄惨な戦いであったことは容易に想像できる。牛や熊のような大型動物と大型の猟犬の戦いはヘビー級ボクシングのようだが、フライ級のような戦いもある。それは、街中を走り回っているドブネズミを犬に噛み殺させるスポーツ(?)で「ネズミいじめ」(Rat-Killing)と呼ばれている。ヘンリー・メイヒューの『ロンドン路地裏の生活誌: ヴィクトリア時代(下)』(原書房)に「ネズミいじめ競技場での一夜」として描かれている、実に凄惨な場面だ。参考まで、英語の原文サイトを紹介しよう。
"London labour and the London poor" by Henry Mayhew,
A Night at Rat-Killing
キリスト教国のイギリスでは、長らくこのような非人情的な残忍な催し物が庶民の間だけでなく、王侯貴族によっても堂々と行われていたようだ。近代になって反省し、現代ではかつての悪癖を撲滅するだけでなく、まるっきり正反対に、声高らかに「動物愛護」を謳うようになった。

イギリス(だけでなく欧米)の手のひら返しのような処置を「他山の石」として、日本にも旧来の悪癖をひっくり返して欲しいことがある。それは、樹木の剪定だ。街中の公園や街路樹を見てみよう。どれもたいていは剪定されていて、自然の枝ぶりの美しさを完全に損なっている。美観だけの問題ではなく、樹木の生命力も削いでいる。よく見るとわかるが、切られた枝はかなりの確率で枯れる。中には、枝だけでなく樹木が丸ごと枯れ死に至るケースも少なくない。
日本では、行政が管理している樹木は、本来的には植えてから順調に生育さすべき義務があるはずだが、意図的に枯れ死に至らせていることになる。それに反し、ドイツのある都市ではコンピュータが天候に応じて自動的に公園の樹木や街路樹に、適切な時間に適切な量の水を散布することで、無駄な水やりを無くし、同時に樹木が枯れるのを防いでいる。このような事例から判断すると、日本人は自分たちは「自然を愛する」国民を考えているようだが、ドイツの樹木に対するこの思いやりを見ると、全くの虚構であることが分かる。
日本のこの残念な傾向は、何も公園や街路樹などに止まらず、樹木の自然の姿を学ばせるための施設であるはずの植物園ですら、不要な剪定をしているのを見かける。(全国的にはどうだか分からないが、少なくとも私の住む大阪市の長居植物園はそうだ。)それだけでなく「生きとし、生けるもの」に慈愛を注ぐことを理念としている仏教寺院ですら無惨な剪定の例外ではない。大阪の四天王寺は 593年に聖徳太子が建立した日本最古の官寺と誇っているが、境内の楠は本来なら高さ、幅とも10メートルにも及んでもおかしくない位の古木であるのに、毎年の剪定に継ぐ剪定で、醜い姿を呈している。聖徳太子がご覧になれば、きっと血の涙を流されることだろうと、構内を歩くつど私は胸につまされる思いがする。
ついでに個人的な感傷を述べると、母校の京都大学も残念ながらこの悪疫に罹った。私の学生時代(1973年から1980年) 、土木会館の前あたりの道路には樹木が一面鬱蒼と茂っていた。雨が降った翌日などその前を通ると、マイナスイオン一杯の森林浴に浸ることができた。それから数十年して、2008年に京都大学に奉職するようになってキャンパスを巡ると、ほとんどの樹木は惨めな姿をさらしていた。驚くのはそれだけでなく、そのような写真が恥ずかし気もなく堂々と京大のサイトに掲載されていることだ。著作権の関係でその写真をここに転載できないが、是非下記のURLをクリックして、いかに樹木が無惨な形にされたかを確認してほしい。
【写真】総合研究14号館(旧土木工学教室本館)
【写真】人文科学研究所本館
【写真】尊攘堂(夕暮れ)
ここ2、3年のコロナ禍による影響は無視すると、近年、日本を訪問する外国人は大幅に増加している。彼らは、無惨な剪定された樹木をみて、きっと「日本人は何て、品のない、無情なことをする人たちなんだろう!」といや~な、そして、気味悪い思いをしている、と私は確信している。それはあたかも、冒頭で述べたような、爆撃されたウクライナの街の様子を目のあたりにしているような気持ちに違いない。このような日本に「是非、観光に来てください」と頼めたものではない!一刻も早く、「植物愛護法」を国会で審議し、無惨な剪定を取り締まって頂きたく思う。
【参照ブログ】
惑鴻醸危:(第52回目)『あくどい整形外科医』











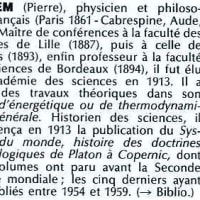















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます