私は現在、「リベラルアーツ研究家」と自称しているが、そもそもリベラルアーツを極めてみたいと思った根源は、ドイツに留学してヨーロッパ文明・文化が、それまで日本に居るときには感じられなかった大きな衝撃を受けたところにある。この衝撃は俗にいう「カルチャーショック」というような生易しい、表層的なものではなく、ヨーロッパ人の思考体系は我々日本人と根本的に全く異なる、という感覚であった。その差が一体何に起因するのか、その理由が知りたくて、自力でさがし探し出そうとしたことがリベラルアーツ道にはまり込むきっかけであった。
当初はヨーロッパ古代から近代にかけての哲学・宗教などの思想書に集中していたが、読んでいる内に徐々に不満が溜まってくるのを感じた。それは思想書は必ずしも、一般人の生活実感を表しているものではないということだ。例えば、私にとっては読破した中では最大の哲学書といえるカントの『純粋理性批判』を考えてみよう。カントは、大学の教授として安定した生活を送っていた。理性を自分の指導原理とした振舞いをしていたが、独身ではあったものの豊かな社交性を身につけ、知的にも社会的にも上流社会の一員であった。『教養を極める読書術』にも述べたように、このカントの哲学書から大いなる知的恩恵を受けた。しかし、一方では18・19世紀当時の庶民はカントのような高踏的思考など無縁の生活を送っていたことも知った。

カンドの時代より少し古いが、中世ドイツの生活実態はオットー・ボルストの『中世ヨーロッパ生活誌』やアルノ ボルストの『中世の巷にて―環境・共同体・生活形式』に書かれているが、同じドイツ人といってもまったく別世界に住む別人種のような生活を送っていたことが分かる。例えば、中世人にとって着物は貴重で、貴族せすら13世紀には下着をつけていなかった。家は木造がほとんどで、石は礎石のみ。また、庶民の家はわずか一部屋で、家族全員が暮らしていたという。カントより後の時代では、19世紀イギリスの庶民生活を描いたメイヒューの『ロンドン路地裏の生活誌』やリーダーの『英国生活物語』がある。それによると、19世紀初頭に産業革命で世界の覇者になったイギリスですら、庶民は普段は肉など食べることができず、日曜にようやく一切れの肉にありつけるというありさまだった。そういった栄養状態なので、平均年齢はわずか25歳だったという。
思想書を中心とした、20代に始まったリベラルアーツの探訪は早くも数十年が経ち、西洋だけでなく対象範囲が広がり、イスラム、インド、中国、朝鮮、東南アジアにも手をひろげ、数多くの本を読んだ。そうして45歳を過ぎるころに漸く自分なりに世界の各文化圏のコア概念がわかるようになった。しかし、これらはいずれもいわゆる人文・社会系からの知識がベースとなっている。
ところが、20年ほど前にふとしたきっかけで科学技術史への興味がわき、大冊の『ダンネマン大自然科学史』(安田徳太郎・訳)、Rene Taton(ルネ・タトン)の "Histoire générale des Sciences"、チャールズ・シンガーの『技術の歴史』(高木純一・他訳)などを次々と読了した。この間に、科学技術史に関する数多くの著作も読んだ。とりわけ、私の知見を大いに広げてくれた日本人の科学技術史家では(順不同で挙げると)三枝博音、中山茂、矢島祐利、薮内清、平田寛、吉田光邦、伊藤俊太郎、山本義隆の諸氏だ。これらの諸氏はいずれも、科学技術に関するだけでなく、広く基底文化を深く理解している。また、多文化圏との比較においても鋭い考察を放っている。このような明敏な先達をもったことに感謝したい気持ちで一杯だ。
さて、矢島祐利氏は現在では知る人は少ないだろう。私が氏を知ったのは、イスラム科学を調べていたときに出会った『アラビア科学の話』と『アラビア科学史序説』の本である。日本では、イスラム学者は数多くいるが、ほとんど全てが思想・宗教・政治・生活史がらみで、イスラム科学(アラビア科学)に関連する成書は至って少ない。矢島祐利氏はそういったなか、戦前にすでにイスラム科学史に関心を深め、戦後になって成果を発表した。アラビア科学の2冊の本を読み、矢島祐利氏の学究的関心がどこにあったのかを知りたくて、自叙伝である『科学史とともに五十年』を読んだ。
その内容はともかくとして、この本の一節『先駆者ピエル・デュエム』に、中世科学史の泰斗であるサートンが、「デュエムの本は気をつけて読まないといけない。気をつけてよめば宝庫である」との言葉が私の心に刺さった。ピエル・デュエム(皮耶・杜漢)は科学者としても優れていて、物理学の本も残しているが、注力したのがヨーロッパ中世の科学史であったという。科学というとガリレオやニュートン以降のいわゆる17世紀科学革命後の近代科学しか思いつかない人がほとんどだが、私は学生時代のドイツ滞在中にヨーロッパ各地を旅行して、現代ヨーロッパにおいても根幹の思想は中世ヨーロッパだと確信した。それゆえ、中世ヨーロッパの科学技術を知る必要性を強く感じている。それで、サートンの大著『古代中世科学文化史』を読んだ。確かに、古代中世の科学に関する事項に関してサートンの博学には敬服するものの、アリストテレス哲学を軸としたキリスト教との関連など、いわば科学史を逸脱した話は至ってすくなかった。
矢島祐利氏が推奨するデュエム(杜漢)のこの本には私の関心に応えてくれる、科学や技術を越えたもっと幅広い話があるものと期待して、全10巻(推定・5500ページ)もあるこのフランス語の
Le Système du Monde(『世界体系』)
に最近とりかかったところである。本稿はこの本を読みつつ、ざっくばらんに感じたところをメモ書き程度に書き留めるものである。
(続く。。。)
当初はヨーロッパ古代から近代にかけての哲学・宗教などの思想書に集中していたが、読んでいる内に徐々に不満が溜まってくるのを感じた。それは思想書は必ずしも、一般人の生活実感を表しているものではないということだ。例えば、私にとっては読破した中では最大の哲学書といえるカントの『純粋理性批判』を考えてみよう。カントは、大学の教授として安定した生活を送っていた。理性を自分の指導原理とした振舞いをしていたが、独身ではあったものの豊かな社交性を身につけ、知的にも社会的にも上流社会の一員であった。『教養を極める読書術』にも述べたように、このカントの哲学書から大いなる知的恩恵を受けた。しかし、一方では18・19世紀当時の庶民はカントのような高踏的思考など無縁の生活を送っていたことも知った。

カンドの時代より少し古いが、中世ドイツの生活実態はオットー・ボルストの『中世ヨーロッパ生活誌』やアルノ ボルストの『中世の巷にて―環境・共同体・生活形式』に書かれているが、同じドイツ人といってもまったく別世界に住む別人種のような生活を送っていたことが分かる。例えば、中世人にとって着物は貴重で、貴族せすら13世紀には下着をつけていなかった。家は木造がほとんどで、石は礎石のみ。また、庶民の家はわずか一部屋で、家族全員が暮らしていたという。カントより後の時代では、19世紀イギリスの庶民生活を描いたメイヒューの『ロンドン路地裏の生活誌』やリーダーの『英国生活物語』がある。それによると、19世紀初頭に産業革命で世界の覇者になったイギリスですら、庶民は普段は肉など食べることができず、日曜にようやく一切れの肉にありつけるというありさまだった。そういった栄養状態なので、平均年齢はわずか25歳だったという。
思想書を中心とした、20代に始まったリベラルアーツの探訪は早くも数十年が経ち、西洋だけでなく対象範囲が広がり、イスラム、インド、中国、朝鮮、東南アジアにも手をひろげ、数多くの本を読んだ。そうして45歳を過ぎるころに漸く自分なりに世界の各文化圏のコア概念がわかるようになった。しかし、これらはいずれもいわゆる人文・社会系からの知識がベースとなっている。
ところが、20年ほど前にふとしたきっかけで科学技術史への興味がわき、大冊の『ダンネマン大自然科学史』(安田徳太郎・訳)、Rene Taton(ルネ・タトン)の "Histoire générale des Sciences"、チャールズ・シンガーの『技術の歴史』(高木純一・他訳)などを次々と読了した。この間に、科学技術史に関する数多くの著作も読んだ。とりわけ、私の知見を大いに広げてくれた日本人の科学技術史家では(順不同で挙げると)三枝博音、中山茂、矢島祐利、薮内清、平田寛、吉田光邦、伊藤俊太郎、山本義隆の諸氏だ。これらの諸氏はいずれも、科学技術に関するだけでなく、広く基底文化を深く理解している。また、多文化圏との比較においても鋭い考察を放っている。このような明敏な先達をもったことに感謝したい気持ちで一杯だ。
さて、矢島祐利氏は現在では知る人は少ないだろう。私が氏を知ったのは、イスラム科学を調べていたときに出会った『アラビア科学の話』と『アラビア科学史序説』の本である。日本では、イスラム学者は数多くいるが、ほとんど全てが思想・宗教・政治・生活史がらみで、イスラム科学(アラビア科学)に関連する成書は至って少ない。矢島祐利氏はそういったなか、戦前にすでにイスラム科学史に関心を深め、戦後になって成果を発表した。アラビア科学の2冊の本を読み、矢島祐利氏の学究的関心がどこにあったのかを知りたくて、自叙伝である『科学史とともに五十年』を読んだ。
その内容はともかくとして、この本の一節『先駆者ピエル・デュエム』に、中世科学史の泰斗であるサートンが、「デュエムの本は気をつけて読まないといけない。気をつけてよめば宝庫である」との言葉が私の心に刺さった。ピエル・デュエム(皮耶・杜漢)は科学者としても優れていて、物理学の本も残しているが、注力したのがヨーロッパ中世の科学史であったという。科学というとガリレオやニュートン以降のいわゆる17世紀科学革命後の近代科学しか思いつかない人がほとんどだが、私は学生時代のドイツ滞在中にヨーロッパ各地を旅行して、現代ヨーロッパにおいても根幹の思想は中世ヨーロッパだと確信した。それゆえ、中世ヨーロッパの科学技術を知る必要性を強く感じている。それで、サートンの大著『古代中世科学文化史』を読んだ。確かに、古代中世の科学に関する事項に関してサートンの博学には敬服するものの、アリストテレス哲学を軸としたキリスト教との関連など、いわば科学史を逸脱した話は至ってすくなかった。
矢島祐利氏が推奨するデュエム(杜漢)のこの本には私の関心に応えてくれる、科学や技術を越えたもっと幅広い話があるものと期待して、全10巻(推定・5500ページ)もあるこのフランス語の
Le Système du Monde(『世界体系』)
に最近とりかかったところである。本稿はこの本を読みつつ、ざっくばらんに感じたところをメモ書き程度に書き留めるものである。
(続く。。。)













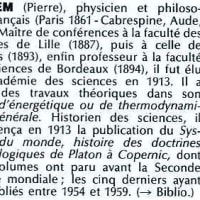













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます