『敗北』本メモ①~⑦
白土kamui
2015年11月7日~12月19日
ブログ:「狂おしく悩ましく」から転載
http://blogs.yahoo.co.jp/hutagoyama_1
《管理者から一言》長文のため①~⑦と⑧~⑩の二つに分割して掲載します。また文中では、ブログ「狂おしく悩ましく」の当該箇所へのリンクが指定されていますが、再掲に当たってはリンク処理を省きました。悪しからず、ご了承ください。
◆① 全体像と著者らの想い?
今回はできるだけ「中立的目線」を意識して書いてみたい。
本書でいいたいことは、ほぼ全体の半分を占める第1部「3・14Ⅱ」だろう。
2006年の関西の3・14(党の革命、3・14Ⅱ)での攻防と敗北、そして失脚がすべてといえる。「路線闘争を腐敗問題にすりかえて与田にテロ・リンチを加えたのは不当だ」というに尽きる。
関西の3・14を受けての中野・天田さんそして清水さんの変貌の前に、いわば「抵抗勢力」として槍玉に挙げられて追放された過程が「本体」になる。
関連する諸事件がそれなりに網羅され、ま、資料としては数少ないまとまったもの、ともいえるかもしれない。
入り口段階で2点の修正と指摘をしておこう。
①当ブログでの修正。3・14当日の本社での「党内集会」について。
「留守番内閣云々」は誤認のようだ。(修正済み)
②西島文書による「天田と中野があらかじめ仕組んだ3・14」説は、この本では撤回されている。
第1部のなかの「深夜の政治局会議」では、その「決定」の仕方が異様だ。
「書記長と(欠席した)副議長が賛成だから決定だ」とする天田さんに、「反対意見も併記してくれ」とすがる水谷さんら。これが「政治局決定」というものかとあらためて唖然とする。とはいえ「それが中核派の実態」という思いもぬぐえない。片言であいまいな清水メモが場を決する。
天田・木崎が清水さんに激しく噛み付いた瞬間の描写もある。ある種ショッキングな事件だ。「清水打倒」の臨場感があふれる。
清水さんの「3年でひっくり返すから」発言にすがった水谷さんらの沈黙と「違約」。「清水マジック」云々。
政治局に連なる地方や戦線などの3・14Ⅱへの賛否などの一覧は注目に値する。ただ、その色分けが適切か否かはよく分からない。
かつての共産党をも上回る「閉鎖集団」と化した中核派の実像を嫌というほど読まされる。
第2部は、その歴史に沿った検証ということになろうか。
いいかえれば、〈裏切りと変節の清水さん〉の実像に迫る、ということになる。75年の3・14以降を政治局内の目線から描いている。
「清水=中野『密約』説」の当否はおいて、いくつかの誰も知らないビックリ事実も書かれている。「左右の軸足」に乗ってジグザグを繰り返す定見の無い清水さん。91年の5月テーゼ(6月の挑戦-「8・1路線」)のヌエ性ということか?
91年段階の「このままで行くことは党の死」「絶対的飢餓の現実」という清水さんの認識(?虚言?)自体は私も同感だ。
参考までに当ブログから5 革命軍戦略の敗北
問題はこの現状をどうみつめてどう打開しようとしたのか?
本の中で繰り返される90年代以降の「左派」と「2つの右派」の内容・定義が分からない。折に触れてかすかに分かるのは「左派」とは武装闘争の継続路線だということ。「右派」とは「組織拡大唯一主義」と言いたいらしい。ただ、06年のこの時点では、もはや武装闘争は停止または廃棄されている。もちろん対革マル戦争も絶えて久しい。この時点での「蜂起の陣形維持」派とは何か?
中野さんの思惑や路線、折々の揺れの暴露はそれなりに描かれている。
ただ、各地方や産別そして諸戦線での実情や反応が描かれていないので、検証の仕様が無い。動労千葉特化路線の下では、全逓・国労共闘や教労・自治労などの「他の4大産別」との齟齬・あつれきも少なくない。それがまったく描かれていない。
地方や県や地区のキャップを労働者に置き換えて、「担当常任」が書記として仕切る体制への移行などは出てこない。
ある意味で最大の暴露は2つ。松崎せん滅にブレーキをかけた清水さん。そしてスト処分の和解のための亀井静香と中野さんの会談。後者は歯にモノの挟まったような議論で、中途半端だ。この時代、党と権力の関係をどう整理するか?難しい問題だったはずだけれど、スルーしてしまった。
荒川スパイ事件が再録され、栗山スパイ事件が大きく書かれている。
「主張」に近いものとして、三里塚3・8分裂にかかわる第4インターへのテロや67年10・8羽田前夜の解放派へのテロの自己批判などがある。
大事なことだが先行する小西誠さんや白井朗さん、今井公雄さんや小野田譲二さんなど諸人士の総括や自己批判の焼き直しでもある。すでに関西派の〈組織としての自己批判〉もある。2番煎じ・3番煎じとしてはそうした先駆けを受け継ぐという姿勢もほしい。(参考文献とするなど)
あとがきでは、「本多正統派」「7・7派」らしき自己主張か。
全体としては、「政治局目線」から描くことでひとつの資料集としての価値はあるのかもしれないが、抜け落ちた重大事案も多すぎる。それに多くの問題は「清水さんの忠臣」としての評価のままであり、実態が伴わない。この一冊だけから何かを得ようとすれば時間の無駄でもある。
結果として、「闇の党首 清水丈夫を仮借なくヒキはがす」のに成功したか否かの判断は人に任せよう。
ただ、清水さんを神か鬼神かのように畏敬した公然政治局員たちの絶望と恨みの心は、あふれるように滲みだしていることは確かだ。「これが当時の、長年続いた中核派の中央の実像だった」ことだけははっきりと分かる。清水さんの崩壊、そして清水体制の政治局員の実像としてはその意味でよく描かれている。
繰り返して読むには味がないかも。まわし読みして流し読み、ていどがふさわしい気もする。
………………………………………………………………………………………
◆② 清水政治局は「打倒された」
Ⅰ.「政治局は打倒された」
一連の政治局会議でのもうひとつのキーワードはこの言葉だ。
与田氏の腐敗の数々、それを事実上容認し続けて、放置し続けてきた清水さんと政治局。
絵としては、事件への対応をめぐって「動労千葉を取るか、全国連を取るか」を清水さんに迫って〈決起した〉中野(故人)・天田さんの姿が浮かびあがる。
「打倒された」にはとりあえず3つの意味がありそうだ。
①関西の決起によって、いわば桎梏以外の何者でもないことが鮮明になった党中央、それが本質的に打倒された。積年の党員の不満と怒りが全党的に噴出した。「俺も含めて打倒された」(天田さん)というのは、単にカラ文句だけではなく実感でもありそうだ。
②実態的には塩川派(後の関西派)の捨て身の決起。展開しだいでは中央派と同志会によって戦争的に打倒・一掃されていた?
③中野・天田さんらの「動労千葉を取るか?」という決起によって清水議長とその政治局(左派)が実際に打倒された。
現状としては打倒されきってはいない。清水さんや清水政治局があり、攻防の先行きはあまりに不透明だ。「打倒された」「党の革命」を旗印に泥沼の抗争に突入する。清水さんは「3年でひっくり返す」と水谷さんらを抑えて再起を画策する。
Ⅱ.追い詰められた中野動労千葉路線
中野さんの動きの分析はいまいちだ。
『敗北』本から抽出すると、大きくはこんな図式になりそうだ。
90年代始めの反戦共同行動での小西さんとの蜜月。
同時期には秋山さんの〈自滅的〉ゲリラ戦争が火を噴いている。(清水さんの「左」ぶれ)
95年、中野さんの政治局入り、97年副議長。
ここから98年、「11月全国労働者集会」路線が始まる。けれども前年来の安保ガイドラインをめぐる「20労組」運動が大規模の発展すると中野さんの〈中核派主導・基軸〉の構図としては空洞化する。
02年から03年の中野さんの「内部崩壊的危機」を経て、「サボタージュ」「ボイコット」「脱党の脅し」の末に、5月新指導方針(路線)への大転換が起こり、3・14Ⅱへの雪崩が始まる。
著書の国鉄決戦認識と中野さんの認識は対照的でもある。
著書によれば、00年国労臨大の演壇占拠と02年8人の逮捕・裁判闘争で展望が開かれた、という。
逆に、荒川硯哉氏のパンフ(荒川スパイ事件当該)によれば「01年国労臨時大会で「4党合意」を巡る国労内攻防で反対派が統制処分されていく。この頃から、(中野さんは)国鉄闘争に展望を失っていくのである」
「2003年の新指導路線の核心はなにか。中野洋氏はこの頃から盛んに国際連帯とか四大産別とか青年部運動とか強調を始める。この根底にあるのは国鉄1047名闘争、闘う国労闘争団の獲得に失敗した党中央への失望である。新指導路線から始まり、2007年の党の革命にまでとどまることがない一貫した中野氏の意識は、党中央の解体的出直しであった。」http://arakawa410.blog.fc2.com/blog-entry-1.html
両者の認識の開きはあまりに大きい。切り口の違いとだけはいえない。
こんな中で降って湧いた06年の「3・14」。
中野さんの最後の戦い、乾坤一擲の決起があったということか?
中野さんに関しては、平田氏(九州)の監禁をできなかったことで天田さんを非難するなど、党内権力抗争ならではの他の一面を描いている。やはり内ゲバ党派の最高幹部「副議長」の姿を垣間見せる。
Ⅲ.自信喪失で自壊する清水体制
最大の疑問は、なぜあれほど磐石に見えた清水体制は「簡単に打倒された」のか、だ。
当たり前の党派なら、暴かれた与田氏の罪状は「政治局員全員の引責辞任」に値するかもしれない。けれど、中核派にあってはどうか?
野島さんや秋山さんの(その後に分かった)失脚の直接の犯罪では、すべてを闇にほうむってすんだ。
そうした前例を見る限り、中野さんらの勝算は見えない。
では、かすかなりとも中野さんらには「勝算」は見えたのか?
水谷さんらには見えなかった清水さんの揺らぎや地盤沈下は見えたのか?
中野さんの数度にわたる会議や集会への「ボイコット」。
その過程での清水さんの対応。
組織的には、「政治局」の上に新設された清水さん直轄の「現場労働者を交えたWOB会議」の恒常化もある。これがもう少し描かれていい。
生きた清水さんの実像が中野さんらの前にあらわれ、そのあまりに無残で無知としか言いようが無い姿をくりかえし体感することの中で、中野さんらはある種の確信を強めていた、ということではないだろうか?
「地に落ちた偶像」という言葉がふさわしい
清水政治局は打倒されたし、いまでは復活の芽もないらしい。(とはいえ…)
………………………………………………………………………………………
◆③ 二つの戦争での清水さん
大事なことも少なくないけれど、ここではパスして見出しだけ。
「軍」の関係者の証言が衝撃的だ。内容とともに、証言したという事実自体には経緯と賞賛を惜しまない。「軍の内戦史」こそ本当に求められているものだけれど、あまりに激しかった実績と(人民のでなく)「党の軍隊」の狭い世界からはなかなか課題が浮かび上がらない。
………………………………………………………………………………………
◆④ 「3・14Ⅱの真相」を語れ
松 「本当のこと」を何一つ語っていない。
竹 うーん。書かれていることの大半は事実なんだろうけれど。
松 「左派」とか「正論」とか「テロは許せない」とか、言葉だけが浮いている。
梅 「肝心なこと。へそになる事実」から逃げている、ということかな?
第一部の「3・14Ⅱ」について。
桜 2006年の関西の行動の実際の背景とは何か?
もともと当日の関西支社での政治集会は、今の関西派につながる人々をたたき出す場として仕組まれていたという話だ。これが事実かウソか?まずしっかりと語ってほしい。「兵庫問題」とは何か?共闘や統一行動の中で協会派と親しくなったことが、清水さんや与田の怒りを買ったともきく。水谷・岸の両氏は、だからこそ「腐敗の問題ではない」「路線問題だ」と「正論」を声高に叫んでいたのではないか?
松 事件がなければ、当日か直後には反対側の「テロ・リンチ」が予定されていたといってもいい。
清水氏のその後の自己批判をみても、清水さんを筆頭とした「会議における暴力性」は限度をはるかに超えるものだったことが分かる。
参考までに(水谷さん主宰とチマタでいわれる)「現代革命論争資料蒐集」から。 政治局会議Ⅱへの提起(清水丈夫)1(2006年7月)
梅 筆者らのキーワードは「テロはいけない」「路線問題」「対峙」「元に戻せ」「正論」などか?
戦闘同志会が荒本に拠ってクーデタと「対峙」していたと何度か強調している。
では「対峙」や「元に戻せ」とはどういうことか?
関西支社に突入して再占拠(奪還)する。反乱分子を残らず捕捉し叩きのめし、「元に戻す」。監禁-追放する。
うまく行けば反乱分子はあきらめて無抵抗で開城するだろうけれど、でなければ、大阪・京都・兵庫などの拠点で篭城する。素手になるか鉄パイプまで発展するかは不明にしても、一個の「大戦争」も想像された。
これが「テロはいけない」論?
ことの正否はおいて、何か民青の「正常化」みたいな表現だ。
桜 「暴力に対する暴力の応酬」。素朴にはそんなことではないのか、否か?自らが黙々と屈していった日々を振り返って中核派の「組織的本性」は分かっていたという。自ら担ってきた「組織的本性」だ。02年、白井朗さんや角*さんへのテロを企画・実行したのはだれか?「左派」であることは今や自明だ。
「正論」の中身があまりに乏しくて、肝心なこと、筆者らの立場が隠蔽されていること、これが最大の問題だ。
そう、「政治的な卑劣さ」というべきか?
竹 関西のそういう力による「強訴」「対峙」、が中野さんたちを動かすバネになったことはたぶん間違いなさそうだ。
桜 直後の「しばらく様子を見よう」という中野さんの対応は、それ自体としてはそういう「戦争的」事態への、ま、順当な判断ともいえる。
梅 そうだ。仮に「東西の全面戦争」にでもなったら収拾がつかない。それどころではなく、政治力学的には「左派・武闘派」の奪権にも直結しかねない。世間的にも「内ゲバから内内ゲバの復活・回帰」と受け止められたろう。いわば岸武闘派政権の誕生か?つまりは「左派」によるカウンター・クーデタ??
桜 そうだ。著者らにはその辺を語って欲しかった。
松 同じことだが自称「左派」と「二つの右派」論。
中身の解説がなくてさっぱり分からない。
「左派」が何と対峙し、何に拠ったのか?
竹 後の中央派の『50年史』によると問題は「血債主義」と「政治決戦主義」だという。
後者は「万年決戦主義」批判を超えた「無条件の、反『政治闘争主義』」ともいえそうだけれど、その背後には「内戦による組織の極限的疲弊」がある。「ゲリラ・パルティザン」路線の行き詰まりをめぐる形を変えた抗争が、意味不明な論争やにはまり込んだとも思える。
岸氏も自身が責任者となった杉並選挙ではこれを意識して「総力動員」による方式を改めたとしてはいる。とはいえ(清水さんに直接口説かれて)三里塚担当になった岸氏の自己批判には、現地責任者として自らこだわった三里塚基軸主義の継続もある。
そんなことを踏まえてなお、「70年代-80年代の蜂起の陣形」と組織のあり方-その継続と変革の問題をめぐって、収拾のつかないような混乱・矛盾が山積していたことが分かる。
桜 ここでの無定義な「左派」とは(その方向が何であれ)「変える」ことへの抵抗、安住、既得権の護持--以外の何を意味するのだろうか?
そもそも清水さんに提起されるまで、断末魔の「極限的疲弊」の認識が2人には無かったのか?ま、なかったらしい。
梅 少なくとも、70年代には青忠さんと組んで首都圏委員会で激論し、意見書を出して「謹慎処分?」を受けたという(初めて聞くが)岸氏には、その辺の見識はあって良さそうとも感じるのだけれど。
竹 ところで中央派によって「血債主義者」に名を連ね、二人の著者に加えて「著者」とされる岩本さんやその後反党フラクションを理由に除名された甘粕氏はここではどういう態度だったのか?
梅 岩本さんは「関西を支持」、甘粕氏は「保留」かな?当時は政治局員の山森氏は、「左派」だったけれど、降格で許された。荒川スパイ事件では「銀行ギャング」事件の現場で逮捕されている。
粛清の穴埋めに?鈴木たつお氏ら60年世代が復活している。
………………………………………………………………………………………
◆⑤ 与田という人
与田氏の人物像や関西の実像も欲しかった。もちろん「兵庫」問題も。
私は与田氏とは一度会ったか無かったか程度だ。
澤山氏へのテロで潜って久しく90年前後に浮上した人だと思う。
公然面での前指導部を押しのけて、トップに復帰した。後の解同全国連の指導者でもある。
関西の幾多の成功と活動家の疲弊の責任をともに負う人だ。
『敗北』本によれば「左派」の要、実態的に大黒柱だ。その彼が中野さんに屈して「右派」の尖兵として別の「右派」への攻撃を強めたのが発端であり、その2面性が同時に左右の怨嗟の標的になったということらしい。
関西前進社の彼の部屋には黒田著作選が揃っていたという。
白井さんが住まいを中央に襲われて逃避行を続けていたころ、一時、荒本に匿われていたこともあるという話は聞いた。度量の大きい反骨の人でもあったということか?そんな人物が陥ったアナ。そういう視角からも検証が必要なのだと思う。
与田氏の「罪状」それ自体にも水谷さんらは深く触れようとはしない。「財政・私財・私腹の腐敗」「3日4日生活」「浅尾スパイ問題で政治局は腐っていた」等々、とは触れる。けれども「与田腐敗問題は口実にすぎなかった」というのが結論だ。
その結論の妥当性はおいて、浅尾スパイ問題(04年に発覚)とは関西の構成員のほとんどが実名とともに公安につかまれていたという事実に発する。関西に3人のスパイがいることなども暴露されていた。
『公安調査庁マル秘文書集―市民団体をも監視するCIA型情報機関』(2001/2)で
「第2章 左翼諸団体の動向と調査」
第4 革共同・中核派の組織と実態
[革共同中核派組織系統図]
第5 革共同・中核派関西地方委員会の組織と構成員
[平成6年度年報用]
「聖と俗」。「黒猫も白猫も…」。使い古した言葉だけれど、政治学・「革命論」にあって欠くことのできない一分野であることを改めて感じ入る。清水さんの「俗物的大きさ」に切り捨てられた両氏にとっても不可欠のテーマであるはずだ。
………………………………………………………………………………………
◆⑥ 中野=亀井会談と清水さん
●2枚ジタと野合の10余年?
清水さんと中野さんの入り組んだ関係や清水さんの2枚ジタぶりが印象的だ。フェイズⅡ(80年代を貫く対権力のゲリラ戦と動労革マル(JR東))はやるべきではなかったという中野さん。「分かってもらう」とする清水さん。「血債」についても同じだった。こんな議論をしながら両者の野合が進んだのだという。
ことの当否は置いて、総括も路線も展望もまったく一致しない両者による10余年があったという事自体が「革命党」としては不思議としか言いようが無い。
●中野=亀井会談について
著者によれば会談は94年12月。当時運輸相の亀井静香が中野さんを呼び出して会談したのだという。その結果96年3月には三里塚のジェット闘争の大量解雇について、いわば金銭和解が成り立つ。(「たかだか動労千葉を相手にした」トップ会談)
三里塚ゲリラは新指導路線の直前までつづいた。中野=亀井会談以降には中野さんが何度もゲリラの停止を求めて他の政治局員たちから「たしなめられた」ともある。(亀井との取引を匂わせて。もともと中野さんの持論でもあるが)
とはいえ、その後にはやはり停止されたのも事実だ。ゲリラの停止(武闘路線の放棄)はいつ、どういう形で決まったのかも知りたいところだ。
著者らはこの会談の事実は知らされながら、その評価・議論は許されなかったように見える。「労働組合の指導者だから」と受け入れただけでらしい。会談の中身もほぼ知らないらしい。すべては清水さんと中野さんの胸のうち、ということか?「中野は…ゲリラ戦をやめさせろと恫喝され、それを呑んでいたのだった」
中野さんももともとゲリラ反対だし、私自身、この時期にはとっくに終わるものと思っていた。
けれども卑しくも「唯一の革命党」「武闘派」を骨の髄までしみこんだ中核派の政治局が、それですませて良いものだったろうか?済ませられたのだろうか?「権力=公安との内通・密通」という言葉が浮かぶ。それは中野さんにとどまらない。清水さんを始め、政治局全体の「密通」…。
事後にせよ何にせよ、「非合法の党」「公非・合非」のありかたそのものの全面的検討・整理なしには「スパイの党」への転落は避けられないのではないか?そんな大きな問題だったはずだと思える。
「非合法云々」の空叫びがただただ虚しい。事態の根底には労働組合運動の現実や現場のさまざまな葛藤への無関心・無定見がありそうだ。「難しいバランス感覚」に対して「意見がもてない問題の大きさ」に屈したのだ。「武装する党」はもちろん、「労働者党」としても「転向」という以外に何が言えるのだろう?
動労千葉の和解の後、分割民営化の問題ではあるが「4党合意」粉砕で檄を飛ばす中野さん。しかしこの会談の事実が(実は亀井サイドなどから)広がるにつけ、それに胸を温くしたり呼応することが国労・動労千葉の中でもどれだけの人にできたろうか?「労働組合だから」とはこの場合もあてはまる。大闘争に終止符を打った後、少なくともしばらくは、「休養」に入るのは常識だ。
清水=中野体制を批判するに当たって、著者らにとっては本来、第1級の事件と私には思えるのだけれど、見出しも立てずに本文に短く埋もれさせている。(P386,第10章の「20全総は政治局内左右対立の始まり」)
(亀井静香:1971年警察庁警備局の極左事件に関する初代統括責任者となり、成田空港事件、連合赤軍あさま山荘事件、日本赤軍テルアビブ空港事件等を陣頭指揮)。
………………………………………………………………………………………
◆⑦ 閑話―90年代半ばとは
本書によれば、91年の5月テーゼに反発して秋山さんが「やけのやんぱち」でゲリラ戦を総発動させて力尽き、自身の罪状を告白した年であり、平行して地下からの浮上が大量に進んだときだ。清水さんの「左ブレ」が元の「右ブレ」に戻る。権力に対してもそういうシグナルを送り続けた時期だ。白井さんが偽りの「政治局会議」におびき出されて自宅を襲撃された年でもある。90年代半ばを「亀井=中野会談」をキーワードに振り返ってみたい。
会談の意味
桜 「たかだか千葉機関区の少数派の1組合」に担当大臣が乗り出す。しかも元公安、浅間山荘の亀井だ。会談の設定そのものに「政府・公安と中核派のすり合わせ」が意図されていたと言われて普通はおかしくない。
梅 そう思う。否定する材料がない限り、断定していい。考えれば考えるほど、スルーできない。
私 中野=亀井会談の94年とは、年末に本社が移転した時期であり、私の本社生活の最後の1年にあたる。職場で生活し、組合で活動して分かったこともある。警察や会社側との付き合いは実に色んな形いろんな場面である。小さな職場でもガラス張りと並んで「非合法・非公然」の領域はある。桜 あえていえば、「武装闘争の党」であれ「非非の党」何であれ、国家とのシグナルの交換やホットラインは事実上あったしあっていい。「一時停戦」や「部分停戦」のために「取引」や「ボス交」はあるものだと腹をくくることも必要な気がする。双方が相手への妄想や誤解で攻撃しあったら、とんでもない事態を生むこともあるからだ。「権力」や「体制」は必ずしも一枚岩ではないし、「誤認による無益な犠牲」も少なくないからだ。ただ、「当面どこまで〈法やルール〉を守るかの暗黙の?」シグナルはできるだけ公開であることが望ましい。
(参考までに1 鉄壁防御の要塞)
梅 ただそうであればあるほど、一定の規模と時間をかけて、(少なくとも執行部(政治局))では、それがどういう事態を生み、その対策にどれほどの力を注ぎ込むかを真剣に議論しておくことが不可欠だ。それを運動全体の新たな社会認識・政治認識にまで高めていくという努力が必要なのだと思う。それなしには「取り込まれる」。力関係があまりに偏っているからこそ、「転向」「党としての転向」でしかない。多くの場合は「即転向」というべきではないとしても、だ。
90年代とは?
桜 さて、では90年代の半ばとは組織的にはどんな時代だったのだろう?
梅 91年の5月テーゼでの「転換」を経て、気持ちは大衆運動に向かっていた時期だ。現場の要請などを受けて、色んな地域や産別の闘う人々との交流を深めなおしていた時。地域や産別の「絵地図」を描き、その中に中核派の存在が多少は入ってくる。そんな時にゲリラが起き、「軍報(実行声明)」がでると「まだこんなことをやってるのかよ」と思った。「中核派は変わっていないんだね」と言われて、色んな努力が無に帰すという思いが強かった。まして「対革マル」のせん滅戦などあると、もう最悪だった。「何を考えてるんだ」と怒鳴り込みたい思いがあった。「左派」を自称する人たちが今でも胸を張ろうとしていることには違和感が強い。
海 90年天皇決戦にはもう「党のガラス張り化」はどんどん進んでいて、労働者は自宅に住み、会議もそこで開かれた。94年の前進社の新社屋移転は色んな転換を一気に進めた時でもある。本社への出入りが最寄のバス停からの徒歩で良くなり、タクシー代が浮いた。本社からの帰りも同じで、車に乗って延々走ってわけの分からないところに放り出されることもなくなった。時には張り込み中の公安に逝く手を阻まれることもあったけれど、気にしない。時間的にも金銭的にも「もうだめ」「転換」という実感から生まれた変化だったと思う。
竹 地区常任の活動費も行き詰まってきた。地方では「遅配・減配」が相次いでいた。「県委員」でない「専従」の「活動費」が「無給」になり、やがて90年代後半には「常任」も減俸から(県からは)無給になった。人によっては自分が握る地区財政から自分の金をひねり出してもいたようだし、地区によっては労働者からの新しい「基金」で糊口をしのいだ場合もある。
桜 本社メンバーも結婚して近くに住んで自転車で通うことも生まれた。もちろん本社からバイトに出たりもする。人によって色んなバイトに関わり出した。これも「天田改革」だね。(この項つづく)
………………………………………………………………………………………
◆⑦ 閑話2
(承前)
「浮上」が対権力で意味したもの
私 地下から大量に浮上してきた結果、何が生まれたのかな?
梅 もう地下を支えられないという実情から始まったことは事実だと思う。あわせて、「かつては優秀な活動家」だった人々がフル回転すれば、大衆的展開も新しい可能性が開かれる。そういう期待があったのも事実だと思う。ただ、一部を除いて、表の惨状に触れた浮上組の「浦島太郎」感覚も大きくて、結果としては…。荒木氏は酒によって転落し…。そう、出獄組の荒川氏の活躍も大きかったとは思うけれど。
桜 集会・デモの「合法化」も一段進んだ。反戦共同行動委や労組交流センター主催のデモは、それ以前のでも警備と比べるとずいぶんとゆるいものになった。都心や市街地でのデモも増えたからとはいえないレベルだったと思う。
梅 だいぶ後にはなるけれど、現役の「全学連委員長」が訪米のビザを受けられたと聞いて驚いた。アメリカの「テロ指定団体」には入れなかったんだなと。公安の判断がどんなものだったのか、よくは分からないが。
松 うん。結局は浮上組が本社や公然事務所にたむろして、権力に対しては「いつでも誰でもパクれる」という状態。結果的にはほとんどパクは出なかったけれど、「わき腹をさらけ出して、権力側のさじ加減次第」の時期だ。
つまり「権力側のシグナル」に神経を集中させて、次の一手を決める。とはいえもはや「浮上路線」「軍の解体路線」は戻せない。仮に一斉逮捕が出ても、大きくは変えられない。
たがいに「シグナル」を出し合い、読みあっていた時期だということか?!
梅 今から見れば、権力側も中核派の方向性をつかむのに躍起だったのだろう。「パクらない」ことで「右」に誘導することには、内部でも一枚岩ではなかったのでは?
桜 テロもゲリラもぎりぎり2003年まで続いた。しかも時にはかなりの巨弾もあった。8月の千葉県警幹部宅への爆発物を伴う放火が最後だと思う(誤爆)。政治局内での中野さんと「左派」の議論は、わずかだけれど、「多数派」が「継戦」にこだわっていたことは良く分かる。「ゲリラの巨弾で中野路線を吹き飛ばしたい」か?
清水さんのマヌーバー。とはいえ、地方や現場のメンバーにとっても反応は主々雑多。どこに向かうのかは不鮮明という頃でもある。
竹 時代的には総評・社会党の解体が「メイン」だった。中核派の存在は残念ながら、2次的問題として、別の要因から考えるべき問題も多そうだ。主客を代えて考え直したいと思う。
梅 角度は違うけれど、「軍の解体=社会復帰」は、やはり「党の浮沈のかかった」最大の課題だったという面を見逃して欲しくない。「凶状持ち」の内心・内省と「時効」の問題は、組織にとってどんな犠牲を払っても全力で解決すべき課題で、「路線」や権力闘争に還元してはならない。
いくつか付け足し
松 公安の地盤も低落した。後になってからだけれど、警察庁・警視庁のツートップを「交通畑出身」に奪われる事態が続いている。警察も「生まれ変わる」過程にありそうな。とはいえ、どこがどうなるのかは、あれたちには分からない。「変わらない」ことも多いわけだし。「中核派唯一論」からは見えないことも多そうだ。
梅 公安との対決では、15年現在では71年渋谷暴動がらみなどで時効が廃止されたままだ。全体と個別それぞれの領域がありそうで、一口でまとめることはできない。ただ、「非公然」の清水さんには累は及ばない、少なくともおおいにゆとりがあることは、確かだろう。
竹 当時からも、天田氏らの「3人組」は最低だったと思う。官僚的・恫喝政治。会話ができない。「3・14Ⅱ」の経過やその後の経緯を聞いても、すんなり理解できることが多い。ま、坂木は比較的対応がうまかったけれど、「官僚的自己保身」にたけた奴、「官僚的な優秀さ」というべきところかな?
桜 かなり荒削りだけれど、今後に託そう。
………………………………………………………………………………………
(つづく)
白土kamui
2015年11月7日~12月19日
ブログ:「狂おしく悩ましく」から転載
http://blogs.yahoo.co.jp/hutagoyama_1
《管理者から一言》長文のため①~⑦と⑧~⑩の二つに分割して掲載します。また文中では、ブログ「狂おしく悩ましく」の当該箇所へのリンクが指定されていますが、再掲に当たってはリンク処理を省きました。悪しからず、ご了承ください。
◆① 全体像と著者らの想い?
今回はできるだけ「中立的目線」を意識して書いてみたい。
本書でいいたいことは、ほぼ全体の半分を占める第1部「3・14Ⅱ」だろう。
2006年の関西の3・14(党の革命、3・14Ⅱ)での攻防と敗北、そして失脚がすべてといえる。「路線闘争を腐敗問題にすりかえて与田にテロ・リンチを加えたのは不当だ」というに尽きる。
関西の3・14を受けての中野・天田さんそして清水さんの変貌の前に、いわば「抵抗勢力」として槍玉に挙げられて追放された過程が「本体」になる。
関連する諸事件がそれなりに網羅され、ま、資料としては数少ないまとまったもの、ともいえるかもしれない。
入り口段階で2点の修正と指摘をしておこう。
①当ブログでの修正。3・14当日の本社での「党内集会」について。
「留守番内閣云々」は誤認のようだ。(修正済み)
②西島文書による「天田と中野があらかじめ仕組んだ3・14」説は、この本では撤回されている。
第1部のなかの「深夜の政治局会議」では、その「決定」の仕方が異様だ。
「書記長と(欠席した)副議長が賛成だから決定だ」とする天田さんに、「反対意見も併記してくれ」とすがる水谷さんら。これが「政治局決定」というものかとあらためて唖然とする。とはいえ「それが中核派の実態」という思いもぬぐえない。片言であいまいな清水メモが場を決する。
天田・木崎が清水さんに激しく噛み付いた瞬間の描写もある。ある種ショッキングな事件だ。「清水打倒」の臨場感があふれる。
清水さんの「3年でひっくり返すから」発言にすがった水谷さんらの沈黙と「違約」。「清水マジック」云々。
政治局に連なる地方や戦線などの3・14Ⅱへの賛否などの一覧は注目に値する。ただ、その色分けが適切か否かはよく分からない。
かつての共産党をも上回る「閉鎖集団」と化した中核派の実像を嫌というほど読まされる。
第2部は、その歴史に沿った検証ということになろうか。
いいかえれば、〈裏切りと変節の清水さん〉の実像に迫る、ということになる。75年の3・14以降を政治局内の目線から描いている。
「清水=中野『密約』説」の当否はおいて、いくつかの誰も知らないビックリ事実も書かれている。「左右の軸足」に乗ってジグザグを繰り返す定見の無い清水さん。91年の5月テーゼ(6月の挑戦-「8・1路線」)のヌエ性ということか?
91年段階の「このままで行くことは党の死」「絶対的飢餓の現実」という清水さんの認識(?虚言?)自体は私も同感だ。
参考までに当ブログから5 革命軍戦略の敗北
問題はこの現状をどうみつめてどう打開しようとしたのか?
本の中で繰り返される90年代以降の「左派」と「2つの右派」の内容・定義が分からない。折に触れてかすかに分かるのは「左派」とは武装闘争の継続路線だということ。「右派」とは「組織拡大唯一主義」と言いたいらしい。ただ、06年のこの時点では、もはや武装闘争は停止または廃棄されている。もちろん対革マル戦争も絶えて久しい。この時点での「蜂起の陣形維持」派とは何か?
中野さんの思惑や路線、折々の揺れの暴露はそれなりに描かれている。
ただ、各地方や産別そして諸戦線での実情や反応が描かれていないので、検証の仕様が無い。動労千葉特化路線の下では、全逓・国労共闘や教労・自治労などの「他の4大産別」との齟齬・あつれきも少なくない。それがまったく描かれていない。
地方や県や地区のキャップを労働者に置き換えて、「担当常任」が書記として仕切る体制への移行などは出てこない。
ある意味で最大の暴露は2つ。松崎せん滅にブレーキをかけた清水さん。そしてスト処分の和解のための亀井静香と中野さんの会談。後者は歯にモノの挟まったような議論で、中途半端だ。この時代、党と権力の関係をどう整理するか?難しい問題だったはずだけれど、スルーしてしまった。
荒川スパイ事件が再録され、栗山スパイ事件が大きく書かれている。
「主張」に近いものとして、三里塚3・8分裂にかかわる第4インターへのテロや67年10・8羽田前夜の解放派へのテロの自己批判などがある。
大事なことだが先行する小西誠さんや白井朗さん、今井公雄さんや小野田譲二さんなど諸人士の総括や自己批判の焼き直しでもある。すでに関西派の〈組織としての自己批判〉もある。2番煎じ・3番煎じとしてはそうした先駆けを受け継ぐという姿勢もほしい。(参考文献とするなど)
あとがきでは、「本多正統派」「7・7派」らしき自己主張か。
全体としては、「政治局目線」から描くことでひとつの資料集としての価値はあるのかもしれないが、抜け落ちた重大事案も多すぎる。それに多くの問題は「清水さんの忠臣」としての評価のままであり、実態が伴わない。この一冊だけから何かを得ようとすれば時間の無駄でもある。
結果として、「闇の党首 清水丈夫を仮借なくヒキはがす」のに成功したか否かの判断は人に任せよう。
ただ、清水さんを神か鬼神かのように畏敬した公然政治局員たちの絶望と恨みの心は、あふれるように滲みだしていることは確かだ。「これが当時の、長年続いた中核派の中央の実像だった」ことだけははっきりと分かる。清水さんの崩壊、そして清水体制の政治局員の実像としてはその意味でよく描かれている。
繰り返して読むには味がないかも。まわし読みして流し読み、ていどがふさわしい気もする。
………………………………………………………………………………………
◆② 清水政治局は「打倒された」
Ⅰ.「政治局は打倒された」
一連の政治局会議でのもうひとつのキーワードはこの言葉だ。
与田氏の腐敗の数々、それを事実上容認し続けて、放置し続けてきた清水さんと政治局。
絵としては、事件への対応をめぐって「動労千葉を取るか、全国連を取るか」を清水さんに迫って〈決起した〉中野(故人)・天田さんの姿が浮かびあがる。
「打倒された」にはとりあえず3つの意味がありそうだ。
①関西の決起によって、いわば桎梏以外の何者でもないことが鮮明になった党中央、それが本質的に打倒された。積年の党員の不満と怒りが全党的に噴出した。「俺も含めて打倒された」(天田さん)というのは、単にカラ文句だけではなく実感でもありそうだ。
②実態的には塩川派(後の関西派)の捨て身の決起。展開しだいでは中央派と同志会によって戦争的に打倒・一掃されていた?
③中野・天田さんらの「動労千葉を取るか?」という決起によって清水議長とその政治局(左派)が実際に打倒された。
現状としては打倒されきってはいない。清水さんや清水政治局があり、攻防の先行きはあまりに不透明だ。「打倒された」「党の革命」を旗印に泥沼の抗争に突入する。清水さんは「3年でひっくり返す」と水谷さんらを抑えて再起を画策する。
Ⅱ.追い詰められた中野動労千葉路線
中野さんの動きの分析はいまいちだ。
『敗北』本から抽出すると、大きくはこんな図式になりそうだ。
90年代始めの反戦共同行動での小西さんとの蜜月。
同時期には秋山さんの〈自滅的〉ゲリラ戦争が火を噴いている。(清水さんの「左」ぶれ)
95年、中野さんの政治局入り、97年副議長。
ここから98年、「11月全国労働者集会」路線が始まる。けれども前年来の安保ガイドラインをめぐる「20労組」運動が大規模の発展すると中野さんの〈中核派主導・基軸〉の構図としては空洞化する。
02年から03年の中野さんの「内部崩壊的危機」を経て、「サボタージュ」「ボイコット」「脱党の脅し」の末に、5月新指導方針(路線)への大転換が起こり、3・14Ⅱへの雪崩が始まる。
著書の国鉄決戦認識と中野さんの認識は対照的でもある。
著書によれば、00年国労臨大の演壇占拠と02年8人の逮捕・裁判闘争で展望が開かれた、という。
逆に、荒川硯哉氏のパンフ(荒川スパイ事件当該)によれば「01年国労臨時大会で「4党合意」を巡る国労内攻防で反対派が統制処分されていく。この頃から、(中野さんは)国鉄闘争に展望を失っていくのである」
「2003年の新指導路線の核心はなにか。中野洋氏はこの頃から盛んに国際連帯とか四大産別とか青年部運動とか強調を始める。この根底にあるのは国鉄1047名闘争、闘う国労闘争団の獲得に失敗した党中央への失望である。新指導路線から始まり、2007年の党の革命にまでとどまることがない一貫した中野氏の意識は、党中央の解体的出直しであった。」http://arakawa410.blog.fc2.com/blog-entry-1.html
両者の認識の開きはあまりに大きい。切り口の違いとだけはいえない。
こんな中で降って湧いた06年の「3・14」。
中野さんの最後の戦い、乾坤一擲の決起があったということか?
中野さんに関しては、平田氏(九州)の監禁をできなかったことで天田さんを非難するなど、党内権力抗争ならではの他の一面を描いている。やはり内ゲバ党派の最高幹部「副議長」の姿を垣間見せる。
Ⅲ.自信喪失で自壊する清水体制
最大の疑問は、なぜあれほど磐石に見えた清水体制は「簡単に打倒された」のか、だ。
当たり前の党派なら、暴かれた与田氏の罪状は「政治局員全員の引責辞任」に値するかもしれない。けれど、中核派にあってはどうか?
野島さんや秋山さんの(その後に分かった)失脚の直接の犯罪では、すべてを闇にほうむってすんだ。
そうした前例を見る限り、中野さんらの勝算は見えない。
では、かすかなりとも中野さんらには「勝算」は見えたのか?
水谷さんらには見えなかった清水さんの揺らぎや地盤沈下は見えたのか?
中野さんの数度にわたる会議や集会への「ボイコット」。
その過程での清水さんの対応。
組織的には、「政治局」の上に新設された清水さん直轄の「現場労働者を交えたWOB会議」の恒常化もある。これがもう少し描かれていい。
生きた清水さんの実像が中野さんらの前にあらわれ、そのあまりに無残で無知としか言いようが無い姿をくりかえし体感することの中で、中野さんらはある種の確信を強めていた、ということではないだろうか?
「地に落ちた偶像」という言葉がふさわしい
清水政治局は打倒されたし、いまでは復活の芽もないらしい。(とはいえ…)
………………………………………………………………………………………
◆③ 二つの戦争での清水さん
大事なことも少なくないけれど、ここではパスして見出しだけ。
「軍」の関係者の証言が衝撃的だ。内容とともに、証言したという事実自体には経緯と賞賛を惜しまない。「軍の内戦史」こそ本当に求められているものだけれど、あまりに激しかった実績と(人民のでなく)「党の軍隊」の狭い世界からはなかなか課題が浮かび上がらない。
………………………………………………………………………………………
◆④ 「3・14Ⅱの真相」を語れ
松 「本当のこと」を何一つ語っていない。
竹 うーん。書かれていることの大半は事実なんだろうけれど。
松 「左派」とか「正論」とか「テロは許せない」とか、言葉だけが浮いている。
梅 「肝心なこと。へそになる事実」から逃げている、ということかな?
第一部の「3・14Ⅱ」について。
桜 2006年の関西の行動の実際の背景とは何か?
もともと当日の関西支社での政治集会は、今の関西派につながる人々をたたき出す場として仕組まれていたという話だ。これが事実かウソか?まずしっかりと語ってほしい。「兵庫問題」とは何か?共闘や統一行動の中で協会派と親しくなったことが、清水さんや与田の怒りを買ったともきく。水谷・岸の両氏は、だからこそ「腐敗の問題ではない」「路線問題だ」と「正論」を声高に叫んでいたのではないか?
松 事件がなければ、当日か直後には反対側の「テロ・リンチ」が予定されていたといってもいい。
清水氏のその後の自己批判をみても、清水さんを筆頭とした「会議における暴力性」は限度をはるかに超えるものだったことが分かる。
参考までに(水谷さん主宰とチマタでいわれる)「現代革命論争資料蒐集」から。 政治局会議Ⅱへの提起(清水丈夫)1(2006年7月)
梅 筆者らのキーワードは「テロはいけない」「路線問題」「対峙」「元に戻せ」「正論」などか?
戦闘同志会が荒本に拠ってクーデタと「対峙」していたと何度か強調している。
では「対峙」や「元に戻せ」とはどういうことか?
関西支社に突入して再占拠(奪還)する。反乱分子を残らず捕捉し叩きのめし、「元に戻す」。監禁-追放する。
うまく行けば反乱分子はあきらめて無抵抗で開城するだろうけれど、でなければ、大阪・京都・兵庫などの拠点で篭城する。素手になるか鉄パイプまで発展するかは不明にしても、一個の「大戦争」も想像された。
これが「テロはいけない」論?
ことの正否はおいて、何か民青の「正常化」みたいな表現だ。
桜 「暴力に対する暴力の応酬」。素朴にはそんなことではないのか、否か?自らが黙々と屈していった日々を振り返って中核派の「組織的本性」は分かっていたという。自ら担ってきた「組織的本性」だ。02年、白井朗さんや角*さんへのテロを企画・実行したのはだれか?「左派」であることは今や自明だ。
「正論」の中身があまりに乏しくて、肝心なこと、筆者らの立場が隠蔽されていること、これが最大の問題だ。
そう、「政治的な卑劣さ」というべきか?
竹 関西のそういう力による「強訴」「対峙」、が中野さんたちを動かすバネになったことはたぶん間違いなさそうだ。
桜 直後の「しばらく様子を見よう」という中野さんの対応は、それ自体としてはそういう「戦争的」事態への、ま、順当な判断ともいえる。
梅 そうだ。仮に「東西の全面戦争」にでもなったら収拾がつかない。それどころではなく、政治力学的には「左派・武闘派」の奪権にも直結しかねない。世間的にも「内ゲバから内内ゲバの復活・回帰」と受け止められたろう。いわば岸武闘派政権の誕生か?つまりは「左派」によるカウンター・クーデタ??
桜 そうだ。著者らにはその辺を語って欲しかった。
松 同じことだが自称「左派」と「二つの右派」論。
中身の解説がなくてさっぱり分からない。
「左派」が何と対峙し、何に拠ったのか?
竹 後の中央派の『50年史』によると問題は「血債主義」と「政治決戦主義」だという。
後者は「万年決戦主義」批判を超えた「無条件の、反『政治闘争主義』」ともいえそうだけれど、その背後には「内戦による組織の極限的疲弊」がある。「ゲリラ・パルティザン」路線の行き詰まりをめぐる形を変えた抗争が、意味不明な論争やにはまり込んだとも思える。
岸氏も自身が責任者となった杉並選挙ではこれを意識して「総力動員」による方式を改めたとしてはいる。とはいえ(清水さんに直接口説かれて)三里塚担当になった岸氏の自己批判には、現地責任者として自らこだわった三里塚基軸主義の継続もある。
そんなことを踏まえてなお、「70年代-80年代の蜂起の陣形」と組織のあり方-その継続と変革の問題をめぐって、収拾のつかないような混乱・矛盾が山積していたことが分かる。
桜 ここでの無定義な「左派」とは(その方向が何であれ)「変える」ことへの抵抗、安住、既得権の護持--以外の何を意味するのだろうか?
そもそも清水さんに提起されるまで、断末魔の「極限的疲弊」の認識が2人には無かったのか?ま、なかったらしい。
梅 少なくとも、70年代には青忠さんと組んで首都圏委員会で激論し、意見書を出して「謹慎処分?」を受けたという(初めて聞くが)岸氏には、その辺の見識はあって良さそうとも感じるのだけれど。
竹 ところで中央派によって「血債主義者」に名を連ね、二人の著者に加えて「著者」とされる岩本さんやその後反党フラクションを理由に除名された甘粕氏はここではどういう態度だったのか?
梅 岩本さんは「関西を支持」、甘粕氏は「保留」かな?当時は政治局員の山森氏は、「左派」だったけれど、降格で許された。荒川スパイ事件では「銀行ギャング」事件の現場で逮捕されている。
粛清の穴埋めに?鈴木たつお氏ら60年世代が復活している。
………………………………………………………………………………………
◆⑤ 与田という人
与田氏の人物像や関西の実像も欲しかった。もちろん「兵庫」問題も。
私は与田氏とは一度会ったか無かったか程度だ。
澤山氏へのテロで潜って久しく90年前後に浮上した人だと思う。
公然面での前指導部を押しのけて、トップに復帰した。後の解同全国連の指導者でもある。
関西の幾多の成功と活動家の疲弊の責任をともに負う人だ。
『敗北』本によれば「左派」の要、実態的に大黒柱だ。その彼が中野さんに屈して「右派」の尖兵として別の「右派」への攻撃を強めたのが発端であり、その2面性が同時に左右の怨嗟の標的になったということらしい。
関西前進社の彼の部屋には黒田著作選が揃っていたという。
白井さんが住まいを中央に襲われて逃避行を続けていたころ、一時、荒本に匿われていたこともあるという話は聞いた。度量の大きい反骨の人でもあったということか?そんな人物が陥ったアナ。そういう視角からも検証が必要なのだと思う。
与田氏の「罪状」それ自体にも水谷さんらは深く触れようとはしない。「財政・私財・私腹の腐敗」「3日4日生活」「浅尾スパイ問題で政治局は腐っていた」等々、とは触れる。けれども「与田腐敗問題は口実にすぎなかった」というのが結論だ。
その結論の妥当性はおいて、浅尾スパイ問題(04年に発覚)とは関西の構成員のほとんどが実名とともに公安につかまれていたという事実に発する。関西に3人のスパイがいることなども暴露されていた。
『公安調査庁マル秘文書集―市民団体をも監視するCIA型情報機関』(2001/2)で
「第2章 左翼諸団体の動向と調査」
第4 革共同・中核派の組織と実態
[革共同中核派組織系統図]
第5 革共同・中核派関西地方委員会の組織と構成員
[平成6年度年報用]
「聖と俗」。「黒猫も白猫も…」。使い古した言葉だけれど、政治学・「革命論」にあって欠くことのできない一分野であることを改めて感じ入る。清水さんの「俗物的大きさ」に切り捨てられた両氏にとっても不可欠のテーマであるはずだ。
………………………………………………………………………………………
◆⑥ 中野=亀井会談と清水さん
●2枚ジタと野合の10余年?
清水さんと中野さんの入り組んだ関係や清水さんの2枚ジタぶりが印象的だ。フェイズⅡ(80年代を貫く対権力のゲリラ戦と動労革マル(JR東))はやるべきではなかったという中野さん。「分かってもらう」とする清水さん。「血債」についても同じだった。こんな議論をしながら両者の野合が進んだのだという。
ことの当否は置いて、総括も路線も展望もまったく一致しない両者による10余年があったという事自体が「革命党」としては不思議としか言いようが無い。
●中野=亀井会談について
著者によれば会談は94年12月。当時運輸相の亀井静香が中野さんを呼び出して会談したのだという。その結果96年3月には三里塚のジェット闘争の大量解雇について、いわば金銭和解が成り立つ。(「たかだか動労千葉を相手にした」トップ会談)
三里塚ゲリラは新指導路線の直前までつづいた。中野=亀井会談以降には中野さんが何度もゲリラの停止を求めて他の政治局員たちから「たしなめられた」ともある。(亀井との取引を匂わせて。もともと中野さんの持論でもあるが)
とはいえ、その後にはやはり停止されたのも事実だ。ゲリラの停止(武闘路線の放棄)はいつ、どういう形で決まったのかも知りたいところだ。
著者らはこの会談の事実は知らされながら、その評価・議論は許されなかったように見える。「労働組合の指導者だから」と受け入れただけでらしい。会談の中身もほぼ知らないらしい。すべては清水さんと中野さんの胸のうち、ということか?「中野は…ゲリラ戦をやめさせろと恫喝され、それを呑んでいたのだった」
中野さんももともとゲリラ反対だし、私自身、この時期にはとっくに終わるものと思っていた。
けれども卑しくも「唯一の革命党」「武闘派」を骨の髄までしみこんだ中核派の政治局が、それですませて良いものだったろうか?済ませられたのだろうか?「権力=公安との内通・密通」という言葉が浮かぶ。それは中野さんにとどまらない。清水さんを始め、政治局全体の「密通」…。
事後にせよ何にせよ、「非合法の党」「公非・合非」のありかたそのものの全面的検討・整理なしには「スパイの党」への転落は避けられないのではないか?そんな大きな問題だったはずだと思える。
「非合法云々」の空叫びがただただ虚しい。事態の根底には労働組合運動の現実や現場のさまざまな葛藤への無関心・無定見がありそうだ。「難しいバランス感覚」に対して「意見がもてない問題の大きさ」に屈したのだ。「武装する党」はもちろん、「労働者党」としても「転向」という以外に何が言えるのだろう?
動労千葉の和解の後、分割民営化の問題ではあるが「4党合意」粉砕で檄を飛ばす中野さん。しかしこの会談の事実が(実は亀井サイドなどから)広がるにつけ、それに胸を温くしたり呼応することが国労・動労千葉の中でもどれだけの人にできたろうか?「労働組合だから」とはこの場合もあてはまる。大闘争に終止符を打った後、少なくともしばらくは、「休養」に入るのは常識だ。
清水=中野体制を批判するに当たって、著者らにとっては本来、第1級の事件と私には思えるのだけれど、見出しも立てずに本文に短く埋もれさせている。(P386,第10章の「20全総は政治局内左右対立の始まり」)
(亀井静香:1971年警察庁警備局の極左事件に関する初代統括責任者となり、成田空港事件、連合赤軍あさま山荘事件、日本赤軍テルアビブ空港事件等を陣頭指揮)。
………………………………………………………………………………………
◆⑦ 閑話―90年代半ばとは
本書によれば、91年の5月テーゼに反発して秋山さんが「やけのやんぱち」でゲリラ戦を総発動させて力尽き、自身の罪状を告白した年であり、平行して地下からの浮上が大量に進んだときだ。清水さんの「左ブレ」が元の「右ブレ」に戻る。権力に対してもそういうシグナルを送り続けた時期だ。白井さんが偽りの「政治局会議」におびき出されて自宅を襲撃された年でもある。90年代半ばを「亀井=中野会談」をキーワードに振り返ってみたい。
会談の意味
桜 「たかだか千葉機関区の少数派の1組合」に担当大臣が乗り出す。しかも元公安、浅間山荘の亀井だ。会談の設定そのものに「政府・公安と中核派のすり合わせ」が意図されていたと言われて普通はおかしくない。
梅 そう思う。否定する材料がない限り、断定していい。考えれば考えるほど、スルーできない。
私 中野=亀井会談の94年とは、年末に本社が移転した時期であり、私の本社生活の最後の1年にあたる。職場で生活し、組合で活動して分かったこともある。警察や会社側との付き合いは実に色んな形いろんな場面である。小さな職場でもガラス張りと並んで「非合法・非公然」の領域はある。桜 あえていえば、「武装闘争の党」であれ「非非の党」何であれ、国家とのシグナルの交換やホットラインは事実上あったしあっていい。「一時停戦」や「部分停戦」のために「取引」や「ボス交」はあるものだと腹をくくることも必要な気がする。双方が相手への妄想や誤解で攻撃しあったら、とんでもない事態を生むこともあるからだ。「権力」や「体制」は必ずしも一枚岩ではないし、「誤認による無益な犠牲」も少なくないからだ。ただ、「当面どこまで〈法やルール〉を守るかの暗黙の?」シグナルはできるだけ公開であることが望ましい。
(参考までに1 鉄壁防御の要塞)
梅 ただそうであればあるほど、一定の規模と時間をかけて、(少なくとも執行部(政治局))では、それがどういう事態を生み、その対策にどれほどの力を注ぎ込むかを真剣に議論しておくことが不可欠だ。それを運動全体の新たな社会認識・政治認識にまで高めていくという努力が必要なのだと思う。それなしには「取り込まれる」。力関係があまりに偏っているからこそ、「転向」「党としての転向」でしかない。多くの場合は「即転向」というべきではないとしても、だ。
90年代とは?
桜 さて、では90年代の半ばとは組織的にはどんな時代だったのだろう?
梅 91年の5月テーゼでの「転換」を経て、気持ちは大衆運動に向かっていた時期だ。現場の要請などを受けて、色んな地域や産別の闘う人々との交流を深めなおしていた時。地域や産別の「絵地図」を描き、その中に中核派の存在が多少は入ってくる。そんな時にゲリラが起き、「軍報(実行声明)」がでると「まだこんなことをやってるのかよ」と思った。「中核派は変わっていないんだね」と言われて、色んな努力が無に帰すという思いが強かった。まして「対革マル」のせん滅戦などあると、もう最悪だった。「何を考えてるんだ」と怒鳴り込みたい思いがあった。「左派」を自称する人たちが今でも胸を張ろうとしていることには違和感が強い。
海 90年天皇決戦にはもう「党のガラス張り化」はどんどん進んでいて、労働者は自宅に住み、会議もそこで開かれた。94年の前進社の新社屋移転は色んな転換を一気に進めた時でもある。本社への出入りが最寄のバス停からの徒歩で良くなり、タクシー代が浮いた。本社からの帰りも同じで、車に乗って延々走ってわけの分からないところに放り出されることもなくなった。時には張り込み中の公安に逝く手を阻まれることもあったけれど、気にしない。時間的にも金銭的にも「もうだめ」「転換」という実感から生まれた変化だったと思う。
竹 地区常任の活動費も行き詰まってきた。地方では「遅配・減配」が相次いでいた。「県委員」でない「専従」の「活動費」が「無給」になり、やがて90年代後半には「常任」も減俸から(県からは)無給になった。人によっては自分が握る地区財政から自分の金をひねり出してもいたようだし、地区によっては労働者からの新しい「基金」で糊口をしのいだ場合もある。
桜 本社メンバーも結婚して近くに住んで自転車で通うことも生まれた。もちろん本社からバイトに出たりもする。人によって色んなバイトに関わり出した。これも「天田改革」だね。(この項つづく)
………………………………………………………………………………………
◆⑦ 閑話2
(承前)
「浮上」が対権力で意味したもの
私 地下から大量に浮上してきた結果、何が生まれたのかな?
梅 もう地下を支えられないという実情から始まったことは事実だと思う。あわせて、「かつては優秀な活動家」だった人々がフル回転すれば、大衆的展開も新しい可能性が開かれる。そういう期待があったのも事実だと思う。ただ、一部を除いて、表の惨状に触れた浮上組の「浦島太郎」感覚も大きくて、結果としては…。荒木氏は酒によって転落し…。そう、出獄組の荒川氏の活躍も大きかったとは思うけれど。
桜 集会・デモの「合法化」も一段進んだ。反戦共同行動委や労組交流センター主催のデモは、それ以前のでも警備と比べるとずいぶんとゆるいものになった。都心や市街地でのデモも増えたからとはいえないレベルだったと思う。
梅 だいぶ後にはなるけれど、現役の「全学連委員長」が訪米のビザを受けられたと聞いて驚いた。アメリカの「テロ指定団体」には入れなかったんだなと。公安の判断がどんなものだったのか、よくは分からないが。
松 うん。結局は浮上組が本社や公然事務所にたむろして、権力に対しては「いつでも誰でもパクれる」という状態。結果的にはほとんどパクは出なかったけれど、「わき腹をさらけ出して、権力側のさじ加減次第」の時期だ。
つまり「権力側のシグナル」に神経を集中させて、次の一手を決める。とはいえもはや「浮上路線」「軍の解体路線」は戻せない。仮に一斉逮捕が出ても、大きくは変えられない。
たがいに「シグナル」を出し合い、読みあっていた時期だということか?!
梅 今から見れば、権力側も中核派の方向性をつかむのに躍起だったのだろう。「パクらない」ことで「右」に誘導することには、内部でも一枚岩ではなかったのでは?
桜 テロもゲリラもぎりぎり2003年まで続いた。しかも時にはかなりの巨弾もあった。8月の千葉県警幹部宅への爆発物を伴う放火が最後だと思う(誤爆)。政治局内での中野さんと「左派」の議論は、わずかだけれど、「多数派」が「継戦」にこだわっていたことは良く分かる。「ゲリラの巨弾で中野路線を吹き飛ばしたい」か?
清水さんのマヌーバー。とはいえ、地方や現場のメンバーにとっても反応は主々雑多。どこに向かうのかは不鮮明という頃でもある。
竹 時代的には総評・社会党の解体が「メイン」だった。中核派の存在は残念ながら、2次的問題として、別の要因から考えるべき問題も多そうだ。主客を代えて考え直したいと思う。
梅 角度は違うけれど、「軍の解体=社会復帰」は、やはり「党の浮沈のかかった」最大の課題だったという面を見逃して欲しくない。「凶状持ち」の内心・内省と「時効」の問題は、組織にとってどんな犠牲を払っても全力で解決すべき課題で、「路線」や権力闘争に還元してはならない。
いくつか付け足し
松 公安の地盤も低落した。後になってからだけれど、警察庁・警視庁のツートップを「交通畑出身」に奪われる事態が続いている。警察も「生まれ変わる」過程にありそうな。とはいえ、どこがどうなるのかは、あれたちには分からない。「変わらない」ことも多いわけだし。「中核派唯一論」からは見えないことも多そうだ。
梅 公安との対決では、15年現在では71年渋谷暴動がらみなどで時効が廃止されたままだ。全体と個別それぞれの領域がありそうで、一口でまとめることはできない。ただ、「非公然」の清水さんには累は及ばない、少なくともおおいにゆとりがあることは、確かだろう。
竹 当時からも、天田氏らの「3人組」は最低だったと思う。官僚的・恫喝政治。会話ができない。「3・14Ⅱ」の経過やその後の経緯を聞いても、すんなり理解できることが多い。ま、坂木は比較的対応がうまかったけれど、「官僚的自己保身」にたけた奴、「官僚的な優秀さ」というべきところかな?
桜 かなり荒削りだけれど、今後に託そう。
………………………………………………………………………………………
(つづく)












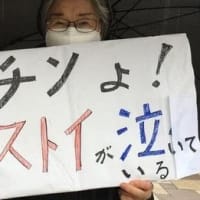






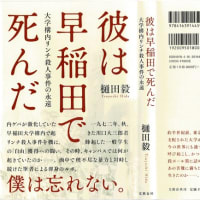
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます