資料:革共同26全総 議案(前半)

【管理者のコメント】
革共同中央派の第26回全国委員会の報告文および議案を前半と後半の二つに分けて転載します(『共産主義者』202号、2019年11月1日刊)。
議案の方は、26全総当日に配布された議案に加除修正をほどこしています。総会での討議やその後の検討を経たものなので、「議案」というより「決定」というべきものでしょう。
26全総を開かざるをえなかった‘政治局崩壊’という事態についての事実関係の記述がほとんど何も公開されていません。「組織防衛上の配慮」を一定認めるとしても、ほとんどまったく触れていないのは、党員および労働者人民にたいしてあまりに不誠実、官僚主義の極みであり、ほんとうのところ何も自己批判していないものといわざるをえません。この点で、当日配布の議案には、次の文章があったとのことです。いわく。「……とりわけても同盟本部(前進社本社)にあった政治局の指導的同志の責任についてあいまいにすることはできません。しかしわれわれは、倫理的弾劾と自己批判に終始するわけにはいかない。」と。「倫理的弾劾と自己批判」はやらないというのですから、それは開き直りの常套文句です。そこに26全総の本音があるといっていいでしょう。
自らが陥ったおぞましくも腐敗した現実に向き合い、切開することなしに、何の総括にもなりません。
………………………………………………………………………………………………………
革共同第26回全国委員会総会を開催
革命的共産主義者同盟政治局
2019年9月、革共同は第26回全国委員会総会を開催しました。今総会は、改憲阻止決戦への本格的突入を前に、2015年1月に開催した第7回大会以来の闘いを全面的に総括し、革命に勝利する新たな党の路線的再確立、中央指導体制の再確立をめざしてかちとられました。
それは、このかんの政治局による国鉄闘争と階級的労働運動、改憲阻止闘争における指導の誤りを明確に認め、その指導の破産から生みだされた中央における党規律の解体、女性解放闘争への敵対を含む重大な組織問題の自己批判的総括の基本的方向性を示していくことと一体でした。
①現場労働働者の苦闘から遊離した空論主義的な指導の誤りを総括
26全総の提起と討論は、第一に、第7回大会報告(第2報告、特別報告2)の全面的再検討と批判をおこない、それが新自由主義攻撃との闘いの最先端をなす国鉄闘争を基軸とする階級的労働運動、現実の労働者階級・労働者党員の実践的苦闘・格闘から遊離した空論主義に陥(おちい)っていたことを明確に突き出しました。
7回大会を前後する過程において、党が直面していた最大の課題は、2010年4・9政治和解による国鉄闘争解体とJR全面外注化攻撃の激化にたいしていかに立ち向かうか、ということでした。すでに動労千葉や国労郡山(こおりやま)工場支部などにおいて現場から外注化阻止闘争をつくりだす闘いが必死に取り組まれていました。党にはこの闘いと一体となって、職場から新自由主義を打ち破る国鉄決戦勝利の路線を打ち立て、全力で闘うことが求められていたのです。しかし、7回大会を主導した政治局指導部は、この動労千葉や国労郡山工場支部の職場における実践的格闘には向き合わず、「党と労働組合の一体的建設」論をもって「革共同の労働運動だけが新自由主義と闘える」とし、「党の労働組合(実際には「党の言うことを聞く組合」)としての動労総連合」建設という方針を打ち出したのです。それは、動労千葉や国労郡山工場支部などにおける職場からの外注化阻止闘争の組織化を否定する形で「党づくり」を一面的に強調し、現実の運動を阻害し、妨害することになったのです。
職場での資本との現実的攻防、階級闘争実践から身を避けた党は、資本・権力と闘えない党となり、政治闘争、さらに理論闘争においても後退と歪みを生みだすことになりました。そして、その現実をますますマルクス主義から逸脱・背反した観念的空論・空語でごまかしていくことになったのです。その結果は、①資本・権力と闘うことによってのみ生まれる「共産主義者としての自覚」、②階級闘争の実践によって養われる「大衆と結びつく政治能力」、③大衆によって検証される「正しい理論」、レーニンがあげた党規律を保障するこの3つの条件の喪失でした。第26回総会は、中央指導部から起きたこの現実を徹底的に暴き出し、その根拠をえぐり出しました。
②動労千葉に学び、ともに闘って労働者階級の勝利切り開く党へ
もちろん7回大会以降の5年近くの闘いが、すべて誤りだったとか、歪んでいたということではありません。政治局の指導上の誤りと歪みにもかかわらず、党の革命(2006~8年)と階級的労働運動路線の確立をへた全党の同志の奮闘によって、国鉄決戦、階級的労働運動と改憲阻止闘争において、全国・全戦線において大きな前進をかちとってきたことは明白です。とりわけ2010年3月の中野顧問の逝去(せいきょ)、直後の4.9政治和解という試練をのりこえて国鉄闘争全国運動を開始し(2015年には最高裁で国家的不当労働行為を確定させた)、反合・運転保安闘争路線をもって職場から外注化阻止闘争を組織してきた動労千葉が、改憲阻止闘争や国際連帯闘争においても先頭に立ちつづけ、階級的労働運動再生の展望を切り開いてきたことをしっかりと確認する必要があります。政治局・党中央指導部には、この動労千葉とともに闘い、この闘いを党として全力で支え、全階級の闘いとして発展させていくことが求められていたのです。
ところが政治局は、この動労千葉の実践にたいして空論的な方針を対置し、闘いを阻害し、国鉄闘争と階級的労働運動の桎梏(しっこく)になってしまったのです。このことについて厳しく自己批判と総括をおこないました。この重大な指導の誤り、マルクス主義の逸脱・解体が、なぜわが党の中央から起きたのか、その現実的根拠をマルクス主義的に解明し、その総括から今の時代に通用する党に変わるために、何を変える必要があったのか、あるのかを引き出すための提起と妥協のない徹底的に主体的な総括をかけた討論がおこなわれました。これが26全総の最大の中身をなすものでした。
第二に、革共同の原点、マルクス主義、レーニン主義党組織論などをあらためてとらえ返し、党の生まれ変わりの出発点とすることを確認しました。あらためて党とは何か、労働組合とは何かを明確にし、労働者階級の究極的解放、プロレタリア革命の勝利に向かっていくために、党と労働組合の関係は、いかなるものであるべきかについての、マルクス主義・レーニン主義、そして革共同の出発点である1962年3全総における原点的提起にも立ち返って、綱領的一致をつくりだす討議が開始されました。
③マルクス主義の原点に立ち返り全党の革命的団結への出発点築く
第三に、戦後労働運動史上空前の関生(かんなま)(全日建運輸連帯労組関西地区生コン支部)弾圧とJR攻防を最大の焦点とする「労組なき社会」づくりを核心とする、日帝・安倍政権の改憲・戦争攻撃を規定している今の時代についての認識をあらためて再確立し、改憲・戦争阻止決戦を巨大な政治決戦・階級決戦として、革命の勝利をかけて闘いとらなければならないことを確認しました。
第四に、この改憲・戦争阻止決戦の成否をかけた11月労働者集会の大成功に向かって、関生弾圧粉砕、国鉄決戦勝利、改憲・戦争阻止!大行進運動の発展、排外主義粉砕・日韓国際連帯の闘いに向かって、党の再団結と総決起体制をつくり出しました。 そして最後に、7回大会以後の政治局全員の辞任を受けて、8回大会での正規の全国委員と政治局の選出がなされるまでの暫定体制として、清水丈夫議長(再任)-秋月丈志(たけし)書記長を軸とする新たな政治局を選出しました。
26全総において、全党の基本組織から選出された、労働者党員を過半とする○○人の全国委員は、19年秋から20年の国鉄決戦・改憲阻止決戦に向かっての党の再生・再団結を、革共同に命と人生を賭けてきたみずからの誇りと全党員・労働者階級にたいする責任をもって、かちとりました。すでに、9・22水戸集会・デモ、関生弾圧粉砕の闘いとJR攻防に勝ちぬきながら、11・3労働者集会・改憲・戦争阻止!大行進への進撃が開始されています。
どこまでも労働者階級の党であろうとする革共同、星野文昭(ふみあき)同志をはじめ幾多の同志が命を賭けて守りぬき、つくりあげてきた革共同は、この時代に求められる自己変革を必ず成し遂げ、反帝国主義・反スターリン主義プロレタリア世界革命の勝利まで闘いぬきます。
………………………………………………………………………………………………………
【革共同第26回全国委員会総会 議案】
党の根底的変革かちとり改憲阻止・日帝打倒へ
7回大会路線の誤りを徹底総括し、党指導体制の再確立を
26全総実行委員会・議案起草委員会
本来、全国委員会総会では政治局からの報告がおこなわれ、その報告にもとづいて討論と諸決定がおこなわれるが、26全総を前に全政治局員が辞任を表明した。そのため、革共同中央労働者組織委員会の責任での全総実行委員会と総会議案起草委員会を設置し、政治局報告に代わって26全総議案が作成された。本議案の提起は、起草委員会の秋月丈志同志がおこない、2日間の討議をへて賛成多数で採択された。公表にあたり、組織防衛上必要な最小限の修正をおこなった。
【1】重大な組織問題を生みだした政治局の政治的・理論的・組織的破産はどこから生まれたのか ―7回大会総括を中心に
(1)7回大会以来の政治局の重大な誤り
7回大会を前後する過程からこの数年間に起きた、あるいは明らかになった政治局の組織問題、指導上の重大な誤りは、以下のようなものです。
①政治局の中枢的指導部がかかわった重大な女性差別事件とその開きなおり、隠蔽(いんぺい)を許した党中央における思想的腐敗。
②国鉄闘争指導における重大な誤謬(ごびゅう)。2000年以来の動労千葉の、職場から外注化阻止闘争を組織する必死の格闘に学ばず、それに敵対する形で7回大会「第2報告」「特別報告2」において「動労総連合を全国へ」を「革共同の労働組合」をつくることにねじ曲げたこと。そして階級的労働運動路線を「党づくり」の一面的強調にすり替え、事実上放棄し、破壊したこと。動労千葉・動労総連合にたいしてこの誤った党の方針を押しつけるあり方をとったこと。
③階級闘争史観を否定した2017年2月大原武史論文とその機関紙掲載強行にまで行き着いたマルクス主義からの逸脱、党中央・政治局から起きたマルクス主義の解体。大原の「労働の奪還」論を「マルクス主義の新地平」と持ち上げ、綱領草案、党のマルクス主義、理論闘争を歪(ゆが)めたこと。
17年2月大原論文は、「国鉄闘争論文」であり、国鉄闘争指導でもマルクス主義においても大原が完全に破綻(はたん)した証(あかし)であった。政治局中枢はその深刻さをとらえることができず、大原論文の機関紙掲載を編集局の同志の反対を押し切って強要し、批判も討議もまともにおこなわないままに容認し、称揚までした。政治局が理論闘争、イデオロギー闘争を放棄し、党に深刻な矛盾と混乱を生み、打撃を与えた。
④階級闘争の現実の困難性から身をそらしたことで、政治局の組織指導と党建設指導は実践的立場を失い、空論主義的な党建設論となった。労働運動、政治闘争・選挙闘争、あらゆる闘いを党の狭い枠でしか組織しえず、その破産の総括・検証を拒み、抑圧的・官僚的に正当化し、種々の腐敗を容認するまでに陥った。
⑤労働者指導部建設の敗北と労働者指導部と常任との分断。常任建設の意識性の欠如。さらに女性解放組織委員会建設における指導の後退など、政治局の組織指導は種々の破産を生みだしている。
⑥非合法・非公然体制をめぐる国家権力との闘いの重圧に屈した全国委員会総会・大会開催の「ネグレクト」と党員・階級からの検証を受けない政治局人事・指導体制は、全国委員会を実質解体して〈中央委―細胞〉を破壊した。
(2)国鉄決戦指導の敗北が誤りの核心
一個一個が、深刻な組織問題です。この一連の組織問題、国鉄闘争と階級的労働運動における指導、政治的指導の全面破産がいくつも重なって、とくに2015年年頭の7回大会を前後して重大な問題が集中的に起きました。
なぜこうしたことが起きたのか。結論的に言えば、政治局の国鉄決戦指導の敗北がその核心にあります。政治局が、新自由主義と戦後世界体制の崩壊と革命の時代の本格的開始にたいして、とくに2010年4・9政治和解による国鉄闘争解体の激しさから身をそらし、その試練に立ち向かう動労千葉を先頭とする国鉄労働者、労働者階級と結びついて階級闘争に責任をとる立場を見失い、その政治的・組織的指導能力を形成することができなくなっていたのです。階級闘争・政治闘争の激しさにおいて求められていた具体的実践組織指導を放棄し、空論的な党の論理を振り回し、総括・検証を拒否して責任を現場に押しつけるようなあり方が続いてきました。その破産をさらなる観念的・空論的言辞と強権的・官僚的指導で覆い隠し、結果として党規律を崩壊させ、とんでもない思想的腐敗まで生みだしていったのです。
(3)「党の革命」以後、何が求められていたのか
革共同は、「党の革命」(06~08年)によって、5月テーゼ反対派・血債主義派を最後的に打倒・一掃し、労働者階級の党、マルクス主義の党、動労千葉とともに闘う階級的労働運動路線の党への転換・飛躍を開始しました。09年には『綱領草案』を採択し、プロレタリア革命勝利に向かっての党の基本的綱領を確立したのです。
しかし問題はこれからでした。革共同は、ここから重大な歴史的試練に次つぎと直面し、そのなかで綱領草案、マルクス主義、階級的労働運動路線を実践的に貫徹していくことが求められたのです。
まず07~08年のパリバ・リーマンショックで大恐慌の爆発が現実化し、帝国主義戦後体制の崩壊的危機の中で、米帝を先頭に新自由主義的延命の攻撃が、労働者階級にたいする階級戦争のエスカレーションと社会崩壊が一挙に進行しました(全面外注化・総非正規化・貧困・地域破壊など)。
帝国主義体制における「最弱の環」=日帝において、戦後自民党支配が崩壊するなかで、民主党政権が自民党以上に規制緩和、社会保障破壊、民営化・外注化、総非正規職化の雇用破壊攻撃を激化させました。その核心に、国鉄労働運動解体、国労つぶし、動労千葉・動労総連合壊滅をすえて国鉄1047名解雇撤回闘争を解体する2010年4・9政治和解に踏み込んできたのです。それは、2000年以来のJR全面外注化攻撃による労働組合つぶしと完全に一体でした。
国鉄1047名解雇撤回闘争を守りぬき、戦後労働運動の要(かなめ)をなす国鉄労働運動を、解雇撤回を貫き外注化・非正規職化と職場生産点で対決する労働運動として発展させることが求められました。このとき動労千葉は、「国鉄闘争の火を消すな」の呼びかけを発し、関生支部・港合同との3労組陣形を中心に国鉄闘争全国運動を立ち上げ、ギリギリのところからの反撃を開始したのです。
そこに2011年3・11東日本大震災と福島原発事故という未曽有(みぞう)の事態が襲いかかり、フクシマを引き起こした新自由主義資本と国家への怒りが爆発し、反原発の巨大な大衆的決起が始まりました。しかし、4・9政治和解を推し進めた日本共産党スターリン主義や社民、そして連合は「国難下での階級休戦」「復興」攻撃に全面的に加担し、被曝(ひばく)を強いられた福島の子どもたちの命を守ろうとする大衆的運動に分断を持ち込み、破壊しようとしました。
そして労働者人民が民主党・連合への怒りと失望を高めるなかで、日本会議的な極右国家主義勢力と結託した第2次安倍政権が登場しました(12年12月)。第2次安倍政権は、3・11にまでいたった日本帝国主義の没落と「存亡の危機」への反革命的危機感・絶望的恐怖に駆り立てられ、国家主義イデオロギーを全面に掲げ、改憲による戦後体制転覆をめざした政権であり、旧来の自民党政権とは明らかに質を異(こと)にするものでした。
安倍政権は、2014年7・1閣議決定で集団的自衛権行使を合憲とし、翌5年7月の安保戦争法の強行成立を改憲への突破口と位置づけてきました。これにたいして、日本労働者階級の広範な戦争絶対反対の怒りが再び3・1直後の巨大な国会デモとなって爆発しました。しかし、ここでも日共スターリン主義を先頭に全体制内指導部が、国家権力になりかわって数万のデモを規制線内に封じ込め、安倍打倒の巨万の大衆的闘いを抑圧する側に回ったのです。
以上のような党の革命、綱領草案採択から2015年にいたる5~6年の過程を振り返ってみるならば、それは新自由主義の大崩壊の開始と国鉄闘争、労働運動解体の大攻撃が押し寄せ、改憲・戦争へと戦後史を画する攻撃が始まった過程だったと言えます。一方で、3.11で「新自由主義の犯罪」を実感し、既成政党の裏切り、屈服を目(ま)の当たりにした膨大な労働者大衆の社会の変革を求める根源的な決起・大流動が始まり、改憲と戦争をめぐる戦後史上最大の階級決戦・政治決戦がいよいよ待ったなしとなったということは明らかです。
(4)歴史的要請とは真逆な7回大会路線
革共同には、この日本帝国主義の未曽有の危機と改憲・戦争攻撃、そこに向かっての国鉄闘争破壊、労働運動壊滅の攻撃に立ち向かう路線と方針が求められていました。綱領草案と「50年史」発刊という党創成以来の総括をもふまえ、70年決戦を準備した1966年3回大会に比すような、いやそれをはるかに超えるような歴史的大会を開催し、国鉄決戦勝利・改憲阻止をかけた戦後最大の階級決戦に打って出る準備と決断を迫られていたのです。
だが、7回大会とそこで出された報告と方針、その後の政治局における指導は、この歴史的要請に真正面から応えるものになっていないどころか、綱領草案とは真逆の方向へ、現実の階級闘争から逃避・遊離したところに陥ってしまいました。
日帝の危機にかられた労働組合つぶし、階級的なものを解体・一掃する攻撃の激しさとそれが生みだした困難、孤立的状況のなかにあっても、労働者と現場の闘いを信頼してマルクス主義を貫き、職場生産点の困難に立ち向かうなかで理論闘争・政治闘争・経済闘争を組織するという革命党の本来の役割を見失い、階級を本格的に組織することへの日和見主義に陥ってしまっていたのです。
(5)7回大会第2報告「革共同の労働組合」論は「階級的労働運動路線への敵対・破壊
このような政治局指導の誤りが顕著に表れたのが7回大会第2報告、および特別報告2です。7回大会は、第1報告で「大恐慌が戦争に発展し革命情勢が全世界で到来」という時代認識を示した上で、第2報告と特別報告2で「7回大会最大の確認、実践方針」「2010年代中期階級決戦の核心課題」として「動労総連合を全国に」の方針を打ち出しました。
① 第2報告は、以下のように提起しています。
「ようやく党が動労千葉の闘いに肉迫できるようになった時に明らかになったことは、動労千葉にとっても党建設が死活的課題となっていたということである。強行される外注化によるすさまじい団結破壊にたいして、たとえ動労千葉といえども、労働組合だけの力ではとうてい太刀打ちできるものではなかった。労働組合の枠を越えた革命党の分厚い建設と一体化しなかったら、JRのすさまじい分断攻撃に勝利することはできない」(7回大会第2報告)
政治局は動労千葉の外注化との闘いに、「ようやく......肉迫できるようになった」と言いますが、その中身は「動労千葉にとっても党建設が死活的課題」ということでした。なぜなら外注化には、「動労千葉といえども、労働組合だけの力ではとうてい太刀打ちできるものではなかった」からとしています。結論は「労働組合の枠を越えた革命党の分厚い建設」です。
しかし、外注化攻撃との闘う路線・具体的方針もまったく提起されず、外注化との闘いの困難に立ち向かう中でいかに党細胞を建設するかも一切語られません。
そして、「『動労総連合を全国に』の大方針こそ、このかんの階級的労働運動路線の実践をとおしてかちとった最大の獲得地平であり実践方針である。それは国鉄職場において革共同の階級的労働運動路線を徹底的に実践するということであり、そうした労組拠点を全国につくり出すという方針である。それは国労か動労かという次元をこえて、JRの外注化や被曝の強制と徹底非和解で闘い抜き、革共同の労働運動をつくり出すということだ」(同)と、「『動労総連合を全国に』の大方針」は「革共同の労働運動をつくり出す」ことだとさかんに強調されます。
特別報告2では、「革共同の労働組合、動労総連合を全国に1000人規模でうち立てることが唯一の回答なんだ。これは党の蜂起です」と、動労総連合が「革共同の労働組合」とまで断言されています。
②ここで事実としてはっきりさせられなければならないことは、実際には政治局の中枢的指導部は、動労千葉の外注化阻止闘争に「肉迫」するどころか、職場での外注化との具体的攻防を軽視し、政治局会議での討論すらまともにおこなっていなかったということです。政治局は動労千葉の外注化阻止闘争に必死に食らいつき、ともに闘い、ともに学ぶという立場にまったく立っていなかった。本当に恥ずべき姿ですが、それが事実です。
1999年の「再雇用機会提供制度」(シニア制度)の提案、2000年の「ニューフロンティア21」は、全面的な外注化・非正規職化を貫徹する第2の国鉄分割・民営化攻撃でした。シニア制度では外注化=非正規職化を推進する協定を拒否する動労千葉の組合員は再雇用が拒否されます。動労千葉はシニア制度を粉砕するまでの5年間で、33人の組合員が再雇用を拒否されましたが、その困難を避けずに動労千葉は外注化阻止闘争を闘いぬきました。そして、民営化・外注化・非正規職化こそ新自由主義攻撃の中心であり、労働組合の団結した闘いのみがそれに勝利することができる、いかに困難に見えようとも団結して闘い、組織拡大を実現していくことで外注化攻撃に勝てることをつかんだのでした。
シニア制度廃止後も動労千葉組合員は再雇用に際しては、外注化攻撃の対象である検修・構内業務ではなく、あえて体力的には大変な清掃業務を選択してきました。2012年の職場丸ごと強制出向という攻撃は、激しい職場攻防のうえで強制されました。しかし、CTS(千葉鉄道サービス)幕張の職場代表選挙の勝利と職場の組織化に示されるような外注化阻止・非正規職撤廃の闘いと、CTSで働く仲間の動労千葉への組織化を実現しています。
7回大会は2015年年頭です。2000年からの動労千葉の外注化阻止闘争から、政治局の中枢的指導部は何を学んだのか、党としていかなる闘いを指導し、組織したのかを第2報告では一言たりとも語ってはいません。語ることができないのです。
「たとえ動労千葉といえども、労働組合だけの力ではとうてい太刀打ちできるものではなかった。」と言うなら、政治局中枢はそれにたいしてどのように闘ったのか。「革共同の労働運動」「革共同の労働組合」が外注化攻撃といかに闘うかがまったくありません。逆に、動労千葉の困難に立ち向かう闘いに対立するものとして「動労総連合を全国に」が「革共同の労働組合」をつくることとして提起されているのです。
③政治局の中枢的指導部は、「動労総連合を全国へ」という本来は階級的労働運動路線の要であり土台をなす国鉄決戦の組織政策を、「革共同の労働組合をつくる」として推進することで、階級的労働運動路線とは違うものに歪めました。重大な組織破壊です。
「動労総連合を全国に」「革共同の労働組合として」「1000人つくる」という方針は、動労千葉と動労総連合の主体を無視して押し付けられました。そして実際に、動労千葉と動労総連合に深刻な矛盾と不信を生みだしました。党は動労千葉破壊に手を染めたと言っても過言ではなく、動労千葉自身の階級性において救われたのです。
しかるに第2報告では、「たとえ動労千葉といえども、労働組合だけの力ではとうてい太刀打ちできるものではなかった」という党建設の一面的な強調が、組合の上に立つような傲慢(ごうまん)さでおこなわれました。そして、外注化阻止・非正規職撤廃の新自由主義と闘う労働運動を職場から必死につくりだしている動労千葉・動労千葉細胞にたいして、まず党づくりを優先すべき、ということを「大会決定」にまでしたのです。さらに許しがたいことには、動労千葉と対照的に動労水戸が「革共同の時代認識と路線が貫かれた労働組合」「革共同の労働運動の模範であり、手本」(第2報告)として押し出され、動労千葉と動労水戸との分断を組織するようなことまでなされました。
いかにして正規・非正規の分断をのりこえ、外注化を阻止する反合理化闘争、具体的運動をつくりだしていくのか、困難な現場で必死に格闘している動労千葉、JR職場に政治局自身が身を投じて、ともに闘うなかで路線・方針をつくっていくという実践的な努力はなされずに、「党さえつくればいい」と安易な方へ流れたのです。
④この第2報告の立場、「革共同の労働組合」をつくるとは、3全総以来の革共同の地平、とりわけ「党の革命」を実現した階級的労働運動路線とは無縁の思想・路線であり、階級的労働運動路線を破壊するものでした。
「この党建設は、資本との絶対非和解を貫く労働者階級の階級的団結の形成を一切の軸にすえて闘う中でこそかちとられる。現代においては、何よりも、闘う労働組合をよみがえらせることと一体で形成・確立されるものである」「労働者階級は党をつくりだすことで、自らを一個の政治勢力として登場させる」と、綱領草案(第7項)で提起されています。この立場からの逸脱・離反があったことを痛苦な自己批判としてはっきり認めなくてはなりません。
それは「党の革命」の地平をも失わせることです。
6回大会第1報告「Ⅱ党建設の基本的諸問題」で以下のように提起しています。
「いまひとつは、革命的情勢の急速な接近、戦争と大失業時代の到来の中で、われわれは今こそ5月テーゼの『労働者の中へ』の本格的・全面的展開をかちとっていくことである。ここでは、このかんのたたかいの成果をふまえて、〈労働組合の労働組合としての防衛と再生〉ということが、まさにわが革共同の肩にかかってきていることを自覚しよう。この〈労働組合の防衛と再生〉というテーマを、革共同の最大の運動方針として確認しよう。労働運動への取り組みを徹底的に強め、そこに革共同の生命をかけるということである」(報告集・上119ページ)
〈労働組合の防衛と再生〉に革共同の命をかける、動労千葉とともに国鉄決戦に責任をとり、階級的労働運動を守り発展させる、これこそが関西の労働者同志を先頭にした「党の革命」を準備し、貫いた思想と路線です。
さらに革共同の結党の精神・原点からとらえ返す必要があります。
「社会民主主義とスターリン主義から決別した革命家の組織が不可欠の前提条件となることはいうまでもないことである。まさにこのような革命家の組織(党・同盟)の活動のみが現実的な労働者階級の『イデオロギー的危機』を克服するための唯一の根拠をなすのである。だがだからこそ革命的共産主義者は、党と階級と大衆の再結合の方向にむかって、社会民主主義やスターリン主義の支配する労働組合(運動)の内部で根気づよく活動の場を拡大し、既成の指導部に反逆するいっさいの戦闘的潮流と結合、その最良の部分をわが戦列に獲得するために闘争=組織戦術に習熟し、実際的活動にうつすことが絶対に必要なのである」「わが同盟が一般的=抽象的に党と階級と大衆の弁証法を確認するのみならず、こんにちにおいて、その組織活動を通して階級情況とふかく結合すること、行動の能力、活動の方法と内容をたかめることに失敗するならば、わが同盟と日本革命的共産主義運動は、労働者階級の本体から孤立したセクト的集団に転落してしまうであろう」(『三全総と革命的共産主義運動の現段階』本多著作選第1巻253ページ)
7回大会第2報告での「革共同の労働組合」論はまさに、革共同を「労働者階級の本体から孤立したセクト的集団に転落」させ、階級的労働運動路線を破壊する重大な誤りであったことは明白です。
⑤なぜこのような政治局指導の誤りが生みだされたのかを総括したうえで、何を変える必要があるのか。一つには、国鉄1047名解雇撤回闘争解体の4.9政治和解にたいして立ち上げた国鉄闘争全国運動を発展させ、それと一体で外注化阻止・非正規職撤廃の闘いを動労千葉とともに職場からつくりだすことです。新自由主義の攻撃の激しさ、職場の困難な現実にこそ、実は敵の支配の危機があり、絶対に労働者が勝利する道筋を見いだすことができるのだ、ということを、現場に身を置いて、現場の労働者とともに格闘していくことなしに、党の指導路線や方針がつくれるはずはありません。
実際に東労組崩壊情勢が示すように、東労組カクマルとの結託体制ですら桎梏(しっこく)となるほど、JR資本と日帝は支配の危機に陥っていたのです。この危機を生みだしたのは動労千葉の存在と闘いを軸とする、JRで働く仲間の怒りと闘いです。
二つには、外注化阻止・非正規職撤廃の職場闘争が新自由主義攻撃を打ち砕き、階級的団結を生みだすこと、反合理化闘争、反合・運転保安闘争の意義をとらえ、それを全産別における路線にすえることです。国鉄分割・民営化攻撃から日本の新自由主義攻撃が始まり、全社会的に襲いかかり、現下では「労働組合のない社会」の攻撃との攻防です。動労千葉の外注化阻止・非正規職撤廃の反合闘争に学び、ともに闘う労働運動をJR職場―全国の職場に広げて組織していくことです。
三つには、理論闘争・政治闘争・経済闘争という階級闘争の3つの闘争形態を正しく復権し、プロレタリア独裁樹立への党の意識性を堅持して闘うということです。
「経済闘争というのは、一言でいうと、労働者階級の完全な解放をめざして、労働者の直接的な諸利益の擁護、改善のためにたたかうということ」(『前衛党組織論序説』本多著作選第7巻)です。日帝の危機の深まりとともに生活と権利を守るための必死の反撃が広範に始まっています。労働者階級の完全な解放を目指す立場から経済闘争を、動労千葉に学び、創意的につくりだしていくことこそが求められています。
四つには、〈中央委―細胞〉の生きいきとした関係をつくりだすことです。7回大会第2報告の「動労総連合を全国に」の方針を動労千葉細胞との討議もおこなわずに提起すること自身が、〈中央委―細胞〉の破壊です。革共同を「その階級意識を最も鋭く体現する最高の団結形態であり、最も鍛え抜かれた階級の前衛」(綱領草案)として建設する力は、地区党建設を土台とした細胞建設です。政治局こそが地区党建設、細胞建設に責任を取らなくてはなりません。
⑥「党と労働組合の一体的建設」論が、労働組合(運動)における具体的実践・組織活動と切断された「左翼」空論主義的な党組織論、日和見主義を合理化する論として使われました。それは7回大会で「党の労働組合」「党の言うことを聞く労働組合」となってしまったのです。
労働者階級自己解放にとって党の必要性と労働組合の意義のそれぞれをあらためて鮮明にさせなければなりません。「労働者階級(プロレタリアート)の解放は、労働者自身の事業である」(綱領草案)がマルクス主義の核心です。「この目的を実現するために、プロレタリアートは、自らを独自の政党(革命的労働者党)に組織して闘うことを必要とする」。
「労働組合は、労働者が団結して資本と闘う武器であり、労働者階級の最も基礎的な団結形態である」「この労働者階級による職場生産点の支配とその全社会的な拡大こそ、ブルジョア国家権力の打倒=プロレタリア革命の勝利を保障する決定的条件である」(同)。
さらに『なにをなすべきか?』『共産主義における左翼空論主義』などレーニン主義党組織論に学び、実践し、深めていくことが必要です。党とは何か、労働組合とは何か、その関係はいかにあるべきかということについて、きわめてあいまいで、ばらばらな「解釈」を生んだ「党と労働組合の一体的建設」論自身にはらまれていた問題も検証しなければなりません。
(6)権力をめざす本来の政治闘争からの後退
「国際連帯共同行動研究所」「許すな改憲!大行動」に典型的に表れたことは、「一言で言って権力をめざす闘争」(『前衛党組織論序説』)であるべき政治闘争からの後退です。いかなる局面であれ、政治闘争にはブルジョアジーの独裁をプロレタリアートの独裁に置き換える意識性、権力をめざす意識性が貫かれなくてはなりません。
国鉄決戦という帝国主義、資本との最前線の攻防から身を引いて、労働者階級を帝国主義打倒・プロレタリア革命に組織する政治闘争が指導・組織できるはずはありません。国政への挑戦という巨大な政治決戦を闘いぬきながら、革共同への労働者階級の検証にたいする総括をおこなわず、現場と地区党に責任と矛盾を押しつけてきました。
(7)マルクス主義の解体と党規律の崩壊、解党主義
7回大会以後、大原は、国鉄闘争の具体的中身についてふれることがますます少なくなっていきます。政治局指導部が、大原を持ち上げることを「指導」であるかのように押しつけるなかで、「労働の奪還論」「共同性」「強烈な人格・リーダー」「屹立(きつりつ)」「愛と誠実」「心の分かち合い」といった実践から遊離した言葉がどんどん一人歩きしていくのです。
大原が実践の中から具体的方針を提起できなくなるなかでの「強烈な人格・指導部像」の自己演出、自己矛盾から内的規律の崩壊へ向かったのは必然でしたし、それは大原を持ち上げることをもって、国鉄決戦と階級的労働運動にたいする指導ならざる指導に置き換えていた政治局指導部の破綻と崩壊そのものだったのです。
大原の「労働の奪還」論を絶対化し「マルクス主義の新地平」とまで押し上げた政治局の決定的誤りについて、明確にしておく必要があります。労働者が労働力商品としてあつかわれ、賃金奴隷制の鎖につながれていても、生産の主人公は実は自分たち労働者であり、社会を実際に支えているのだという、階級的存在からにじみ出る意識を労働者は持つし、そのような意識を階級的労働運動・革命的共産主義運動の側から積極的に呼び起こし、資本の理不尽な労働条件の切り下げ、合理化・非正規化・賃下げなどにたいする闘いへの決起を呼びかける契機として、「労働の奪還」論は受けとめられたと言えます。
とくに職場での団結を一切奪われ、分断され、徹底的に使い捨ての商品のように扱われてきた非正規の青年労働者、新自由主義資本に支配された職場の労働者にとって、「労働の奪還」という呼びかけが職場での資本との闘争を開始する決起のバネとして受け入れられたということもあります。
ところが大原は、資本制の転覆―資本制権力を打倒し、生産手段を奪取し、プロレタリア革命を戦取していくということを抜きにして、労働組合のもとに団結し共同性と誇りをもって労働すれば、「労働の奪還」なるものが可能であるかのように幻想をふくらませてしまいました。これは完全にマルクス主義を変質させ解体しようとするものであり、当然にも党内から批判の声があがりました。ところが大原と政治局指導部は、これらの批判を一切受け付けずに称揚し、大原の提起を「労働者指導部による提起」として全党に押しつけたのです。この政治局の「指導」は、党のマルクス主義と理論闘争を大きく歪めるものとなってしまいました。
2017年2月の大原論文で、大原と彼を持ち上げてきた政治局指導部の破産は、全面的に露呈します。この大原論文は、「国鉄決戦のために」と題する論文でありながら、ほとんどまともに国鉄決戦が直面している問題について触れないものでした。JR東資本の第3の分割・民営化と言うべき外注化攻撃、分社化・非正規職化の攻撃、動労千葉の解体という狙いを定めた大攻撃をいかにはじき返すべきかということについて対応しないものでした。
それは、大原と政治局の指導部自身が、国鉄決戦の指導路線内容を失っていたことのあらわれです。人間史を超階級的に人間の共同性の発展の歴史だと描きあげ、「愛と誠実が決定的」という、国鉄決戦論なき国鉄論文は、大原と彼を押し立てた政治局が、現実のJR攻防と階級闘争から完全に遊離していたこと、その結果ますますマルクス主義から逸脱し、ついには破壊するにいたったことを決定的に示していたのです。
理論の正しさ、どんなに困難でもマルクス主義の原理・原則を貫くことは、党の生命線です。
どこで党を生まれ変わらせることができるのか。それは一つに、マルクス主義・レーニン主義でのオーソドックスで生きいきとした党の再建、綱領草案に立ち戻ったマルクス主義の復権です。政治局が先頭に立って、理論闘争、学習・研究活動、イデオロギー活動を再建することです。
二つには、労働者階級に拠って立つ党に戻ること、動労千葉とともに国鉄決戦と国鉄闘争全国運動、改憲・戦争阻止!大行進運動に責任をとることです。
三つには、機関紙誌の変革、充実を軸に階級決戦を闘う党の指導能力と態勢を養うことです。
四つには、情勢の流動・激動に柔軟に対応して労働運動・大衆運動を宣伝・扇動、組織することです。
五つには、政治警察と対決して非合法・非公然の党を建設する能力と態勢をつくることです。
徹底議論で路線的対立も明らかにしながら、団結を生みだせる党へと変革していくこと、その出発点となることが26全総の最大の課題です。
(つづく)












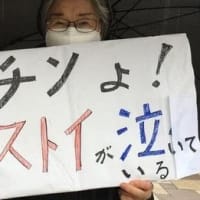






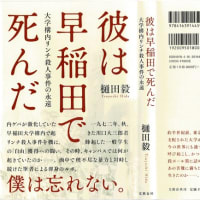
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます