著者への手紙:さらば革共同! わが青春と人生の全て
竜 奇兵
2015年9月22日
中央派は著者を襲撃するのか
拝読いたしました。予想外の大作に圧倒されています。
連れ合いが言いました。「水谷さんと岸さん、こんなの書いて大丈夫? 中央派に襲撃されるのと違う?」と。私は少し考えた後「大丈夫と思うよ。著者たちもそこいらは読みきっているはずだし、第一、襲撃すれば書かれてあることが全て事実だと認めることになる。清水氏もそんなに愚かではない。襲撃すれば恥の上塗りになることぐらい分かっている。中央派お得意の無視をする以外ないと思うよ」と答えました。
清水氏と言えば、『前進』紙上【管理者註 『前進』2681号、15年5月18日】で政治局の名をもって著者らを「史上最高のスパイ」呼ばわりしましたが、それは「買わない・読まない・広めない」の「三ない」運動を指示する類のことでした。笑ってしまいました。だって、そうでしょう。清水丈夫が「スパイの書いたものだから読むな」と言えば、党員・シンパがひれ伏し、従うと思い込んでいるのですから。未だに清水氏=政治局の名前が「神通力」を有すると思い込んでいるのですから。感性・感覚がここまで現実と遊離するとは! 「清丈衰えたり」と思わざるを得ません。
対カクマル戦の真実
さて本題に入ります。この著作は様々な視点から読まれると思います。ある人は、暴露本と読み、ある人は党内闘争のドキュメントと読み、またある人は革命運動上の路線論争と読むでしょう。どの読み方も可です。それぞれの立場で、それぞれの思い込みを持って読まれてしかるべきだと思います。
そのなかで、多くの読者が、最も知りたがり、注目したのは次の点ではないでしょうか? 249ページに書かれている「じつは当時の軍は黒田の組織活動と生活実態の法則性や習慣と不規則な動きの様子をほとんどつかんでおり、黒田のターゲット化は煮つまっていた。同じく松崎の存在形態と動向を具体的に把握しており、とくに松崎の動きの最大の弱点を握っていた」の箇所です。黒田寛一のターゲット化の煮つまり、松崎明の最大の弱点とは具体的にどういうことだったのでしょうか? そしてそれは、実行段階=作戦化していたのでしょうか。それともそれ以前の調査段階だったのでしょうか。どこまで進行していたのか?
詳細を知りたいと思った読者は私だけではないと思います。何と言っても「報復戦貫徹」「三頭目処刑」は果たされていないのですから。圧倒的に勝ち抜き、勝利感を横溢していても、「復讐未だならず」の悔しさだけは払拭できていないのですから……。
本多さんの構想の意外性と納得性
それにしても本多延嘉さんがカクマル戦の早期終結を考えていたとは意外でした。
著作の中で何度も何度も繰り返されるフリーズ「対カクマル戦を第一にしたあり方の倒立性」の指摘は全くそのとおりです。絶対許されざる民間反革命との内乱を如何にして権力との垂直的闘いに止揚させていくのか。如何にして弁証法的に一体化するのか。ここに問題の全てが凝縮されていたことは明白です。民間内部の反革命(水平的構造)を決して軽視することなく、しかし、革命本来の在り方である権力との闘い(垂直的構造)をしっかりと位置づけ、止揚させていく。この課題にわれわれは挑戦していたのです。
その意味では長すぎたと思います。もっと早い段階でケリをつけることが可能でしたし、つけるべきでした。本多さんの対カクマル戦の構想は意外ではありましたが、十分に納得できるものです。
革命の路線をめぐる混乱と対立を止揚できず
それともう一つ。路線上の問題で言えば、「労働運動路線」に言及せざるをえません。
それは全党を巻き込んだ混乱と対立でした。私の所属するある地区委員会では、「左派」(政治闘争推進派)は「右派」(経済闘争推進派)を「経済主義者」「組合主義者」と罵倒し、「革共同は政治闘争の党派だ」「その政治闘争を否定するのか」と罵倒していました。かたや「右派」は「経済闘争抜きに革命が成り立つのか」「経済闘争の意義が分かっていない」と軽蔑し弾劾していました。
実際この時の混乱は目を覆うばかりでした。「右派」の諸君の一部は党の会議に全く出て来ず、組合事務所に入りびたりでした。もちろん党の設定した政治闘争にも出てきませんでした。「左派」はそんな「右派」の諸君をまるで他党派を見るように異端視し蛇蝎のごとく忌み嫌っていました。あの時の党内の冷え冷えとした雰囲気は今でも忘れられません。
もちろん党内の左右の傾向的違いは1991年5月テーゼ以前からもありましたが、5月テーゼ以降、反戦闘争推進と11月労働者集会動員をめぐってその混乱と対立が次第に露わとなりました。とりわけ2003年の新指導路線をもって修復しがたいものとなったのでした。それは私の所属する地区委員会だけではなかったでしょう。
本多時代以後、消滅した哲学
何故あのような不毛な対立が党内に派生し、止揚できなかったのでしょうか? 全ては哲学の不在=弁証法的に事物をとらえることが出来なかったのが原因だと考えています。
政治闘争と経済闘争は車の両輪であり、革命運動の最も大きな二つの領域です。このどちらか片方が欠けても成就しないのが革命です。この自明のことを忘れていたとしか言いようがありません。より正確に言うならば、この両者を弁証法的に一体化するという手法を有していなかったのです。
こう書いてくると「そんなことはない。革共同はその問題を解決していたのだ。政治闘争と経済闘争の結合と言う形で…」との反論が聞こえてきそうです。私も良く聞きました。「政治闘争と経済闘争の結合論」を…。しかしこの結合論は誤りです。これでは何も解決しませんし、事実解決しませんでした。せいぜい「政治闘争も大事だし、経済闘争も大事だ。どちらも全力で闘うのだ」という答えしか出てきません。これでは足して2で割る折衷案でしかありません。第一、政治闘争と経済闘争という全く異なる領域の闘いを結合できるはずがありません。大事なことは弁証法的に止揚するという思考法です。量と質との関係といっても良いでしょう。経済闘争(量)を政治闘争(質)へと止揚(転化)していく哲学こそ、党内の混乱を解決する唯一の手法でした。
思うに、本多さんの時代はまた、哲学の時代でもありました。史的唯物論と弁証法が党内学習の基本でした。弁証法とは何か、唯物論とは何か、を必死の想いで学習しました。対立する二つの概念を弁証法で止揚していく。そして新たな段階を切り開く(前進していく)。このような作風・党風が党内にあふれていました。本多さん亡き後もこの党風が遺産として残っていれば、対カクマル戦争も労働運動も変わっていたかもしれませんね。本多さんと共に、哲学も消滅してしまいました。残念です。
新たな革命運動が創生されることを
カクマルとの戦争で斃れていったかけがえのない多くの同志について述べておきたいと思います。
なかには「こんなもの書きやがって」「死んでも死にきれねえ」と喚く同志もいるかもしれません。が大半の同志は「良く書いてくれた」「俺の想いは、ここに全て書かれてある」と共感の声を上げるのではないでしょうか? この著作を読みながら、志半ばで命を奪われた何人もの知己である同志たちの顔が一つ一つ瞼に浮かんできます。
また多くの読者は、この著作をとおして得た真実で、革共同の呪縛から解き放され、己の革命運動史を対象化しえたのではないでしょうか?
最後に。この著作を糧にして新たな革命運動が創生されることを望みます。この著書を必要とする新たな革命党が生まれ出ることを切望します。
さらば革共同! わが青春と人生の全て。
竜 奇兵
2015年9月22日
中央派は著者を襲撃するのか
拝読いたしました。予想外の大作に圧倒されています。
連れ合いが言いました。「水谷さんと岸さん、こんなの書いて大丈夫? 中央派に襲撃されるのと違う?」と。私は少し考えた後「大丈夫と思うよ。著者たちもそこいらは読みきっているはずだし、第一、襲撃すれば書かれてあることが全て事実だと認めることになる。清水氏もそんなに愚かではない。襲撃すれば恥の上塗りになることぐらい分かっている。中央派お得意の無視をする以外ないと思うよ」と答えました。
清水氏と言えば、『前進』紙上【管理者註 『前進』2681号、15年5月18日】で政治局の名をもって著者らを「史上最高のスパイ」呼ばわりしましたが、それは「買わない・読まない・広めない」の「三ない」運動を指示する類のことでした。笑ってしまいました。だって、そうでしょう。清水丈夫が「スパイの書いたものだから読むな」と言えば、党員・シンパがひれ伏し、従うと思い込んでいるのですから。未だに清水氏=政治局の名前が「神通力」を有すると思い込んでいるのですから。感性・感覚がここまで現実と遊離するとは! 「清丈衰えたり」と思わざるを得ません。
対カクマル戦の真実
さて本題に入ります。この著作は様々な視点から読まれると思います。ある人は、暴露本と読み、ある人は党内闘争のドキュメントと読み、またある人は革命運動上の路線論争と読むでしょう。どの読み方も可です。それぞれの立場で、それぞれの思い込みを持って読まれてしかるべきだと思います。
そのなかで、多くの読者が、最も知りたがり、注目したのは次の点ではないでしょうか? 249ページに書かれている「じつは当時の軍は黒田の組織活動と生活実態の法則性や習慣と不規則な動きの様子をほとんどつかんでおり、黒田のターゲット化は煮つまっていた。同じく松崎の存在形態と動向を具体的に把握しており、とくに松崎の動きの最大の弱点を握っていた」の箇所です。黒田寛一のターゲット化の煮つまり、松崎明の最大の弱点とは具体的にどういうことだったのでしょうか? そしてそれは、実行段階=作戦化していたのでしょうか。それともそれ以前の調査段階だったのでしょうか。どこまで進行していたのか?
詳細を知りたいと思った読者は私だけではないと思います。何と言っても「報復戦貫徹」「三頭目処刑」は果たされていないのですから。圧倒的に勝ち抜き、勝利感を横溢していても、「復讐未だならず」の悔しさだけは払拭できていないのですから……。
本多さんの構想の意外性と納得性
それにしても本多延嘉さんがカクマル戦の早期終結を考えていたとは意外でした。
著作の中で何度も何度も繰り返されるフリーズ「対カクマル戦を第一にしたあり方の倒立性」の指摘は全くそのとおりです。絶対許されざる民間反革命との内乱を如何にして権力との垂直的闘いに止揚させていくのか。如何にして弁証法的に一体化するのか。ここに問題の全てが凝縮されていたことは明白です。民間内部の反革命(水平的構造)を決して軽視することなく、しかし、革命本来の在り方である権力との闘い(垂直的構造)をしっかりと位置づけ、止揚させていく。この課題にわれわれは挑戦していたのです。
その意味では長すぎたと思います。もっと早い段階でケリをつけることが可能でしたし、つけるべきでした。本多さんの対カクマル戦の構想は意外ではありましたが、十分に納得できるものです。
革命の路線をめぐる混乱と対立を止揚できず
それともう一つ。路線上の問題で言えば、「労働運動路線」に言及せざるをえません。
それは全党を巻き込んだ混乱と対立でした。私の所属するある地区委員会では、「左派」(政治闘争推進派)は「右派」(経済闘争推進派)を「経済主義者」「組合主義者」と罵倒し、「革共同は政治闘争の党派だ」「その政治闘争を否定するのか」と罵倒していました。かたや「右派」は「経済闘争抜きに革命が成り立つのか」「経済闘争の意義が分かっていない」と軽蔑し弾劾していました。
実際この時の混乱は目を覆うばかりでした。「右派」の諸君の一部は党の会議に全く出て来ず、組合事務所に入りびたりでした。もちろん党の設定した政治闘争にも出てきませんでした。「左派」はそんな「右派」の諸君をまるで他党派を見るように異端視し蛇蝎のごとく忌み嫌っていました。あの時の党内の冷え冷えとした雰囲気は今でも忘れられません。
もちろん党内の左右の傾向的違いは1991年5月テーゼ以前からもありましたが、5月テーゼ以降、反戦闘争推進と11月労働者集会動員をめぐってその混乱と対立が次第に露わとなりました。とりわけ2003年の新指導路線をもって修復しがたいものとなったのでした。それは私の所属する地区委員会だけではなかったでしょう。
本多時代以後、消滅した哲学
何故あのような不毛な対立が党内に派生し、止揚できなかったのでしょうか? 全ては哲学の不在=弁証法的に事物をとらえることが出来なかったのが原因だと考えています。
政治闘争と経済闘争は車の両輪であり、革命運動の最も大きな二つの領域です。このどちらか片方が欠けても成就しないのが革命です。この自明のことを忘れていたとしか言いようがありません。より正確に言うならば、この両者を弁証法的に一体化するという手法を有していなかったのです。
こう書いてくると「そんなことはない。革共同はその問題を解決していたのだ。政治闘争と経済闘争の結合と言う形で…」との反論が聞こえてきそうです。私も良く聞きました。「政治闘争と経済闘争の結合論」を…。しかしこの結合論は誤りです。これでは何も解決しませんし、事実解決しませんでした。せいぜい「政治闘争も大事だし、経済闘争も大事だ。どちらも全力で闘うのだ」という答えしか出てきません。これでは足して2で割る折衷案でしかありません。第一、政治闘争と経済闘争という全く異なる領域の闘いを結合できるはずがありません。大事なことは弁証法的に止揚するという思考法です。量と質との関係といっても良いでしょう。経済闘争(量)を政治闘争(質)へと止揚(転化)していく哲学こそ、党内の混乱を解決する唯一の手法でした。
思うに、本多さんの時代はまた、哲学の時代でもありました。史的唯物論と弁証法が党内学習の基本でした。弁証法とは何か、唯物論とは何か、を必死の想いで学習しました。対立する二つの概念を弁証法で止揚していく。そして新たな段階を切り開く(前進していく)。このような作風・党風が党内にあふれていました。本多さん亡き後もこの党風が遺産として残っていれば、対カクマル戦争も労働運動も変わっていたかもしれませんね。本多さんと共に、哲学も消滅してしまいました。残念です。
新たな革命運動が創生されることを
カクマルとの戦争で斃れていったかけがえのない多くの同志について述べておきたいと思います。
なかには「こんなもの書きやがって」「死んでも死にきれねえ」と喚く同志もいるかもしれません。が大半の同志は「良く書いてくれた」「俺の想いは、ここに全て書かれてある」と共感の声を上げるのではないでしょうか? この著作を読みながら、志半ばで命を奪われた何人もの知己である同志たちの顔が一つ一つ瞼に浮かんできます。
また多くの読者は、この著作をとおして得た真実で、革共同の呪縛から解き放され、己の革命運動史を対象化しえたのではないでしょうか?
最後に。この著作を糧にして新たな革命運動が創生されることを望みます。この著書を必要とする新たな革命党が生まれ出ることを切望します。
さらば革共同! わが青春と人生の全て。












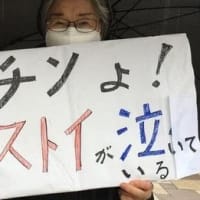






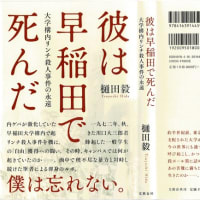
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます