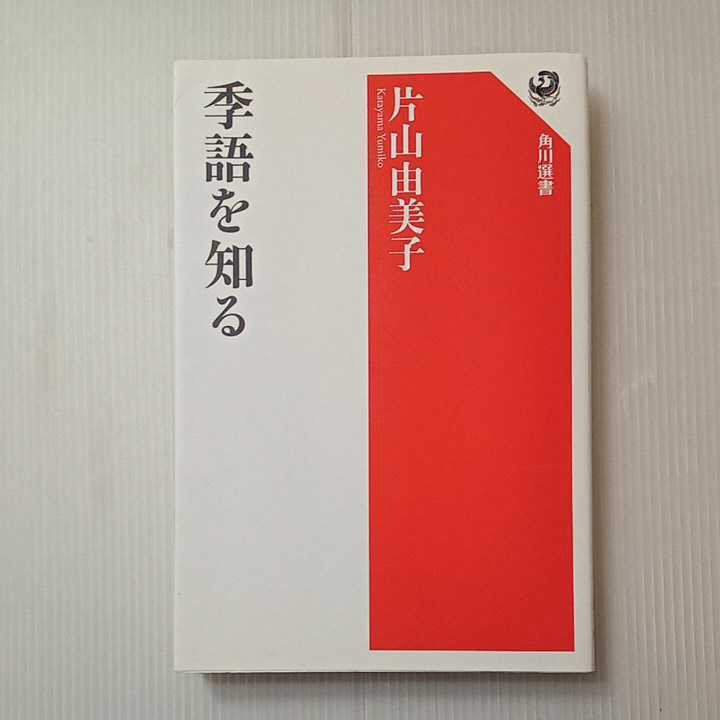
季語って凄いです。
季語の勉強をしてなかったら、こんなこと知りませんでした。
「夜の秋」と「秋の夜」の違いなんて考えたことありますか?
同じでしょうと言うのが最初の印象ですよね。
これが違うそうです。
「夜の秋」とは、夏も終わりの頃になれば、夜に秋の如き感じを催すときがある。それを言うのである。秋の夜のことではない。
これは高浜虚子の見解です。
ところが、青木月斗はこの見解に反対している。
「改造社の俳諧歳時記には夏の土用に入れば夜は北風が吹きて涼しく、宛ら秋の如くなるよりかく言うと記せる書あれど、よろしからず。」と記されています。
ところで「宛ら」読めましたか。
これ、「さながら」と読みます。
これは気象状態の見解の違いではなく、江戸期の俳句の解釈の違いなのです。
芭蕉以降の俳句を読んで鑑賞しながら、季語の意味づけしているのです。
例句として高浜虚子が上げた句が以下の句です。
くらがりにかがみ話や夜の秋 竹城子
俳諧の寝物語や夜の秋 水竹居
雨戸くる隣の家や夜の秋 七三郎
晩夏の風情があります。ただ、挽夏とは言えないような句もあって、定まっていないというのです。
どうなのでしょうか、いずれにして知りませんでしでした。
誤解されやすい季語として、片山氏が指摘している季語として「青時雨」があります。
「青時雨」これ「あおしぐれ」と読みます。
これは空から降る雨ではないのです。
「山本健吉編の季寄せ 文藝春秋社」には「青葉の頃木々に降り溜まった雨が、木の下を通りかかったときにバサリと落ちること。青葉時雨」と解説してある。
例句として
結界の身に青葉時雨埒もなや 角川源義
大原や青葉しぐれに髪打たす 鍵和田柚子
辞書には「青時雨」はなく、よくにた表現に「樹雨」がある。
「樹雨」は木の葉や枝についた霧が水滴となって落ちることとなっている。
季語ではないのですが、日本国語大辞典には季語とされている。
季語って本当に難しいと思いませんか。
そこで一句は本日お休みです。
疲れちゃって。



















