2022年度 第1回うとう塾 5/26(木)
講師:青森県発達障害者支援センター「ステップ」所長 町田 徳子さん
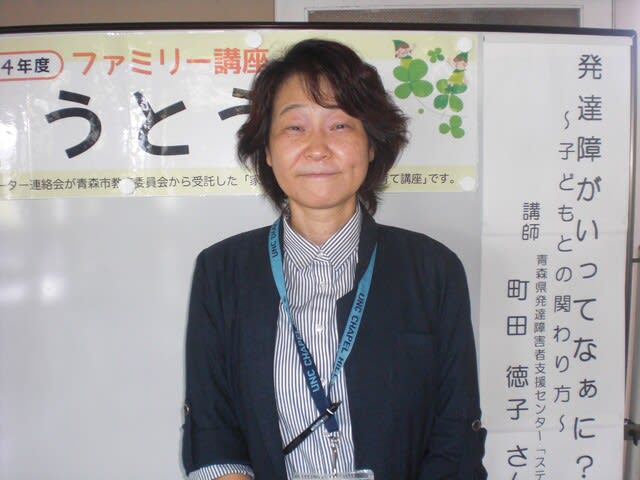
発達に心配のある子ども達の様々な課題を解決するために発達障がいの特性を理解する。また、それぞれの時期に必要な子どもへの関わり方や考え方を知り、次のステップに踏み出すきっかけとなるよう開催しました。
「発達障がい」は、脳機能の発達に関連する生まれつきの障がいで、脳の働き方に違いがあります。原因は、はっきりしていません。障がいの特性は、十人十色で非常に多様です。「自閉スペクトラム症」「注意欠如多動症」「発達性協調運動障害」「チック」「吃音」等があります。一見して「違い」が分かりにくい障がいです。例えば、学び方や物事の捉え方が難しい特性の子の場合、「ちゃんとやりなさい」と言われても、「ちゃんとって、何?」と理解することが難しいのです。「オモチャを箱にいれてね」と具体的に伝えると理解できます。子どもが困っている障がいの特性を知ると、その子に必要な支援(関わり方、教え方)が分かり、早期から適した関わり方をする事で、適応行動(社会性)が改善することが期待できます。
自閉スペクトラム症の小学4年の男児が「障がいの特性を知ってほしい」との思いで作成した資料から当事者だから言える「何をやれば良いか具体的に説明してほしい、感じ方がみんなと違うことを知ってほしい、言葉だけでなく見て分かるものを使ってほしい」という内容が紹介されました。
「障がい」があるから何でもOKではありません。何も知らなくても良い、何もしなくても良いわけではありません。社会のマナーや様々なスキルを学び経験する権利が子ども達にはあります。
発達障がいのある子のことを理解するうえで以下のことがあります。
1 言葉だけでなく、見てわかるものを使ってほしい。
2 「はじめ」と「おわり」をはっきりしてほしい。
3 指示や質問は、具体的に短くゆっくりしてほしい。
4 何をやればいいのか具体的に説明してほしい。
5 感じ方がみんな違うことを知ってほしい。
6 他の人の気持ちがわからないと知ってほしい。
この他に、「本人の気持ちを受け止め自尊心を大切にすること。そして、叱らないで禁止の理由や社会のルールを教えることや、一貫した態度で接することなど」の視点をお話していただきました。


参加者アンケート(一部抜粋)
 自閉症の症状が具体的でわかりやすかったです。
自閉症の症状が具体的でわかりやすかったです。
 子どもの関わり方の振り返りができて良かったです。
子どもの関わり方の振り返りができて良かったです。
 子どもがどう思っているか、どう困っているか聞いてみたいと思いました。
子どもがどう思っているか、どう困っているか聞いてみたいと思いました。
 DCD(発達性協調運動障害)、吃音等初めて知りました。
DCD(発達性協調運動障害)、吃音等初めて知りました。
 自分の心の持ち方でどうなるのかやってみたいと思います。
自分の心の持ち方でどうなるのかやってみたいと思います。
 チックという言葉は初めて知りました。
チックという言葉は初めて知りました。
講座へのご参加、アンケートのご記入ありがとうございました



















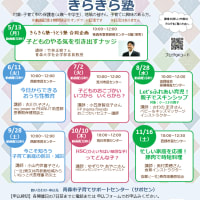






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます