
2007年10月17日に未来科学館大ホールで開催されたNIMEのシンポジウム。今週は
後半のパネル2「「諸外国における教員のICT活用による教育向上に向けての教
育手法の改善に関する取組み」についてお伝えいたします。
プログラム等Webサイト:
http://www.nime.ac.jp/sympo-2007/
前半部分のBlog記事:
http://blog.goo.ne.jp/sanno_el/e/81a77944f7dbd53e7aa6429e41b1654c
当日の模様はオンデマンド配信されておりますので、ぜひそちらもご覧ください。
http://p4web.nime.ac.jp/p4web3/public.asp
パネル2「諸外国における教員のICT活用による教育向上に向けての教育手法の改善に関する取組み」
◆eラーニング実践者に必要なFDニーズ
(Heather Kanuka アサバスカ大学)
アサバスカ大学(以下AUと略。携帯電話会社に非ず)はカナダ最大の通信制大学
です。この大学では今まで紙と郵便の通信教育を教育手段として用いてきました
が、近年ITの活用を推進しているということで、通信教育事業者の中でeラーニ
ングを考える筆者にとっては非常に参考となる話でした。
同大学は、毎年32,000人の卒業生を送り出し、過去6年間で在学生の数は倍増、
現在260,000人が在籍しているとのことです。位置づけとしては、日本の放送大
学やイギリスのOpen Universityと同じと思われます。
Kanuka先生は、AU内で「eラーニングコースを担当する先生がどういう支援を欲
しているか」を調査しました。調査のフレームワークはCommunity of inquiry
(Garrison, Anderson, & Archer, 2000;2001)というモデルに準拠しています。
community of inquiryとは、CMC(コンピュータを介在したコミュニケーショ
ン)をを用いて教育体験を支援するフレームワークを提供することを目的に開発
されたそうです。
つまりeラーニングでネットチューターのような人を想定した場合に、それらの
人への支援のあり方がどうあるべきかを考察するためのフレームということのよ
うです。下記のWebサイトにCommunity of inquiryに関する論文が掲載されてい
ます。筆者はプリントアウトしたものの、論文要旨までしか読んでいません。
http://www.communitiesofinquiry.com/なんとなく使えそうな枠組みです。ぜひどなたか日本語訳を!
◆学習と教授におけるICTの融合
(Andrew Hannan University of Plymouse)
プリマス大学は29000人の学生と1600人のアカデミックスタッフを擁するイギリ
ス南西部の大学です。ハンナン先生は、教員、IT技術者、職員3つの立場の人へ
の定性的インタビューをもとに課題を抽出しました。印象に残ったのは、「すべ
ての授業にICTを使うというのは間違っている。教科や教える中身によって使わ
ない方ことが正当化されるものが必ずあるからだ」という話です。これも「Firs
t PEDAGPGY, Then Technology」の典型的な考え方といえるでしょう。
◆高等教育におけるBlended Learning の効果的な活用
(韓国淑明女子大学 Jae kyung lee)
韓国淑明女子大学では、以前より2つの課題に直面していました。一つは、学生
のことをあまり考慮しないコンテンツ中心のインストラクション、もう一つは、
学生の受身教育の態度です。そうした課題の解決に向けてブレンデットラーニン
グを導入し、授業改善をした事例を発表いただきました。
ブレンデットの形態も、オンラインが主で集合研修が従のものと、逆にオンライ
ンが従で集合研修が主のものの2パターンがあり、現在ブレンデットのeクラス
とよばれるコースが韓国淑明女子大学全体で提供されるコースの5割になってい
るそうです。eクラスでは、様々な学習アクティビティが展開されています。課
題の提出やフィードバックをはじめとして、オンラインでのディスカッションや、
メンタリング、グループ討議などです。
これらの成果として、先生は学生の進捗をよくモニターするようになった、生徒
は他の学生から学ぶといった成果がでているそうです。
また、eクラス成功の秘訣は、学内のサポートセンターを設立したことにあった
と語っています。このセンターではteaching learning media の3つのサービス
と研究開発を行っているとのことです。
◆eティーチングシステム、FDテクノロジーとしてのTIES
(帝塚山大学 中島先生)
「やれFDだ、次はeラーニングだと、最近あまりにも教員に色々と押し付けすぎ。
これでは面倒で新しいものが嫌いな傾向にある大学教員が取り組まないのは当た
り前ではないか」
中島先生はそういった問題意識から「教員を助ける」コンセプトで教育の情報化
に着手したそうです。eラーニングの前にeティーチングがあり、その基盤として
eティーチングについてのハッピーでフレンドリーなコミュニティを作る。そし
てそれらの支援組織として4人のサポート要員のいるセンターを作ったとのこと
です。
活動も極めて地道なところから支援の手を差し伸べているそうです。例えば「黒
板では色が使えないのだが何とかならないか」という教員に、パワーポイントス
ライドの作成を支援したり、「授業でのハンドアウトが多くて印刷が大変」とい
う教員に、eラーニングWebサイトへの教材のアップロード方法を教えてあげたり
といったレベルから開始すると、徐々に高度な活用をしていくようになるという
ことです。
その結果、現在手塚山大学で運営しているTIESというeラーニングシステムには、
13000ものコンテンツが登録されているそうです。
http://www.tiesnet.jp/
シンポジウム全体の感想
今回のシンポジウムで発表いただいた先生方は日々現場で悪戦苦闘している方々
ばかりでした。そうした中から生まれる知見、例えばHannan先生の「ICTを活用
しない授業の正当化」や、中島先生の「教師を助けるeティーチング」の考え方
は、非常に共感できる発表内容でした。First PEDAGPGY, Then Technology ICT
に踊らされないeラーニングに向けてのスタートラインにやっと立つことができ
た。これが今回のシンポジウムに参加しての筆者の感想です。
後半のパネル2「「諸外国における教員のICT活用による教育向上に向けての教
育手法の改善に関する取組み」についてお伝えいたします。
プログラム等Webサイト:
http://www.nime.ac.jp/sympo-2007/
前半部分のBlog記事:
http://blog.goo.ne.jp/sanno_el/e/81a77944f7dbd53e7aa6429e41b1654c
当日の模様はオンデマンド配信されておりますので、ぜひそちらもご覧ください。
http://p4web.nime.ac.jp/p4web3/public.asp
パネル2「諸外国における教員のICT活用による教育向上に向けての教育手法の改善に関する取組み」
◆eラーニング実践者に必要なFDニーズ
(Heather Kanuka アサバスカ大学)
アサバスカ大学(以下AUと略。携帯電話会社に非ず)はカナダ最大の通信制大学
です。この大学では今まで紙と郵便の通信教育を教育手段として用いてきました
が、近年ITの活用を推進しているということで、通信教育事業者の中でeラーニ
ングを考える筆者にとっては非常に参考となる話でした。
同大学は、毎年32,000人の卒業生を送り出し、過去6年間で在学生の数は倍増、
現在260,000人が在籍しているとのことです。位置づけとしては、日本の放送大
学やイギリスのOpen Universityと同じと思われます。
Kanuka先生は、AU内で「eラーニングコースを担当する先生がどういう支援を欲
しているか」を調査しました。調査のフレームワークはCommunity of inquiry
(Garrison, Anderson, & Archer, 2000;2001)というモデルに準拠しています。
community of inquiryとは、CMC(コンピュータを介在したコミュニケーショ
ン)をを用いて教育体験を支援するフレームワークを提供することを目的に開発
されたそうです。
つまりeラーニングでネットチューターのような人を想定した場合に、それらの
人への支援のあり方がどうあるべきかを考察するためのフレームということのよ
うです。下記のWebサイトにCommunity of inquiryに関する論文が掲載されてい
ます。筆者はプリントアウトしたものの、論文要旨までしか読んでいません。
http://www.communitiesofinquiry.com/なんとなく使えそうな枠組みです。ぜひどなたか日本語訳を!
◆学習と教授におけるICTの融合
(Andrew Hannan University of Plymouse)
プリマス大学は29000人の学生と1600人のアカデミックスタッフを擁するイギリ
ス南西部の大学です。ハンナン先生は、教員、IT技術者、職員3つの立場の人へ
の定性的インタビューをもとに課題を抽出しました。印象に残ったのは、「すべ
ての授業にICTを使うというのは間違っている。教科や教える中身によって使わ
ない方ことが正当化されるものが必ずあるからだ」という話です。これも「Firs
t PEDAGPGY, Then Technology」の典型的な考え方といえるでしょう。
◆高等教育におけるBlended Learning の効果的な活用
(韓国淑明女子大学 Jae kyung lee)
韓国淑明女子大学では、以前より2つの課題に直面していました。一つは、学生
のことをあまり考慮しないコンテンツ中心のインストラクション、もう一つは、
学生の受身教育の態度です。そうした課題の解決に向けてブレンデットラーニン
グを導入し、授業改善をした事例を発表いただきました。
ブレンデットの形態も、オンラインが主で集合研修が従のものと、逆にオンライ
ンが従で集合研修が主のものの2パターンがあり、現在ブレンデットのeクラス
とよばれるコースが韓国淑明女子大学全体で提供されるコースの5割になってい
るそうです。eクラスでは、様々な学習アクティビティが展開されています。課
題の提出やフィードバックをはじめとして、オンラインでのディスカッションや、
メンタリング、グループ討議などです。
これらの成果として、先生は学生の進捗をよくモニターするようになった、生徒
は他の学生から学ぶといった成果がでているそうです。
また、eクラス成功の秘訣は、学内のサポートセンターを設立したことにあった
と語っています。このセンターではteaching learning media の3つのサービス
と研究開発を行っているとのことです。
◆eティーチングシステム、FDテクノロジーとしてのTIES
(帝塚山大学 中島先生)
「やれFDだ、次はeラーニングだと、最近あまりにも教員に色々と押し付けすぎ。
これでは面倒で新しいものが嫌いな傾向にある大学教員が取り組まないのは当た
り前ではないか」
中島先生はそういった問題意識から「教員を助ける」コンセプトで教育の情報化
に着手したそうです。eラーニングの前にeティーチングがあり、その基盤として
eティーチングについてのハッピーでフレンドリーなコミュニティを作る。そし
てそれらの支援組織として4人のサポート要員のいるセンターを作ったとのこと
です。
活動も極めて地道なところから支援の手を差し伸べているそうです。例えば「黒
板では色が使えないのだが何とかならないか」という教員に、パワーポイントス
ライドの作成を支援したり、「授業でのハンドアウトが多くて印刷が大変」とい
う教員に、eラーニングWebサイトへの教材のアップロード方法を教えてあげたり
といったレベルから開始すると、徐々に高度な活用をしていくようになるという
ことです。
その結果、現在手塚山大学で運営しているTIESというeラーニングシステムには、
13000ものコンテンツが登録されているそうです。
http://www.tiesnet.jp/
シンポジウム全体の感想
今回のシンポジウムで発表いただいた先生方は日々現場で悪戦苦闘している方々
ばかりでした。そうした中から生まれる知見、例えばHannan先生の「ICTを活用
しない授業の正当化」や、中島先生の「教師を助けるeティーチング」の考え方
は、非常に共感できる発表内容でした。First PEDAGPGY, Then Technology ICT
に踊らされないeラーニングに向けてのスタートラインにやっと立つことができ
た。これが今回のシンポジウムに参加しての筆者の感想です。











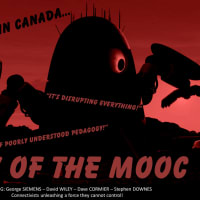



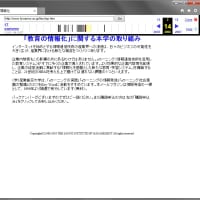
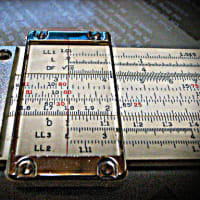

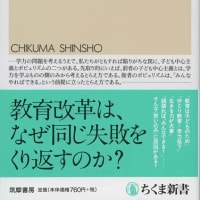
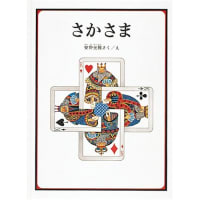
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます