【論文タイトルと著者】
表題:Developmental changes in feeding behaviors of infant chimpanzees at Mahale, Tanzania: implications for nutritional independence long before cessation of nipple contact
(タンザニア・マハレのチンパンジーの採食行動の発達変化:乳首接触の終了よりも早い栄養的自立の示唆)
著者:Takuya Matsumoto1, 2
(松本卓也1, 2)
所属:1 Research Institute for Humanity and Nature, 2 Graduate School of Science, Kyoto University
(1 総合地球環境学研究所、2 京都大学理学研究科)
(※1は現所属、2は論文執筆時の所属です)
掲載誌:American Journal of Physical Anthropology (DOI: 10.1002/ajpa.23212)
【まとめ】
予想より早かったチンパンジーの離乳
行動研究からわかったチンパンジーの栄養的自立の時期
【要約】
赤ちゃんが母乳を必要としなくなる時期はいつなのか。この問いは、子育て中の家庭にとってだけでなく、人類の進化の過程を考える上でも重要な問題です。ヒトに最も遺伝的に近いチンパンジーは、お乳をくわえるのをやめる時期や、母親が次の子を妊娠する時期を基準に、およそ4−5歳で離乳するとされていました。一方、近年の長期調査の成果では、3歳近くのチンパンジーの赤ちゃんは、母親が失踪し孤児になっても生き残る可能性があることがわかってきました。つまり、チンパンジーの赤ちゃんは、3歳近くで栄養的に母乳に頼らなくなり、自立している可能性があります。
そこで、総合地球環境学研究所の松本卓也(日本学術振興会特別研究員)は、タンザニアのマハレ山塊国立公園でフィールドワークを行い、野生チンパンジーの赤ちゃんの食生活を調べました。その結果、3歳以上の赤ちゃんは、より長い時間を食事にあてるようになることがわかりました。また、消化が難しい植物の葉をより長い時間食べるようになることや、堅い殻に覆われた実などの食べ難い食物を、自力で食べるようになることがわかりました。こうした食生活の大きな変化は、チンパンジーの赤ちゃんが母乳に頼らずに生きていくための基礎になっていると考えられます。本研究成果は、赤ちゃんの食生活の変化が人類の進化にどのような影響を与えたかについて考える上での、重要な足がかりになると考えられます。
本研究成果は、国際学術誌『American Journal of Physical Anthropology』誌(電子版)に2017年3月20日付けにて掲載されました。
URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.23212/full
【背景】
人類の進化の過程を考える上で、ヒトとその他の霊長類の生活史(性成熟する年齢、初産の年齢、寿命など)を比較することは重要な方法です。生活史に関するこれまでの先行研究で明らかになった、ヒトに特徴的な生活史のパターンとして、「離乳時期の早期化」が挙げられます。nonindustrialなヒトの集団を網羅的に調査した研究によれば、赤ちゃんがおよそ2.5-3歳になった時期に、母親は授乳をやめるとされています。ヒトに遺伝的に最も近いチンパンジーの離乳時期は、お乳をくわえるのをやめる時期や、母親が次の子を妊娠する時期を基準に4−5歳とされてきました。
赤ちゃんが早く離乳すると、母親はより短い間隔で次の子を妊娠することができます。つまり、「離乳時期の早期化」は、ヒトが多産になったことと関連付けられます。ヒトの祖先は、森で暮らし続けた類人猿の祖先とは対照的に、捕食者による危険が大きい開けた環境で暮らしていたと考えられており、ヒトの「離乳時期の早期化」は、こうした環境への適応と関係していると考えられています。
一方、ヒトとチンパンジーでは、離乳時期を調べる方法が両者で異なっていることが問題点として挙げられます。ヒトは「母親からの聞き取り」のデータに基づいているのに対し、チンパンジーは「お乳をくわえなくなる時期」や「母親が次の子を妊娠する時期」など、主にフィールドでの観察から得られたデータに基づいてきました。こうしたデータでは、乳首をくわえているだけで実際にお乳を飲んでいない「甘え吸い」や、夜間に授乳している可能性を確かめることができず、赤ちゃんにとっての離乳時期、つまり「母乳への依存度を下げ、他の食物で栄養をまかなうことができる時期」を調べることができません。
近年の研究では、長期にわたるフィールド調査の結果から、孤児が生き残ることができる境界の年齢が3歳前後であることや、多くの霊長類で離乳時期との一致がみられる第一大臼歯の萌出年齢が、野生チンパンジーでは3歳前後であることなどが明らかになり、これまで野生チンパンジーの行動観察の結果から考えられてきた「4−5歳」より早期に離乳している可能性が示唆されています。
【研究手法・成果】
そこで私は、タンザニアのマハレ山塊国立公園(以下、マハレ)でフィールドワークを行い、野生チンパンジーの赤ちゃんの食生活の発達変化を調べました。マハレは、京都大学を中心とした研究チームが、50年近くにわたって野生チンパンジーの観察を続けているフィールドです。野生のチンパンジーはオスが比較的人に慣れやすいのに対し、メスは人に慣れにくいため、観察が難しいとされてきました。マハレは長期調査のおかげでチンパンジーが人によく慣れており、特に赤ちゃんの詳細な観察が可能であるという点で、世界でも有数のフィールドであると言えます(図1)。マハレでの2年近い観察の結果、チンパンジーの赤ちゃんは3歳前後において以下の傾向を示すことがわかりました(図2)。
・より長い時間を採食に費やす
・消化の難しい「葉」をより長い時間採食する
・他個体からの分配なしに、自力で「物理的に処理の難しい食べ物」を採食する割合が高くなる
赤ちゃんは消化器官や身体機能が未発達なので、赤ちゃんならではの食べ難さがあると言えます。植物の葉は一般的にタンパク質含有量が高く、野生チンパンジーにとって重要な食物です。しかし、葉はタンニンなど2次代謝物を多く含むため、消化器官が未発達な赤ちゃんにとっては多く食べられないものであると言えます。本研究結果から、3歳前後のチンパンジーの赤ちゃんは、葉を長時間食べることができるようになる、ということがわかりました。また、赤ちゃんは咀嚼器官などが未発達のため、例えば堅い殻に覆われた果実など、自力で採食が困難な食物が存在します。本研究結果から、3歳前後の赤ちゃんは、そういった「物理的に処理の難しい食物」を、他個体からの食物分配を受けずに、自力で採食する時間割合が高くなる、ということがわかりました。これらの結果をまとめると、チンパンジーの赤ちゃんは3歳前後において、赤ちゃんならではの食べ難さが緩和し、大人と同様の食べ方ができるようになる、と言えます。つまり、本研究は、「野生チンパンジーの赤ちゃんが、これまで考えられていた離乳時期よりもかなり早い段階で、母乳への依存度を大きく下げている」という予想を、行動学的見地から初めて支持したものと言えます。
【考察】
本研究結果を踏まえて、霊長類学における先行研究を、「お乳をくわえなくなる時期は栄養的自立とは無関係である」という観点から調べ直し、考察しました。離乳時期について調べられている類人猿(チンンパンジー・ゴリラ・オランウータン)以外の霊長類では、「お乳をくわえなくなる時期」「赤ちゃんが栄養的に自立する時期」「母親が次の子を妊娠する時期」が概ね一致していました。しかし、類人猿においては、「お乳をくわえなくなる時期」と「母親が次の子を妊娠する時期」は一致するものの、「赤ちゃんが栄養的に自立する時期」がかなり前である可能性があります。本研究は、これまで「離乳」という言葉でひとくくりにされてきた、これらの時期のずれの存在を、行動から初めて示唆した研究といえます。
翻ってヒトの特徴を考えると、ヒトは「赤ちゃんが栄養的に自立する時期」よりも前に、「母親が次の子を妊娠する時期」がくることが可能です。この特徴は、類人猿と比較すると、より特殊なものであるということがわかります。このヒトの特徴的な離乳方法について重要な役割を果たしているのは、やわらかく調理され、なおかつ母親以外の誰かが赤ちゃんに与えることができる「離乳食」の存在かもしれません。本研究成果は、赤ちゃんの食生活の変化が人類の進化にどのような影響を与えたかについて考える上での、重要な足がかりになると考えられます。
表題:Developmental changes in feeding behaviors of infant chimpanzees at Mahale, Tanzania: implications for nutritional independence long before cessation of nipple contact
(タンザニア・マハレのチンパンジーの採食行動の発達変化:乳首接触の終了よりも早い栄養的自立の示唆)
著者:Takuya Matsumoto1, 2
(松本卓也1, 2)
所属:1 Research Institute for Humanity and Nature, 2 Graduate School of Science, Kyoto University
(1 総合地球環境学研究所、2 京都大学理学研究科)
(※1は現所属、2は論文執筆時の所属です)
掲載誌:American Journal of Physical Anthropology (DOI: 10.1002/ajpa.23212)
【まとめ】
予想より早かったチンパンジーの離乳
行動研究からわかったチンパンジーの栄養的自立の時期
【要約】
赤ちゃんが母乳を必要としなくなる時期はいつなのか。この問いは、子育て中の家庭にとってだけでなく、人類の進化の過程を考える上でも重要な問題です。ヒトに最も遺伝的に近いチンパンジーは、お乳をくわえるのをやめる時期や、母親が次の子を妊娠する時期を基準に、およそ4−5歳で離乳するとされていました。一方、近年の長期調査の成果では、3歳近くのチンパンジーの赤ちゃんは、母親が失踪し孤児になっても生き残る可能性があることがわかってきました。つまり、チンパンジーの赤ちゃんは、3歳近くで栄養的に母乳に頼らなくなり、自立している可能性があります。
そこで、総合地球環境学研究所の松本卓也(日本学術振興会特別研究員)は、タンザニアのマハレ山塊国立公園でフィールドワークを行い、野生チンパンジーの赤ちゃんの食生活を調べました。その結果、3歳以上の赤ちゃんは、より長い時間を食事にあてるようになることがわかりました。また、消化が難しい植物の葉をより長い時間食べるようになることや、堅い殻に覆われた実などの食べ難い食物を、自力で食べるようになることがわかりました。こうした食生活の大きな変化は、チンパンジーの赤ちゃんが母乳に頼らずに生きていくための基礎になっていると考えられます。本研究成果は、赤ちゃんの食生活の変化が人類の進化にどのような影響を与えたかについて考える上での、重要な足がかりになると考えられます。
本研究成果は、国際学術誌『American Journal of Physical Anthropology』誌(電子版)に2017年3月20日付けにて掲載されました。
URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.23212/full
【背景】
人類の進化の過程を考える上で、ヒトとその他の霊長類の生活史(性成熟する年齢、初産の年齢、寿命など)を比較することは重要な方法です。生活史に関するこれまでの先行研究で明らかになった、ヒトに特徴的な生活史のパターンとして、「離乳時期の早期化」が挙げられます。nonindustrialなヒトの集団を網羅的に調査した研究によれば、赤ちゃんがおよそ2.5-3歳になった時期に、母親は授乳をやめるとされています。ヒトに遺伝的に最も近いチンパンジーの離乳時期は、お乳をくわえるのをやめる時期や、母親が次の子を妊娠する時期を基準に4−5歳とされてきました。
赤ちゃんが早く離乳すると、母親はより短い間隔で次の子を妊娠することができます。つまり、「離乳時期の早期化」は、ヒトが多産になったことと関連付けられます。ヒトの祖先は、森で暮らし続けた類人猿の祖先とは対照的に、捕食者による危険が大きい開けた環境で暮らしていたと考えられており、ヒトの「離乳時期の早期化」は、こうした環境への適応と関係していると考えられています。
一方、ヒトとチンパンジーでは、離乳時期を調べる方法が両者で異なっていることが問題点として挙げられます。ヒトは「母親からの聞き取り」のデータに基づいているのに対し、チンパンジーは「お乳をくわえなくなる時期」や「母親が次の子を妊娠する時期」など、主にフィールドでの観察から得られたデータに基づいてきました。こうしたデータでは、乳首をくわえているだけで実際にお乳を飲んでいない「甘え吸い」や、夜間に授乳している可能性を確かめることができず、赤ちゃんにとっての離乳時期、つまり「母乳への依存度を下げ、他の食物で栄養をまかなうことができる時期」を調べることができません。
近年の研究では、長期にわたるフィールド調査の結果から、孤児が生き残ることができる境界の年齢が3歳前後であることや、多くの霊長類で離乳時期との一致がみられる第一大臼歯の萌出年齢が、野生チンパンジーでは3歳前後であることなどが明らかになり、これまで野生チンパンジーの行動観察の結果から考えられてきた「4−5歳」より早期に離乳している可能性が示唆されています。
【研究手法・成果】
そこで私は、タンザニアのマハレ山塊国立公園(以下、マハレ)でフィールドワークを行い、野生チンパンジーの赤ちゃんの食生活の発達変化を調べました。マハレは、京都大学を中心とした研究チームが、50年近くにわたって野生チンパンジーの観察を続けているフィールドです。野生のチンパンジーはオスが比較的人に慣れやすいのに対し、メスは人に慣れにくいため、観察が難しいとされてきました。マハレは長期調査のおかげでチンパンジーが人によく慣れており、特に赤ちゃんの詳細な観察が可能であるという点で、世界でも有数のフィールドであると言えます(図1)。マハレでの2年近い観察の結果、チンパンジーの赤ちゃんは3歳前後において以下の傾向を示すことがわかりました(図2)。
・より長い時間を採食に費やす
・消化の難しい「葉」をより長い時間採食する
・他個体からの分配なしに、自力で「物理的に処理の難しい食べ物」を採食する割合が高くなる
赤ちゃんは消化器官や身体機能が未発達なので、赤ちゃんならではの食べ難さがあると言えます。植物の葉は一般的にタンパク質含有量が高く、野生チンパンジーにとって重要な食物です。しかし、葉はタンニンなど2次代謝物を多く含むため、消化器官が未発達な赤ちゃんにとっては多く食べられないものであると言えます。本研究結果から、3歳前後のチンパンジーの赤ちゃんは、葉を長時間食べることができるようになる、ということがわかりました。また、赤ちゃんは咀嚼器官などが未発達のため、例えば堅い殻に覆われた果実など、自力で採食が困難な食物が存在します。本研究結果から、3歳前後の赤ちゃんは、そういった「物理的に処理の難しい食物」を、他個体からの食物分配を受けずに、自力で採食する時間割合が高くなる、ということがわかりました。これらの結果をまとめると、チンパンジーの赤ちゃんは3歳前後において、赤ちゃんならではの食べ難さが緩和し、大人と同様の食べ方ができるようになる、と言えます。つまり、本研究は、「野生チンパンジーの赤ちゃんが、これまで考えられていた離乳時期よりもかなり早い段階で、母乳への依存度を大きく下げている」という予想を、行動学的見地から初めて支持したものと言えます。
【考察】
本研究結果を踏まえて、霊長類学における先行研究を、「お乳をくわえなくなる時期は栄養的自立とは無関係である」という観点から調べ直し、考察しました。離乳時期について調べられている類人猿(チンンパンジー・ゴリラ・オランウータン)以外の霊長類では、「お乳をくわえなくなる時期」「赤ちゃんが栄養的に自立する時期」「母親が次の子を妊娠する時期」が概ね一致していました。しかし、類人猿においては、「お乳をくわえなくなる時期」と「母親が次の子を妊娠する時期」は一致するものの、「赤ちゃんが栄養的に自立する時期」がかなり前である可能性があります。本研究は、これまで「離乳」という言葉でひとくくりにされてきた、これらの時期のずれの存在を、行動から初めて示唆した研究といえます。
翻ってヒトの特徴を考えると、ヒトは「赤ちゃんが栄養的に自立する時期」よりも前に、「母親が次の子を妊娠する時期」がくることが可能です。この特徴は、類人猿と比較すると、より特殊なものであるということがわかります。このヒトの特徴的な離乳方法について重要な役割を果たしているのは、やわらかく調理され、なおかつ母親以外の誰かが赤ちゃんに与えることができる「離乳食」の存在かもしれません。本研究成果は、赤ちゃんの食生活の変化が人類の進化にどのような影響を与えたかについて考える上での、重要な足がかりになると考えられます。















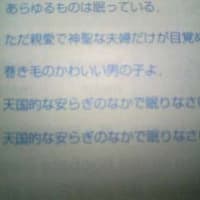
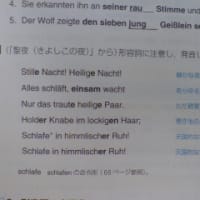



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます