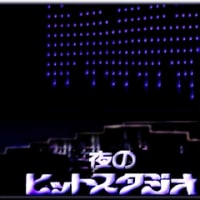夜のヒットスタジオという番組は、何かと司会者の力量や雰囲気に番組の雰囲気が左右されやすい番組でもありました。
そこで、今回は歴代8名の司会者の、夜ヒット司会となるまでの経緯や番組内での司会スタイルを中心として、「夜ヒット司会者考」という観点から22年の番組史を検証したいと思います。
番組スタート当初の司会は前田武彦さん・芳村真理さんのコンビ。60代~50代後半当りの年代の人にとっての夜ヒット司会者といえばこのコンビ、という人が多分多いと思います。この2人のコンビでの司会となったきっかけは、以前も番組立ち上げについての記事でも触れたようにラジオ番組(ニッポン放送「女性対男性」)でマエタケさんのゲストパートナーを芳村さんが務めたときのやり取りが、構成作家の塚田茂さんらが大変気に入り、この司会コンビでの歌謡番組を、ということで夜ヒットが用意されました。
マエタケさんは、もともとは放送作家としてテレビ放送の黎明期からテレビジョンに関わりあいを持ち、クレイジーキャッツの名を一躍全国区に押し上げた「シャボン玉ホリデー」(日本テレビ)も番組スタート時の主要作家陣の一人として彼も名前を連ねていました。その後、「象印歌のタイトルマッチ」(NET、現・テレビ朝日)などの審査員として、テレビ番組に自ら顔を出すようになったり、1960年代後半に入り、ラジオ番組パーソナリティーを受け持つようになり、彼の真面目なところあり、毒舌もあり、ユーモアあり、という巧みなフリートークがリスナーの間で評判となり、それに比例するように、構成作家から放送タレントへと活動の軸足を移すこととなります。
「司会者・前田武彦」の名前が一躍クローズアップされたのは、やはり1968年4月に放送開始されたフジテレビ「お昼のゴールデンショー」から。この番組ではまだ売り出し中であったコント55号(萩本欽一さん・坂上二郎さん)をアシスタントに従え、生放送であるにも関わらず、台本をときに度外視しつつ、時間勺に収める見事なフリートークの技量が遺憾なく発揮され、新たな時代のテレビ司会者のモデル的存在として視聴者にも彼の顔と名前が浸透していくようになりました。
そして、同年の秋の「夜のヒットスタジオ」のメイン司会者抜擢がその人気を決定的なものへとさせていきます。
マエタケさんや、大橋巨泉さんは、「テレビ司会者」のイメージをいい意味で「ぶち壊した」画期的な存在でした。彼らが活躍する前のテレビ司会者といえば、大抵は台本どおりの司会をなぞり、高橋圭三さんや玉置宏さんなどになってくると時に機転の利いたアドリブを台本通りのセリフの中は挟み込みつつ進行をするというスタイルが一般的でしたが、マエタケさんの場合には後年、「台本通りやったってつまらないだけ」という言葉を仰っていることでも象徴されるように、とにかく台本から脱線してフリートークを展開しつつ進行も行っていくという当時のテレビ司会者の手法からすれば「異端中の異端」ともいえる手法でした。
当時の守旧派は当然のように彼の自己主張も織り交ぜた司会スタイルを「生意気だ」とかなり批判的な目で見ていたようですが、夜ヒットやお昼のゴールデンショー、そして1969年秋からの「ゲバゲバ90分」や「笑点」への抜擢など、彼の司会番組が軒並み人気番組になっていくに従い彼の評価は特に若い年代の視聴者を中心に「フリートークの天才」という評価へと変って行くようになりました。今のテレビ番組でも明石家さんまさんや島田紳助さんの司会スタイルは「フリートーク」主流の手法ですが、このころのマエタケさんの司会ぶりを見ていた人からは、「この時代のマエタケには、今のさんまも紳助もかなわない」という評価を良く耳にすることがあります。如何に彼が卓抜したトーク技量を持ち、その発言一つ一つの説得力なり影響力なりが大きかったがが後年のこのような評価からも窺い知ることができるような気がします。
また、夜ヒットに限定していえば、これもフリートークを展開する中での延長線上での行動なのであろうと思いますが、歌手やスタッフにもあだ名をつけて呼ぶという点もかなり特徴的でした。相方の芳村真理さんには上記のラジオ番組でのやり取りから「ナマズのおばさん」、構成の塚田茂さんには「どんどんクジラ」、そして歌手にも小川知子さんには当時ボーイッシュなイメージがあったせいか「金太郎」、布施明さんには鼻の高さから「ピノキオ」、ちあきなおみさんには「びっくり人形」、南沙織さんには肌が褐色に焼けているところから「チョコレートモンキー」、菅原洋一さんには「3日前のハンバーグ」といった具合で初出演する歌手には大抵あだ名をつける慣例がありました。ただ、これもファンによっては歓迎されず、むしろ猛抗議を受けたものもあったそうです(例えば、都はるみさんにつけた「海坊主」など)が、これもそれまでの歌謡番組ではある程度の距離感があった司会者と歌手の存在を繋ぎ合わせる意味では大きな役割を果たしていたように思います。
他方、芳村真理さんは、1966年末に当時のフジテレビの朝の人気ワイドショー番組「小川宏ショー」で前任の木元教子さんが産休に入ったため代わりに2代目の女性アシスタント役として登板したのが契機となり8年間続けた女優業を一切降り、司会者業にシフトしていきました。
当初は、後年の夜ヒットや他の番組での人柄からすれば意外な話ですが、東映のお色気映画にも出演していたり、女優としての役柄もどちらかといえば意地悪な女性、悪女というイメージの役が多い(自分の性格に女優業が合わなかったという趣旨の発言も後年彼女は述べていますが、多分この役柄ともともとの性格にギャップがあったからかと思います)という点から「夜」というイメージが強く、当初は、視聴者だけでなく小川ショーのスタッフの間でも彼女の登板は抵抗感があったそうですが、一旦司会をやらせてみると、その評価は大きく変わりました。この番組の司会の時代にはまだ彼女は前夫のミッキー・カーティスさんとの間に授かった子供をシングルマザーという立場で育てており、ちゃんと「主婦としての視点」から、小川宏さんを立てつつ、主婦としての意見を主張し、また、元モデルという経験を十分に生かすべく、主婦の視点から立って当時まだ日本には入っていなかった「ミニスカート」を着て司会をしたりと、流行のファッションを自ら進んでモデルとなって紹介していくなど、彼女と同年代の若い主婦層を中心に彼女の司会スタイルや洒落たセンスが広く受け入れられ、「司会者・芳村真理」の礎がこの小川ショーのアシスタント時代に築かれていきました。
この小川ショーで築かれた司会者としての彼女のカラーは「夜ヒット」で一気に広い視聴者層にも浸透していきました。時にマエタケさんの往々にしてある失言やそれに近い誤解を招きかねない発言を巧くオプラートに包み、またあるときには、しゃべくり漫才のようにマエタケさんのとぼけた発言や行動にすかさずツッコミを入れたりと、「フリートークの天才」マエタケさんをして「頭の回転が速い」と言わしめる司会ぶりを行い、それまでの大物の男性司会者の陰に隠れ存在感が薄かった女性司会者の概念を大きく覆しました。
芳村さんの、男性司会者の「暴走」を巧みに宥める「猛獣使い」ともいえる役割や存在感は以降の夜ヒットでも番組の雰囲気を維持していく上で重要なファクターとして機能していきますが、それはまた以後の記事で追々触れていくこととしたいと思います。
このように、共に守旧派からは批判を受け、他方で新しい世代には新鮮な雰囲気と共に受け入れられたという共通項を持つマエタケ・芳村コンビの司会ぶりは時にやはり厳しい批判も受けながらもそれらの批判をものともしないほどの勢いがあり、「泣きの夜ヒット事件」以来続く番組人気を底辺から支えてきました。大物ゲストの中には彼らの司会だから出演をしようと出演を快諾した歌手もいたり、マエタケさんに巧くいじってもらって、飾らない部分をアピールしようと、各事務所・レコード会社がこぞって毎週のように放送日前になると一押しの新人を猛プッシュするなど、視聴者だけでなく、歌手や音楽関係者の中にもこのコンビの司会に対し高い信頼を寄せていました。それゆえに番組に出演する歌手たちは常連として出演していた中尾ミエさんや梓みちよさん、布施明さん当りになってくるとなんら気取ることなくリラックスした気分で番組に出演しており、この歌手や司会者の気取らない(悪く言えば、視聴者に下手な媚を売らないという風にも取れるかもしれませんが)出演中のやり取りや様子が番組全体のカラーとして継承されていった「アットホームさ」を際立たせていたという気もします。
このように好調の真っ只中にあった夜ヒットですが、ところが上記にも述べたマエタケさんの誤解を招きかねない「余計な一言」が仇になる形で、今度は一転して番組混迷の時代へと叩き落とされることとなってしまいます。それが、時の放送業界の権力や政治思想なども複雑に絡み合い、夜ヒットを含め全てのマエタケさん担当番組から、一挙に「マエタケ追放」の包囲網が構築されるという、夜ヒット史上でも最も衝撃的で出来事ともいえる、1973年6月の「共産党・バンザイ発言事件」なわけですが、この点については次回の同項目の記事にて重点的に取り上げたいと思います。
そこで、今回は歴代8名の司会者の、夜ヒット司会となるまでの経緯や番組内での司会スタイルを中心として、「夜ヒット司会者考」という観点から22年の番組史を検証したいと思います。
番組スタート当初の司会は前田武彦さん・芳村真理さんのコンビ。60代~50代後半当りの年代の人にとっての夜ヒット司会者といえばこのコンビ、という人が多分多いと思います。この2人のコンビでの司会となったきっかけは、以前も番組立ち上げについての記事でも触れたようにラジオ番組(ニッポン放送「女性対男性」)でマエタケさんのゲストパートナーを芳村さんが務めたときのやり取りが、構成作家の塚田茂さんらが大変気に入り、この司会コンビでの歌謡番組を、ということで夜ヒットが用意されました。
マエタケさんは、もともとは放送作家としてテレビ放送の黎明期からテレビジョンに関わりあいを持ち、クレイジーキャッツの名を一躍全国区に押し上げた「シャボン玉ホリデー」(日本テレビ)も番組スタート時の主要作家陣の一人として彼も名前を連ねていました。その後、「象印歌のタイトルマッチ」(NET、現・テレビ朝日)などの審査員として、テレビ番組に自ら顔を出すようになったり、1960年代後半に入り、ラジオ番組パーソナリティーを受け持つようになり、彼の真面目なところあり、毒舌もあり、ユーモアあり、という巧みなフリートークがリスナーの間で評判となり、それに比例するように、構成作家から放送タレントへと活動の軸足を移すこととなります。
「司会者・前田武彦」の名前が一躍クローズアップされたのは、やはり1968年4月に放送開始されたフジテレビ「お昼のゴールデンショー」から。この番組ではまだ売り出し中であったコント55号(萩本欽一さん・坂上二郎さん)をアシスタントに従え、生放送であるにも関わらず、台本をときに度外視しつつ、時間勺に収める見事なフリートークの技量が遺憾なく発揮され、新たな時代のテレビ司会者のモデル的存在として視聴者にも彼の顔と名前が浸透していくようになりました。
そして、同年の秋の「夜のヒットスタジオ」のメイン司会者抜擢がその人気を決定的なものへとさせていきます。
マエタケさんや、大橋巨泉さんは、「テレビ司会者」のイメージをいい意味で「ぶち壊した」画期的な存在でした。彼らが活躍する前のテレビ司会者といえば、大抵は台本どおりの司会をなぞり、高橋圭三さんや玉置宏さんなどになってくると時に機転の利いたアドリブを台本通りのセリフの中は挟み込みつつ進行をするというスタイルが一般的でしたが、マエタケさんの場合には後年、「台本通りやったってつまらないだけ」という言葉を仰っていることでも象徴されるように、とにかく台本から脱線してフリートークを展開しつつ進行も行っていくという当時のテレビ司会者の手法からすれば「異端中の異端」ともいえる手法でした。
当時の守旧派は当然のように彼の自己主張も織り交ぜた司会スタイルを「生意気だ」とかなり批判的な目で見ていたようですが、夜ヒットやお昼のゴールデンショー、そして1969年秋からの「ゲバゲバ90分」や「笑点」への抜擢など、彼の司会番組が軒並み人気番組になっていくに従い彼の評価は特に若い年代の視聴者を中心に「フリートークの天才」という評価へと変って行くようになりました。今のテレビ番組でも明石家さんまさんや島田紳助さんの司会スタイルは「フリートーク」主流の手法ですが、このころのマエタケさんの司会ぶりを見ていた人からは、「この時代のマエタケには、今のさんまも紳助もかなわない」という評価を良く耳にすることがあります。如何に彼が卓抜したトーク技量を持ち、その発言一つ一つの説得力なり影響力なりが大きかったがが後年のこのような評価からも窺い知ることができるような気がします。
また、夜ヒットに限定していえば、これもフリートークを展開する中での延長線上での行動なのであろうと思いますが、歌手やスタッフにもあだ名をつけて呼ぶという点もかなり特徴的でした。相方の芳村真理さんには上記のラジオ番組でのやり取りから「ナマズのおばさん」、構成の塚田茂さんには「どんどんクジラ」、そして歌手にも小川知子さんには当時ボーイッシュなイメージがあったせいか「金太郎」、布施明さんには鼻の高さから「ピノキオ」、ちあきなおみさんには「びっくり人形」、南沙織さんには肌が褐色に焼けているところから「チョコレートモンキー」、菅原洋一さんには「3日前のハンバーグ」といった具合で初出演する歌手には大抵あだ名をつける慣例がありました。ただ、これもファンによっては歓迎されず、むしろ猛抗議を受けたものもあったそうです(例えば、都はるみさんにつけた「海坊主」など)が、これもそれまでの歌謡番組ではある程度の距離感があった司会者と歌手の存在を繋ぎ合わせる意味では大きな役割を果たしていたように思います。
他方、芳村真理さんは、1966年末に当時のフジテレビの朝の人気ワイドショー番組「小川宏ショー」で前任の木元教子さんが産休に入ったため代わりに2代目の女性アシスタント役として登板したのが契機となり8年間続けた女優業を一切降り、司会者業にシフトしていきました。
当初は、後年の夜ヒットや他の番組での人柄からすれば意外な話ですが、東映のお色気映画にも出演していたり、女優としての役柄もどちらかといえば意地悪な女性、悪女というイメージの役が多い(自分の性格に女優業が合わなかったという趣旨の発言も後年彼女は述べていますが、多分この役柄ともともとの性格にギャップがあったからかと思います)という点から「夜」というイメージが強く、当初は、視聴者だけでなく小川ショーのスタッフの間でも彼女の登板は抵抗感があったそうですが、一旦司会をやらせてみると、その評価は大きく変わりました。この番組の司会の時代にはまだ彼女は前夫のミッキー・カーティスさんとの間に授かった子供をシングルマザーという立場で育てており、ちゃんと「主婦としての視点」から、小川宏さんを立てつつ、主婦としての意見を主張し、また、元モデルという経験を十分に生かすべく、主婦の視点から立って当時まだ日本には入っていなかった「ミニスカート」を着て司会をしたりと、流行のファッションを自ら進んでモデルとなって紹介していくなど、彼女と同年代の若い主婦層を中心に彼女の司会スタイルや洒落たセンスが広く受け入れられ、「司会者・芳村真理」の礎がこの小川ショーのアシスタント時代に築かれていきました。
この小川ショーで築かれた司会者としての彼女のカラーは「夜ヒット」で一気に広い視聴者層にも浸透していきました。時にマエタケさんの往々にしてある失言やそれに近い誤解を招きかねない発言を巧くオプラートに包み、またあるときには、しゃべくり漫才のようにマエタケさんのとぼけた発言や行動にすかさずツッコミを入れたりと、「フリートークの天才」マエタケさんをして「頭の回転が速い」と言わしめる司会ぶりを行い、それまでの大物の男性司会者の陰に隠れ存在感が薄かった女性司会者の概念を大きく覆しました。
芳村さんの、男性司会者の「暴走」を巧みに宥める「猛獣使い」ともいえる役割や存在感は以降の夜ヒットでも番組の雰囲気を維持していく上で重要なファクターとして機能していきますが、それはまた以後の記事で追々触れていくこととしたいと思います。
このように、共に守旧派からは批判を受け、他方で新しい世代には新鮮な雰囲気と共に受け入れられたという共通項を持つマエタケ・芳村コンビの司会ぶりは時にやはり厳しい批判も受けながらもそれらの批判をものともしないほどの勢いがあり、「泣きの夜ヒット事件」以来続く番組人気を底辺から支えてきました。大物ゲストの中には彼らの司会だから出演をしようと出演を快諾した歌手もいたり、マエタケさんに巧くいじってもらって、飾らない部分をアピールしようと、各事務所・レコード会社がこぞって毎週のように放送日前になると一押しの新人を猛プッシュするなど、視聴者だけでなく、歌手や音楽関係者の中にもこのコンビの司会に対し高い信頼を寄せていました。それゆえに番組に出演する歌手たちは常連として出演していた中尾ミエさんや梓みちよさん、布施明さん当りになってくるとなんら気取ることなくリラックスした気分で番組に出演しており、この歌手や司会者の気取らない(悪く言えば、視聴者に下手な媚を売らないという風にも取れるかもしれませんが)出演中のやり取りや様子が番組全体のカラーとして継承されていった「アットホームさ」を際立たせていたという気もします。
このように好調の真っ只中にあった夜ヒットですが、ところが上記にも述べたマエタケさんの誤解を招きかねない「余計な一言」が仇になる形で、今度は一転して番組混迷の時代へと叩き落とされることとなってしまいます。それが、時の放送業界の権力や政治思想なども複雑に絡み合い、夜ヒットを含め全てのマエタケさん担当番組から、一挙に「マエタケ追放」の包囲網が構築されるという、夜ヒット史上でも最も衝撃的で出来事ともいえる、1973年6月の「共産党・バンザイ発言事件」なわけですが、この点については次回の同項目の記事にて重点的に取り上げたいと思います。