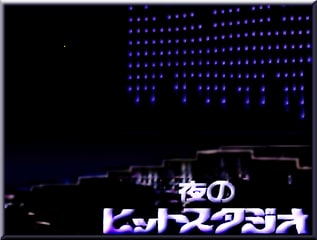【補足Ⅰ-当日披露された曲目について】
・YOKOHAMA HONKY TONK BLUES 詞:藤 竜也/曲:エディ藩
◆80年5月1日リリース、アルバム「TOUCH」より。81年には作曲者のエディ藩が「横浜ホンキートンク・ブルース」のタイトルで、更に82年には作詞者の藤竜也も歌詞を一部改編した上で「ヨコハマ・ホンキートンキー・ブルース」のタイトルでそれぞれ同曲のシングル盤をリリースしている。
・白昼夢 詞:松田優作/曲:芳野藤丸◆80年5月21日リリース、アルバム「TOUCH」からのシングルカット。
・BONNY MORONIE 訳:松田優作/詞・曲:Larry Williams◆81年11月21日リリース、ライブアルバム「HARDEST NIGHT LIVE」収録。オリジナルはアメリカ・ニューオリンズ出身のピアニスト・シンガーソングライター、ラリー・ウィリアムスによる1958年発表のロックンロールのスタンダード的作品。後に元ビートルズのジョン・レノンがカバーしたことでも知られている。
◆80 年・81年に行われたライブツアーでは、アルバム「TOUCH」「HARDESTDAY」(81年5月リリース)に収録されたオリジナル楽曲に並んで、同 曲も含め洋楽、R&Bのスタンダードとされる作品も松田自身が日本語詞を付けた上で数曲、ライブナンバーに組み入れられた。
◆80 年・81年に行われたライブツアーでは、アルバム「TOUCH」「HARDESTDAY」(81年5月リリース)に収録されたオリジナル楽曲に並んで、同 曲も含め洋楽、R&Bのスタンダードとされる作品も松田自身が日本語詞を付けた上で数曲、ライブナンバーに組み入れられた。
【補足Ⅱ-松田優作について】
◆1949
年(戸籍上は1950年)9月21日生。山口・下関出身。地元の高校を2年で中退した後、1967年、叔母が滞在しているアメリカに単身渡り、弁護士を目
指して現地のシーサイド大学附属高校に入学するも、叔母の家の家庭事情もあり、1年でこれも中退し帰国。帰国後、東京・豊島区にあった実兄の家に居候の身
となり、夜間高校に編入し卒業。俳優・岸田森(1982年逝去)が主宰する劇団「六月劇場」の裏方を経験した後、1970年に関東学院大学文学部へと進
学。同大の学園祭でアメリカから来日してきたアングラ劇団の芝居に衝撃を覚え、これが俳優を志す契機となった。
◆1971年、一旦文学座附属演技研究所の入所試験を受験するも不合格。一時、金子信雄主宰の「新演劇人クラブ・マールイ」の演劇教室に通い、同劇団の研究生として残ることが許されたが、文学座への入団の夢を捨てきれず、72年に再度文学座研究所の試験を受け合格、第12期研究生となる。この養成所時代に先輩の桃井かおり、同期の阿川泰子、後輩の中村雅俊の親交を築く。生活のため子供向けの特撮番組の主役オーディションを数度受験するなど、苦労しながら役者修行を続ける。
◆1973年、無名時代より親交のあった村野武範が自身が当時主演していたドラマ「飛びだせ!青春」(日本テレビ系)の製作担当であった、東宝の岡田晋吉プロデューサーが同じく自身が製作を担当している「太陽にほえろ!」(日本テレビ系)で「マカロニ刑事」役を演じていた萩原健一が降板する事になり、萩原の後釜となりうる新人の俳優を探しているという話を聞きつけ、松田を推薦。これをきっかけに「太陽にほえろ!」へのレギュラー出演が決定。「ジーパン刑事」役 を演じ、中学時代より習っていた空手によって培われた抜群の運動神経とタフな体力を駆使した激しいアクションや、180cmを越える長身で全力で走りぬけ る様で注目を集める。同ドラマでの彼の殉職シーンはその後の俳優の多くにも影響を与えるテレビドラマ史上に残る場面となった。同年には、東宝映画「狼の紋章」への客演でスクリーンデビューも果たしている。
◆その後も、山口百恵とのコンビによる「赤い迷路」(TBS系)、文学座研究所時代の後輩・中村雅俊とのコンビによる「俺たちの勲章」(日本テレビ系)などの話題作に出演を続け、着実にスターダムを駆け上がっていたが、76年、雑誌記者に暴行を働き、傷害容疑で逮捕され、半年間の謹慎を強いられる。その後、東映映画「暴力教室」への出演を皮切りに俳優業を再開。
以後、東映セントラルフィルム映画「最も危険な遊戯」「蘇える金狼」「野獣死すべし」等、アクション路線の映画に立て続けで主演。ハードボイルドなイメージを全面に押し出したキャラクター設定と体当たりのアクションで新感覚のアクションスターとしての地位を獲得。他方、同時期に主演したテレビドラマ「探偵物語」(日本テレビ系)ではハードボイルドなイメージを踏襲しつつも、コミカルな主人公「工藤俊作」役を演じ、これがファン層の拡大へと繋がった。
◆1981年、「フィルム歌舞伎」とも評された鈴木清順監督による日本ヘラルド映画「陽炎座」でアクションシーンを最大限排除した演技を展開(これは鈴木氏が直径1mの円を描き「この中から出ないような演技をしてくれ」と松田に直接指導を行った事によるものであったといわれている)し新境地を開拓。83年には、ATG映画「家族ゲーム」で主役である、風変わりな家庭教師役「吉本勝」役を演じ、各映画賞を制覇。続いて、角川映画「探偵物語」、東映映画「それから」でも高い演技力を発揮し、個性派・演技派俳優としての評価が確立。86年には、東映=キティ・フィルム映画「ア・ホーマンス」で映画初監督を経験(元々は他の人物が監督を担当し、松田は主演のみを務めることとなっていたが、その人物が撮影方針を巡って製作陣と対立したことから監督を降板。そのため急遽、主演の松田に監督を兼任することが決まったといわれている)。ロックバンド「ARB」のボーカル・石橋凌の役者としての才能をここで発掘した。また、この時期にはミュージシャンとしての活動も並行して行い、80年・81年には全国縦断のライブツアーを敢行したほか、シングル「白昼夢」「夢・誘惑」、アルバム「HARDEST DAY」「DEJA-V」など数枚のアルバム・シングルを製作。迫力のあるボーカルとセンスの良さで音楽ファンをも魅了した。
◆長年、ハリウッド進出を目標として掲げてきたが、88年、アメリカ映画「ブラック・レイン」のオーディションを受ける機会に恵まれ、見事これに合格し、マイケル・ダグラス演じる、主人公のニューヨーク市警の刑事の執念の追跡を様々な手口でかわし続けながら逃走をつづける、敵役の「佐藤」役を好演。ショーン・コネリー監督の次回作のオファーが来るなど、彼の上記映画における徹底した「悪役」ぶりはハリウッド界でも大いに注目されることとなったが、実はこの映画撮影時に膀胱癌を発症しており、同映画の関係者には一切そのことを知らせることなく、密かに闘病を続けながらの命がけの熱演であった。同映画出演後もテレビドラマ「華麗なる追跡」、トーク番組「オシャレ30・30」(日本テレビ系、文学座研究所の同期である阿川泰子が司会を務めていた)に病を押して出演したが、その後、病状が悪化、89年11月6日、41歳の若さで逝去した。これからの更なる飛躍が期待されていた最中での癌死に多くのファン・後輩俳優が衝撃を受けた。
◆ 結婚歴は2回あり、1回目は、上記の「マールイ」の演劇教室に通っていた際から親交のあった作家・松田美智子(「完全なる飼育」などの著作で知られる)と 長い同棲の末、75年に結婚、1児をもうけた。しかし、ドラマ「探偵物語」での共演をきっかけとして、女優・熊谷(現・松田)美由紀との交際がその後発覚し、これが原 因で81年に離婚。熊谷とは未入籍の状態のまま前妻との離婚後も交際を続けていたが、83年に長男が生まれたのを機に正式に再婚。以後、1男1女をもうけ た。現在、二人の間に生まれた三児のうち、長男・龍平、次男・翔太は、父・優作の意志を受け継ぎ俳優として活躍している。
◆1971年、一旦文学座附属演技研究所の入所試験を受験するも不合格。一時、金子信雄主宰の「新演劇人クラブ・マールイ」の演劇教室に通い、同劇団の研究生として残ることが許されたが、文学座への入団の夢を捨てきれず、72年に再度文学座研究所の試験を受け合格、第12期研究生となる。この養成所時代に先輩の桃井かおり、同期の阿川泰子、後輩の中村雅俊の親交を築く。生活のため子供向けの特撮番組の主役オーディションを数度受験するなど、苦労しながら役者修行を続ける。
◆1973年、無名時代より親交のあった村野武範が自身が当時主演していたドラマ「飛びだせ!青春」(日本テレビ系)の製作担当であった、東宝の岡田晋吉プロデューサーが同じく自身が製作を担当している「太陽にほえろ!」(日本テレビ系)で「マカロニ刑事」役を演じていた萩原健一が降板する事になり、萩原の後釜となりうる新人の俳優を探しているという話を聞きつけ、松田を推薦。これをきっかけに「太陽にほえろ!」へのレギュラー出演が決定。「ジーパン刑事」役 を演じ、中学時代より習っていた空手によって培われた抜群の運動神経とタフな体力を駆使した激しいアクションや、180cmを越える長身で全力で走りぬけ る様で注目を集める。同ドラマでの彼の殉職シーンはその後の俳優の多くにも影響を与えるテレビドラマ史上に残る場面となった。同年には、東宝映画「狼の紋章」への客演でスクリーンデビューも果たしている。
◆その後も、山口百恵とのコンビによる「赤い迷路」(TBS系)、文学座研究所時代の後輩・中村雅俊とのコンビによる「俺たちの勲章」(日本テレビ系)などの話題作に出演を続け、着実にスターダムを駆け上がっていたが、76年、雑誌記者に暴行を働き、傷害容疑で逮捕され、半年間の謹慎を強いられる。その後、東映映画「暴力教室」への出演を皮切りに俳優業を再開。
以後、東映セントラルフィルム映画「最も危険な遊戯」「蘇える金狼」「野獣死すべし」等、アクション路線の映画に立て続けで主演。ハードボイルドなイメージを全面に押し出したキャラクター設定と体当たりのアクションで新感覚のアクションスターとしての地位を獲得。他方、同時期に主演したテレビドラマ「探偵物語」(日本テレビ系)ではハードボイルドなイメージを踏襲しつつも、コミカルな主人公「工藤俊作」役を演じ、これがファン層の拡大へと繋がった。
◆1981年、「フィルム歌舞伎」とも評された鈴木清順監督による日本ヘラルド映画「陽炎座」でアクションシーンを最大限排除した演技を展開(これは鈴木氏が直径1mの円を描き「この中から出ないような演技をしてくれ」と松田に直接指導を行った事によるものであったといわれている)し新境地を開拓。83年には、ATG映画「家族ゲーム」で主役である、風変わりな家庭教師役「吉本勝」役を演じ、各映画賞を制覇。続いて、角川映画「探偵物語」、東映映画「それから」でも高い演技力を発揮し、個性派・演技派俳優としての評価が確立。86年には、東映=キティ・フィルム映画「ア・ホーマンス」で映画初監督を経験(元々は他の人物が監督を担当し、松田は主演のみを務めることとなっていたが、その人物が撮影方針を巡って製作陣と対立したことから監督を降板。そのため急遽、主演の松田に監督を兼任することが決まったといわれている)。ロックバンド「ARB」のボーカル・石橋凌の役者としての才能をここで発掘した。また、この時期にはミュージシャンとしての活動も並行して行い、80年・81年には全国縦断のライブツアーを敢行したほか、シングル「白昼夢」「夢・誘惑」、アルバム「HARDEST DAY」「DEJA-V」など数枚のアルバム・シングルを製作。迫力のあるボーカルとセンスの良さで音楽ファンをも魅了した。
◆長年、ハリウッド進出を目標として掲げてきたが、88年、アメリカ映画「ブラック・レイン」のオーディションを受ける機会に恵まれ、見事これに合格し、マイケル・ダグラス演じる、主人公のニューヨーク市警の刑事の執念の追跡を様々な手口でかわし続けながら逃走をつづける、敵役の「佐藤」役を好演。ショーン・コネリー監督の次回作のオファーが来るなど、彼の上記映画における徹底した「悪役」ぶりはハリウッド界でも大いに注目されることとなったが、実はこの映画撮影時に膀胱癌を発症しており、同映画の関係者には一切そのことを知らせることなく、密かに闘病を続けながらの命がけの熱演であった。同映画出演後もテレビドラマ「華麗なる追跡」、トーク番組「オシャレ30・30」(日本テレビ系、文学座研究所の同期である阿川泰子が司会を務めていた)に病を押して出演したが、その後、病状が悪化、89年11月6日、41歳の若さで逝去した。これからの更なる飛躍が期待されていた最中での癌死に多くのファン・後輩俳優が衝撃を受けた。
◆ 結婚歴は2回あり、1回目は、上記の「マールイ」の演劇教室に通っていた際から親交のあった作家・松田美智子(「完全なる飼育」などの著作で知られる)と 長い同棲の末、75年に結婚、1児をもうけた。しかし、ドラマ「探偵物語」での共演をきっかけとして、女優・熊谷(現・松田)美由紀との交際がその後発覚し、これが原 因で81年に離婚。熊谷とは未入籍の状態のまま前妻との離婚後も交際を続けていたが、83年に長男が生まれたのを機に正式に再婚。以後、1男1女をもうけ た。現在、二人の間に生まれた三児のうち、長男・龍平、次男・翔太は、父・優作の意志を受け継ぎ俳優として活躍している。