
大学教授のラウリーは二度の離婚後、娼婦を買うなどして自身の性欲を処理してきた。しかしあるとき自分の受け持つ女生徒に手を出したことから事態は一変。査問会が開かれて教授を辞任する羽目になる。ラウリーは娘のいる田舎の農場に移るが、そこで新たな事件と直面する。
ノーベル賞作家J・M・クッツェーのブッカー賞受賞作。
鴻巣友季子 訳
出版社:早川書房(ハヤカワepi文庫)
主人公のラウリーは共感できる要素の少ない人間だ。
自身の老いや醜悪さを自覚しながら欲望のままに走り、ひとりの女の心を傷つけている。メラニーに対する愛情も恋愛感情というよりも性欲にしか見えず、他人に対する視点や感情はきわめて冷めている。加えて独善と偏見の塊で、人を評する言葉は辛らつだ。娘に対する愛情は伝わるものの、少なくとも僕はこの男とは友達になりたくはない。
しかしラウリーの考えが徹底しているのは事実だ。
彼は教授の職を追われるとき、自分の職を守るチャンスもあったにも関わらず、その提案には乗らなかった。彼は自分の考えに反することだったり、自分の考えを変えなければならなくなったら、恥辱に追いやられることも辞さない男なのだ。賛成できるかはともかく、自分を貫こうとするその姿はある意味すごい。
ラウリーはその後、娘の元に身を寄せることになるが、そこでも恥辱に等しいできごとに見舞われることとなる。その事件を受け、父であるラウリーはレイプを受けた娘に対して、この土地から出ることを勧めている。
彼の意見は理解できるし、正論であろう。このままこの土地にいてレイプ犯の思惑通りの人生を選択することはないというのは筋が通っているし、少なくとも娘を思う気持ちはうかがえる。
たとえそれが自分自身に返りかねない言葉としても彼の言葉に何の間違いもない。
しかしその言葉に対して娘はノーと言う。その意見が僕には受け入れにくいものであった。確かに娘の論理はわかるけれど、僕にはそれが必ずしも正しいものとは思えない。
しかしそれも僕が平和な国に暮らしているから言えることなのかもしれない。大地と結びついた南アフリカでは南アフリカなりの生き方がある。彼女が語った通り、もっと上等な生活なんてどこにもなく、あるのはこの生活だけということなのだろう。
たとえそこに犬のような恥辱が待ち受けた最低限の生活であろうとも、この生活を生き、しっかりと踏みとどまって進まなければならないのかもしれない。理不尽が溢れたこの世界ではそれくらいの覚悟が必要なのだろう。
ラウリーは娘の意見に対して、少しずつ心境の変化が起こりはじめる。少なくとも途中まではそんな予感が伝わってきた。しかし多くの部分では彼は結局なにも変わろうとしなかったし、やはり自分の考えを変えることを拒否している。。
しかしこの理不尽な世界と、希望がないかもしれない状況下を、最後は彼も受け入れている。彼は本質的には何も変わらなかったが、それはある意味では変化と言えるのかもしれない。
その状況を希望とは言えないかもしれない。だが虚無からの出発とでもいうべきその姿にある種の感銘を受けることができた。
個人的には解説の解釈がおもしろかった。なるほどそんな見方もあるのかと驚くばかりだ。
評価:★★★★★(満点は★★★★★)
そのほかのJ・M・クッツェー作品感想
『マイケル・K』
そのほかのノーベル文学賞受賞作家の作品感想
・1929年 トーマス・マン
『トニオ・クレエゲル』
『トニオ・クレーゲル ヴェニスに死す』
・1947年 アンドレ・ジッド
『田園交響楽』
・1982年 ガブリエル・ガルシア=マルケス
『百年の孤独』
・1999年 ギュンター・グラス
『ブリキの太鼓』
・2003年 J・M・クッツェー
『マイケル・K』
・2006年 オルハン・パムク
『わたしの名は紅』
そのほかのブッカー賞受賞作感想
・1983年: J・M・クッツェー『マイケル・K』
・1989年: カズオ・イシグロ『日の名残り』
・1992年: マイケル・オンダーチェ『イギリス人の患者』
・1998年: イアン・マキューアン『アムステルダム』










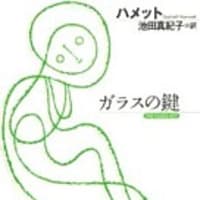

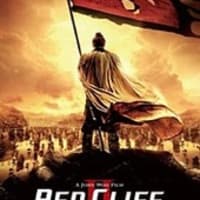
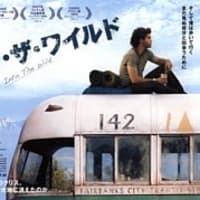
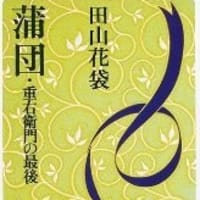
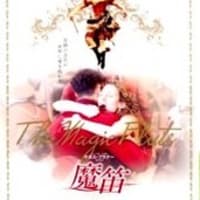
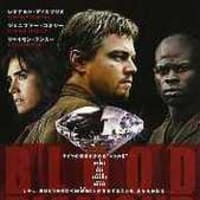
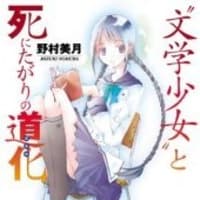
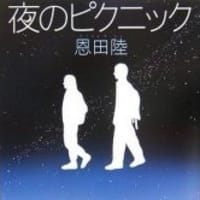








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます