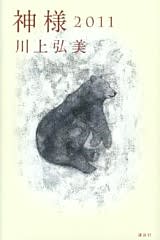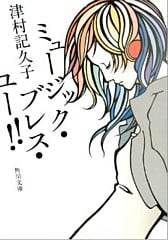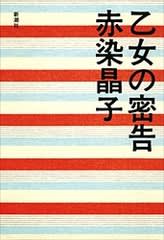僕の中から湧いて出た初めてのこの感じ。つまり性欲? でも、それだけじゃないはず――高校一年、斉藤卓巳。好きだった同級生に告白されたのに、なぜだか頭の中は別の女のことでいっぱい。切っても切り離せない「性」と「生」を正面から描き、読者の熱い支持を得た驚異のデビュー作。
出版社:新潮社
感想を書きづらい作品である。
読んでいる間はそのすばらしさに胸ふるえたのだけど、そう感じた部分をはっきりと明示することができない。
それがとってももどかしくてならない。
だからせめて、最初に結論だけを声に大にして、ここに言っておこう、と思う。
本作は本当にすばらしい作品である、と。
『ふがいない僕は空を見た』は、5篇の短篇から成っているが、そのうち前半3篇はきわどい性描写がなされている。
「女による女のためのR-18文学賞」を取っているためか、エロい――文学的に言うなら官能的な部分が多く見られる。本屋大賞で1位を取れなかったのも納得である。
だが性に関心のない人間はそうそういない。
性はすなわち生であり、覆い隠すことはできない存在でもある。
それを象徴的に現すのが、デビュー作でもある『ミクマリ』だ。
高校生を主人公にした不倫もので、恋愛部分だけ取っても切なく、若さがあふれていて、胸を打つ作品だ。
だけど、本作のすごいところは、主人公の背景に出産を持ってきているところだ。
セックスと出産は当然ひとつながりなのだけど、その物事を並べて描き、そこから人の営みと生き方を浮かび上がらせている様は印象的である。
作者のセンスの高さがうかがえるようだ。
続く作品たちもすべてすばらしい。
『世界ヲ覆フ蜘蛛ノ糸』は、『ミクマリ』を主婦の側から描いた作品だ。
変に気を遣い、流されるように生きて、皆から軽く見られ、姑や夫との関係に少しずつうんざりしている、あんずのキャラクターが印象的。
作者の観察眼や、心理描写の冴えが光る一品である。
『2035年のオーガズム』も好きな作品だ。
高校生の七菜が主人公だが、家庭、恋人、セックスと、何かと問題を抱えている。
だが最後の洪水のシーンで、それらすべてが浄化されるような雰囲気があり、その力強さが心に届いた。
『セイタカアワダチソウの空』は、この中では個人的には一番せつなく感じた。
苛酷な環境で暮らす少年が、そこから抜け出す手段を見つけ、それに賭けようか、と考えるけれど、現実はなかなか彼に厳しい。
最後に見せた、彼の優しい思いがじんわりと心に残る。
『花粉・受粉』は、大人になったいまだから心に響くのかもしれない。
主人公は出産のプロなのだけど、子育てに関しては、いつも手探りだ。
子どもの写真がネットに送られてくるときも、仕事の忙しさに逃げていた、と感じる部分が読んでいて、ぐっと来る。大人になってもわからないことは多い。
それでもラストに希望が滲んでいて、その温かさに胸が震える。
どうもまとまりを欠いた感想になってしまった。
ともあれ、作者の高い感性を垣間見るような作品集ということは、改めて述べたい。
この作者の別作品も読んでみたい。そう思わせるだけの魅力に富んだ一品であった。
評価:★★★★★(満点は★★★★★)