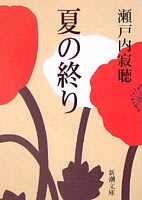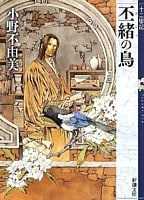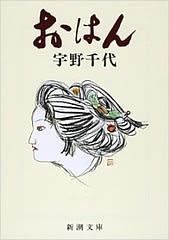〈わたしたちは仲間です〉――十四歳のある日、同級生からの苛めに耐える〈僕〉は、差出人不明の手紙を受け取る。苛められる者同士が育んだ密やかで無垢な関係はしかし、奇妙に変容していく。葛藤の末に選んだ世界で、僕が見たものとは。善悪や強弱といった価値観の根源を問い、圧倒的な反響を得た著者の新境地。
出版社:講談社(講談社文庫)
『ヘヴン』は紛れもなく一級の作品である。
そのいじめの描写はつらく、相手を思う気持ちは胸苦しく、そして展開される哲学的な思惟は深く、文章もいい。
再読ではあるが、僕はやっぱりこの作品が大好きだと改めて思った。
物語は中学二年の生徒で、学校で凄惨ないじめにあっている「僕」と、同じくいじめられているコジマの交流を中心として描かれている。
そこで描かれる、「僕」へのいじめは本当に苛酷だ。
「僕」は斜視であることをからかわれ、上履きを突然投げつけられたり、チョークを無理やり食べさせられたり、机の中にごみを詰め込まれたり、体に跡がつかないよう殴られたり蹴られたりしている。
読んでいるだけでつらくなってくるような陰惨な場面ばかりだ。
実際、作中の「僕」もつらいらしく、死を考えることもある。
そのように「僕」の心が追いつめられていく様子は本当に見ていて苦しい。
そんな中で、もっとも残酷だったのは、人間サッカーであろう。そのシーンは圧巻であった。
体育館へ連れ込まれるときの不安、ボールになれ、と言われて、バレーボールをかぶせられた後、何が起こるかわからず待っているときの恐怖など、「僕」の感情が激しく伝わる。
おかげでそのシーンを読んでいるときは、胃が痛くなってしまったほどだ。
その場面は、「僕」を蹴り飛ばした後のところもすばらしい。
いじめを行なった二ノ宮が「僕」に言った言葉は本当にひどかったからである。
そのときの二ノ宮の言葉を読んだときは、あまりに卑劣過ぎて、戦慄が走った。
それはもう、人でなし、としか言いようがなく、そのクズっぷりにむしろ感嘆すらしてしまう。
そして、こんな苛酷な場面でも、容赦なく描写する川上未映子の筆力に、圧倒されるほかなかった。見事と言うほかない。
そして、そのいじめの描写が苛酷であるからこそ、「僕」とコジマの交流が胸に響くのだろう。
最初の方の手紙のやり取りなんかはとってもすてきだ。
はっきり言って、話している内容には大したことはないのだけど、二人の距離感が縮まっていく様子がよく伝わり、温かい気分になる。
だからこそ「僕」は、「コジマが苛められているのを見」るのがつらくなるし、自分が「苛められているのを見られていると思うのも」つらいと思うようになる。
それはすごく自然な心の動きだ。
そして、そんな風に感じるのは、「僕」が優しい子だからってのもあるのだ。
自分がいじめられているのに(あるいはいじめられているからこそ)、親身になって他者のことを心配し、悲しんでもいる。
そんな「僕」の心に触れて、読み手であるこちらも彼と同じように苦しい気分になってしまう。
そうして二人の仲もどんどん親密さを増していく。
個人的には夏休みのデートのシーンが好きだ。
そこでお金のことや着ていく服のことを考えて、おろおろする「僕」がとってもかわいらしい。
もちろん髪を切るところもすばらしかった。
たぶん「僕」はコジマが話すはさみの理屈はあんまりわかってはいないのだと思う。
しかしそれがコジマにとって重要なことだということは、「僕」にもわかっている。
だから自分の髪を切っていいのだと、言えるのだ。
それもまた、相手の気もちになって考える、彼の優しさの表れなのだろう。
そんな「僕」の行動に胸を打たれてしまう。そして「僕」のことをこちらも好きになってしまう。
そしてやがて、コジマに対して、直接的なものを求めたくなっていく「僕」の気持ちに、せつなさのようなものさえ感じてしまうのだ。
とは言え、コジマという少女は変わった子である。
その変わった感性のため、「僕」との間に、どこか齟齬が生じているのは否めない。
まず彼女が自分の体を汚くしている理由は理解できないし、先にも触れた彼女のはさみの論理も意味がわからない。
「僕」の斜視があいつらはこわいのだ、というのは何となくわかるけれど、僕にはコジマの思想を、最後までわかることができなかった。
だが端的に言ってしまうなら、彼女の理屈は、周囲のものに意味をつけていく、という点で共通しているような気もする。
「ふだん感じてる不安もこの安心も」「とくべつなことだって思ってたい」とコジマは思っている。だからだろうか、自分をいじめるやつらは、何もわからずいじめているにすぎないと、彼女は軽蔑したように語ってもいる。
コジマの考えは、ニーチェ辺りなら、畜群のルサンチマンとでも言いそうな内容である。もっともコジマ的には自分らの側が超人なのだろうけれど。
ともあれ、それはどこか宗教に通じるようなにおいも感じられる。
言うなればファナティックなのだ。
そしてそんなコジマの論理は百瀬の論理と明確な対照を成しているのだ。
百瀬の思想を一言で語るならば、ニヒリズムである。
彼によると、事物には意味がないらしく、いじめもしたいからしていると言う。そして自分の身は自分で守れ、とも言っている。
一見すると、それは真実の一端をついているようにも思う。
だがニヒリズムとは、理性で世界を割り切ろうとする代物である。
理性で割り切ろうとしているから、一面的には正しく見える。
だけどそれは理性で割り切れない感情などを黙殺してもいるのだ。ゆえに冷酷な空気をはらんでもいる。
百瀬の理屈は、別の言い方をするなら、物事の意味を剥ぎ取るということでもある。
そういう点において、物事に意味を付与しようとする、コジマの意見とは対立しているようにも見える。
だけど、意味を付与するにせよ、意味を剥ぎ取るにせよ、それはすべて理性で割り切られることであるという点では共通しているのだ。
コジマと百瀬は異なるようで、実のところ表裏一体なのである。
だからだろうか、思想という点において見ると、「僕」はどちらの側にも与することはできないのだ。
コジマが特別だと言った、「僕」の斜視だって、一万五千円で治るものでしかない。
しかし百瀬が言ったように、斜視は関係ない、と突き放すのも何かが違う。
そしてその「僕」の態度が結果的にはコジマとの仲を裂くことにもなったのだと思う。
「僕」がコジマに斜視の手術のことを話して、仲違いしてしまう場面は、心底悲しかった。
「僕」に限らず、読み手である僕も、コジマには理解してほしかったのだが、偏った考えを持っているコジマには伝わらなかったらしい。それが本当に悲しくてならない。
そして二人の仲が決裂したまま、ラストシーンを迎えるに至る。
ラストの雨の中のシーンは、すばらしいとしか言いようがなかった。
物語的にも、思想的にも、エモーショナルな部分に訴えかけるという点でもまさにクライマックスである。
その中で、個人的に僕が気になったのは、「僕」がいじめられているからと言って、最後まで相手に対して仕返しをできなかったことだ。
どんなことがあれ、「僕」はいじめられていることを理由に、いじめ返すことのできない人間なのだろう。
それはある意味では優しさだと思うのだが、見ようによっては軟弱さでもあると思う。
そしてその軟弱さを、二ノ宮は虐げ、コジマは意味を付与しようとした。
それは、良い悪いと言った倫理的なものではないのだと思う。
そこにあるのは、ただそうである、という事実だけなのだ。
しかしそこで起こった事実こそが、紛れもなくすべてでもあるのだ。
「僕」が二ノ宮たちを殴り返せなかった事実も、コジマが「たったひとりの、僕の大切な友達だ」という事実も、最後に斜視が治った目で見た世界の美しさも、それが事実であり、それがすべてなのである。
そこには意味はないし、意味は付与できない。
しかし、だからと言って、それで切り捨てられるものでもない。
ただ彼の中の倫理と、愛しい者を愛しいと感じる感情と、美しいものを美しいと感じる感性、それこそが意味とかを超越した「僕」にとっての絶対なのだろう、と思う。
あきれるほどの長文になった。
だが『ヘヴン』はそれだけ、長々しくいろいろなことを語りたくなるような作品でもある。
心を動かされ、知的に刺激され、いろいろなことを思わずにいられない。
嫌いな人は嫌いな作品なのだろう。
しかし僕は、『ヘヴン』は長く読まれるに足る傑作である、と本気で信じている。
評価:★★★★★(満点は★★★★★)
初読時の『ヘヴン』感想
『ヘヴン』
そのほかの川上未映子作品感想
『乳と卵』
『わたくし率 イン 歯ー、または世界』