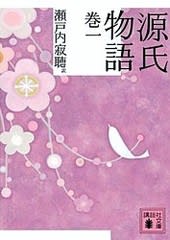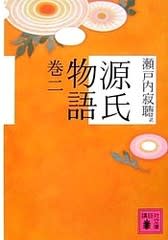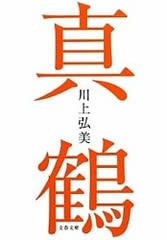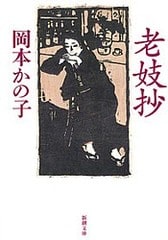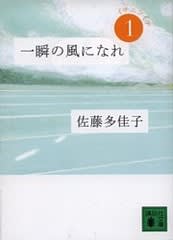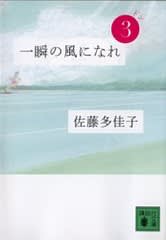成長した薫の君は、宇治に隠棲した源氏の異母弟・八の宮の美しい姫宮二人を垣間見た。姉の大君に求愛するがどこまでも拒まれる一方で老女・弁の君から自らの出生の秘密を明かされる。匂宮と妹宮・中の君との愛の行方は…。
傑作「宇治十帖」の物語が華麗にその幕を開ける。
瀬戸内寂聴 訳
出版社:講談社(講談社文庫)
宇治十帖をけなす人もいる。そう瀬戸内寂聴は言っている。
確かに、宇治十帖は要るかと聞かれたら、要らないのは明白だ。
『源氏物語』というタイトルである以上、光源氏が死んだところで終わるのが、物語的には一番すっきりしているだろうし、宇治十帖の終わり方が、いかにも尻切れとんぼである点も、物語全体の印象を悪くしている。
だが、宇治十帖はおもしろいかと聞かれたら、困ったことにおもしろいのである。
親子四代の物語の締めとして見ると、否定的な印象しか湧いてこないが、宇治十帖を単品として見るなら、(問題点もあるけれど)好きな作品と言わざるをえない。
個人的に、特におもしろかったのは「総角」と「浮舟」の二帖だ。
「総角」で描かれているのは、八の宮の長女、大君と薫の恋である。
この二人が、すばらしいくらいに、イライラさせられるのだ。
この帖で、大君は薫の求婚を徹底的に拒むことになる。
大君がそんな行動に出たのは、父親である八の宮の、軽はずみに結婚するな、という言葉が呪縛のように働いていることが大きい。そのほかにも彼女なりのプライド、引け目、捨てられるのではないかという不安があることも大きいだろう。
そのため、自分は独身を通そうと、大君は頑なに決めている。
正直、彼女の論理を読んでいると、この人は男性不信なんじゃないか、と見えなくもない。
しかし徹底的に突っぱねながらも、彼女は薫を憎からず思ってもいるのだ。
一方の薫は、自分が不義の結果生まれた子という負い目もあってか、世の男のような強引な方法で、女を落とそうとはしない。あくまで相手の気持ちがなびくのを気長に待とうとする。
それは女とは強引に関係を結ぶ、という、当時の常識からすれば異質であろう。
「世間の常識とは異なった並外れた愚か者」と自嘲気味に言うだけのことはあるというものだ(もっとも「総角」以降は負い目よりも欲望を優先するようになるけれど)。
そんな薫の姿は、誠実と言えば、響きはいい。
だが、どっちかと言うと、優柔不断でうじうじとしているだけでもある。
そんな融通の利かない女と、優柔不断な男の恋が、読んでいてやきもきとさせられる。
なぜおまえらはくっつかないんだ、と読んでいて何度思ったことか。
しかしそれゆえに、物語的には楽しめるつくりになっているのだ。
一方の「浮舟」は、薫の愛人であった浮舟が、匂宮に犯されて関係を持つという話である。
この帖のいいところは、薫の愛人でありながら、浮舟がどんどん匂宮に惹かれていっている点だろう。
マジメな薫は、結構細かいところにも目が届いて、気配りもできるし、わりに面倒見もいい方だと思う。
少なくとも浮舟にとって、薫といれば、生活は安定するし、将来も安心して暮らすことはできる。彼女は薫に捨てられるわけにはいかない。
にもかかわらず、浮舟自身は、どんどん匂宮に惹かれていく。そこがおもしろい。
確かに匂宮は女の扱いは上手いし、薫とちがって情熱的に愛を訴えるなど、口説くのも上手い。
女のためなら、遠い道のりをやってくるような行動力はあるし、読む分には性的にも魅力なのだろう(この帖が、『源氏物語』の中で、一番エロティックと思う)。
中の君の妹ということを考えても、浮舟がねちっこい薫より、匂宮に惚れるのは納得できるというものだ。
しかしそれがゆえに、浮舟は悩まざるをえない。
薫には匂宮との関係を隠し続けなくてはいけないけれど、匂宮を好きという気持ちは否定できない。その匂宮が姉の夫とあっては、悩みもひとしおだ。
彼女が精神的に追い詰められていく様は、物語的には非常におもしろい。何ともメロドラマティックである。
このほかにもいろいろ楽しめるポイントはあるが、以上の二つが、宇治十帖のおもしろさを凝縮していると思う。
欠点もあるし、ラストも気に入らないが、個人的に宇治十帖は好きである。
評価:★★★★★(満点は★★★★★)
そのほかの『源氏物語』の感想
『源氏物語 巻一~巻五(桐壺~藤裏葉)』
『源氏物語 巻六・巻七(若菜上~紅梅)』
●追記(あるいはキャラクター論)
宇治十帖のメインキャラクターは基本的にろくでもないやつばかりだ、と僕個人は思う。
たとえば、主人公の薫。
彼は確かに誠実で、細かい気配りができる人なのかもしれない。
だが大君が死んでから、彼の行動はちょっとおかしくなっているとしか思えないのだ。
基本的に彼の行動の基準は、好きだった大君の代わりを求めるということにあるのだろう。
その結果、人妻である中の君を口説いたりもする。その行動を見ていると、何をやっているんだよ、なんて思ってしまう。
浮舟を手に入れたのも、結局は大君の代わりでしかないのだろう。
誰かの代わりに、ちがう女を求めようとする。そんな薫の行動は、どこが誠実? と思ってしまう。
また薫が浮舟を最初に手に入れる場面も、個人的には気に入らなかった。
大君や中の君を口説いているとき、薫は彼女らを抱くチャンスもあった。だが結局抱かず、積極的な行動を差し控える場面は多かったと思う。
しかし浮舟を抱くとき、薫は何のためらいもなく、行動に移している。
この理由は、多分、大君と中の君が八の宮の正妻の子であり、浮舟が妾腹という点が大きいと思う。
薫は身分が低い人には、尊大な態度を取る。
実際、薫は浮舟に関して、愛人として囲うという以上の考えを起こしていない。
彼の誠実は、その程度でしかないのだろう。
そのほかにも陰湿で、煮え切らないなど、欠点ばかりがやたら目に付く(あまり人のことは言えんが)。
前半はいい奴っぽく見えただけに、後半の彼にはがっかりである。
匂宮も結構ダメダメだと思うのだ。
匂宮は確かに情熱的で、女の扱いも上手い。誰が読んでも、まぎれもないプレイボーイである。
それ自体は問題ではない。ただ、いただけないのは、親友である薫の愛人を自分で奪っておきながら、親友を裏切ってしまった、恥ずかしい、と臆面もなく考えていることだ。
言うにことかいて、何言ってんの?バカなの? とそれを読むと、思ってしまう。
匂宮は、浮舟が薫の愛人とわかっていて、行動したはずだ。
恥ずかしいと思うのなら、じゃあ、やんなよ、とどうしてもつっこみたくなる。
ほかにも匂宮に関しては、アホなの?と問いかけたくなる部分が多い。
基本的に考えなしで、節操もないという点がすべてなのだろう。
こんな奴が東宮候補って、このときの朝廷は大丈夫だったのか、と他人事ながら、少し不安になってしまう。
男ばかりけなしているが、女性である浮舟も、ダメな人と思うのだ。
個人的に強くそう思ったのは、小野にかくまわれているときの浮舟の行動にある。
そこでの彼女は命を助けてくれ、かくまってもくれている尼たちとは決して打ち解けようとせず、引きこもっている始末。そこに住んでいるときに言い寄ってきた中将に対する対応だって、それはどうよ、と思うようなまずい対応をとっている。
確かに浮舟には、同情すべき余地が大量にある。
うじうじしたくもなり、引きこもりたくなる気持ちもわかる。何も決定したくない気持ちだってわかる。
記憶喪失になるほどのショックを受けていることからして、ひょっとしたら、彼女はPTSD、というか適応障害を患ったのかもしれない、とちょっと思ったりする。
薫や匂宮のように安易に責めるのも酷だ。
でも、彼女の対応を見ていると、この人は、自分自身のことをかわいそうだと思い、かわいそうな自分に酔っているだけなんじゃないか、という風に読んでいる間、思ってしまった。
ちょっとでもそんなことを思ってしまったために、浮舟の印象は個人的には悪い。
『更級日記』の少女は夕顔と、この浮舟に憧れていた。
それは身分が近いゆえのシンパシーだろうが、僕には
『更級日記』の少女のような気分にはなれなかった。
だがそんな彼女も、出家を決意するときだけは能動的に動いている。
その行動は、浮舟が普段うじうじしているだけに、光るものがある。
それが彼女にとっても、物語にとっても、唯一であり、大きな意味のある光明なのだろう。読後にちょっと、そう思った。