人の主観は科学的に扱いうるか?
と,ブチ上げておきながら,こんなこと,こんなブログで何をか言うことが既に間違ってるのですが,お察しのとおり,何かを結論づけるつもりなど毛ほどもございません。これ,ゼロね。
それどころか,昔話しちゃう,psy-pub,昔話しちゃう,なんて思うのですね,オッサンだから。オサーンだから。
ま,「主観的なものを扱う」つうのは,心理学における永遠の命題のひとつ,ですね。というより,部外者が思う「心理」って,ひとつには,まあ「主観」のことですね。でも,個人にとっては「主観」としか思えないものが,実は「客観的に」理解できたりもするから,まあややこしい。
というか,心理学の父,ヴントさんなんかは,バリバリ主観扱うぜ的なノリ(彼自身は客観を目指したようですが)ありますけどね。やっぱ草創期から,気になるのね,気になってきたのね,主観が。
ただ,以前,どの先生がどこで仰ってたのか忘れたのですが,精神科医の先生が,「医学生(看護学生)が遺体解剖実習を通して,対象化することを学ぶように,心理学の学生は量的研究(質問紙調査等)によって対象化することを学ぶのではないか?」とおっしゃっていた(私信&うろ覚え,ま,この論はかなり好意的ですな)のをいつも思い出すのですが,医師や看護師にとっては,まず対象化ありきなんですな。
とはいえ,医学(あるいは看護学)が,対象化,客観的,科学的と言いつつも(あるいは部外がそういうイメージを持ちつつも),主観あるいは経験あるいは熟練に頼る部分が結構多かったというのは,EBM,なんつうのが出てきたことからも自明ですが,結局ミクスチャーですよ,J-POPですよ,ってことね。人が何かを為す限り,主観的な判断の方が勝っちゃうってことだと思います。Viva赤ひげ先生! ブラックジャック先生,宜しくお願い申し上げまーす,てなもんだ。コトーもいるよ。でもみんな結構当時の最先端を勉強してるのね(フィクションだけどよ)。
ま,ちょい話ずれますけど,心理学って,哲学と科学の鬼子なんて呼ばれたりしますが,主に,科学の方にコンプレックスもっちゃってるので,「客観的であれ」という文言にことさら弱いような気がするのですが,そうやってウジウジやってる間に,脳科学者にクオリアなんて曖昧極まりない概念をゲリラ的に提唱されちゃったりして,なんとも悔しいことになってるわけですよ。アレ,ある種,反則だよな。
ま,学問の歴史は,常に同時並行的でありますから,こうした流れを受けて,というわけでもないけれど,「心理学でも主観扱ってこうよ」ってんで,近年注目を浴びてるのが,質的研究というものであります。聞いたことあると思います。
ま,でもね,考えてみてほしいんですが,心理学さんは幼馴染の主観さんのことがずっと好きなんですが,怖いオヤジ科学さんへのコンプレックスがバリバリなわけで,そのコンプレックスをある種,アイデンティティにして,ここまで成長してきたわけですな。
持ってまわった言い方やめますと,科学コンプレックスがあったおかげで,他領域に負けず劣らずの,強固な研究法の牙城を構築できたわけで,ま,そのおかげで,数々の達成があったわけですよ。変な話,それを捨てたら,心理学が心理学でなくなっちゃう,そんなのイヤン。主観さんにだって,そんな人だとは思わなかったワ,なんて振られちゃうかもしれません。虻蜂取らず,どうする,俺ぇー?
というわけで,科学組系広域暴力団心理組の末端構成員と主観さんとの悲恋は成るのか?(なんだ,そら?)
①心理組の発展のためなら鉄砲玉になる(主観さん,さようなら,俺のこと忘れないでね)
②心理組の運命なんて知ったことか,俺は主観と添い遂げる(オヤジ,今までありがとう)
と,ココで,皆様,ある人のことをお忘れではないでしょうか。そうです,心理学のもう一人の親いわば母親,哲学さんですな。哲学さんはたいへんな肝っ玉母さんでして,ま,やり口自体はクラシックな思索オンリーなわけですが,懐が結構深いのネ。現象学やら,記号論理学だやら,科学哲学やら,生命倫理学やら,なんでもオールジャンルで生み出しちゃう。論客としても宗教さんに匹敵するくらいの長いキャリアをお持ちなんですよ。
と,ここまで書いたところで,うん,じゃあ,どうしよっか? カラオケでも行く? なんてサッパリ盛り上がらなかった合コンの後で,気乗りしないこと夥しいのですが,どうしようかな……。
①どっちつかずが俺のいいところなんだ,と開き直る
②二律背反を止揚するのが知性だろうが,と言葉遊びに逃げつつ逆ギレる
よくわからんね。ま,ここらが限界ですよ。ちなみに以前ロテ職人さんのブログで議論がされておりました。
●質的研究と量的研究
なるほどですね。オモロ。
ま,でも,主観つうのは魅力的ですな。人が何を考えてるんだろう? と思うのは,コミュニケーションの本質でもあります。それを知りたいと思うのも無理からぬこと。しかしながら,魅力的な女性に漠然とアプローチしても,ダメなように,合コンにおいて事前のキャラ作りおよび仲間との打ち合わせが必須なように,アプローチには一考を要すると思われます。敵を知り,己を知れば,百戦危うからず。とりあえず困ったら「竹内結子に似てるね」って言っとけ!(関係ねぇー)。
心理学の枠組みのなかで何かを為したいなら,まず心理学の枠組みを知らねばなりませんね。人の人生には背景があるように,学問にも背景があります。それを肯定的にであれ否定的にであれ,踏まえないことには,それは学問ではありませんな。方法というのは学問自体のアイデンティティでありますから,それを簡単に放棄するのは,私はいかがなものかと思いますよ。
もちろん,新たな可能性を探るのはアリ,です。ただ,自分が何をやろうとしているのか,それが従来の研究法ではなぜできないのか,そこんとこの,最低限の理論武装だけは,よろしく頼むぜ!(※コメント欄に「DIPEx」のことを付記)
というわけで,新刊紹介であります。
執筆陣が,遠藤利彦,能知正博,桜井 厚,茂呂雄二,森岡正芳,南博文と,おおー豪華だー,と思ってたら,質的心理学会のシンポ本でした。あるようで意外となかったのが,背景をおさえたものですが,各論客がきっちり論じてくれてますですよ。
ついでに,各先生の著作,軽く列挙しとこうかね(読んだことないのはコメントなしで)。
上記編者の能智先生による一品。かなり入門編的な内容です。
これ,すごいでっせ。こういうものが書ける人であれば,質的・量的問わず,優れた研究ができるのだろうなあと思います。
質的あるいはナラティブの極北,といった趣。スゴ。
以下は,読んでないけど,オモロそう。
…………
というわけで,投げっぱなし感,なきにしもあらずどころか,例によって,投げっぱなし感オンリーでしかないわけですが,ま,そこんとこは宜しく勘弁,そしてゴッド・ブレス・ユーということで,今日はByeナラ。
と,ブチ上げておきながら,こんなこと,こんなブログで何をか言うことが既に間違ってるのですが,お察しのとおり,何かを結論づけるつもりなど毛ほどもございません。これ,ゼロね。
それどころか,昔話しちゃう,psy-pub,昔話しちゃう,なんて思うのですね,オッサンだから。オサーンだから。
ま,「主観的なものを扱う」つうのは,心理学における永遠の命題のひとつ,ですね。というより,部外者が思う「心理」って,ひとつには,まあ「主観」のことですね。でも,個人にとっては「主観」としか思えないものが,実は「客観的に」理解できたりもするから,まあややこしい。
というか,心理学の父,ヴントさんなんかは,バリバリ主観扱うぜ的なノリ(彼自身は客観を目指したようですが)ありますけどね。やっぱ草創期から,気になるのね,気になってきたのね,主観が。
ただ,以前,どの先生がどこで仰ってたのか忘れたのですが,精神科医の先生が,「医学生(看護学生)が遺体解剖実習を通して,対象化することを学ぶように,心理学の学生は量的研究(質問紙調査等)によって対象化することを学ぶのではないか?」とおっしゃっていた(私信&うろ覚え,ま,この論はかなり好意的ですな)のをいつも思い出すのですが,医師や看護師にとっては,まず対象化ありきなんですな。
とはいえ,医学(あるいは看護学)が,対象化,客観的,科学的と言いつつも(あるいは部外がそういうイメージを持ちつつも),主観あるいは経験あるいは熟練に頼る部分が結構多かったというのは,EBM,なんつうのが出てきたことからも自明ですが,結局ミクスチャーですよ,J-POPですよ,ってことね。人が何かを為す限り,主観的な判断の方が勝っちゃうってことだと思います。Viva赤ひげ先生! ブラックジャック先生,宜しくお願い申し上げまーす,てなもんだ。コトーもいるよ。でもみんな結構当時の最先端を勉強してるのね(フィクションだけどよ)。
ま,ちょい話ずれますけど,心理学って,哲学と科学の鬼子なんて呼ばれたりしますが,主に,科学の方にコンプレックスもっちゃってるので,「客観的であれ」という文言にことさら弱いような気がするのですが,そうやってウジウジやってる間に,脳科学者にクオリアなんて曖昧極まりない概念をゲリラ的に提唱されちゃったりして,なんとも悔しいことになってるわけですよ。アレ,ある種,反則だよな。
ま,学問の歴史は,常に同時並行的でありますから,こうした流れを受けて,というわけでもないけれど,「心理学でも主観扱ってこうよ」ってんで,近年注目を浴びてるのが,質的研究というものであります。聞いたことあると思います。
ま,でもね,考えてみてほしいんですが,心理学さんは幼馴染の主観さんのことがずっと好きなんですが,怖いオヤジ科学さんへのコンプレックスがバリバリなわけで,そのコンプレックスをある種,アイデンティティにして,ここまで成長してきたわけですな。
持ってまわった言い方やめますと,科学コンプレックスがあったおかげで,他領域に負けず劣らずの,強固な研究法の牙城を構築できたわけで,ま,そのおかげで,数々の達成があったわけですよ。変な話,それを捨てたら,心理学が心理学でなくなっちゃう,そんなのイヤン。主観さんにだって,そんな人だとは思わなかったワ,なんて振られちゃうかもしれません。虻蜂取らず,どうする,俺ぇー?
というわけで,科学組系広域暴力団心理組の末端構成員と主観さんとの悲恋は成るのか?(なんだ,そら?)
①心理組の発展のためなら鉄砲玉になる(主観さん,さようなら,俺のこと忘れないでね)
②心理組の運命なんて知ったことか,俺は主観と添い遂げる(オヤジ,今までありがとう)
と,ココで,皆様,ある人のことをお忘れではないでしょうか。そうです,心理学のもう一人の親いわば母親,哲学さんですな。哲学さんはたいへんな肝っ玉母さんでして,ま,やり口自体はクラシックな思索オンリーなわけですが,懐が結構深いのネ。現象学やら,記号論理学だやら,科学哲学やら,生命倫理学やら,なんでもオールジャンルで生み出しちゃう。論客としても宗教さんに匹敵するくらいの長いキャリアをお持ちなんですよ。
と,ここまで書いたところで,うん,じゃあ,どうしよっか? カラオケでも行く? なんてサッパリ盛り上がらなかった合コンの後で,気乗りしないこと夥しいのですが,どうしようかな……。
①どっちつかずが俺のいいところなんだ,と開き直る
②二律背反を止揚するのが知性だろうが,と言葉遊びに逃げつつ逆ギレる
よくわからんね。ま,ここらが限界ですよ。ちなみに以前ロテ職人さんのブログで議論がされておりました。
●質的研究と量的研究
なるほどですね。オモロ。
ま,でも,主観つうのは魅力的ですな。人が何を考えてるんだろう? と思うのは,コミュニケーションの本質でもあります。それを知りたいと思うのも無理からぬこと。しかしながら,魅力的な女性に漠然とアプローチしても,ダメなように,合コンにおいて事前のキャラ作りおよび仲間との打ち合わせが必須なように,アプローチには一考を要すると思われます。敵を知り,己を知れば,百戦危うからず。とりあえず困ったら「竹内結子に似てるね」って言っとけ!(関係ねぇー)。
心理学の枠組みのなかで何かを為したいなら,まず心理学の枠組みを知らねばなりませんね。人の人生には背景があるように,学問にも背景があります。それを肯定的にであれ否定的にであれ,踏まえないことには,それは学問ではありませんな。方法というのは学問自体のアイデンティティでありますから,それを簡単に放棄するのは,私はいかがなものかと思いますよ。
もちろん,新たな可能性を探るのはアリ,です。ただ,自分が何をやろうとしているのか,それが従来の研究法ではなぜできないのか,そこんとこの,最低限の理論武装だけは,よろしく頼むぜ!(※コメント欄に「DIPEx」のことを付記)
というわけで,新刊紹介であります。
 | “語り”と出会う―質的研究の新たな展開に向けて能智 正博 ミネルヴァ書房 2006-12売り上げランキング : 18041Amazonで詳しく見る by G-Tools |
執筆陣が,遠藤利彦,能知正博,桜井 厚,茂呂雄二,森岡正芳,南博文と,おおー豪華だー,と思ってたら,質的心理学会のシンポ本でした。あるようで意外となかったのが,背景をおさえたものですが,各論客がきっちり論じてくれてますですよ。
ついでに,各先生の著作,軽く列挙しとこうかね(読んだことないのはコメントなしで)。
 | 動きながら識る、関わりながら考える―心理学における質的研究の実践伊藤 哲司 田中 共子 能智 正博 ナカニシヤ出版 2005-04売り上げランキング : 144295Amazonで詳しく見る by G-Tools |
上記編者の能智先生による一品。かなり入門編的な内容です。
 | 読む目・読まれる目―視線理解の進化と発達の心理学遠藤 利彦 東京大学出版会 2005-12売り上げランキング : 102541Amazonで詳しく見る by G-Tools |
これ,すごいでっせ。こういうものが書ける人であれば,質的・量的問わず,優れた研究ができるのだろうなあと思います。
 | うつし 臨床の詩学森岡 正芳 みすず書房 2005-09売り上げランキング : 221073Amazonで詳しく見る by G-Tools |
質的あるいはナラティブの極北,といった趣。スゴ。
以下は,読んでないけど,オモロそう。
 | ライフストーリー・インタビュー―質的研究入門桜井 厚 小林 多寿子 せりか書房 2005-12売り上げランキング : 2878Amazonで詳しく見る by G-Tools |
 | 実践のエスノグラフィ茂呂 雄二 金子書房 2001-10売り上げランキング : 124983Amazonで詳しく見る by G-Tools |
 | 環境心理学の新しいかたち南 博文 誠信書房 2006-03売り上げランキング : 246975Amazonで詳しく見る by G-Tools |
…………
というわけで,投げっぱなし感,なきにしもあらずどころか,例によって,投げっぱなし感オンリーでしかないわけですが,ま,そこんとこは宜しく勘弁,そしてゴッド・ブレス・ユーということで,今日はByeナラ。












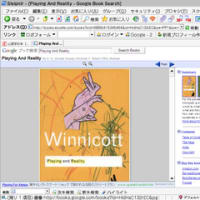


オックスフォード大学などが運営する「患者の“語り”のデータベース」つうのがあるのね。通称「DIPEx」というやつです。スゴイよね,これ。
http://www.dipex.org/DesktopDefault.aspx
日本にも組織ができたのね。
http://homepage2.nifty.com/dipex-j/
目が離せない展開になっております。