
昨日は、社大の学内学会の初日でした。
僕は事務局長として1日、講堂の全体会の司会進行でした。
朝の開会式から、夜の懇親会まで…。
いささか、疲れました。
初日の参加者は、約500人。
「緊張したでしょう?」とか、いろんな方から気遣って頂きました。
笑いも取れず、少々硬い進行になってしまったのは、確かですね。
でも、1会場だけでの進行なら、アドリブでなんとか過ごせますね。
進行の組み立てが、ハッキリしていますし。
裏方の事務局の皆さんが、毎年のことで慣れていますし。
僕は、大会プログラムの舞台を進行管理していくだけの役割です。
☆
午前中は教員による研究報告でした。
研究所特任教授の秋元樹さんの「ソーシャルワークの第3ステージ」。
秋元さんはAPSWEの会長で、昨年のAPC21でもお世話になりました。
世界の動向を踏まえた、グローバルな視点でのベクトルを示して下さいました。
プロフェッショナルのソーシャルワーカーが、やれていることは極めて限られている。
世界の中で、ソーシャルワーカーが仕事として成り立っている国は限られている。
多くの国では、様々な人々の暮らしの課題の解決は、宗教者が担っている。
アジア各国の仏教の寺院は、365日24時間、様々な生活の問題に対応している。
欧米で発達したソーシャルワークをベースとした、アジア視点の定義の見直しは可能か?
遠大な宿題を、ひとつ頂いたような気がします。
専門職大学院教授の今井幸充さんの「認知症高齢者への『介護の手間』指標」の報告。
今井さんは、僕が着任した時の研究科長で、いろいろお世話になっています。
今年で大学を離れ、臨床現場に復帰することが、もうハッキリしています。
「長谷川式」に代わりうるようなイージーな指標は可能か?
認知症に伴うADLの低下と、BPSDによる障害を評価する指標の試み。
それらと実際の「介護の手間」との整合性や距離。
医学的判断と、福祉・介護の関わり方の間にある乖離。
エビデンスを重視する医学と同じようなアウトカムを、福祉領域は示せるのか?
明日のワークショップでの報告につなぐ、興味深い報告でした。
☆
NHKの町永さんの講演の時が、聴衆はやっぱり一番多かったですね。
映像も交えた90分の講演の進行は、さすがでした。
プロのキャスターですから、滑舌の良さは当たり前なんでしょうけど。
パワポの操作も、舞台上で歩きながら、ご自身で後ろ手のリモコン操作で。
聴衆は、画像のタイミングがどうなってるんだろうと思ったのではないでしょうか?
様々な現場を訪ね、色々な人の生活の現実を見てきた上での、メディアからの発信。
「幻想としての福祉」を、どのように暮らしに密着したものにするか?
閉塞的な少子超高齢社会のネガを、どうポジティブに転化できるか?
結論と答えがないと視聴者からクレームが届く、テレビの世界。
答えの出ない問題に、どう思考し、福祉の活路を見出していくのか?
そもそも、「福祉」とはなんなのか?
社会福祉の牙城たる社大は、何を発信していけるのか?
講演だけでなく、控室でもいろいろな示唆に富む話を頂きました。
☆
学会賞(木田賞)の受賞記念スピーチのことは、また改めて。
まもなく、第2日目のプログラム(分科会)がスタートします。










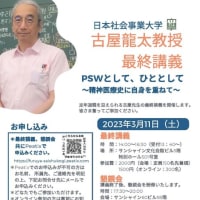
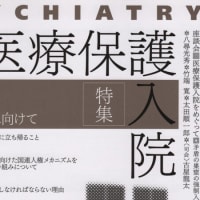
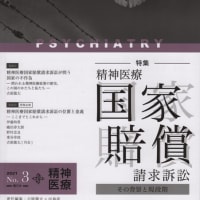




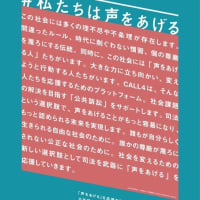
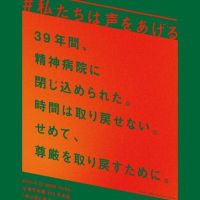
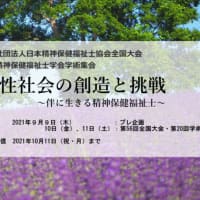
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます