ゆっくり朝食をとる時間は無いので、ホテルの部屋でコーヒーとメロンパンを詰め込んで、いざ出陣!
今回の取材旅行のメインは、本日午前の部。
以前から葉書で申し込んでいた、園城寺にある二つの客殿、光浄院・勧学院の拝観であります。
園城寺は天台寺門宗の総本山。
ものすごく巨大かつ色々なお寺の集合体で、敷地内には国宝、重文の建物がゴロゴロゴロと。
その中でも2つの客殿は、まさに関ヶ原の頃、戦国末期に建てられた、書院造の原型(お寺の方は「試作品」とおっしゃってました)のような建物なのであります。
信長様が建てた本能寺の客殿は、この光浄院に近い構造であったらしいという事で、是非一度見たい見たいと思いつつ、なかなか時間が取れませんでした。
その願い叶ってようやく拝観実現。
国宝という事で写真を撮る事はできませんでしたが、隅々までじっくり見て、思いっきり色々と質問をぶつけてきました。
他の方々と一緒に10人ぐらいの団体で見せて頂いたのですが、その中で一番しつこくねちっこかった奴は、きっとこのわたくしでありましたよ。
変な質問ばかりしてすみませんでした、お坊様。
しかしもんのすごく面白かったです。
目からウロコが落ちまくりだったし。
嘘ばっか描いてんじゃん、自分

と思ったり。
建物自体は本能寺変の10年ほど後に建てられたものだそうですが、その前身の客殿は足利義昭を報じて上京する際、信長公が使っていたそうでして

「この庭は室町期のものなので、信長が眺めたそのままですよ」
と、お坊様。

スゲー!なんだかスゲーッ!!
もう1つ凄いのはこの二棟の客殿、襖絵も全部ホンモノでして、光浄院は狩野山楽、勧学院は狩野光信(永徳の嫡男、「天下一!!」にもちらっと出てる少年)の手によるもの。
普通なら美術館のガラス越しに見るような襖絵を、自然光の元で、殆ど顔をくっつけんばかりにして眺める事ができちゃったりするわけです。

スゲーッ!!めっちゃ楽しいいーん!!
勧学院の、この光信の襖絵の前では、松嶋奈々子の生茶のCM撮影や、B’zのジャケ写撮影なんかも行われたそうで、初期書院造や狩野派の絵なんかどーだっていいやって方々には、そっちの方がよほどスゲーッって感じだったみたいですが。
とにかくとっても面白くて、とっても有意義な時間でありました。

勧学院のお坊様のにゃんこ。
拝観の間ずっと外で待ってて、拝観が終わって帰られるお坊様にくっついて帰っていきました。

「襖絵や柱で爪とぎなんかされたら大変な事になっちゃいますからね…」
とお坊様。
国宝で爪とぎ…ふふふ。
うちの猫どもなら…やる。
きっとやる。
この子は大変に賢い子で、けっして中には入らないようですが。
ソマリに見えるけどミックスだそうで、人懐こい美人さんでした。
お昼ごはんは園城寺門前の食堂で、京都近辺に来たら必ず一度は食べたいにしんそば。
うどん圏の人間なので、蕎麦はあんまり好きじゃないんですが、にしんそばだけは大好きなんですよね。
園城寺を出て、坂本へ。
やはり去年は行き損ねてしまった明智様の坂本城址。

安土の方角を眺めてみました。
その後。琵琶湖大橋を渡って安土へ。
3回目ですよ。安土。

「や、もう安土城址はいいわ…あんな、山のてっぺん…」
と言いながら、桑実寺へ。
先月発売号でちょうど桑実寺事件(?)の前半を描いたところですが、やはり去年行き損ねて、資料本の写真を参考に絵に起こして貰っていて。
しかしやはり臨場感が足らぬので、後半を描く前に一度行っておきたかったのであります。

「六角氏の城があった観音寺山の麓にあるんだって」
と、いいながら、軽い気持ちで参道に車で突っ込んだら、突然行き止まり。
駐車場に車を入れたら「山門まであと××丁(忘れた…)」という表示。

悪い予感…。
…は、的中して、坂道を登った先の目の前に現れたのは…
…石段。
ちょっと、安土城の百々橋口(総見寺側昇り口)を思い出す感じの。

「…ふ、ふもと、なんだよ…ね?」
と、言いつつ続く石段。
そしてようやくたどり着いた山門に置いてあったのは…

…杖!
何故にこんなところに杖…
いやなんとなく分るけれども…考えたく…ない。

山門から先、足場のますます悪くなった石段を、昇れども昇れども本堂は見えず。
…いやもう、罰ゲームですよこれ。

「安土こんなとこばっかーー!!」
…と、ひいひい言いながら昇り続ける事30分ぐらい。
ようやく本堂の屋根が見えてきました。

「お疲れ様でした」
…と、お坊様に頂いたのは「思いやり梅」と書かれた梅干し。
汗で塩分随分流れちゃったしね。
ありがとうございますです。

本堂は、想像していたよりずっと小さくてびっくり。
写真じゃ大きく見えたのになあ。
こういう事があるから、実際見てみないと分んないんだ。
室町期開祖以来、一度も戦禍に合っていないお寺なのだそうで、おそらくはここも当時のまんまであります。
でも後半は、これでもっとリアリティ持って描けるハズ。
帰りはまたふらふらしながら石段を下る下る。
それにしても当日、安土山を降りて長浜まで馬、竹生島まで船のコースを日帰り往復して、また安土山に登って降りて、更にこの本堂まで駆け上がってきた筈の信長様とお小姓ズ。

「信長様のお小姓は、ぜっっったい体育会系でないと勤まらんっっ!」
と、ひいひい言いながら下って行きました。
…良かった。
虎を体育会系女子高生に設定しておいて。
後で調べたら、桑実寺と安土城天守の標高は、ほぼ同じ位の高さでした。
…かんのんじやまの、「ふもと」…。
つまり観音寺山は、安土山の何倍もでっかい山なわけで。
信長は最初、安土城を観音寺山に建てようとしたけど、家臣の大反対にあって安土山に変更した…という話を、資料本のうちのどこかで読んだ気がするんだけど…分るよその気持ち。…うん。

観音寺山の山裾に建つ資料館、「信長の館」。
「戦国の城・安土城まで」という特別展が開催されていると知り、急遽予定変更して明日もう一度安土を訪れる事に。
それにしても、去年も同じ時期に来たせいか、安土は田を焼く香りと煙の棚引く、静かな土地という印象。
信長様の安寧楽土。
落ち着くなあ。好きだなあここ。
しみじみと夕暮れの安土を眺めて、帰りは近江八幡「毛利志満」へ。

去年食べ損ねて、夢にまで出た近江牛。
刺身~石焼~握りのコースで頂きました。
出されたポン酢ではなく、テーブルに備えてあった塩で食べてたら、気づいたお店の方がわざわざゲラントの岩塩を出して下さいました。
初めて食べた近江牛は、霜降りでもあっさりしたお味でした。
美味しかった~。
とにかくメインの取材を無事終えて、ホッとしましたの事。

ポチッと応援してやって下さい!
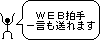

 「よくこんな過去があるのにそっくりさんな虎にきゅんきゅんできますよね…」
「よくこんな過去があるのにそっくりさんな虎にきゅんきゅんできますよね…」 「Mだからさ
「Mだからさ 」
」 させられる状態に弱いんですよきっと。
させられる状態に弱いんですよきっと。 「おうおう、聖武天皇は今週のマンガ日本史で読んだし、鑑真和上は来週だよっ」
「おうおう、聖武天皇は今週のマンガ日本史で読んだし、鑑真和上は来週だよっ」
 「やっぱ来年あたり奈良行きたいねえ」
「やっぱ来年あたり奈良行きたいねえ」
 ポチッと応援してやって下さい!
ポチッと応援してやって下さい!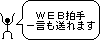


















 「ウィングス」(「天下一!!」12話掲載)発売
「ウィングス」(「天下一!!」12話掲載)発売 「スピカ」(「デアマンテ」カウントダウン・ラストまで4話目掲載)配信
「スピカ」(「デアマンテ」カウントダウン・ラストまで4話目掲載)配信
 」
」 」と喜んでらした設定が出ます。
」と喜んでらした設定が出ます。 「ブログに載せるイラストを、もう少し大きくできませんか?」
「ブログに載せるイラストを、もう少し大きくできませんか?」

 よく作る料理のひとつで、ダンナさまの大好物、豚の角煮であります。
よく作る料理のひとつで、ダンナさまの大好物、豚の角煮であります。


 さて。今夜もまだこれからどっぷりと資料読みです。
さて。今夜もまだこれからどっぷりと資料読みです。 クリックしたら飛べます)
クリックしたら飛べます)
 「織田信長の墓参り。お彼岸だし」
「織田信長の墓参り。お彼岸だし」
 「お土産もの屋さんの真空パックのとかはね、かなり危険なものもありますよ…」
「お土産もの屋さんの真空パックのとかはね、かなり危険なものもありますよ…」 時既に遅く、もう買っちゃってたし。
時既に遅く、もう買っちゃってたし。 「開けた瞬間、家中がう×こ
「開けた瞬間、家中がう×こ の臭いになっちゃってっっ!!」
の臭いになっちゃってっっ!!」 「あっ!あれ欲しい!あれどこで買ったんやろ!?」
「あっ!あれ欲しい!あれどこで買ったんやろ!?」 「本当は長浜の『時代屋』ってお店に行ってみたかったんだよなー」
「本当は長浜の『時代屋』ってお店に行ってみたかったんだよなー」

 リアル歴女
リアル歴女 先日編集部から返信ありました。
先日編集部から返信ありました。
 「この角度の山の形が分んないんすよ!!」
「この角度の山の形が分んないんすよ!!」



 と思ったり。
と思ったり。 「この庭は室町期のものなので、信長が眺めたそのままですよ」
「この庭は室町期のものなので、信長が眺めたそのままですよ」 スゲーッ!!めっちゃ楽しいいーん!!
スゲーッ!!めっちゃ楽しいいーん!!
 「襖絵や柱で爪とぎなんかされたら大変な事になっちゃいますからね…」
「襖絵や柱で爪とぎなんかされたら大変な事になっちゃいますからね…」

 「安土こんなとこばっかーー!!」
「安土こんなとこばっかーー!!」 「お疲れ様でした」
「お疲れ様でした」
















 」みたいなネタバレ部分に関するご質問が結構ありました。
」みたいなネタバレ部分に関するご質問が結構ありました。





