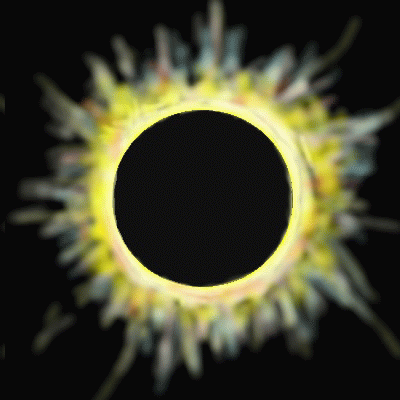FC2ブログ「パそぼとベルルのあれこれフリーク Part2」に引っ越しました。
2025年5月22日 GooブログからFC2ブログへ引越しました。
NEW FC2ブログ パそぼとベルルのあれこれフリーク Part2
★ 皆さん! 新しいブログでお会いしましょう! (*^_^*)♪
NEW FC2ブログ パそぼとベルルのあれこれフリーク Part2
★ 皆さん! 新しいブログでお会いしましょう! (*^_^*)♪





8月以降、近日点通過の11月29日までは、日の出前の東の空に位置し、8月にはふたご座からかに座方向に移動します。この頃の太陽からの距離は2天文単位以上とまだ遠く、まだまだ観察しやすい明るさにはなりません。
9月から10月にかけてしし座方向へと移り、見かけ上、火星と接近します。
10月上旬から中旬は、順行する火星と一緒にしし座の中を移動していきます。
2013年11月から近日点通過まで
アイソン彗星は、11月上旬には、日の出前の空で、しし座からおとめ座方向に移ります。ようやく太陽からの距離も1天文単位を切るようになり、1日の見かけの移動量も大きくなります。
11月後半には双眼鏡で見つけられる程度の明るさになると予想されており、条件がよければ肉眼でも見つけられるかもしれません。
ただし、東の空での高度は日に日に低くなるため、東の空が開けた場所での観察が必要になります。
11月18日にはおとめ座の1等星スピカと見かけ上近づき、スピカが彗星を探す際のよい目印になります。
11月17日、18日、19日には、スピカとアイソン彗星を双眼鏡の同一視野で見ることができます。
11月下旬には、急激に増光する可能性があります。肉眼でも尾が確認できるようになることを期待したいものです。
この頃には、おとめ座からてんびん座方向へと移り、日の出前の東の空での高度はどんどん低くなって行きます。
11月24日前後には、東の低空にある水星、土星と見かけ上近づきます。
近日点通過数日前のこの頃には、アイソン彗星の明るさはいよいよマイナス等級に達すると予想されますが、見かけの位置も太陽にひじょうに近く高度も低くなり、観察はかなり難しくなります。
以降、近日点通過後まで眼視での観察は小休止となります。
12月に入ると、近日点を過ぎたアイソン彗星は、次第に太陽から遠ざかり、再び日の出前の東の空に姿を現します。へびつかい座からへび座(頭)方向に移動し、高度は日に日に高くなって、日を追うごとに観察しやすくなります。尾は近日点通過前よりも長く伸びて見やすくなると予想されています。
12月後半は、へび座(頭)からヘルクレス座、かんむり座方向へと移動し、下旬には日の出前の東の空だけでなく日の入り後の西の空でも観察できるようになります。
12月27日頃には地球に最も近づきますが、近日点通過直後のような明るさはおそらく期待できないでしょう。
12月末から1月末までは、周極星となり一晩中沈まずに北の空に見え続け、1月8日には北極星に最も近づきます。
この頃には、双眼鏡や望遠鏡を使わないと見つけられない明るさになっているでしょう。




国立天文台では、多くの方に夜空を眺める機会を持っていただこうと、8月に活動するペルセウス座流星群を対象にして、「夏の夜・流れ星を数えよう」キャンペーンをおこないます。ペルセウス座流星群の活動が活発になる8月11日の夜から14日の朝にかけて、15分以上夜空を眺めていただき、その間に何個の流れ星を見ることができたかを報告ページから報告してください。...(詳細はこちらをご覧ください)













東京では、2時43分に東の空に昇って間もない半月状の金星が、月の明るく輝く側から1分ほどかけて月の後ろに隠れていく。そして3時28分から1分半ほどかけて月の影になっている部分から姿を見せる。金星が月の後ろに隠れるときの高度は、全国的に10度前後と低いので、観望は東の空が地平線まで開けたところを事前に探しておこう。金星が姿を見せるころには、月の高度は20度ほどになっている。
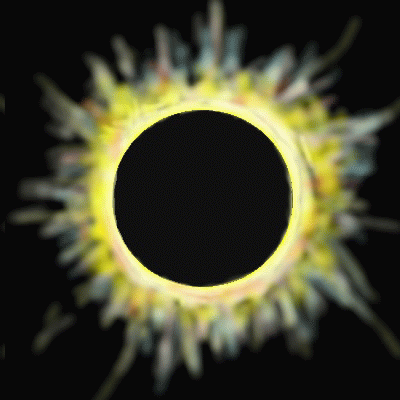
金環日食では、太陽がドーナツ状に見え、曇りのときのようにあたりが薄暗くなる様子を観察することができます。
(皆既日食のようにコロナやプロミネンスが見えたり、星が見えるほどに暗くなったりはしません)
日本の陸地に限ると、金環日食が観察できるのは、1987年9月23日に沖縄本島などで見られた金環日食以来のことです。
次回も 2030年6月1日に北海道で見られる金環日食まで、18年間起こりません。非常に珍しい現象と言えるでしょう。









皆既月食、16日夜明け前に 国内半年ぶり、関東以西で
2011年6月14日19時40分
16日の夜明け前、月が地球の影に完全に隠れる皆既月食が関東以西の地域で見られる。
国立天文台によると、皆既は午前4時22分から6時3分。
茨城県と新潟県を結ぶ線より北の地域では、皆既になる前に月が沈むため、部分月食しか見られないという。
皆既月食は太陽と地球、月が一直線に並ぶ現象。国内では昨年12月以来となる。
今回の皆既は、月が高い位置にある南西の地域が見られる可能性が高い。
東京では高度が0.5度と低く、月が沈むまで5分間だけ。
名古屋は18分間、大阪は25分間、福岡は49分、沖縄は1時間19分となる。



今年6月、日本の小惑星探査機「はやぶさ」が7年の旅を終えて地球に帰還した。人類初の快挙となった小惑星「イトカワ」への往復の旅は、次々に降りかかる困難との闘いでもあった。
2003年5月に打ち上げられたはやぶさは、2年後に小惑星イトカワに到達、世界で初めて小惑星への離着陸に成功した。しかしその直後、燃料漏れやエンジンの損傷などが相次ぎ、当初4年で帰還する予定だった計画を7年に延期する必要に迫られた。
はやぶさのトラブル続きの旅を支え、ミッションを成功に導く原動力となったのが、日本が独自に開発した「イオンエンジン」だ。イオンエンジンは燃費に優れているのが特徴で1960年代にアメリカで開発された。これまで静止衛星の方向転換などに使われてきたが、惑星間を飛行するための連続運転には向かないとされてきた。そこで、はやぶさプロジェクトでは、耐久性を高めて長期間の連続運転を実現するために「マイクロ波イオンエンジン」を開発。1万8千時間=750日に及ぶ耐久試験を2回敢行し、惑星間の飛行に耐えるエンジンを完成させた。
さらにイオンエンジンは、最後の難関となった地球帰還の場面でも活躍。方向転換用の化学エンジンが損傷したため、イオンエンジンから燃料を噴出するという想定外の運用で軌道修正を行い、地球への再突入を成功させたのだ。
はやぶさは自らは大気圏で燃え尽きながら、イトカワのサンプルを入れるカプセルを分離、無事地球に送り届けた。カプセルには、これまでに数十粒の微粒子が入っていることが確認され、イトカワのものであるかどうか分析が進められている。微粒子の大きさは、いずれも10マイクロメートル程度。この微少なサンプルを分析するのは、最新の2次イオン質量分析装置・通称「SIMS」だ。SIMSで微粒子を解析すれば、イトカワなどの小惑星が太陽系誕生からどれくらい後に出来たかを特定できるため、地球を含めた太陽系形成のプロセスを知る大きな手がかりになると期待されている。
スタジオには、はやぶさプロジェクトのリーダー・川口淳一郎さんを迎え、7年に及ぶはやぶさプロジェクトの舞台裏について語ってもらう。