作品を読む ⑨ (加藤治郎)
※加藤治郎の以下の短歌は、ツイッターの「加藤治郎bot」から採られている。
表現の世界に入り込まない普通の生活者でも、ふと自分の子ども時代やその家族を振り返ることはあるだろう。そのような過去には、客観的な視線では数え切れないほどたくさんの場面があるはずだとなるが、記憶の海からよく引き揚げられるものとそうでないものとがあり、引き揚げられてくるものはそんなに多くないように感じられる。よく想起されものは、記憶の海からなぜかよく引き揚げられるものであるが、それにはその人の「太洋期」(吉本隆明『母型論』)辺りに始まる心性の固有性の有り様が大きく関わっているように思われる。他人にも自身にも、意識的・無意識的なものが関わるその場面の微妙を伴う総量はよくわからない。また、そのような人間的な心的な機構については現在でも依然としてよくわかってはいない。
表現者の場合には、普通の人々がふと自分の過去を想起したり、振り返ってみたりする自然性とは少し違っている。作者は、自らの想起する自然性を含めて、表現の場に或るモチーフを携えて意識的に内省的にイメージを構成することになる。もちろん、そこにも作者の無意識的な部分も存在する。
おそらく少年期や青年期やその頃の家族を対象としたと思われる作品を任意に取り出してみる。
85.父の音妹の音思い居り蜜柑の霧につつまれて寝る 加藤治郎『ハレアカラ』
86.弟は鏡の裏の錆をいうそれはわたしのとおい砂浜 加藤治郎 『雨の日の回顧展』
87.ママの肩にタオルがのせてあることの悲しくて去る昼の美容院 加藤治郎『昏睡のパラダイス』
88.くらがりに下着をたたむいもうとをみまもるわれはかなしかりけり 加藤治郎『しんきろう』
89.ひるさがり天道虫を手首から腕に這わせて妹は眠る 加藤治郎『ハレアカラ』
90.てのひらの花びらを吹くいもうとよおろかな恋におちてわたしは 加藤治郎 『雨の日の回顧展』
91.きりんさんしゃんぷうかして はいはあい電球いろのいもうとの足 加藤治郎『マイ・ロマンサー』
92.みのむしのふかるる昼はねむたくてぼくらダンボールの聖堂にいる 加藤治郎『しんきろう』
93.父とわれ食券それぞれ握ってたビーフカレーのとろけるビーフ 加藤治郎『しんきろう』
94.人生に夜明けがあれば小学校野球部入部テストの暴投 加藤治郎『ハレアカラ』
95.人形のお腹を裂けば(おにいちゃんったら)地下鉄の路線図みたい 加藤治郎『環状線のモンスター』
96.王冠のビールの匂い嗅いでいたあの夏の午後少年だった 加藤治郎『しんきろう』
97.おひるねのうさぎの顔を先生がまたいでゆくぜ ぼくらの薄目 加藤治郎『マイ・ロマンサー』
98.シーソーの上がったままのいもうとを見つめてぼくはゆうばえのなか 加藤治郎『しんきろう』
人が詩(短歌)を作る場合、表現世界に向かう〈作者〉に変身して、具体的には物語で言えば〈語り手〉や〈登場人物〉のように〈私〉あるいは〈彼(彼女)〉が表現の舞台上を走行する。〈作者〉は、それを書き留める者でもあるが、その舞台を背後で監督のように眺める者でもある。物語の場合、作者のモチーフを担うのは、作品世界全体ではあるが、主要には〈語り手〉に導かれた〈登場人物〉の中の主人公である。詩の場合は、作者のモチーフを担うのは、物語の〈語り手〉と〈登場人物〉が二重化した〈私〉の振る舞いにおいてと言えそうである。〈作者〉と作者が表現の舞台に派遣する〈私〉とは同じと見なしてもよさそうだが、実際は〈私〉は、私小説的な〈私〉をも含む想像によって仮構された〈私〉である。また、例えば、作者はそのひとつひとつの作品群の歴史をも担いそれらに責任を持つ者であるが、〈私〉はある表現の舞台における一回性の存在である。こういう意味でも〈作者〉と作者が表現の舞台に派遣する〈私〉とは区別すべきだと思われる。
この少年期・青年期やその頃の家族を対象とした作品には、大まかに三種類に分けられるように見える。ひとつは、子ども時代に遡行した〈私〉がその過去の時空に入り込んで見聞きしたことや行動したこと自体の表現(85、87、88、89、90、91、95、98)。ふたつ目は、前者のようでありつつ、そこに〈私〉の現在の視線や考えが介入している表現(92「みのむしのふかるる昼は」、94「人生に夜明けがあれば」、97「(またいで)ゆくぜ」)。最後は、現在の〈私〉が過去を回想的に表現したもの(86、93,96)。
93は、ひとつ目に入れてもよさそうだとか、はっきりと分け難いのもあるが、これは、作者の表現の手法を示すもので、別に大きな意味はない。しかし、これらはわたしたちが自身の過去を対象化する場合のやり方でもある。
いずれにしても、表現の世界を志向したとき、現在の〈作者〉の意識的、無意識的なモチーフが、過去の時空へ行って帰ってきて、これらの言葉を引き寄せ、連結し、かたち成さしめたという点では同一である。
ここに描かれている場面は、日常の中のささいな場面である。なぜそれが読者の感動を呼び起こすのだろうか。無数に言葉が消費されている現代では、風景と同じように言葉を眺めていたら、感興もなくそのまま通り過ぎてしまいそうである。自分自身の言葉の場合を含めて、言葉も眺められる外皮は、月並みな乾いたものに見えるかもしれない。現在は、心と同じく言葉も疲弊している。正しくは、疲弊した外界の精神的な大気に浸かった心は、つい疲弊した言葉の風景を引き寄せると言うべきか。それでも人は、みどりやひかりを求めようとする。
そうした時、作品の言葉との出会いは、なにものかを起動させる。誰もが同じような少年期や家族を経験して現在がある。その「同じような」ということが、作品の言葉によって読者の過去を喚起させ、作品のイメージ世界にダイブさせる。そうして、ある場合には苦を伴いつつも、生きてきた、生きているということに柔らかなライトが当たる。それが言葉に言い表しがたい無量の思いをわたしたちに湧き上がらせるのだろうと思う。作品との出会いは、同時に自分との出会いにもなっている。
※加藤治郎の以下の短歌は、ツイッターの「加藤治郎bot」から採られている。
表現の世界に入り込まない普通の生活者でも、ふと自分の子ども時代やその家族を振り返ることはあるだろう。そのような過去には、客観的な視線では数え切れないほどたくさんの場面があるはずだとなるが、記憶の海からよく引き揚げられるものとそうでないものとがあり、引き揚げられてくるものはそんなに多くないように感じられる。よく想起されものは、記憶の海からなぜかよく引き揚げられるものであるが、それにはその人の「太洋期」(吉本隆明『母型論』)辺りに始まる心性の固有性の有り様が大きく関わっているように思われる。他人にも自身にも、意識的・無意識的なものが関わるその場面の微妙を伴う総量はよくわからない。また、そのような人間的な心的な機構については現在でも依然としてよくわかってはいない。
表現者の場合には、普通の人々がふと自分の過去を想起したり、振り返ってみたりする自然性とは少し違っている。作者は、自らの想起する自然性を含めて、表現の場に或るモチーフを携えて意識的に内省的にイメージを構成することになる。もちろん、そこにも作者の無意識的な部分も存在する。
おそらく少年期や青年期やその頃の家族を対象としたと思われる作品を任意に取り出してみる。
85.父の音妹の音思い居り蜜柑の霧につつまれて寝る 加藤治郎『ハレアカラ』
86.弟は鏡の裏の錆をいうそれはわたしのとおい砂浜 加藤治郎 『雨の日の回顧展』
87.ママの肩にタオルがのせてあることの悲しくて去る昼の美容院 加藤治郎『昏睡のパラダイス』
88.くらがりに下着をたたむいもうとをみまもるわれはかなしかりけり 加藤治郎『しんきろう』
89.ひるさがり天道虫を手首から腕に這わせて妹は眠る 加藤治郎『ハレアカラ』
90.てのひらの花びらを吹くいもうとよおろかな恋におちてわたしは 加藤治郎 『雨の日の回顧展』
91.きりんさんしゃんぷうかして はいはあい電球いろのいもうとの足 加藤治郎『マイ・ロマンサー』
92.みのむしのふかるる昼はねむたくてぼくらダンボールの聖堂にいる 加藤治郎『しんきろう』
93.父とわれ食券それぞれ握ってたビーフカレーのとろけるビーフ 加藤治郎『しんきろう』
94.人生に夜明けがあれば小学校野球部入部テストの暴投 加藤治郎『ハレアカラ』
95.人形のお腹を裂けば(おにいちゃんったら)地下鉄の路線図みたい 加藤治郎『環状線のモンスター』
96.王冠のビールの匂い嗅いでいたあの夏の午後少年だった 加藤治郎『しんきろう』
97.おひるねのうさぎの顔を先生がまたいでゆくぜ ぼくらの薄目 加藤治郎『マイ・ロマンサー』
98.シーソーの上がったままのいもうとを見つめてぼくはゆうばえのなか 加藤治郎『しんきろう』
人が詩(短歌)を作る場合、表現世界に向かう〈作者〉に変身して、具体的には物語で言えば〈語り手〉や〈登場人物〉のように〈私〉あるいは〈彼(彼女)〉が表現の舞台上を走行する。〈作者〉は、それを書き留める者でもあるが、その舞台を背後で監督のように眺める者でもある。物語の場合、作者のモチーフを担うのは、作品世界全体ではあるが、主要には〈語り手〉に導かれた〈登場人物〉の中の主人公である。詩の場合は、作者のモチーフを担うのは、物語の〈語り手〉と〈登場人物〉が二重化した〈私〉の振る舞いにおいてと言えそうである。〈作者〉と作者が表現の舞台に派遣する〈私〉とは同じと見なしてもよさそうだが、実際は〈私〉は、私小説的な〈私〉をも含む想像によって仮構された〈私〉である。また、例えば、作者はそのひとつひとつの作品群の歴史をも担いそれらに責任を持つ者であるが、〈私〉はある表現の舞台における一回性の存在である。こういう意味でも〈作者〉と作者が表現の舞台に派遣する〈私〉とは区別すべきだと思われる。
この少年期・青年期やその頃の家族を対象とした作品には、大まかに三種類に分けられるように見える。ひとつは、子ども時代に遡行した〈私〉がその過去の時空に入り込んで見聞きしたことや行動したこと自体の表現(85、87、88、89、90、91、95、98)。ふたつ目は、前者のようでありつつ、そこに〈私〉の現在の視線や考えが介入している表現(92「みのむしのふかるる昼は」、94「人生に夜明けがあれば」、97「(またいで)ゆくぜ」)。最後は、現在の〈私〉が過去を回想的に表現したもの(86、93,96)。
93は、ひとつ目に入れてもよさそうだとか、はっきりと分け難いのもあるが、これは、作者の表現の手法を示すもので、別に大きな意味はない。しかし、これらはわたしたちが自身の過去を対象化する場合のやり方でもある。
いずれにしても、表現の世界を志向したとき、現在の〈作者〉の意識的、無意識的なモチーフが、過去の時空へ行って帰ってきて、これらの言葉を引き寄せ、連結し、かたち成さしめたという点では同一である。
ここに描かれている場面は、日常の中のささいな場面である。なぜそれが読者の感動を呼び起こすのだろうか。無数に言葉が消費されている現代では、風景と同じように言葉を眺めていたら、感興もなくそのまま通り過ぎてしまいそうである。自分自身の言葉の場合を含めて、言葉も眺められる外皮は、月並みな乾いたものに見えるかもしれない。現在は、心と同じく言葉も疲弊している。正しくは、疲弊した外界の精神的な大気に浸かった心は、つい疲弊した言葉の風景を引き寄せると言うべきか。それでも人は、みどりやひかりを求めようとする。
そうした時、作品の言葉との出会いは、なにものかを起動させる。誰もが同じような少年期や家族を経験して現在がある。その「同じような」ということが、作品の言葉によって読者の過去を喚起させ、作品のイメージ世界にダイブさせる。そうして、ある場合には苦を伴いつつも、生きてきた、生きているということに柔らかなライトが当たる。それが言葉に言い表しがたい無量の思いをわたしたちに湧き上がらせるのだろうと思う。作品との出会いは、同時に自分との出会いにもなっている。











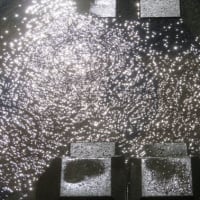








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます