「Listening――あなたの声を聞きたい」は、記事をもとに読者の皆さんと議論を深める場所です。たくさんの自由で率直なご意見をお待ちしています。利用規約はこちら
2014年06月13日
福井地裁が、関西電力に大飯原発3、4号機(福井県)の運転差し止めを命じる判決を言い渡した。
東日本大震災を受けて示されたこの異例の判断を、どう受け止めるべきか。
◇司法の矜恃と覚悟、示した−−井戸謙一・弁護士
大飯原発の運転差し止めを命じた福井地裁判決は、「司法の矜恃(きょうじ)」を示した。東京電力福島第 1原発事故を経験した今、裁判所が原発の具体的危険性の有無について判断を避けるのは、重大な責務の放棄を意味する。しかし今回の判決は、真正面から原発 の問題に向き合い「具体的危険性がある」と結論付けた。担当裁判官たちの強い覚悟や思い入れが表れている。
原発訴訟で裁判所は、行政による原発の設置許可や安全基準が妥当かどうかを判断枠組みとして採用し、大 半のケースで行政の判断を追認してきた。しかし、今回の判決は、行政の判断は一つの判断に過ぎないとし、主体的に原発の具体的危険性の有無に踏み込んだ。 「行政は行政、司法は司法」という姿勢を明確に打ち出している。
私は2006年に金沢地裁の裁判長として志賀原発2号機の運転差し止めを命じる判決を出した。当時はま だ国内で原発の過酷事故が起きておらず、原発の危険性といっても現実味が乏しかった。「なんだかんだ言っても大丈夫なのではないか」という雰囲気があり、 プレッシャーがなかったわけではない。しかし今はあらゆる状況が変わった。
福島第1原発事故で、国民も過酷事故は起こりうると認識するようになった。一方で裁判所が危険性の有無を判断する際に依拠してきた専門家の信頼性は損なわれた。原発を止めると国民の生活に深刻な支障が出るとしてきた国の説明も事実と異なることが判明した。
今回の判決に対しては「ゼロリスクを求める内容で、科学技術の発展を阻害する」との批判があるが、それ は当たらない。判決は「隕石(いんせき)が落ちるかもしれない」といった抽象的な危険性を指摘しているわけではない。関電が設定した基準地震動を超える大 地震が実際に起きているという具体的根拠に基づいて現実的な危険性を示している。「判決の論理だと新幹線だって止めないといけない」との指摘も、判決内容 を全く理解していない。
原子力規制委員会の審査が終わる前に判決を出したことに対する批判もあるが、これも当たらない。判決 は、規制委員会の新しい規制基準自体がおかしいとの考えに基づいている。審査の前提となる基準がナンセンスだと言っている以上、その基準に沿って審査して いる規制委員会の結論を待つ必要はない。
裁判は控訴審に移るが、高裁でも1審判決が維持される可能性が高いと思う。明確な根拠に基づいて具体的 な危険性があるとした判決に対し、関電側がさらに反論するのは難しい。同種訴訟への影響も大きい。今回の判決は基準地震動の設定の仕方や使用済み核燃料の 保管状況など、どの原発にも共通する問題で差し止めを命じており、他の裁判所が今回と同じ判断枠組みを採用すれば、同様の判断をすることになるだろう。
行政には政策的な裁量があるが、国民の生活の根底を破壊しかねない原発の問題では、個人の人権救済を責 務としている司法が遠慮せずものを言う必要がある。今、全国で多くの原発訴訟が起きている。国や電力会社を相手取って裁判を起こすこと自体、大変な覚悟や 負担がいるにもかかわらず、国民が声を上げている。裁判官は、その声を正面から受け止めて判断してほしい。【聞き手・伊藤一郎】
◇根拠は一方的な決めつけ−−住田健二・元原子力安全委員長代理
福井地裁の判決は、原子力に携わる人なら犯さない思い違いや一方的な決めつけを根拠にしている。「原発の運転差し止め」という重大な判断をするなら、科学的根拠に基づかなければならない。上級審で覆すことが極めて易しい、不用意な判決といえる。
大飯原発は加圧水型で、沸騰水型の東京電力福島第1原発と原子炉の形が違う。さらに福島第1原発は沸騰 水型の中でも古い。判決ではこうした点を論じず、ただ「原発」と十把一からげにして飛躍しすぎている。例えるならば、最新式の車も、古いタイプと一緒にし て「車は危険」と言っているようなものだ。
具体的には、原発事故で250キロ圏の人格権が損なわれる▽地震によって冷却や閉じ込めの機能が維持で きなくなる、などが主な指摘だが、どれも科学的根拠に乏しい。250キロとしたのは、福島第1原発事故のさなかに近藤駿介原子力委員長(当時)が出した私 見に過ぎず、実際に250キロ圏の全住民に被害があったのではない。関西電力が最大の地震の揺れ「基準地震動」として想定した700ガル(ガルは加速度の 単位)も、国内で観測した最大の揺れが4022ガルであることや、これまで4原発で計5回、基準地震動を超える揺れが起きたことなどを理由に「信頼性がな い」とした。しかし、大飯原発は揺れに強い岩盤の上に建ち、地質の構造が違う。これら4原発も福島第1原発を除いて事故は起こさなかった。
安全設計の基本的な考え方は「多重防護」にある。基準を設定し、基準を超えた場合でも耐えられる余裕を 持たせる。さらにそれ以上の事態が起きた場合に備え、複数の手段による安全対策を設け、どれか一つでも機能すれば事故の進展を食い止められるようにする。 これは原発に限らず工学全般に言える。だが判決では多重防護を否定し、地震の揺れが700ガルを超えなくても機器がすぐに壊れたり、事故に進展したりする 危険性があると指摘しており、工学的考え方と相いれない。
私は1999年のJCO臨界事故(茨城県東海村)で、原子力安全委員長代理として現場の陣頭指揮を執っ た。臨界が続いているかを確認する危険な作業だったが「事故を起こした責任がある」とJCO社員を説得し、十数人に現場に入ってもらった。福島第1原発で は不幸にして事故の進展を止められなかったが、東電の社員や作業員は現場に残った。判決で「混乱と焦燥の中で、適切かつ迅速に(安全対策の)措置をとるこ とを原発の従業員に求めることはできない」と言及したが、職業人の使命感を否定するような言葉であり、かえって現場の萎縮を招いてしまう。
この裁判はわずか1年半で審理された。原子力の「素人」である裁判官が短期間でよく勉強したとは思う が、原告、被告ともに原子力の専門家を証人申請していない。多くの専門家から意見を聞いてより慎重に審理したのなら、たとえ同じ結論であっても、より意味 のある判決になったのではないか。
原発事故という取り返しのつかない失態を犯したことは事実だ。人権を尊重するという裁判所の考え自体は 賛成だが、「絶対安全」というシステムは存在しないことを理解する必要がある。原発を使うことは確かにリスクがあるが「正しく怖がる」ことを考えるべき だ。【聞き手・酒造唯】
◇「経済至上」に一石投じた−−柳田邦男・ノンフィクション作家
福島第1原発事故の最大の教訓は、広大な地域が放射性物質で汚染されたことで、何十万人もの住民が生活 と人生を壊され、その関連で死亡した人が1000人余に上ったことだ。まさに人格権、生存権の重大な侵害だ。しかし政府と経済界は、その教訓を直視せず に、原発なしでは日本経済の再生に重大なブレーキがかかると喧伝(けんでん)し、再稼働を急ごうとしている。
万が一でも原発事故のリスクがある場合、予想される国民の生存権の侵害と経済成長の重要性を同じレベル のものとして選択するというあり方自体に妥当性はあるのか。これは単なる技術論や法律論を超えた国のあり方や倫理に関わる高位の視点からの議論が不可欠 だ。今回の判決は、この問題に真正面から向き合い、発電コストがどうとか貿易収支が赤字になるといった経済活動の問題は人格権に対し低位にあると断じ、こ の国を覆う経済至上主義にくぎを刺した点で意義は大きい。
そして判決は、住民の人格権を守るには、「万が一」の危険性もないことが証明されない限り、原発の再稼 働は認められないと結論づけた。事故発生の確率が極めて低ければ安全性は保証されるとしてきた従来の行政や電力会社の考え方を否定したものだ。この点につ いては政府事故調の報告書でも、津波予測にからんで「確率論的に発生確率が低いとされても、いったんそれが起これば重大な被害が発生すると予測される場合 には、万全の安全対策、防災対策を立てておくべきである」と思想の転換を提言している。
各電力会社はスリーマイルアイランド(米国)やチェルノブイリ(旧ソ連)の原発事故の教訓から、運転員 の人的エラーの防止対策は万全だとしてきたが、福島第1原発のような全電源喪失、3基で炉心溶融(メルトダウン)という混乱と緊迫の中では、プロの吉田昌 郎(まさお)所長(当時)でさえいくつもの判断や指示のエラーをしている。そのことは、深刻な事故時に指揮官の能力を超える事態もありうることを示す。原 子力規制委員会の新規制基準にはそういう項目が入っていない。
戦後の日本の政治・政策が、住民の命を犠牲にしてでも経済至上主義を貫いてきたことは歴史的な事実だ。 その原点を水俣病事件に見ることができる。最初の公的患者確認から3年後の1959年、熊本大研究班が有機水銀汚染によることを解明し、劇症による死者が 50人を超えていた。それにもかかわらず、政府は排水源のチッソを規制したら経済成長が打撃を受けるとの理由から、閣議において原因不明として、その後9 年間もチッソの排水垂れ流しを黙認し、水銀汚染拡大と患者の激増を招いたのだ。
福島原発事故はその延長線にある。石油危機でエネルギー確保が国家の最優先課題になり、各電力が次々に原発を導入する一方で、反対を封じ込めるために安全神話を作り、事故リスクを封印した。
日本の根底にある経済至上の論理は、福島原発事故を経ても、安倍政権で強まっている。判決は、こうした 国のあり方を根本から問うものだ。私たちは何をもって豊かさとし、何を目指すべきなのか。命への高い倫理性を守る国づくりを目指すために、一度立ち止ま り、福島原発事故の原点(本質的な教訓)に返って熟考すべき時期だ。【聞き手・酒造唯】
………………………………………………………………………………………………………
◇大飯原発運転差し止め訴訟
福井県にある関西電力大飯原発3、4号機の再稼働は危険だとして、同県の住民ら計189人が運転差し止 めを求めた訴訟。福井地裁は、東京電力福島第1原発事故を重く見て「冷却や放射性物質の閉じ込めに欠陥がある」「運転により人格権が侵害される危険があ る」などと指摘し、再稼働を認めない判決を出した。
関電は判決を不服として名古屋高裁金沢支部にすでに控訴した。同3、4号機は昨年9月に定期検査のため に運転を停止。関電は、現在進む原子力規制委員会の安全審査に適合し、地元同意などの条件が整えば、控訴審判決の前でも再稼働を進める考えを示している。 判決に沿えば、地震大国・日本の原発の大半が再稼働困難になるが、「安全のための工学」を全面的に否定しているため、論議を呼んでいる。
………………………………………………………………………………………………………
「論点」は金曜日掲載です。opinion@mainichi.co.jp
………………………………………………………………………………………………………
■人物略歴
◇いど・けんいち
1954年大阪府生まれ。東京大教育学部卒。79年に裁判官に任官し、金沢地裁や京都地裁の裁判長など32年間務めた。2011年4月から弁護士。
………………………………………………………………………………………………………
■人物略歴
◇すみた・けんじ
1930年大阪市生まれ。大阪大理学部卒。阪大名誉教授。98~2000年、内閣府原子力安全委員長代理。00年5月から2年間、日本原子力学会長。
………………………………………………………………………………………………………
■人物略歴
◇やなぎだ・くにお
1936年栃木県生まれ。東京大経済学部卒。NHK記者を経てノンフィクション作家。福島原発事故の政府事故調査・検証委員会委員長代理。










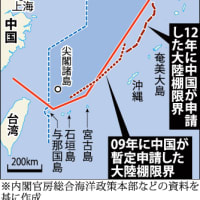





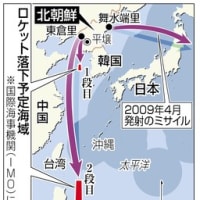
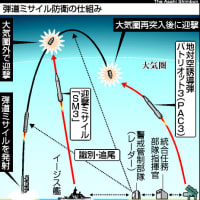







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます