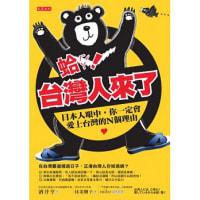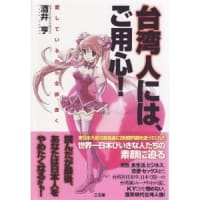台湾の国連加盟申請が国連一般委員会で却下、総会への上程が14年連続で認められなかったことを受けて、陳水扁総統は13日、ニューヨークと衛星回線で結び、現地記者や議員たちに説明、質疑応答を行った。この中で陳総統は来年からは「中華民国」ではなくて「台湾」の名称で、新規加盟という位置づけをより明確にした加盟申請を行う方針であることを明らかにした。
◆これまでの加盟申請は「中華民国」の名称
台湾は1992年国会の全面改選が行われて李登輝総統が政治的実権を固めたあとの93年から中華民国の名称で加盟申請を行ってきた。ただ当初は外交部官僚の古い思考が残っており、中華人民共和国の中国代表権を認めて国府を追放した2758号決議の見直しを求めるなど、中国の代表権を「中華民国」が奪取することを暗に目指す意図が込められていた。とはいえ、一時期はフィリピン、ラトヴィア、コートジボワール、パプアニューギニア、フィジーなども一般演説で事実上の賛成を表明するなど台湾の国交樹立国以外にもそれなりに賛同国はあった。ただ、その後中国の台頭が明らかになるにつれて、2758号決議の見直しという戦術は通用しなくなり、さらに台湾自体の脱中華民国化が進んだこともあって、徐々に「台湾人民の代表権」という主張にシフトしていった。政権交代で民進党政権になってから、「台湾人民を代表する新規加盟」という方向性はより強まった。
しかしそれでも台湾国内には国民党系保守派を中心に「中華民国」にこだわる勢力も少なくなく、特に外交部官僚にもそうした偏狭な思考に固執する人もいたために「中華民国」という名前での加盟申請を行ってきた。
ただ、今年は「中華民国」は申請書の初出だけで、あとはすべて台湾としてリファーしたり、また初めて加盟申請とは別に「台湾海峡の平和と安全は国連の関心事であることを表明する決議」を求める新たな要求案も提示した。
◆国連加盟ってそんなに意味あるの?
ただし、私が思うに、国連ってそんなに意味があるのかと。特に最近レバノンを舞台にした第6次中東戦争について国連がまったく無力だったこと、最多の分担金を拠出している日本が常任理事国となれないこと、米国が国連を無視してイラク戦争を勃発させたこと、人権委員会の理事国改選で、北朝鮮や中国をはじめ人権蹂躙をしている当事諸国が名前を連ねたこと、国連上級職員の腐敗が蔓延していることなどを考えれば、国連に加盟することが本当に意味我あることなのか大いに疑問である。
そもそも国連は英語名を忠実に訳せば、中国語ではそうなっているように「連合国」である。つまり、第二次大戦中にドイツや日本と戦った連合国が発展してできた、戦争を目的にした組織である。だからこそ日本やドイツを対象とした「敵国条項」が憲章にあったのだし、国連平和維持軍など今ひとつ効果も意味も不明で、かえって戦争を触発しているとしか思えない怪しげな制度があったりするのである。
まして最大の分担金責任国である米国は連続滞納し、現実の最大の分担金拠出は日本であるのに、日本は何の発言権もない。単なる税金の無駄遣いになっている。そういう目にあわされている日本国民として言わせてもらえば、国連に入れてもらえない台湾は、税金を国連にムダ遣いする必要もなく、また主権国家として認められないがゆえにイラク戦争にも派兵する必要もなく、実は得をしている部分もあって、羨ましいと思う。
もちろん、台湾政府の説明では、国連に加盟していないために起こる不利益も当然ある。さまざまな国際条約に台湾が加盟できないが、さりとて加盟していないことによるペナルティや義務だけは課せられるという不合理な側面は否定できない。
しかし、だからといって、それでも台湾は今日まで何とかやってきたのだし、国連にムダな金を使うデメリットのほうを考えれば、実は今のほうが幸運と言えないこともない。
台湾で「国連信仰」が強いのは、間接的に日本の影響もあるだろうが、いまやその日本でも国連への疑問論があり、いっそ脱退して第二の国連を立ち上げたほうがいいのではないかという議論も上がっている。確かに加盟させてもらえないからこそ、より欲求や幻想や期待が強まるのは人間の性といえるかもしれないが、加盟できないデメリットとメリットを考えたら、実際には台湾にとってメリットのほうが大きいのではないかと思う。
というのも、仮に加盟できたとしたら、台湾は豊かな国だから多額の分担金の負担を求められる。ヘタすると日本と同じように、いや、日本と同様に外交ベタだから、外のアジア諸国の分の肩代わりもさせられるだろう。そのくせ、声だけは大きく外交が狡猾な中国と比べて、発言権はない。日本よりもさらに惨めな立場に置かれるのは目に見えているのだ。
もちろん、他のより実務的国際組織、たとえばWHOなどは加盟すべきだろうし、そちらに努力を傾けることは正しいといえる。しかし、ほかの国連傘下組織のUNICEFなどは金ばかり取られるだけであまり意味がない。
◆国連に加盟できなくても立派な国の台湾
それに、本当に加盟したいのであれば、正攻法で「国家として新規加盟申請」に固執するのもどうかと思う。
というのも、米国が「一つの中国」なるフィクションに固執し、それに中国も便乗して横車を押したて、ほかの加盟国もあえて米中の主張に歯向かうべき利益も存在しない現在の国際社会を考えれば、台湾が「主権国家」として「新規加盟」が認められるのは、ほとんど現実的にはありえない。もちろん、国際情勢は変化することもあるから、そのときには台湾が認められるかもしれないが、変化は必ずしも台湾に有利になるとは限らない。逆に中国で共産党政権が倒れた暁には、米国が一挙に台湾を売り渡そうとするかもしれない。
台湾として生存は絶対に必要である。そのためにはWHOをはじめとした国際機構への加盟は必要だし、「国連加盟」もあるいは必要かもしれない。しかし、明らかに不可能な名目と方法にこだわって、結果的に台湾に不利な国際情勢が出現した場合、台湾はすべてを失うことになりかねない。つまり、台湾に必要なことは、国際機関の情報を適切に手に入れる立場やチャネルを確保し、現実の国際社会と折り合いをつけることが可能な方法や名目で国際機関に加盟して、実を確保することではないのか?
名目だけにこだわるのは、むしろ悪しき中華的名分論であって、急進独立派のほうが中華的名分論に毒されているのは皮肉というしかない。そうやって名分にこだわって、何も得られていないのが、現実ではないのか。
台湾は小国である。国際政治は小国に冷たく、不公平にできているのが常だ。幸福の女神が小国に微笑んでくれるのは歴史の中ではほんの一瞬に過ぎない。だからこそ、今回の中東戦争でも国連の1701号決議はどうみてもイスラエルや米国に有利でレバノンに不公平なものが出てきたのである。バルト三国が独立できたのも、ソ連の衰退と解体、それから米国・欧州情勢の偶然が重なった僥倖という側面があった。東チモールにしても冷戦崩壊後に米国など大国にとって「反共インドネシアの統一維持」よりも、「邪魔なイスラーム国家インドネシアから分離した東チモール」のほうが好ましくなったというパラダイムシフトがあったからである。
ただ、台湾の場合はソ連支配下のバルトやインドネシア軍事政権下の東チモールよりは現実にはよほど幸運で、実際に中華人民共和国に支配されるわけではなく、実態としては主権独立国家である。国連や大国がその主権性を「承認していない」という単なる神学論争、抽象的観念論の次元の問題に過ぎない。
しかも台湾の経済水準、市民社会の成熟度、社会全体の力を見れば、実際にはほとんどの国連加盟国、主権国家よりもはるかに実態として強いものを持っている。たとえば皮肉な対照例としては北朝鮮が挙げられる。北朝鮮は国連加盟国であり、世界で160カ国近くと外交関係を持っている。台湾が国連に加盟する見込みもなく、外交関係が24カ国しかないのと比べたら北朝鮮は抽象論のレベルでははるかに優位にある。
ところが実際にはどうか?台湾は確かに経済・社会力に比べれば不利な状況にある。たとえば同じような社会経済レベルにある韓国は、そのパスポートで115カ国をビザ免除もしくは着地ビザで入国できるのに対して、台湾は42カ国しかない。
だが、国連加盟国で表面的には台湾より優位にあって、国家としては堅固なものを持っている北朝鮮はたった17カ国しか自由に行けないことになっている。いや、そもそも北朝鮮公民がパスポートを取得するのは在日朝鮮人などを除けば至難の業であるから、北朝鮮の人たちはほとんど外に出られない。
ところが、台湾は韓国と比べて不公平とはいえ、それでも42カ国にビザ免除や着地ビザで訪問できる。しかも台湾人はそうした待遇になれているから、ビザ取得が困難な地域にもあらゆる手段を駆使して、巧みに食い込んだりしている。なんと台湾人が原則的に入国しにくいレバノンでも、台湾人の在住者は40人程度と、日本の60人程度と比べて遜色がない。しかも日本の外相は国交があってもレバノンを訪問することはあまりにないのに、台湾の外交部長は秘密裏とはいえ今年4月にレバノンを訪問しているのである。
そう考えれると、果たして国連に加盟することとは何か、国際的に主権国家として「承認される」こととは何か、国交を持つこととは何かという根本的な意味を改めて考え直さざるを得ない。
読者の中には北朝鮮との比較対照は極端だと思われるかもしれない。しかし、これをたとえば国際的イメージが良好な小国、たとえばルクセンブルク、セネガル、エストニア、コスタリカあたりと比べて、台湾が実質外交や国際競争力、国際的プレゼンスの点で、遜色があるだろうか?
そう考えれると、台湾は国際的に主権性を認められず、国連に加盟させてもらえないとしても実際には危機に陥ることもなく、きわめて立派にやっているという素晴らしい現実や実態が見えてくるのである。逆にいえば、台湾が国連に加盟したり、国際的に国家として認知されたりすることは、現状と比較してほとんどメリットが増加しない。台湾はそれだけ立派な状態にあるということだ。
だとしたら、「国家として認められていないこと」という名分論にこだわるよりも、その現実と実態に台湾人自身がもっともっと自身を持って、それをアピールすることのほうがより必要ではないのか?
◆台湾は未来の新たな「クニ」の形を示した斬新なモデル
一つは本ブログでも何度か言及していることだが、台湾は「国家性」「主権性」という中小的なものに依拠することなく、現実なる高度な市民社会を基礎にして民間の社会力を基礎にして国際的に立派なプレゼンスと地歩を築いているという点で、台湾は「台湾」という新たな社会集合体のモデルとして打ち出すのも一つの手ではないか。
台湾は台湾であって、中国でも国家でもない。そもそも国家や民族などという19世紀以来の陳腐な社会集合体のモデルを止揚、超越した、21世紀の新たな国際社会の主体としての独自性を理論・体系化し、それをアピールしていくということである。
実際、今の台湾人の、特に若者の意識を見ていると、それが中国や韓国に対する忌避・嫌悪感が見られ、台湾の独自性や主体性を認める意識が強まっているが、この場合中国や韓国に嫌悪を抱くのは、ナショナリズムレベルでの嫌悪感というよりは、中国や韓国がナショナリズムに固執して、国家や民族を大上段に振りかざすというレベルに対する嫌悪感という点が指摘できると思う。
だからこそ、「台湾の独自性」についても決してある特定の方向で結集したりすることはない。あるときには華人という概念を持ち出したり、あるときには原住民の基層を持ち出しりしたかと思うと、日本とも米国とも中国ともそれぞれの関係性を肯定するなど、いってみれば縦横無尽に視座が変化しているのである。
中国に対しても、政治的な弾圧や台湾への横暴については嫌悪感を示す一方で、歴史や文化には素直に面白いと思ったり、経済的には関係したいとかなりフレキシブルで実利、現実的に考えている。
そういう人から見ればこそ、中国や韓国、あるいは北朝鮮のように「民族の悠久な歴史」だの「民族の純粋性」だの「伝統や領土の堅持」だのというナショナリズムやショービニズムの主張は、純粋に理解しがたいというか、生理的に忌避感を持ってしまうのである。
もちろん、こうした感覚とか思考は台湾独自のものではなく、フィリピンやタイやインドネシアなど東南アジアや、中東、アフリカなどにも広く見られるものである。ネーションなる観念が、ゲルナーやホブズボームらが指摘するように、近代西欧の特殊な産物、神話であるとすれば、西欧近代とは異なる背景を持った地域で、国家だの民族だのを前提にして強調する思考が希薄なのは当然であろう。
ただし、それでもフィリピンですらフィリピンという国家性を国際社会で認められ、国連にフィリピンという名前で加盟し、そうした観念をいわば外から規定され、それに外から拘束を受けている点では、フィリピンなど東南アジア諸国には「19世紀的な意味での国家性を止揚した何か」を開き直ることは完全にはできない。
その点で考えれば逆に台湾はそういう開き直りを行える有利な立場にあるといえる。
物は考えようで、「台湾は国家として認められないから悲哀」なのではなくて、「国家として束縛されないから自由で斬新」なのである。
そう考えれば、台湾が性質や議題の異なる国際組織(国際オリンピック委員会、国際圭二警察機構、アジア開発銀行など)に、さまざまな異なる名称で加盟しているのは、ある意味ではその自由、柔軟性、多元性を示すものとして、新たなモデルとしてアピールすべきではなかろうか。
◆マルタ騎士団方式で「世界最大のNGO」としてオブザーバー加盟申請すれば?
また、どうしても国連に加盟したいのであれば、一つ抜け道が考えられる。それは、いっそのこと「台湾は世界最大のNGO、開発援助組織」という名目で国連のオブザーバー加盟申請することである。
これにはマルタ騎士団(国)という先例がある。マルタ騎士団は、十字軍時代の病院経営騎士団を起源とした医療援助組織で、かつては領土もあったが、18世紀に消失したあとは、領土を持たないが歴史的に重要な役割を果たしてきた実績に鑑みて、その主権性はある程度認められ、ローマに本部ビルを所有している。ビルを領土とみなせないこともないが、領土はないが、国家に準じた存在として、80数カ国からは国家として承認され外交関係も樹立、「大使館」も設置している(現在の台湾よりよほど多い)。また「国民」としてはその会員が該当する。そういう意味では国家の三要素である領土・国民・主権のうち、領土部分には疑問があるが、国民と主権の部分はほぼ満たしている。主権部分が承認されていないが領土と国民は明らかにある台湾と要素面で対照的な関係にある。
しかも面白いことに、マルタ騎士団を国家承認している国の中には台湾との国交国が含まれていることである。
そのマルタ騎士団は、国連の「加盟」基準が緩和された90年代に、「特殊な目的を有する国際機関」の名目でオブザーバー加盟している。
もちろん、そうした形であっても、台湾独立への一里塚や突破口とみなす中国は徹底して反対するかもしれない。しかし、そういう形であれば、いちおうは中国側が最も譲れない一線だとしている「台湾の主権性の承認」の問題は発生しない。
もちろん、憲法もあり、大統領も選んでいる明らかに事実上の主権独立国家を、国家としての歴史はあるといえ単なる医療ボランティア集団と比較できない、主権性を自ら放棄するとは何事かと急進独立派は承服できないかもしれない。
しかし、考えてみて欲しい。台湾の主権性は、もともと国際的には認められていないのである。確かに現実の実態としては主権性を有することは明らかだが、それと承認という行為とはイコールではない。
たとえば、立派に民主的な選挙で元首を選び、政府を構成し、実効支配を維持しているのにもかかわらず世界のどこからも承認されていない事実上の国家としてソマリアの一部が独立宣言したソマリランド共和国が挙げられる。
ソマリランドの政府と国民からすれば、ソマリランドは立派な主権国家であって、実態としても無政府状態のソマリアに比べるまでもなく、アフリカの中でもかなり立派なほうに属するが、それでも台湾の急進独立派はまずソマリランドの立派さを知らないだろうし、どうでもいいことと考えているであろう。
だとしたら、台湾が国内的にいかに立派な体制を維持しているかどうかは、台湾以外の多くの国や国民の関心事ではないということと同義であろう。
そうであるならなおさら、台湾が「主権性」に固執する利益は国際レベルではほとんどないことになる。
しかも、失礼ながら、統治能力があまり高くなく、NGO的な色彩が強い陳水扁政権、好き勝手なことをやっている今の台湾国民を見れば、いっそのこと「NGO」だと開き直ってもいいのではないか?それが実態ではないのか?
また、台湾は政府や国家としてみれば小さいだが、NGOとしてみれば文句なしに世界最大となり、しかもきわめて有能、有用である。マルタ騎士団など目ではない。
さらにNGOにも規約や綱領は必要であり、それは英語では憲法と同語を使う場合もあるし、NGOには理事長選挙も必要である。
NGOでも役割に応じて、政府に準じた主権性(排他的支配権)や外交権に準じた権限を国際的に認められることもあり、実際それはマルタ騎士団が行っているし、ギリシャにあるアトス山もそれに近い形を持っている。
それで失うものがそれほど多いとは思えないし、中国が必死で守ろうとしているメンツも保てる。
一部ではNGOといったら、中国の主権の支配を受けることになると心配する人もあるかもしれないが、マルタ騎士団方式で、現実に民主的な支配が築かれていることを認める形でのNGOという形なら、現在の統治実体をそこなわれることもない。要はその辺が各国とすり合わせて、知恵を絞るべきところなのである。「正面突破」でいつまでたっても展望が見えないよりは、民主体制や排他的支配権を失わず、統治主体として認められつつも、NGOという名目でオブザーバー加盟する道を追求し、そのために知恵と金を費やすほうが現実的な台湾の利益につながるのではないか?
台湾が中国と違うというなら、まず思考パターンにおいて中国的な名分論から脱却すべきだろう。
◆第二国連を作ることも検討すべし
ただ私としては最初に述べたように、「国連」のような役立たずの無能かつ腐敗した機構になんらかの役割を期待するよりは、正直国連に呆れている諸国と語り合って、新たな構成要件を掲げた、第二の国連を結成することを、マルタ騎士団方式と並行して考えたほうがいいかもしれない。
そもそも中国があれほど必死になって「主権国家」なるものにこだわって、主権国家ではそもそも包摂しきれない、あらゆるエスニックグループの存在や問題、あらゆる環境や弱者の人権の問題を排除している今の国連という概念と機構そのものがすでにアナクロニズムの極致ではないのか?
EUが理想的な形だとまったく思わないし、まったくその逆の世界部分割拠主義だと思うが、それはそうとしてEUの理念や現実の中にも私が評価できて、国連にはないものとしては、カタルーニャやケルトやロマなど少数エスニシティの尊重と地位の保障という部分が上げられる。EUは従来型の主権国家以外にもそうしたエスニシティにもある程度の代表性を認め、そうした権利を保障している点は、中国がわめき散らしている国連における「主権国家主義」よりはよほどまともだ。
そういう意味で、既存の国家だけを構成要件としない、もっと多種多様な市民団体、NGO、NPO、少数エスニックグループなども主体あるいは準主体、アクターとして認める新たな多国間組織が必要ではないのか?
もちろん国際社会ではまだまだ主権国家が主体として動き、より強い武力を持ち、より大きな国が幅を利かせている面は否定できない。
しかし、世界は徐々に変わりつつある。従来型国民国家・主権国家では掬い取れない部分に対する関心は高まっている。中国ですら、華南の沿岸地方を中心に中南海が声高に主張する「中華民族主義」とは正反対のもっと多元的かつ開放的な思考をしている人も増えている。
そういう点では、中国政府が鼓吹する中華民族主義は時代錯誤、前世紀の遺物であり、台湾のあり方こそが新たな時代の潮流を一部代表しているといえる。ところが台湾人は偏狭なマスコミやかつての国民党教育の残滓もあって、台湾の持つ強みを自覚できていない。急進独立派も「国家」にこだわりすぎていて、国家以外のアクター、台湾自身の強みに気づいていないのは問題である。
◆これまでの加盟申請は「中華民国」の名称
台湾は1992年国会の全面改選が行われて李登輝総統が政治的実権を固めたあとの93年から中華民国の名称で加盟申請を行ってきた。ただ当初は外交部官僚の古い思考が残っており、中華人民共和国の中国代表権を認めて国府を追放した2758号決議の見直しを求めるなど、中国の代表権を「中華民国」が奪取することを暗に目指す意図が込められていた。とはいえ、一時期はフィリピン、ラトヴィア、コートジボワール、パプアニューギニア、フィジーなども一般演説で事実上の賛成を表明するなど台湾の国交樹立国以外にもそれなりに賛同国はあった。ただ、その後中国の台頭が明らかになるにつれて、2758号決議の見直しという戦術は通用しなくなり、さらに台湾自体の脱中華民国化が進んだこともあって、徐々に「台湾人民の代表権」という主張にシフトしていった。政権交代で民進党政権になってから、「台湾人民を代表する新規加盟」という方向性はより強まった。
しかしそれでも台湾国内には国民党系保守派を中心に「中華民国」にこだわる勢力も少なくなく、特に外交部官僚にもそうした偏狭な思考に固執する人もいたために「中華民国」という名前での加盟申請を行ってきた。
ただ、今年は「中華民国」は申請書の初出だけで、あとはすべて台湾としてリファーしたり、また初めて加盟申請とは別に「台湾海峡の平和と安全は国連の関心事であることを表明する決議」を求める新たな要求案も提示した。
◆国連加盟ってそんなに意味あるの?
ただし、私が思うに、国連ってそんなに意味があるのかと。特に最近レバノンを舞台にした第6次中東戦争について国連がまったく無力だったこと、最多の分担金を拠出している日本が常任理事国となれないこと、米国が国連を無視してイラク戦争を勃発させたこと、人権委員会の理事国改選で、北朝鮮や中国をはじめ人権蹂躙をしている当事諸国が名前を連ねたこと、国連上級職員の腐敗が蔓延していることなどを考えれば、国連に加盟することが本当に意味我あることなのか大いに疑問である。
そもそも国連は英語名を忠実に訳せば、中国語ではそうなっているように「連合国」である。つまり、第二次大戦中にドイツや日本と戦った連合国が発展してできた、戦争を目的にした組織である。だからこそ日本やドイツを対象とした「敵国条項」が憲章にあったのだし、国連平和維持軍など今ひとつ効果も意味も不明で、かえって戦争を触発しているとしか思えない怪しげな制度があったりするのである。
まして最大の分担金責任国である米国は連続滞納し、現実の最大の分担金拠出は日本であるのに、日本は何の発言権もない。単なる税金の無駄遣いになっている。そういう目にあわされている日本国民として言わせてもらえば、国連に入れてもらえない台湾は、税金を国連にムダ遣いする必要もなく、また主権国家として認められないがゆえにイラク戦争にも派兵する必要もなく、実は得をしている部分もあって、羨ましいと思う。
もちろん、台湾政府の説明では、国連に加盟していないために起こる不利益も当然ある。さまざまな国際条約に台湾が加盟できないが、さりとて加盟していないことによるペナルティや義務だけは課せられるという不合理な側面は否定できない。
しかし、だからといって、それでも台湾は今日まで何とかやってきたのだし、国連にムダな金を使うデメリットのほうを考えれば、実は今のほうが幸運と言えないこともない。
台湾で「国連信仰」が強いのは、間接的に日本の影響もあるだろうが、いまやその日本でも国連への疑問論があり、いっそ脱退して第二の国連を立ち上げたほうがいいのではないかという議論も上がっている。確かに加盟させてもらえないからこそ、より欲求や幻想や期待が強まるのは人間の性といえるかもしれないが、加盟できないデメリットとメリットを考えたら、実際には台湾にとってメリットのほうが大きいのではないかと思う。
というのも、仮に加盟できたとしたら、台湾は豊かな国だから多額の分担金の負担を求められる。ヘタすると日本と同じように、いや、日本と同様に外交ベタだから、外のアジア諸国の分の肩代わりもさせられるだろう。そのくせ、声だけは大きく外交が狡猾な中国と比べて、発言権はない。日本よりもさらに惨めな立場に置かれるのは目に見えているのだ。
もちろん、他のより実務的国際組織、たとえばWHOなどは加盟すべきだろうし、そちらに努力を傾けることは正しいといえる。しかし、ほかの国連傘下組織のUNICEFなどは金ばかり取られるだけであまり意味がない。
◆国連に加盟できなくても立派な国の台湾
それに、本当に加盟したいのであれば、正攻法で「国家として新規加盟申請」に固執するのもどうかと思う。
というのも、米国が「一つの中国」なるフィクションに固執し、それに中国も便乗して横車を押したて、ほかの加盟国もあえて米中の主張に歯向かうべき利益も存在しない現在の国際社会を考えれば、台湾が「主権国家」として「新規加盟」が認められるのは、ほとんど現実的にはありえない。もちろん、国際情勢は変化することもあるから、そのときには台湾が認められるかもしれないが、変化は必ずしも台湾に有利になるとは限らない。逆に中国で共産党政権が倒れた暁には、米国が一挙に台湾を売り渡そうとするかもしれない。
台湾として生存は絶対に必要である。そのためにはWHOをはじめとした国際機構への加盟は必要だし、「国連加盟」もあるいは必要かもしれない。しかし、明らかに不可能な名目と方法にこだわって、結果的に台湾に不利な国際情勢が出現した場合、台湾はすべてを失うことになりかねない。つまり、台湾に必要なことは、国際機関の情報を適切に手に入れる立場やチャネルを確保し、現実の国際社会と折り合いをつけることが可能な方法や名目で国際機関に加盟して、実を確保することではないのか?
名目だけにこだわるのは、むしろ悪しき中華的名分論であって、急進独立派のほうが中華的名分論に毒されているのは皮肉というしかない。そうやって名分にこだわって、何も得られていないのが、現実ではないのか。
台湾は小国である。国際政治は小国に冷たく、不公平にできているのが常だ。幸福の女神が小国に微笑んでくれるのは歴史の中ではほんの一瞬に過ぎない。だからこそ、今回の中東戦争でも国連の1701号決議はどうみてもイスラエルや米国に有利でレバノンに不公平なものが出てきたのである。バルト三国が独立できたのも、ソ連の衰退と解体、それから米国・欧州情勢の偶然が重なった僥倖という側面があった。東チモールにしても冷戦崩壊後に米国など大国にとって「反共インドネシアの統一維持」よりも、「邪魔なイスラーム国家インドネシアから分離した東チモール」のほうが好ましくなったというパラダイムシフトがあったからである。
ただ、台湾の場合はソ連支配下のバルトやインドネシア軍事政権下の東チモールよりは現実にはよほど幸運で、実際に中華人民共和国に支配されるわけではなく、実態としては主権独立国家である。国連や大国がその主権性を「承認していない」という単なる神学論争、抽象的観念論の次元の問題に過ぎない。
しかも台湾の経済水準、市民社会の成熟度、社会全体の力を見れば、実際にはほとんどの国連加盟国、主権国家よりもはるかに実態として強いものを持っている。たとえば皮肉な対照例としては北朝鮮が挙げられる。北朝鮮は国連加盟国であり、世界で160カ国近くと外交関係を持っている。台湾が国連に加盟する見込みもなく、外交関係が24カ国しかないのと比べたら北朝鮮は抽象論のレベルでははるかに優位にある。
ところが実際にはどうか?台湾は確かに経済・社会力に比べれば不利な状況にある。たとえば同じような社会経済レベルにある韓国は、そのパスポートで115カ国をビザ免除もしくは着地ビザで入国できるのに対して、台湾は42カ国しかない。
だが、国連加盟国で表面的には台湾より優位にあって、国家としては堅固なものを持っている北朝鮮はたった17カ国しか自由に行けないことになっている。いや、そもそも北朝鮮公民がパスポートを取得するのは在日朝鮮人などを除けば至難の業であるから、北朝鮮の人たちはほとんど外に出られない。
ところが、台湾は韓国と比べて不公平とはいえ、それでも42カ国にビザ免除や着地ビザで訪問できる。しかも台湾人はそうした待遇になれているから、ビザ取得が困難な地域にもあらゆる手段を駆使して、巧みに食い込んだりしている。なんと台湾人が原則的に入国しにくいレバノンでも、台湾人の在住者は40人程度と、日本の60人程度と比べて遜色がない。しかも日本の外相は国交があってもレバノンを訪問することはあまりにないのに、台湾の外交部長は秘密裏とはいえ今年4月にレバノンを訪問しているのである。
そう考えれると、果たして国連に加盟することとは何か、国際的に主権国家として「承認される」こととは何か、国交を持つこととは何かという根本的な意味を改めて考え直さざるを得ない。
読者の中には北朝鮮との比較対照は極端だと思われるかもしれない。しかし、これをたとえば国際的イメージが良好な小国、たとえばルクセンブルク、セネガル、エストニア、コスタリカあたりと比べて、台湾が実質外交や国際競争力、国際的プレゼンスの点で、遜色があるだろうか?
そう考えれると、台湾は国際的に主権性を認められず、国連に加盟させてもらえないとしても実際には危機に陥ることもなく、きわめて立派にやっているという素晴らしい現実や実態が見えてくるのである。逆にいえば、台湾が国連に加盟したり、国際的に国家として認知されたりすることは、現状と比較してほとんどメリットが増加しない。台湾はそれだけ立派な状態にあるということだ。
だとしたら、「国家として認められていないこと」という名分論にこだわるよりも、その現実と実態に台湾人自身がもっともっと自身を持って、それをアピールすることのほうがより必要ではないのか?
◆台湾は未来の新たな「クニ」の形を示した斬新なモデル
一つは本ブログでも何度か言及していることだが、台湾は「国家性」「主権性」という中小的なものに依拠することなく、現実なる高度な市民社会を基礎にして民間の社会力を基礎にして国際的に立派なプレゼンスと地歩を築いているという点で、台湾は「台湾」という新たな社会集合体のモデルとして打ち出すのも一つの手ではないか。
台湾は台湾であって、中国でも国家でもない。そもそも国家や民族などという19世紀以来の陳腐な社会集合体のモデルを止揚、超越した、21世紀の新たな国際社会の主体としての独自性を理論・体系化し、それをアピールしていくということである。
実際、今の台湾人の、特に若者の意識を見ていると、それが中国や韓国に対する忌避・嫌悪感が見られ、台湾の独自性や主体性を認める意識が強まっているが、この場合中国や韓国に嫌悪を抱くのは、ナショナリズムレベルでの嫌悪感というよりは、中国や韓国がナショナリズムに固執して、国家や民族を大上段に振りかざすというレベルに対する嫌悪感という点が指摘できると思う。
だからこそ、「台湾の独自性」についても決してある特定の方向で結集したりすることはない。あるときには華人という概念を持ち出したり、あるときには原住民の基層を持ち出しりしたかと思うと、日本とも米国とも中国ともそれぞれの関係性を肯定するなど、いってみれば縦横無尽に視座が変化しているのである。
中国に対しても、政治的な弾圧や台湾への横暴については嫌悪感を示す一方で、歴史や文化には素直に面白いと思ったり、経済的には関係したいとかなりフレキシブルで実利、現実的に考えている。
そういう人から見ればこそ、中国や韓国、あるいは北朝鮮のように「民族の悠久な歴史」だの「民族の純粋性」だの「伝統や領土の堅持」だのというナショナリズムやショービニズムの主張は、純粋に理解しがたいというか、生理的に忌避感を持ってしまうのである。
もちろん、こうした感覚とか思考は台湾独自のものではなく、フィリピンやタイやインドネシアなど東南アジアや、中東、アフリカなどにも広く見られるものである。ネーションなる観念が、ゲルナーやホブズボームらが指摘するように、近代西欧の特殊な産物、神話であるとすれば、西欧近代とは異なる背景を持った地域で、国家だの民族だのを前提にして強調する思考が希薄なのは当然であろう。
ただし、それでもフィリピンですらフィリピンという国家性を国際社会で認められ、国連にフィリピンという名前で加盟し、そうした観念をいわば外から規定され、それに外から拘束を受けている点では、フィリピンなど東南アジア諸国には「19世紀的な意味での国家性を止揚した何か」を開き直ることは完全にはできない。
その点で考えれば逆に台湾はそういう開き直りを行える有利な立場にあるといえる。
物は考えようで、「台湾は国家として認められないから悲哀」なのではなくて、「国家として束縛されないから自由で斬新」なのである。
そう考えれば、台湾が性質や議題の異なる国際組織(国際オリンピック委員会、国際圭二警察機構、アジア開発銀行など)に、さまざまな異なる名称で加盟しているのは、ある意味ではその自由、柔軟性、多元性を示すものとして、新たなモデルとしてアピールすべきではなかろうか。
◆マルタ騎士団方式で「世界最大のNGO」としてオブザーバー加盟申請すれば?
また、どうしても国連に加盟したいのであれば、一つ抜け道が考えられる。それは、いっそのこと「台湾は世界最大のNGO、開発援助組織」という名目で国連のオブザーバー加盟申請することである。
これにはマルタ騎士団(国)という先例がある。マルタ騎士団は、十字軍時代の病院経営騎士団を起源とした医療援助組織で、かつては領土もあったが、18世紀に消失したあとは、領土を持たないが歴史的に重要な役割を果たしてきた実績に鑑みて、その主権性はある程度認められ、ローマに本部ビルを所有している。ビルを領土とみなせないこともないが、領土はないが、国家に準じた存在として、80数カ国からは国家として承認され外交関係も樹立、「大使館」も設置している(現在の台湾よりよほど多い)。また「国民」としてはその会員が該当する。そういう意味では国家の三要素である領土・国民・主権のうち、領土部分には疑問があるが、国民と主権の部分はほぼ満たしている。主権部分が承認されていないが領土と国民は明らかにある台湾と要素面で対照的な関係にある。
しかも面白いことに、マルタ騎士団を国家承認している国の中には台湾との国交国が含まれていることである。
そのマルタ騎士団は、国連の「加盟」基準が緩和された90年代に、「特殊な目的を有する国際機関」の名目でオブザーバー加盟している。
もちろん、そうした形であっても、台湾独立への一里塚や突破口とみなす中国は徹底して反対するかもしれない。しかし、そういう形であれば、いちおうは中国側が最も譲れない一線だとしている「台湾の主権性の承認」の問題は発生しない。
もちろん、憲法もあり、大統領も選んでいる明らかに事実上の主権独立国家を、国家としての歴史はあるといえ単なる医療ボランティア集団と比較できない、主権性を自ら放棄するとは何事かと急進独立派は承服できないかもしれない。
しかし、考えてみて欲しい。台湾の主権性は、もともと国際的には認められていないのである。確かに現実の実態としては主権性を有することは明らかだが、それと承認という行為とはイコールではない。
たとえば、立派に民主的な選挙で元首を選び、政府を構成し、実効支配を維持しているのにもかかわらず世界のどこからも承認されていない事実上の国家としてソマリアの一部が独立宣言したソマリランド共和国が挙げられる。
ソマリランドの政府と国民からすれば、ソマリランドは立派な主権国家であって、実態としても無政府状態のソマリアに比べるまでもなく、アフリカの中でもかなり立派なほうに属するが、それでも台湾の急進独立派はまずソマリランドの立派さを知らないだろうし、どうでもいいことと考えているであろう。
だとしたら、台湾が国内的にいかに立派な体制を維持しているかどうかは、台湾以外の多くの国や国民の関心事ではないということと同義であろう。
そうであるならなおさら、台湾が「主権性」に固執する利益は国際レベルではほとんどないことになる。
しかも、失礼ながら、統治能力があまり高くなく、NGO的な色彩が強い陳水扁政権、好き勝手なことをやっている今の台湾国民を見れば、いっそのこと「NGO」だと開き直ってもいいのではないか?それが実態ではないのか?
また、台湾は政府や国家としてみれば小さいだが、NGOとしてみれば文句なしに世界最大となり、しかもきわめて有能、有用である。マルタ騎士団など目ではない。
さらにNGOにも規約や綱領は必要であり、それは英語では憲法と同語を使う場合もあるし、NGOには理事長選挙も必要である。
NGOでも役割に応じて、政府に準じた主権性(排他的支配権)や外交権に準じた権限を国際的に認められることもあり、実際それはマルタ騎士団が行っているし、ギリシャにあるアトス山もそれに近い形を持っている。
それで失うものがそれほど多いとは思えないし、中国が必死で守ろうとしているメンツも保てる。
一部ではNGOといったら、中国の主権の支配を受けることになると心配する人もあるかもしれないが、マルタ騎士団方式で、現実に民主的な支配が築かれていることを認める形でのNGOという形なら、現在の統治実体をそこなわれることもない。要はその辺が各国とすり合わせて、知恵を絞るべきところなのである。「正面突破」でいつまでたっても展望が見えないよりは、民主体制や排他的支配権を失わず、統治主体として認められつつも、NGOという名目でオブザーバー加盟する道を追求し、そのために知恵と金を費やすほうが現実的な台湾の利益につながるのではないか?
台湾が中国と違うというなら、まず思考パターンにおいて中国的な名分論から脱却すべきだろう。
◆第二国連を作ることも検討すべし
ただ私としては最初に述べたように、「国連」のような役立たずの無能かつ腐敗した機構になんらかの役割を期待するよりは、正直国連に呆れている諸国と語り合って、新たな構成要件を掲げた、第二の国連を結成することを、マルタ騎士団方式と並行して考えたほうがいいかもしれない。
そもそも中国があれほど必死になって「主権国家」なるものにこだわって、主権国家ではそもそも包摂しきれない、あらゆるエスニックグループの存在や問題、あらゆる環境や弱者の人権の問題を排除している今の国連という概念と機構そのものがすでにアナクロニズムの極致ではないのか?
EUが理想的な形だとまったく思わないし、まったくその逆の世界部分割拠主義だと思うが、それはそうとしてEUの理念や現実の中にも私が評価できて、国連にはないものとしては、カタルーニャやケルトやロマなど少数エスニシティの尊重と地位の保障という部分が上げられる。EUは従来型の主権国家以外にもそうしたエスニシティにもある程度の代表性を認め、そうした権利を保障している点は、中国がわめき散らしている国連における「主権国家主義」よりはよほどまともだ。
そういう意味で、既存の国家だけを構成要件としない、もっと多種多様な市民団体、NGO、NPO、少数エスニックグループなども主体あるいは準主体、アクターとして認める新たな多国間組織が必要ではないのか?
もちろん国際社会ではまだまだ主権国家が主体として動き、より強い武力を持ち、より大きな国が幅を利かせている面は否定できない。
しかし、世界は徐々に変わりつつある。従来型国民国家・主権国家では掬い取れない部分に対する関心は高まっている。中国ですら、華南の沿岸地方を中心に中南海が声高に主張する「中華民族主義」とは正反対のもっと多元的かつ開放的な思考をしている人も増えている。
そういう点では、中国政府が鼓吹する中華民族主義は時代錯誤、前世紀の遺物であり、台湾のあり方こそが新たな時代の潮流を一部代表しているといえる。ところが台湾人は偏狭なマスコミやかつての国民党教育の残滓もあって、台湾の持つ強みを自覚できていない。急進独立派も「国家」にこだわりすぎていて、国家以外のアクター、台湾自身の強みに気づいていないのは問題である。