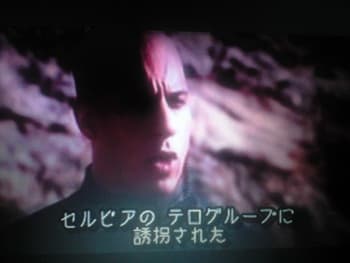1962年製作のアメリカ映画。映画「ティファニーで朝食を」の脚本を書いたジョージ・アクセルロッドの脚本でジョン・フランケンハイマー監督がシナトラ主演で製作したサスペンス。

原題は、「The Manchurian Candedate」で、原作は1959年のリチャード・コンドンの同名小説。同じ原作の映画でリメイクされたのが、「クライシス オブ アメリカ」。こちらは「羊たちの沈黙」の監督ジョナサン・デミがサイコサスペンスに仕立てていて、「影なき狙撃者」の朝鮮戦争が後者では湾岸戦争に変わり、洗脳された人間の背景も共産主義という政治思想から巨大企業に変わって現代アメリカ社会に起こりえる危機を内在したものに変換されています。
社会派サスペンス映画ともいえますが、やはりジョナサン・デミ監督に敬意を表して、私はサイコサスペンス映画に分類。展開も、「影なき狙撃者」と変わりませんしね。主演はデンゼル・ワシントン。
http://www.cinematopics.com/cinema/works/output2.php?oid=5237
さて、話を「影なき狙撃者」に戻すと、
これは冷戦時代の最初の熱い代理戦争となった朝鮮戦争を背景にしたスパイサスペンス。共産主義世界が得意とした洗脳がキーワードの怖い映画です。
朝鮮戦争で捕虜となりながらも仲間と共に生還し、そこでの活躍から名誉勲章まで貰うこととなったレイモンド軍曹、写真のローレンス・ハーベイが熱演していますが、このレイモンド、

どうもヘン・・・・・
戦争での酷い体験から生還すれば、精神的外傷があるのは無理もないことではあるけれど、親子関係もおかしい。

政治に野心を抱いて再婚したママゴンの夫人だが、この母親との関係が際立っておかしいのである。
息子を溺愛し支配するタイプの猛烈な母親と仲たがいするのは自然ながら、仲たがいしたかと思えば、猛烈なマザコン息子のように言いなりになったりする。
結婚相手を母親に決められ反発したかと思えば、次の瞬間には、赤子のようにママっ子になる・・・・
レイモンドといっしょに生還した大尉(フランク・シナトラ)は、その頃から悪夢にうなされるようになる。
夢とはいえ、悪夢そのもののその夢は、仲間を救出したはずのレイモンドが無表情で仲間を殺戮するというもの。
情報省勤務の将校となったフランク・シナトラことマーコばかりではなく、他の捕虜仲間も同じような悪夢にうなされていることを知ったフランク・シナトラは真相究明に乗り出す・・・・
母親とその再婚相手である義父は、レイモンドにとって尊敬できる人間ではない。そんな親にとって政治的に敵対関係にある男は、レイモンドを娘の相手として歓迎する度量の持ち主だが、レイモンドの畏敬の念は苦悩の色を濃くにじませたもので、背景に政治的な陰謀が見え隠れしてくるが・・・・
やがて、フランク・シナトラはレイモンドの恐るべき状況を推察するようになるが、真相を明らかにすべクレイモンドを訪ねると、彼の恋人に自分を信じて彼の事は任せて欲しいと懇願されて黙してしまう。心の病気であるということを理解しているからと。
彼女と幸せな時間を過ごし結婚の許しを得たというのに、頭の中で何かがざわついて汗ばむレイモンド・・・・

電話がかかってくると、無表情になり、
トランプを始めて夢遊病者のごとき別人になるレイモンド。
そんな彼を「秘密の任務」から解放すべく、フランク・シナトラは洗脳を解き、洗脳の最終目的を探ろうとするが、それは本人にもわからない・・・・

そして、運命の無残さ・・・・・
、
かかってきた電話を受け取ったレイモンドが取った行動は、まさに本人の意思や感情など入り込む余地のないものだった。
しかし、彼の最後の仕事はこの後に待っていたのである。
これは、母親の顔ではない。実に冷酷で険しい。
このアスリン夫人を往年の名女優アンジェラ・ランズベリーが見事に演じていて圧倒されます。


電話がかかってくるとトランプを始めて夢遊病者のごとき別人になる息子を見る夫人の目、その険しさに何が秘められているのか。


心身ともに疲弊しきっている息子に、彼女は最後の使命を下すのである。そう、彼女が8年間練りに練った計画をやっと実行に移すときを迎えたのだ。

母親として息子を失いはしたが、永年の野心を遂げるために必要な最後の大仕事をその息子がする!いや、何としてもさせなければならないのだ!・・・・運命を受け入れた野心家にはもう怖いものなどないに違いない。
夫人の権謀術数で政治家として無能な夫をやっとここまでにした、まさにその晴れの舞台。大統領選挙で党の副大統領の指名をとった晴れの席である。ここまで上り詰めるのに敵対する政治家や邪魔な政治家は皆消したので、あと一人・・・・あと一人を消せば、最高権力は自分たちの下に転がってくる。それも最高の舞台で!
汗ばむ夫と違って微動だにしない夫人・・・
夫人は言う。「落ち着きなさい。あの子は間違いなくやってくれる。あの子に限って失敗することはない」
これまでもそうだったのだからという声が聞こえてきそうな自信。この猛烈な母のこの確信はいったいどこから生まれてくるのか。
政治権力を欲しがる人間としては詰が甘いと言わざるを得ないですよね。これまで成功したからといって最後の大仕事も同じように完遂される保証はない。ここ一番というときだからこそ、わずかな失敗も許されないとするなら、その使命を遂げるために選んだ相手の状態は悪すぎる・・・・。愛する女性とその父親である敬愛していた政治家を自分が手に掛けたことをすでに気づいている息子。その心身の状態にまったく気づかない権力の亡者である母親には、気づく術はなかったのだろう。いや、最高権力を手中に収めたなら、息子をこんなふうにしてしまった相手に思い知らせてやるという復讐心に燃え立った心では、何も見えないに違いない。
かくして、フランク・シナトラの努力も空しく悲劇は起こってしまう。
じっくり観るにはおススメのサスペンスです。
いま観ても、緊張感が迫ってきますね。
1962年制作のアメリカ映画ですが、映画の舞台となるのはそれよりも10年遡り、世界が「冷たい戦争」に突入した時代の映画ですが、共産主義世界が得意とした「洗脳」という情報戦略は、冤罪と同じくらい恐ろしい。
当時の日本にも中国やシベリアで抑留され共産主義に洗脳されて帰国した元兵士が少なくなかったらしいという話を思い出します。戦後日本の異様な左傾化、ある思想に洗脳された人たちを中心とする勢力と反日勢力とが合流した昭和の歴史を思うと感慨深いものがありました。
この映画は、いま見てもホラー映画などよりよほど恐ろしいと感じます。