クラシック音楽を生活の糧としている私が出会った演奏会、CDやDVDなど印象に残ったことを紹介をしていきます。
クラシック音楽のある生活
プッチニーニ: 歌劇「トゥーランドット」
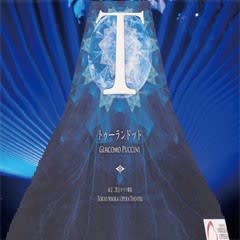
トゥーランドット: 土屋優子
王子カラフ: 城宏憲
リュー: 谷原めぐみ、他
指揮: ディエゴ・マテウス
演出: ダニエル・クレーマー
二期会合唱団/日本フィルハーモニー交響楽団
(2022. 2.26 東京文化会館)

 東京二期会による公演。この公演には2つの大きな特徴がある。1つはプロジェクション(プロジェクト)・マッピングを用いた演出、もう一つは通常用いられるフランコ・アルファーノによる補筆版ではなく、ルチアーノ・ベリオによる補筆版が用いられていることだ。私の関心はもっぱら後者にあり、プロジェクション・マッピングはものの試しにという程度だった。
東京二期会による公演。この公演には2つの大きな特徴がある。1つはプロジェクション(プロジェクト)・マッピングを用いた演出、もう一つは通常用いられるフランコ・アルファーノによる補筆版ではなく、ルチアーノ・ベリオによる補筆版が用いられていることだ。私の関心はもっぱら後者にあり、プロジェクション・マッピングはものの試しにという程度だった。
で、ベリオによる補筆版。もともとアルファーノの補筆には疑問が付きまとっていた。当初から初演指揮者として予定されていたトスカニーニ(プッチーニの信頼が非常に厚かった人だ)は、アルファーノの補筆版に難色を示して100小節以上をカット、それを不服としたアルファーノは訴訟まで用意したほどだったが、なぜか後に納得して、それが現在の多くの劇場で上演される版となった。私はこのトスカニーニの反応、そしてその後のアルファーノとの和解の理由が非常に気になる。
プッチーニが残した「トゥーランドット」は、第1幕も第2幕もド派手に終わる。第3幕は静かに終わるというのがこういう場合の定石だと思うのだが、アルファーノは第3幕も負けずにド派手に終わらせた。これはあり得ない。少なくとも人が一人、トゥーランドットに絡めて死んでいるのに、その結婚の物語がド派手なハッピーエンドというのは、とてもプッチーニが考えていたストーリーとは思えない。私は、トスカニーニはこのあたりの事情をいくらか知っていたのではないかと思う。
ベリオの補筆版は静かに終わるが、トゥーランドットがカラフとの間に愛が芽生えるようなやりとりがある。しかしこのあたりは、最近発売されたパッパーノによるアルファーノ版完全版にもあるらしい。これをカットしたトスカニーニの判断には何も問題を感じない。問題はここではない。問題はアルファーノ版に、死んだリューへの言及がないことだ。
ベリオ版は音楽的には特に際だったものはないようだが、それでもこれらのことに改善を図ったことでは存在意義を見出せるだろう。
トゥーランドットを歌った土屋優子は、思いのほか堂々として立派だった。演出は、特段のものは感じなかった。電子的に処理しながら、入場料がリアルより跳ね上がるというのは、技術の黎明期とはいえ残念。
過去の「トゥーランドット」




