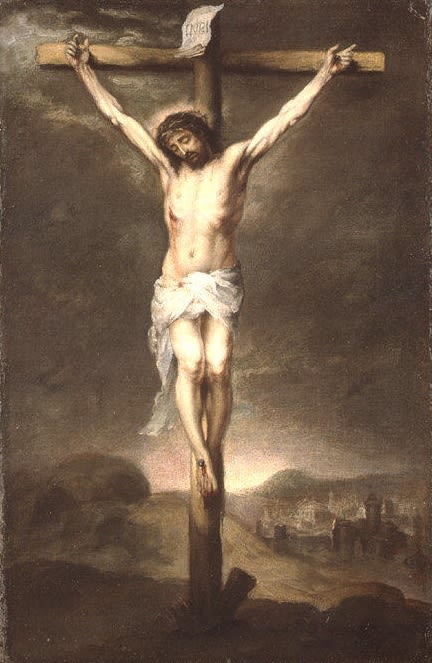No,54
ギュスターヴ・ドレ、「ピア」、19世紀フランス、ロマン主義。
デッサン力と精神性のバランスのとれた画家である。整えられた美は見る者をほっとさせる。挿絵画家としてはA級の技師だ。
近現代的なロマンティシズムもよい。
よけいなことだが、この絵に描かれた女性の印象は、真実の天使の真実の姿に近い。
彼は男性だが、こういう感じの姿をしている。その存在感はまさに女性だ。
しっとりとやさしい。
この世界での彼女の印象も、これに近かったはずである。
これを見ると、彼女を思い出す。
ギュスターヴ・ドレ、「ピア」、19世紀フランス、ロマン主義。
デッサン力と精神性のバランスのとれた画家である。整えられた美は見る者をほっとさせる。挿絵画家としてはA級の技師だ。
近現代的なロマンティシズムもよい。
よけいなことだが、この絵に描かれた女性の印象は、真実の天使の真実の姿に近い。
彼は男性だが、こういう感じの姿をしている。その存在感はまさに女性だ。
しっとりとやさしい。
この世界での彼女の印象も、これに近かったはずである。
これを見ると、彼女を思い出す。