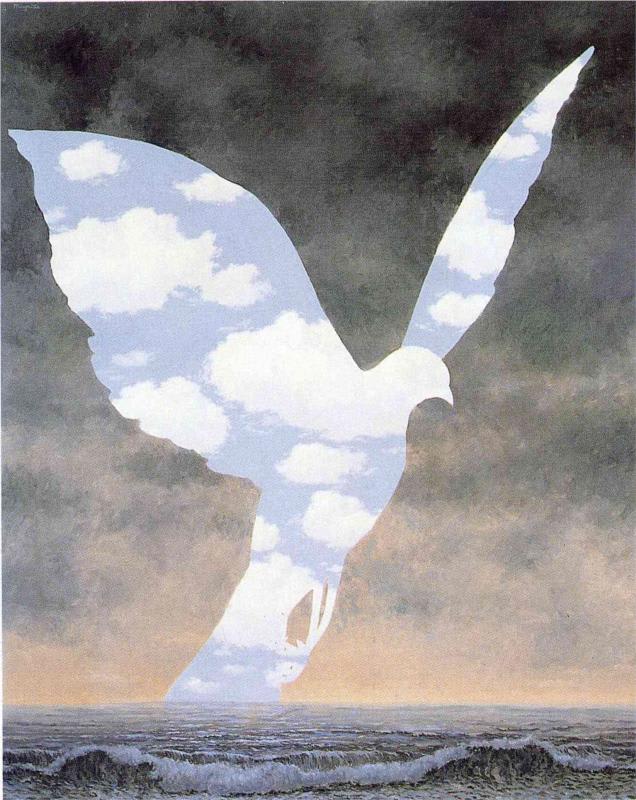No,65
エドガー・ドガ、「リハーサル」、19世紀フランス、印象派。
これはよくない。
女性から形の美しさだけを奪って、描いている。
魂が少しも描けていない。
おそらく、ドガは、女性がいやだったのだ。美しいのに、痛い心がその中にあるというのが、いやだったのだろう。だから、決して、女性の魂を描こうとしなかったのだ。
美しい絵に見えるが、これは男の冷酷なエゴを感じさせる。この絵を見ていると、男は、所詮女はこんなものだ。別に、欲望のために狩っても、痛いものを奪っても、たいしたことではないと、思ってしまう。
これは女性を、物質扱いしている。肉としてしか見ていない。
好色な目で見ている絵の方がまだましだ。愛が全くない。
エドガー・ドガ、「リハーサル」、19世紀フランス、印象派。
これはよくない。
女性から形の美しさだけを奪って、描いている。
魂が少しも描けていない。
おそらく、ドガは、女性がいやだったのだ。美しいのに、痛い心がその中にあるというのが、いやだったのだろう。だから、決して、女性の魂を描こうとしなかったのだ。
美しい絵に見えるが、これは男の冷酷なエゴを感じさせる。この絵を見ていると、男は、所詮女はこんなものだ。別に、欲望のために狩っても、痛いものを奪っても、たいしたことではないと、思ってしまう。
これは女性を、物質扱いしている。肉としてしか見ていない。
好色な目で見ている絵の方がまだましだ。愛が全くない。