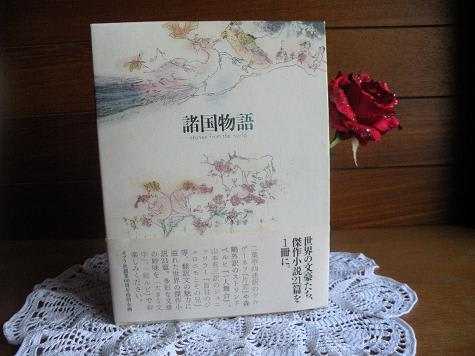大泥棒ホッツェンプロッツ
プロイスラー作・中村浩三訳 偕成社文庫
ホッツェンプロッツのシリーズは三巻あって、(「大泥棒ホッツェンプロッツふたたびあらわる」「大泥棒ホッツェンプロッツみたびあらわる」)写真はその2巻目です。この本にも入院中お世話になりましたが、いかにしてこんな本を選んだかというと、実は苦い思い出があって、その小さなトラウマの傷が一生残ってしまう、という本だからなんです。
今高校生の長男がまだ小学生だったころ、たぶん寝ながらだったと思うんですが、読み聞かせていた本だったんです。でも子供は読み聞かせになんだかうるさそうにして聞いてるもんだから、わたしも途中でやめちゃったんですね。それでね、ずっと、ずっと、あとになってから、長男からいわれたんですよ。ぼくは、いまだにこの本の落ちを知らないって。ああ、ばかですね。あのときは、こどもたちに、むりやり聞かせているような感じがして途中でやめてしまったけれど、ほんとはこどもたちは、きいてたんですね。ちゃんと。
とまあ、こういうトラウマが残っている本なのです。子供にも大人にもとってもおもしろいとてもかわいらしいメルヘンです。今更おそいけど、一巻目ではホッツェンプロッツは、とうぜん警察につかまってるからね。それもとんでもないかんじでね。高校生は興味なんてもたないし、忘れてるだろうけれど。
でも、わたしにとっては、それだけでいつまでも忘れられない本、このさい、三冊ともいっぺんによんでしまいました。一冊目も、読んだのはだいぶ昔なので、内容はすっかり忘れてしまっていましたよ。とってもおもしろかったです。
のちのち、読み聞かせボランティアなんかするようになったのにも、実はこの、ちょっとつらい経験が影響しているかもしれません。
こどもたちがつまらない顔をして聞いているように見えても、それはほんとじゃないんだな。こどもたちはまだ、感情の表わし方が未熟だから、そんなふうにみえたのかな。どちらにしろ、わたしも未熟でした。
とりもどせない失敗は、ずっと残るもの。でもそれを取り戻すために、ずっと、やっていくつもりです。読み聞かせボランティアを。たったひとつの失敗が、大きな大きなほほえみの渦のもとになってくれれば、わたしもうれしい。
そうすれば、あのときしてしまったことの傷が、少しは軽くなるかもしれない。
人間は未熟な者。失敗はつきもの。でも心につきささる失敗は、絶対にほっておかないで、あとで、なんとかしてみましょう。
自分の子供たちにしてあげられなかったことを、ほかのたくさんのこどもたちのために、してあげましょう。
プロイスラー作・中村浩三訳 偕成社文庫
ホッツェンプロッツのシリーズは三巻あって、(「大泥棒ホッツェンプロッツふたたびあらわる」「大泥棒ホッツェンプロッツみたびあらわる」)写真はその2巻目です。この本にも入院中お世話になりましたが、いかにしてこんな本を選んだかというと、実は苦い思い出があって、その小さなトラウマの傷が一生残ってしまう、という本だからなんです。
今高校生の長男がまだ小学生だったころ、たぶん寝ながらだったと思うんですが、読み聞かせていた本だったんです。でも子供は読み聞かせになんだかうるさそうにして聞いてるもんだから、わたしも途中でやめちゃったんですね。それでね、ずっと、ずっと、あとになってから、長男からいわれたんですよ。ぼくは、いまだにこの本の落ちを知らないって。ああ、ばかですね。あのときは、こどもたちに、むりやり聞かせているような感じがして途中でやめてしまったけれど、ほんとはこどもたちは、きいてたんですね。ちゃんと。
とまあ、こういうトラウマが残っている本なのです。子供にも大人にもとってもおもしろいとてもかわいらしいメルヘンです。今更おそいけど、一巻目ではホッツェンプロッツは、とうぜん警察につかまってるからね。それもとんでもないかんじでね。高校生は興味なんてもたないし、忘れてるだろうけれど。
でも、わたしにとっては、それだけでいつまでも忘れられない本、このさい、三冊ともいっぺんによんでしまいました。一冊目も、読んだのはだいぶ昔なので、内容はすっかり忘れてしまっていましたよ。とってもおもしろかったです。
のちのち、読み聞かせボランティアなんかするようになったのにも、実はこの、ちょっとつらい経験が影響しているかもしれません。
こどもたちがつまらない顔をして聞いているように見えても、それはほんとじゃないんだな。こどもたちはまだ、感情の表わし方が未熟だから、そんなふうにみえたのかな。どちらにしろ、わたしも未熟でした。
とりもどせない失敗は、ずっと残るもの。でもそれを取り戻すために、ずっと、やっていくつもりです。読み聞かせボランティアを。たったひとつの失敗が、大きな大きなほほえみの渦のもとになってくれれば、わたしもうれしい。
そうすれば、あのときしてしまったことの傷が、少しは軽くなるかもしれない。
人間は未熟な者。失敗はつきもの。でも心につきささる失敗は、絶対にほっておかないで、あとで、なんとかしてみましょう。
自分の子供たちにしてあげられなかったことを、ほかのたくさんのこどもたちのために、してあげましょう。