2009年2月15日の深夜に放送された、
『音楽ドキュメンタリー:トスカニーニとの会話』と
『トスカニーニのワーグナー』
は、大きな感銘を覚えた。
*『音楽ドキュメンタリー:トスカニーニとの会話』について。
トスカニーニの娘・ワグナーが、
オープンリール・テープに録音していた150時間にもおよぶ、
膨大な父の会話テープをもとに制作された、
ドラマ仕立てのドキュメンタリー。
ドラマと言っても、
1954年の大晦日の夜、
ひとつの部屋に集まったトスカニーニと、
彼の親交があった親族や友人達が、
お茶を飲みながら昔話をすると言った単純な進行。
しかし、この思い出話は、
トスカニーニの生い立ち、成功、戦争、音楽、家族とあらゆる方面に向けられ、
残されたトスカニーニの言葉を現代の俳優達の口で伝えると言った手法で、
言葉の節々に挿入されるモノクロの歴史的映像に興味を持たぬ
クラシック・ファンはいないだろう。
また、
トスカニーニと親族達の会話を字幕でなく、
日本語に吹替えで放送したことも親切な気がする。
凡その内容は、一昨日記述した、
<トスカニーニ特集:歴史的映像公開/NHK-BS2>
の番組予想に通じた。
しかし、
新しい発見としてムッソリーニとの親交の話や、
有名なチェロ奏者からの抜擢の理由、
トゥーランドットの初演の逸話とプッチーニに対する感情の位置の対比など、
意外な話も聞くことができた。
プッチーニやストコフスキーに対しての辛辣な発言に興味を持ったし、
逆にベートーヴェン、ワーグナー、ヴェルディへの信仰を強く感じた。
また、アルフレード・カタラーニの才能を高く評価した。
プッチーニはトスカニーニに言わせると、盗作家で創造性が貧困だそうだ。
また、大衆との迎合を考えておらず、
「奴等は、音楽について何も理解いない。」
と突き放すように語る。
逆を言えば、
ストコフスキーが大衆に迎合したことで、
トスカニーニの逆燐に触れたようだ。
番組中、トスカニーニがストコフスキーに書いた手紙として
(親族の手によって出されなかったが…。)
「これほど野蛮で品がなく非音楽的な演奏は、
神聖なる音楽芸術の冒涜であり、
音楽界にも独裁者のような無法者がいる。」
とこき下ろしている。
しかし、
ストコフスキーに対し、強烈なライバル意識を持っていたことも読み取れ、
音楽芸術の大衆性のあり方ついて考えるヒントを感じた。
また、
映像中ムッソリーニの死の場面を執拗に扱っていたことに異様さを感じた。
路上での遺骸の映像については、歴史映像の中で頻繁に見ることがあるが、
逆さ吊りの場面以上にそれに至るプロセスと市民の集まりが映し出されたことに、
驚きを覚えた。
話題は逸れるが、
先日NHK-BS2で放送された、<手塚治虫特集>の中で紹介された
『紙の砦』のアメリカ兵の件を思い出した。
特異な時代の中で、突然生まれる才能の開花。
人の感受性は、劇的場面の中でこそ鍛えられる。
現代の温室育ちの中で特異な才能開花は生まれ難い。
しかし、
個人崇拝の時代は終わりを告げるべきなのだろう。
あらゆる表現世界で<巨匠に時代>は終わりつつある。
それは、フラットな時代の証なのかもしれない。
世界は、益々フラットに移行するのか?
番組を見ながらそんな事を感じた。
*『トスカニーニのワーグナー』 について。
ワーグナーの演奏会については、
<トスカニーニとの会話>を見た直後だけに、
すんなり耳に入ってきた。
名演と言うには躊躇を覚えるが、
徹底的に鍛えられた管弦楽の響きは驚嘆に値するし、
よく指摘されることだが輪郭のしっかりとしたトスカニーニの音作りは、
フルトヴェングラーの変幻する音作りとの対比を感じることができ、
収穫の多い演奏だった。
それよりも驚いた事実が、
ヴェルディの『諸国民の賛歌』(1944年収録)
15分強の短い曲だが、
音楽史上、最も政治色の強い演奏表現として、
私の記憶に強く留められることとなり、
そのことを忠実にお伝えしたいと考え、
番組内の字幕をそのまま書き写す事にした。
「次の映像は1944年制作。戦時下、イタリア解放と時を同じくして作られました。ファシストに反意を示したトスカニーニは、米国に亡命しヴェルディ作曲『諸国民の賛歌』を指揮。イタリア統一を祝って1862年に作曲された曲です。トスカニーニは原曲に手を加え英・仏の国家とガリヴァルディ賛歌に連合国の歌を加えました。『星条旗よ永遠なれ』と『インターナショナル』です。冷戦時代にあってこの最後の曲は後にアメリカ人の手で映像から削除されました。トスカニーニは原曲の歌詞を変更し<イタリア・わが祖国>を<イタリア・わが裏切られし祖国>としました。」
ストコフスキーの改変作業を強く否定したトスカニーニが、
自分が敬愛するヴェルディの楽曲に手を加えてまでファシズムに抵抗し、
行動に示した事実を証明する歴史的な音楽(映像)の記録に、
悲劇の時代に真っ向から抵抗した一人の音楽家の姿を見た。
戦う姿勢。
音楽でファシズムと戦ったトスカニーニ。
映画でファシズムと戦ったチャップリン。
絵画で戦争に反旗をしめしたピカソ。
芸術が生み出す表現の奥深さを知る番組になっていた。
芸術に於ける直接的な表現。
時にそれは大きな意味を持っている。
読者の皆様に紹介できて良かったと感じています。
<関連記事>
*トスカニーニ特集:歴史的映像公開/NHK-BS2。
http://blog.goo.ne.jp/mimifuku_act08/d/20090214










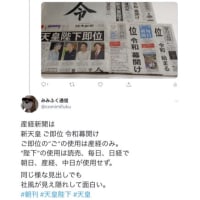

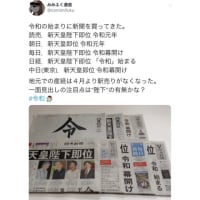

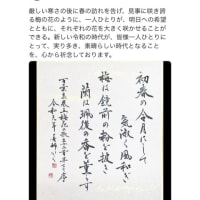
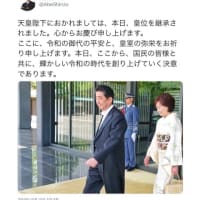



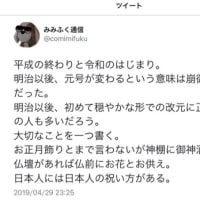







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます