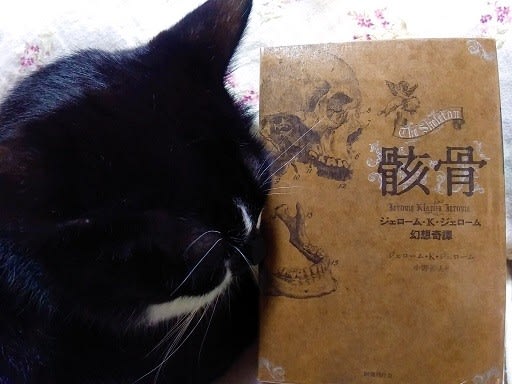神崎宣武著『旅する神々』
古来、神は常在せず、人々の延長線上にあった。
五つの名を持つ大国主神、浦島太郎のモデルとなった山幸彦、吉備津神の温羅退治、民俗行事にみる来訪神など、「旅する神々」の姿を通して、日本独自の神々と人々の関係をさぐり、原信仰を浮かび上がらせる。
序章――呼べば応える日本の神々
第一章 大国主神の旅
第二章 山幸彦の旅
第三章 吉備津彦の旅
第四章 倭姫命の旅
第五章 倭建命の旅
終章――招かねざる神々の旅
この本は夏のうちに読み終わっていたのだけど、内容的に旧暦十月の間(新暦では十月下旬から十二月上旬)に読書感想を載せたかったので、今回の掲載となった。今年の神無月の日付は、十一月五日が朔、十二月三日が晦だそうだ。
それはともかく―――。
日本の神々はたいてい場所から場所へ移動する。
広く知られているのは、旧暦十月の神無月。
この旧暦十月を出雲地方では、ほかの地方とは逆に神在月とする。それは、十月十一日・十五日・十七日に出雲大社・佐太神社・万九千神社で神在祭が行われ、そこに各地の神々が集まるとされているからだ。
では、この時期、出雲以外の土地では、神の不在の神社でどうやって祭りを行うのか。
日本の神々は幾つもの分霊に分かれて、乞われた先を巡ることが出来る。ゆえに、出雲の神在祭にも分霊が赴くとみればよいと、著者はいう。
いないようで、実はいつもいる。乞われればすぐに降りて来る、と考えてよいのだろうか。
出雲以外の土地で神が不在とされる神無月においてさえ、八百万の神は主祭神から分霊を飛ばして各地を移動していると思うとなかなか面白い。この狭い国土にはいったいどれだけの数の神々とその分霊が犇めいているのか。
現在、一般に目にする祭典は、神社で執り行われることが多い。神社には神々が常在であるので、わざわざ招き入れる必要はない。
しかし、神社という建築様式が生まれたのは、仏教伝来によって寺院の影響を受けた奈良時代以降のことである。
それまでは、社を持たない、つまりは常在ではない神々を崇めての祭事が行われていた。そして、それらは神社という建築様式が一般化したのちも廃れることなく、古神道あるいは民間神道として連綿と伝えられてきた。
常在ではない神々は、普段は自然界に住んでおり、人々からの要請によって里に降りたもう。
そのため、神々を招き奉るための依り代というシステムを様々発展させている。御柱、神籠、幣、蓋、オハケ、幟、山鉾など、その種類はあまりにも多い。
“いいかえれば、神々は、人びとの延長線にあるのだ。そして、さらに大胆にいいかえれば、神々は、絶対的な存在ではなく、むしろ人びとに都合よく崇められる超人的な存在なのである。「困ったときの神だのみ」とは、そうした神々と人びとの関係性のなかで生まれた言葉、ということができよう。”
アニミズム(自然信仰)は、かつては世界各地で見られた現象だった。
しかし、時代を経て、異文化からの干渉を受けるに従って、それらの多くは形を変えてしまった。ヨーロッパではキリスト教によって、原初的なアニミズムはほぼ絶えたと言っていいだろう。
日本のアニミズムの特異性とは、外部との接触が生じても、それに吸収されたり滅ぼされることはなく、西欧人の基準からは矛盾すると思われる諸要素が矛盾とされずに併存しているところだ。
先に触れたように神社という建築様式が生まれたのちも、アニミズムは神社や寺院に吸収されることなく、日本各地で連綿と受け継がれてきた。
それを『菊と刀』のルース・ベネディクトは、「日本的原理」と呼んでいる。
日本的原理とは、神仏習合、或いは神仏混淆に通じている。更には、「神さま仏さま、ご先祖さま」にも通じている。
日本の宗教観においては、神と人との関係が極めて近い。「神さま仏さま」までは、まぁわかる。しかし、そこにただの人間である「ご先祖さま」が繋がってしまうのは、なかなか特異な現象だ。外野から見たら、不遜な感性と思われるかもしれない。
三年前に、万城目学の『パーマネント神喜劇』を読んだが、そこでは、神さまが親戚のおっちゃんくらいの親しさで人々と交流していた。そして、人々にお願い事をされるために祀られる存在でもあった(18.05.31の当ブログに感想文掲載)。
『古事記』の神々をより剽軽に親しみやすくした感じであろうか。
話を本書に戻すと、個人的には、序章と終章が読みごたえがあった。
一章から五章の神々についての考察は、話があっちに飛びこっちに飛びで、全体的にやや散漫な印象であった。
最古の典籍『古事記』自体が、細部に辻褄の合わないところが多く、また一柱の神の物語にいくつものテーマを持たせていたりするので、色々解説してみたくなるのかもしれない。
でも、それぞれの章の主人公に当たる神の旅・移動についてのみ語るのに留めておいた方が読み易かったのではないかと思う。
『古事記』は、「上つ巻」「中つ巻」「下つ巻」に分かれている。
「上つ巻」は、神話である。
「中つ巻」「下つ巻」は、神武天皇から推古天皇までの天皇記である。
「中つ巻」が神から人へ、「下つ巻」が人の代とみることが出来る。しかし、それらの殆どが実証できない古ごとである。前後の脈絡が付きにくい所が多い。
『古事記』は、天武天皇の命により、稗田阿礼が誦習するところの帝紀と本辞を太安万侶
が編纂したものだ。
しかし、帝紀・本辞なるものは、記録としてどこにも存在しない。太安万侶の存在を疑問視する説もある。何なら稗田阿礼だって何者なのか明らかではない。
本書では、稗田阿礼一人の誦習ではなく、ほかの語り部たちの協力があったのではないかと疑問を投げかけている。
私は、語り部集団のチーム名というか、共通のペンネームみたいなものが稗田阿礼なのではないかと思ったりもする。
『古事記』の神々の旅とは、主に、国造り・国家の統一を目的としているが、「上つ巻」の神と「中つ巻」の神とでは、その遣り様がかなり異なることが分かったのは、良い収穫だった。
日本には、少なくとも近代までは、教義に厳格な宗教は存在しなかった。
各地方にこれほどに多様なアニミズムを伝承している国民性も、世界では珍しいという。
著者は、「それで、特に残虐な争いごともなかった。しあわせな歴史を共有してきた、としなくてはならないだろう。」と述べている。
なんせ「神さま仏さま、ご先祖さま」くらいのノリで、神々と人々との距離が近い。
甑島のトシドンや男鹿のナマハゲなど、年中行事として各地に伝わる来訪神は、顔には恐ろしげな仮面を着け、身には農民や旅人のように藁蓑を着けている事例が多い。笠を被っていることもある。
仮面に蓑笠。
民俗学の解説書では、ほぼ例外なく、これを来訪神の典型的な姿と位置付けている。この誰もが見慣れた着用具を纏い、来訪神は家々を訪ね、子を諭し、厄を払い、福を授ける。
神々も人々と同じように、風雪に耐えながら旅をする。
仮面を着け、笠と蓑を身に纏った神が、あるいはマレビトが、遠い土地から旅をして、季節の節目を祝福しにやってくる。
古く遡れば各地にあったその種の行事は、世の変遷に伴って少しずつ信仰を失い、物乞いや門付け芸人に化した。
これをもって、神の零落した姿と言えるだろう。或いは、人が神に昇格した姿と言った方が、吉報者を表すのに相応しいか。
この国の神は絶対的な存在ではない。
神が人になり、人が神になるほど、神と人との隔たりが曖昧だ。この精神が不断の連続性を持って現代に続いたことは、確かに尊く、ありがたく、幸せなことと言える。
古来、神は常在せず、人々の延長線上にあった。
五つの名を持つ大国主神、浦島太郎のモデルとなった山幸彦、吉備津神の温羅退治、民俗行事にみる来訪神など、「旅する神々」の姿を通して、日本独自の神々と人々の関係をさぐり、原信仰を浮かび上がらせる。
序章――呼べば応える日本の神々
第一章 大国主神の旅
第二章 山幸彦の旅
第三章 吉備津彦の旅
第四章 倭姫命の旅
第五章 倭建命の旅
終章――招かねざる神々の旅
この本は夏のうちに読み終わっていたのだけど、内容的に旧暦十月の間(新暦では十月下旬から十二月上旬)に読書感想を載せたかったので、今回の掲載となった。今年の神無月の日付は、十一月五日が朔、十二月三日が晦だそうだ。
それはともかく―――。
日本の神々はたいてい場所から場所へ移動する。
広く知られているのは、旧暦十月の神無月。
この旧暦十月を出雲地方では、ほかの地方とは逆に神在月とする。それは、十月十一日・十五日・十七日に出雲大社・佐太神社・万九千神社で神在祭が行われ、そこに各地の神々が集まるとされているからだ。
では、この時期、出雲以外の土地では、神の不在の神社でどうやって祭りを行うのか。
日本の神々は幾つもの分霊に分かれて、乞われた先を巡ることが出来る。ゆえに、出雲の神在祭にも分霊が赴くとみればよいと、著者はいう。
いないようで、実はいつもいる。乞われればすぐに降りて来る、と考えてよいのだろうか。
出雲以外の土地で神が不在とされる神無月においてさえ、八百万の神は主祭神から分霊を飛ばして各地を移動していると思うとなかなか面白い。この狭い国土にはいったいどれだけの数の神々とその分霊が犇めいているのか。
現在、一般に目にする祭典は、神社で執り行われることが多い。神社には神々が常在であるので、わざわざ招き入れる必要はない。
しかし、神社という建築様式が生まれたのは、仏教伝来によって寺院の影響を受けた奈良時代以降のことである。
それまでは、社を持たない、つまりは常在ではない神々を崇めての祭事が行われていた。そして、それらは神社という建築様式が一般化したのちも廃れることなく、古神道あるいは民間神道として連綿と伝えられてきた。
常在ではない神々は、普段は自然界に住んでおり、人々からの要請によって里に降りたもう。
そのため、神々を招き奉るための依り代というシステムを様々発展させている。御柱、神籠、幣、蓋、オハケ、幟、山鉾など、その種類はあまりにも多い。
“いいかえれば、神々は、人びとの延長線にあるのだ。そして、さらに大胆にいいかえれば、神々は、絶対的な存在ではなく、むしろ人びとに都合よく崇められる超人的な存在なのである。「困ったときの神だのみ」とは、そうした神々と人びとの関係性のなかで生まれた言葉、ということができよう。”
アニミズム(自然信仰)は、かつては世界各地で見られた現象だった。
しかし、時代を経て、異文化からの干渉を受けるに従って、それらの多くは形を変えてしまった。ヨーロッパではキリスト教によって、原初的なアニミズムはほぼ絶えたと言っていいだろう。
日本のアニミズムの特異性とは、外部との接触が生じても、それに吸収されたり滅ぼされることはなく、西欧人の基準からは矛盾すると思われる諸要素が矛盾とされずに併存しているところだ。
先に触れたように神社という建築様式が生まれたのちも、アニミズムは神社や寺院に吸収されることなく、日本各地で連綿と受け継がれてきた。
それを『菊と刀』のルース・ベネディクトは、「日本的原理」と呼んでいる。
日本的原理とは、神仏習合、或いは神仏混淆に通じている。更には、「神さま仏さま、ご先祖さま」にも通じている。
日本の宗教観においては、神と人との関係が極めて近い。「神さま仏さま」までは、まぁわかる。しかし、そこにただの人間である「ご先祖さま」が繋がってしまうのは、なかなか特異な現象だ。外野から見たら、不遜な感性と思われるかもしれない。
三年前に、万城目学の『パーマネント神喜劇』を読んだが、そこでは、神さまが親戚のおっちゃんくらいの親しさで人々と交流していた。そして、人々にお願い事をされるために祀られる存在でもあった(18.05.31の当ブログに感想文掲載)。
『古事記』の神々をより剽軽に親しみやすくした感じであろうか。
話を本書に戻すと、個人的には、序章と終章が読みごたえがあった。
一章から五章の神々についての考察は、話があっちに飛びこっちに飛びで、全体的にやや散漫な印象であった。
最古の典籍『古事記』自体が、細部に辻褄の合わないところが多く、また一柱の神の物語にいくつものテーマを持たせていたりするので、色々解説してみたくなるのかもしれない。
でも、それぞれの章の主人公に当たる神の旅・移動についてのみ語るのに留めておいた方が読み易かったのではないかと思う。
『古事記』は、「上つ巻」「中つ巻」「下つ巻」に分かれている。
「上つ巻」は、神話である。
「中つ巻」「下つ巻」は、神武天皇から推古天皇までの天皇記である。
「中つ巻」が神から人へ、「下つ巻」が人の代とみることが出来る。しかし、それらの殆どが実証できない古ごとである。前後の脈絡が付きにくい所が多い。
『古事記』は、天武天皇の命により、稗田阿礼が誦習するところの帝紀と本辞を太安万侶
が編纂したものだ。
しかし、帝紀・本辞なるものは、記録としてどこにも存在しない。太安万侶の存在を疑問視する説もある。何なら稗田阿礼だって何者なのか明らかではない。
本書では、稗田阿礼一人の誦習ではなく、ほかの語り部たちの協力があったのではないかと疑問を投げかけている。
私は、語り部集団のチーム名というか、共通のペンネームみたいなものが稗田阿礼なのではないかと思ったりもする。
『古事記』の神々の旅とは、主に、国造り・国家の統一を目的としているが、「上つ巻」の神と「中つ巻」の神とでは、その遣り様がかなり異なることが分かったのは、良い収穫だった。
日本には、少なくとも近代までは、教義に厳格な宗教は存在しなかった。
各地方にこれほどに多様なアニミズムを伝承している国民性も、世界では珍しいという。
著者は、「それで、特に残虐な争いごともなかった。しあわせな歴史を共有してきた、としなくてはならないだろう。」と述べている。
なんせ「神さま仏さま、ご先祖さま」くらいのノリで、神々と人々との距離が近い。
甑島のトシドンや男鹿のナマハゲなど、年中行事として各地に伝わる来訪神は、顔には恐ろしげな仮面を着け、身には農民や旅人のように藁蓑を着けている事例が多い。笠を被っていることもある。
仮面に蓑笠。
民俗学の解説書では、ほぼ例外なく、これを来訪神の典型的な姿と位置付けている。この誰もが見慣れた着用具を纏い、来訪神は家々を訪ね、子を諭し、厄を払い、福を授ける。
神々も人々と同じように、風雪に耐えながら旅をする。
仮面を着け、笠と蓑を身に纏った神が、あるいはマレビトが、遠い土地から旅をして、季節の節目を祝福しにやってくる。
古く遡れば各地にあったその種の行事は、世の変遷に伴って少しずつ信仰を失い、物乞いや門付け芸人に化した。
これをもって、神の零落した姿と言えるだろう。或いは、人が神に昇格した姿と言った方が、吉報者を表すのに相応しいか。
この国の神は絶対的な存在ではない。
神が人になり、人が神になるほど、神と人との隔たりが曖昧だ。この精神が不断の連続性を持って現代に続いたことは、確かに尊く、ありがたく、幸せなことと言える。