《「ミロのヴィーナス」考 その8 ケネス・クラーク氏のヴィーナス論1》


ケネス・クラーク氏の『ザ・ヌード』 (ちくま学芸文庫)の購入はこちらから
前回のブログでは、ハヴロック氏の著作を紹介して、「クニドスのアフロディテ(=ヴィーナス)」を中心とするヴィーナス像を検討してきた。「ミロのヴィーナス」を知るには、「クニドスのアフロディテ」を源流とする数多くのタイプのヴィーナス像にも目配りする必要がある。ハヴロック氏によれば、「ミロのヴィーナス」は、その中の1つのタイプに位置づけられるヴィーナス像であった。
さて、今回のブログでは、そのハヴロック氏が、その著作の中で高く評価していたイギリスの美術史家ケネス・クラーク氏のヴィーナス論を紹介してみたい。
繰り返しになるが、ハヴロック氏は、クラーク氏の業績を次のように賞賛していた。すなわち、
「オリジナルかコピーかという考古学的な問答の対象ではなく、美術作品として偏見なしにミロのヴィーナスを評価したのは、ケネス・クラークただ一人と言ってよいだろう。彼は、この彫刻を、「小麦畑に立つ楡の木」のようだと感じた」
(ハヴロック、2002年、113頁。「第4章 その後:クニディアに触発された諸作品」より)
ところで、クラーク氏のヴィーナス論を理解するには、氏の数ある著作の中で、大著『ザ・ヌード』に拠るのが最適かと思う。後述するように、この著作は名著の誉れが高く、美術史家が推奨する名著である。ハヴロック氏もその著作の中で参考文献として大いに利用ししているのみならず、ギリシャ美術史家の中村るい氏も絶賛している。そして、何より、この名著を翻訳して日本に紹介したのは、他ならぬ高階秀爾氏であった。
この大著は、幅広いテーマを扱っているが、今回のブログは、「ミロのヴィーナス」を主題としているから、クラーク氏がヴィーナスを対象として叙述した部分を中心に紹介することにする。
以前のブログで紹介したように、高階秀爾氏の著作『ミロのヴィーナスはなぜ傑作か?』(小学館、2014年)において、第2章以下第10章まで、ヴィーナス以外のヘラ、アテナ、レダ、ディアナなど、ギリシャ・ローマ神話の女神を解説していた。ただ、そこでは、ヴィーナス自体の名画を取り上げることが少なかったように思われる。
しかし、クラーク氏の大著は、ハヴロック氏が考察の対象とした、様々なタイプのヴィーナスを主題とする名画や彫刻を数多く解説している。
そこで、今回のブログでは、クラーク氏の「クニドスのヴィーナス」および「ミロのヴィーナス」に関する見解を紹介するとともに、名画・彫刻といった西洋美術に取り上げられたヴィーナス像も説明したい。
なお、字数制限の関係上、クラーク氏の著作を3回に分けて、紹介したい。
(以下、敬称省略)
執筆項目は次のようになる。
ケネス・クラーク(高階秀爾・佐々木英也訳)『ザ・ヌード――裸体芸術論・理想的形態の研究』(美術出版社、1971年[1980年版])の目次は、先に紹介したように、次のようになっている。
「序」以外は次の9章からなる。
I はだかと裸体像
II アポロン
III ヴィーナスI
IV ヴィーナスII
V 力
VI 悲劇性
VII 陶酔
VIII もうひとつの流れ
XI 自己目的としての裸体像
「日本語版への序文」でも記しているように、クラークの「本書の基本的な議論は、人間の身体を幾何学的原理にもとづいたある種の構築に変貌させる裸体芸術というものは、紀元前五世紀のギリシャの流れを受けて」いるという前提がある。西洋の裸体芸術は、紀元前5世紀のギリシャの流れの影響があるといい、本書を通読すると、クラークの古代美術史への強い関心がうかがえる(ただ、「裸体芸術とは、ギリシャ人たちによって生み出された芸術形式だ」というクラークの主張は、エジプトの歴史を考慮に入れると、いささか言い過ぎであると自ら断っている)。
また、クラークは、1956年の出版当時、裸体像という主題をイタリア・ルネサンス芸術の研究者の眼で眺め、ギリシャ、ローマの芸術をラファエロやミケランジェロの眼で見ていたと告白している。ただ、1971年時点では、この点を特に強調しようとは思わないと断わっている。その理由は、本書で最も優れている部分は、ルーベンスを論じたところであると思うからという(4頁)。
目次をみてもわかるように、第2章の「アポロン」に続いて、第3章と第4章を「ヴィーナス」に当てていることから、ヴィーナスに対するクラークの関心の高さがうかがえる。章立てのタイトルとして、第5章から「力」「悲劇性」「陶酔」といった章名をつけている。
この点については、先の序文にも記している。「私が取り上げた主題は広大なものであり、それに秩序を与えるためには、「力」とか「悲劇性」とか「陶酔」といったような範疇で分類する以外に方法がありませんでした。この範疇は、今でも充分有効なものと思いますが、しかし、それが多少とも人為的なものであることは否定し得ません」という(3頁)。
取り上げた主題が広大なものであるから、「力」「悲劇性」「陶酔」といった範疇で分類する方法でそれに秩序を与えたと説明している。
ケネス・クラーク氏の『ザ・ヌード』は名著の誉れが高い。「はじめに」において述べたように、ハヴロック氏はこの著作を高く評価していた。
他にも例えば、著名な美術史家の中山公男は、クラークの『ザ・ヌード』について、次のように評している。
「 力の表現、運動感の提示は、もちろん、これらの先史美術だけのものではなく、全美術史を通じて、ひとつのすばらしい系譜をなしている。ケネス・クラークは、その『ザ・ヌード』で、ギリシャの壺絵や彫刻の躍動的な人体表現からドガの≪スパルタの少女たち≫に至るまでの「力の表現」についてみごとな構成と分析を試みている。それらは、ほとんどすべて写実的な芸術ではあるが、しかし、ほとんどつねに、大なり小なり、人体のフォルムや姿勢に対して、なんらかの歪曲を強制している。ミケランジェロやシニョレルリの場合はもちろんのこと、ミュロンの彫刻ですら、人体に対してひそかな歪曲を行なっている。マニエリズムからバロックにかけての絵画や彫刻の試みたコントラ・ポスト、短縮法、きわめて特異な視点の採用などの諸要素は、すべて「表現」のためのデフォルマシヨンだと考えられる。たぶん、その歪曲が、写実性の基本的な諸要素とほとんど背馳しない限り、私たちはそれを歪曲とは受けとらないし、醜悪だとも考えない。」
(中山公男『レオナルドの沈黙―美の変貌―』小沢書店、1989年、100頁~101頁)。
このように、クラークはその著作で、古代ギリシャの壺絵や彫刻から、ドガの絵に至るまで、「力の表現」について、みごとな構成と分析を試みていると、中山は賞賛している。
また、古代ギリシャ美術史家の中村るいも、今回取り上げている著作『ギリシャ美術史入門』の「コラム9 古代ギリシャの衣装」において、
「美術史家ケネス・クラークは名著『ザ・ヌード』で、人間の肉体こそが、調和や力、陶酔、悲劇性など人間的経験を呼ぶ起こすと述べています。このような身体を演出するのが衣装であり、ギリシャ彫刻を理解する上で不可欠の要素です。」と述べている(中村、2017年[2018年版]、111頁)。
このように、名著の誉れが高い著作であるが、批判もないわけではない。例えば、先述したハヴロックは、その著作で、クラークの著作を批判している。ハヴロックは、「ヘレニズム期ギリシャ美術における女性裸体像という主題の歴史に、クラークが見たのはただ衰退のみだった」(ハヴロック、2002年、91頁)と批判している。
500ページをこえる大著であるが、西洋美術史に関心のある美術好きの人は、是非とも一読をお勧めしたい。
ミュロンは、競技者の活力の永遠の範例を創造した。その作品「円盤投げ」は、活動中の人体を幾何学的な完全性と融合させようとするあらゆる試みのうち最も名高いものである。この彫刻は、天才が人間の可能性の領域を開く際に示す飛躍のひとつであるとして、クラークは高く評価している。ミュロンは、束の間の移ろい易い瞬間の動作を取り上げ、完結性を与えた。
そしてミュロンとポリュクレイトスを比較して次のように述べる。
「ポリュクレイトスは動作にかからんとして静止している状態の人像を表現しようとしたし、ミュロンは動作をとりながら均衡を保っている人像を表現しようとした。彫刻家としてはミュロンの方がより困難な仕事に立ち向っていたと言えよう。なぜなら、動作を急に堰き止められた人像は、固体であるだけに、何か無理をして限界内に踏み留まっている感を与えがちだからである」と(クラーク、1971年[1980年版]、229頁)。
クラークによれば、静止状態の人像を表現したポリュクレイトスの「槍をもつ人」より、動作をとりながら均衡を保っている人像を表現した、ミュロンの「円盤投げ」の方がより困難な仕事であるとみている(ただし、中村は、自然に立つ姿は運動中より、難易度が高いポーズであるという。中村、2017年[2018年版]、150頁参照のこと)。
古代の著述家たちは、ポリュクレイトスが完全に均衡のとれた男性像を創造したことを認めている。しかし、ポリュクレイトスは神の似姿を創造し得なかったと付言している。
それならば、これを為し遂げたのは誰か。古代の著述家たちは、それはフェイディアスであるという。紀元前480年から440年にかけて、一連の競技者像と並行して、一連の神像が見られたが、それはアポロンの幾つかのアポロン像に至って絶頂に達したとクラークは理解している。
これらのアポロン像は、ポリュクレイトスの形態自身の完成をさらに補足して、イメージの完成を表わしている。古典期に属した偉大なアポロンのイメージのひとつが、原作のまま今日に残っている。それは、オリュンピアの神殿の西正面破風に周囲の争闘を超越して立ち、ケンタウロスの激情に叱責を加えているアポロンである。
クラークによれば、晴朗、非情、また肉体美という力に寄せる無上の信頼など、初期ギリシャの理想とするものを、これほど完璧に具現した例はほかにない(ただ、このアポロンには神的な権威を高める意図から故意にアルカイックな性格が与えられており、肢体の方は造形的に平板で非現実的であるともいう)。
またフェイディアス様式を伝えるアポロン像として、「テヴェレのアポロン」(ローマ)がある。ブロンズ像からのコピーであるが、きわめて美しい大理石像である。ここではポリュクレイトス的競技者と、フェイディアス的神との相違が明瞭である。アポロンは、ポリュクレイトスのそれより丈が高く、より優美である。「テヴェレのアポロン」は、「神々の製作者」(古代の文献がフェイディアスについて述べる際に付された肩書)にふわわしいとする(クラーク、1971年[1980年版]、63頁~66頁)。
クラーク氏は、前述したように、第3章と第4章を「ヴィーナスⅠ」「ヴィーナスⅡ」として、ヴィーナス論を叙述している(97頁~219頁)。
クラーク氏は、ヴィーナス論をプラトンの『饗宴』の中に出てくる二種のヴィーナス、天界と俗世のヴィーナスの話から始めている。後世、「天上のヴィーナス」と「自然のヴィーナス」と呼ばれたが、中世とルネサンスの哲学では、それが根本命題となって、女性裸体の存在理由を正当化した。
古くから人間の非理性的本性は、イメージに形式を与え、それによって、ヴィーナスを低俗的なものから天上的なものへ高めることがヨーロッパ芸術の立ち還る目標のひとつとなってきたそうだ。
プラトンはふたりの女神を母と娘だとしたが、ルネサンスの哲学者はふたりが双生児であると認知した。
17世紀以後、女性裸体像は男性のそれよりも、ノーマルで魅惑的な主題のように考えられているが、本来はそうではなかった。ギリシアに紀元前6世紀作とされる女性裸体像はなく、紀元前5世紀にも、なお稀である(クラーク、1971年[1980年版]、99頁~100頁)。
プラクシテレスの「クニドスのヴィーナス」は、彼がマウソレウムの建立に協力した直後、紀元前350年頃につくられたといわれる。東エーゲ海のコス島の人びとが着衣のヴィーナスを好んで、プラクシテレスの裸体のヴィーナスを受け容れなかったとプリニウスは伝えているが、真偽はともかく、ヴィーナス崇拝が長くつづいていた小アジアの南岸に程近いクニドスという島にヴィーナスはふさわしい存在であった。
ともあれ、「クニドスのヴィーナス」は、肉体の欲望を穏やかに甘美に形象化した像であった。そしてその美は、単にプラクシテレスの創造になるばかりでなく、すでにそのモデルでもあるフリュネーその人のなかに具現されていたとクラーク氏はみる(但し、ハヴロックはこの点に異を唱えている)。
プラクシテレスは美しい人体によってギリシャ世界を豊かにしたが、その功績の一端は彼女のものでもあったとみる(ただ、現存する49体の「クニドスのヴィーナス」の全身像レプリカのうち、原作の面影を幽かにでも伝えるものは皆無であるともいわれる。像の表面に微妙な色彩が施されていたため型取りが許されず、そのため模刻することは絶望的であったようだ)。
偽ルキアノスの記述も含めて、この像に関して現在利用できるあらゆる文献資料は、C.S.Blinkenberg, Knidia, Copenhagen, 1933.に収められているという。
本文で挙げなかった主な事実をクラークは列挙している。
・われわれは「クニドスのヴィーナス」のポーズをローマ時代のクニドス島の貨幣から確認することができる。
・この像の成功に大いに寄与した彩色は、有名な画家ニキアス(Nikias)によってなされた。
・この原作の自由なコピーは明らかにブロンズで鋳造された。そしてヴァティカンにある第二のレプリカ、つまり「ベルヴェデーレのヴィーナス」はこのブロンズ・コピーをもとに大理石に刻んだものである。そしてこの大理石像が16世紀にピエール・ポンタンによって改めてブロンズに移し変えられ、こうして生まれた現在ルーヴル美術館所蔵のブロンズ像は、おそらく「クニドスのヴィーナス」の面影を最もよく伝えるものであろうとクラークはみている。
(クラーク、1971年[1980年版]、481頁原注37)
テオドシウス帝によってコンスタンティノープルに運ばれたと伝えられるプラクシテレスの≪クニドスのヴィーナス≫は、十世紀に至っても皇帝コンスタンティヌス・ポルフィロゲニトゥスの讃美の的となっていた。原作か模刻か、いずれにせよ、十字軍によるコンスタンティノープル攻略の報告書のなかで、ロベール・ド・クラーリはこの像に言及している。その上、肉体自身は、ビザンツ人の眼にもなお、つねに興味の対象でありつづけた。その理由を人種的な連続に求めることもできよう。そして運動家たちは円形競走場(キルクス)で技を競っていたし、労働者たちは腰まではだかになってハギア・ソフィア大聖堂の建造に汗を流していた。
(クラーク、1971年[1980年版]、25頁~26頁)
クラークは原注において、次のようなことを記している。
中世における「クニドスのヴィーナス」の運命についての考察は、Blinkenberg, Knidia, 1933.
にみられる。また、ロベール・ド・クラーリの年代記を立論の根拠として、「クニドスのヴィーナス」は1203年にはまだコンスタンティノープルにあったと推定している。だが、ロベールが述べている像は「青銅づくり」であった。彼によれば、像は「優に20フィートの高さ」をもっていたという(他の点では正確な記述の中で寸法だけを誇張があったとしても、等身大を越える大きさのものであったろうとクラークはみている)。
彼の記述から、像が「貞潔のヴィーナス」だったことは明瞭であり、したがっておそらっく「クニドスのヴィーナス」のコピーか派生的作品であったとされる。
(クラーク、1971年[1980年版]、470頁原注8)
ところで、19世紀に芸術の象徴のごとくみなされた白大理石の裸体像は、一般に「クニドスのヴィーナス」からではなくて、「カピトリーノのヴィーナス」と「メディチのヴィーナス」というヘレニスティック期の彫像から派生したものである。それらは基本的にはプラクシテレス的理念の翻案であるとはいえ、重大な相違点があるとクラークは考えている。
「クニドスのヴィーナス」はこれから入ろうとする儀式的水浴のことしか考えていないが、「カピトリーノのヴィーナス」は意識的にポーズをとっている。クニドスの右腕の所作がカピトリーノの場合左腕に与えられているが、カピトリーノの「自由な」側の右腕は衣をおさえる代わりに胴体の上方の、ちょうど乳房の下にまわされている。これは美術史上、「貞潔のヴィーナス(Venus Pudica)」の名で知られているポーズである。
「カピトリーノのヴィーナス」の方が、クニドスのそれよりも肉感的な写実に優れているが、あけっぴろげなプラクシテレスの「クニドスのヴィーナス」の裸体表現が世の憤激を買うような場合にも、このポーズをとったレプリカが後世に受け容れられた。ルネサンス以降の美術において「カピトリーノのヴィーナス」が非常な権威を獲得したその理由の大半が、ひとつの翻案的作品「メディチのヴィーナス」にもとづいていることは奇妙なことであるとクラーク氏はいう。後者は、全身をめぐるリズムが破綻しているようだ。その右腕は貞潔であろうとするために、あまりに鋭い角度をつくって曲がってしまい、軀幹をめぐる運動の流れを中断してしまった。そしてウフィツィ美術館の特別席に君臨していた「メディチのヴィーナス」には気取りとわざとらしさがある。ヴィンケルマンこのかた数多くの優れた鑑識家が「メディチのヴィーナス」をもって女性美の範例と見做しているが、それを理想美とする根拠は薄弱である。そして「メディチのヴィーナス」はだだっ広い応接間の飾りものの域を出ないとクラークはみなしている(クラーク、1971年[1980年版]、110頁~118頁)。
ところで、「クニドスのヴィーナス」は、プラクシテレスの作になる唯一の有名なヴィーナスではなかった。プラクシテレスは、テスピアエの住民のためにも両脚が衣に包まれ胸乳を露わにした像「アルルのヴィーナス」(ルーヴル美術館)を作った。ルイ14世時代の彫刻家ジラルドンの補修前のブロンズ像を見ると、この像はひとつの優れた着想を具体化し、彫刻の主要課題のひとつを解決した。すなわち、トルソという完璧な造形的単位を紡錘状に先細りしてゆく支持脚の上に安定して載せなければならないという彫刻家の悩みの種となっていた問題を解決した。
プラクシテレスはただ脚に衣を巻きつけてトルソをむき出しにし、彫像の足場をきわめて堅固にすることに成功した。その結果、壺や柱や海豚といった支持体なしですまし、自由に両腕を演じさせることができるようになった。
ただ、「アルルのヴィーナス」がありきたりに見えるのは、その無表情な表面もさることながら、どちらかと言えば、動きの乏しい構成のせいであるようだ。とりわけ、身体の軸線が像の活力を削ぎとるほど平行に近い。
そして、この点では、後の彫刻家たちがプラクシテレスの創意をさらに発展させてゆくことができた。すでに紀元前4世紀に、膝で支えたマルスの楯を鏡にしてヴィーナスが自分の姿を眺めるというモティーフにこの創意が応用され、像ははっきり目立つ上昇的な対角線を基本にして組み立てられることとなった。ナポリにある「カプアのヴィーナス」がその主要なレプリカである(クラーク、1971年[1980年版]、118頁~120頁)。
あるいは、女性裸体像から一例を引くなら、カタログや教科書ではドイダルソス(ママ)の作とされているが確実なところ前四世紀初頭の作と思われるあの≪うずくまるヴィーナス≫[281図]の像がある。洋梨のような彼女の身体の造形的な豊かさは、ティツィアーノ、ルーベンス、ルノワールなど、芸術に豊麗な実りをもたらした太陽たちをはじめとして、今日に至るまで、多くの人びとを喜ばせて来た。そして、この場合には、その理由を見出すのは容易である。というのは、それは豊かな実りの完璧な象徴であり、あたかも木になっている実のように大地の牽引力を感じながら、しかもその構造のなかに、官能的エネルギーの泉があることをも隠そうとしないからである。しかし、女性裸体像のその他のポーズの場合、われわれがそれに感ずる完全さは、ほとんど説明し得ない。例えば、そのような作品の一例として、ルネッサンス期の人びとをあれほどまで魅了した≪ポリクレトの寝台≫の名で知られる(今は失われた)ヘレニスティック期浮彫のあのプシュケーの像の輪郭線を挙げることができる。ちょうど、お祭の時にふと耳にした民謡が、ひとたび意識されるとつぎつぎと多くの作曲家たちの主題の素材として使われるように、このプシュケーの輪郭線はラファエルロ、ミケランジェロ、ティツィアーノ、プーサンなどの傑作に姿を現わし、歌のメロディーが最初の言葉から離れて独立した曲に育って行くように、われわれはそれによって裸体像が独立した存在を獲得するようになったと感じさせられる。
(クラーク、1971年[1980年版]、436頁~438頁)。
このモティーフのもつ可能性は、それから200年ほどの間にさらに発展することになる。「カプアのヴィーナス」は像全体が浮彫のようにプロフィルで捉えられていたが、紀元前100年ごろ、ある天才的な彫刻家の手でこれが奥行きの次元で再構成されることになった。こうして生まれたのが、古代ギリシャの最後の偉大な作品である「ミロのヴィーナス」とクラーク氏は理解している。
1820年に発見されてから数年と経たぬ間で、「ミロのヴィーナス」はかつて「メディチのヴィーナス」が占めていた中枢的な地位を掌握していた。そして美術鑑賞家や考古学者の愛顧を失った今日でもなお、「ミロのヴィーナス」は「美」のシンボルとして確固たる地位を占めている(クラーク、1971年[1980年版]、118頁~120頁)。
シャトーブリアンとロダンが誤解していたのも、彼らの生きた時代を想えば、無理もない。クラークも、フルトヴェングラーが「ミロのヴィーナス」の制作年代を引き下げたことを評価して、次のように述べている。
「 ≪ミロのヴィーナス≫の名声の一端は、偶然の賜物であった。一八九三年にフルトヴェングラーがそれまでよりも厳密な分析を加えるまで、彼女は紀元前五世紀の原作と信じられており、首つきのさまという利点までそなえた、この偉大な世紀からの唯一の婦人単身立像と信じられていた。こうして彼女は熱烈な党派心のもとで、「エルギン・マーブルズ」が至高の芸術に祭り上げられた時代にめぐり合わせ、得をしたのである。「エルギン・マーブルズ」は堂々として自然であるため、また気取りや作為が見られないため、それまで称讃されてきたが、≪ミロのヴィーナス≫を冷たくとりすました古典主義の寵姫たちと対比させるときにも、同じ頌辞が使われたのである。古代の他の裸体のヴィーナス像に比べれば、彼女は遥かに頑健で多産型であるかもしれない。≪メディチのヴィーナス≫が温室を想わせるとすれば、≪ミロのヴィーナス≫は麦畑に立つ楡の木を想わせる。しかしながら、実のところ、彼女が古代の作品を通じて最も複雑かつ技巧的な産物のひとつであることを考慮に入れるなら、自然らしさを楯に弁護することにはある種のアイロニーがひそんでいる。この像の作者は、当時のさまざまな創意工夫を活用したばかりでなく、前五世紀作品の効果をも与えようと意識的に試みた。比例ひとつを取り上げただけでも、それを証明することができよう。つまりアルルやカプアのヴィーナスでは両乳間の距離が乳から臍までの距離よりも著しく短いのに対し、ミロのヴィーナスでは古い時代の等距離の形式が回復されている。彼女の身体の各面(プラン)は非常に広く穏やかであるため、一見するとひとつの面が次の面に移るときに通過する角が幾つあるのかわからない。建築に譬えて言えば、彼女は古典的な効果をもったバロック的構造物である。十九世紀に彼女がヘンデルの≪メサイア≫やレオナルド・ダ・ヴィンチの≪最後の晩餐≫と同じ美の範疇に加えられた理由も、この効果に求められよう。フェイディアスの英雄時代の作品ではなく、しかも「感受性」という近代的特質を幾分欠いているらしいことを承知されている今日でも、依然として彼女は最も輝かしい人間の肉体的理想のひとつであることに変りはなく、また芸術作品はそれが属する時代を表現せねばならぬという現代批評の合言葉に対する最も高尚な反駁となっている。」
(クラーク、1971年[1980年版]、120頁~122頁)。
このクラークの「ミロのヴィーナス」に関する叙述のポイントを箇条書きにして、まとめてみよう。
・「ミロのヴィーナス」の名声の一端は、偶然の賜物
・1893年のフルトヴェングラーの分析まで、「ミロのヴィーナス」は紀元前5世紀の原作と信じられていた
・「ミロのヴィーナス」は「エルギン・マーブルズ」とみなされていた時代にめぐり合わせ、得をした
・「ミロのヴィーナス」は、他のヴィーナス像に比べ、頑健で多産型
・「メディチのヴィーナス」が温室を想わせるとすれば、「ミロのヴィーナス」は麦畑に立つ楡の木を想わせる
・「ミロのヴィーナス」は、古代の作品を通じて最も複雑かつ技巧的な産物のひとつ
・「ミロのヴィーナス」像の作者は、前5世紀作品の効果をも与えようと試みた。例えば、比例で、古い時代の等距離の形式が回復されている(両乳間、乳から臍までの距離)
・建築に譬えて言えば、古典的な効果をもったバロック的構造物
・「ミロのヴィーナス」は、今日でも最も輝かしい人間の肉体的理想のひとつ
「ミロのヴィーナス」の作られた後期ヘレニズム時代について、クラークは次のように述べている。
「 ≪ミロのヴィーナス≫の生成は、後期ヘレニスティックの芸術家が創造の問題にどう取り組んで行ったかを明かしてくれる。彼らは偉大な発明の才に恵まれていなかったので、モティーフの組み合わせと発展に技巧の限りを尽した。芸術史を通観すればこれは異常なことでも不真面目なことでもない。例えば中国やエジプトではこれが通則であったし、ルネッサンス以後のヨーロッパ芸術の極度なめまぐるしさをそのまま優越のしるしと受け取ることはできないのである。ところで、こと女性裸体像に関して、およそ永続的な価値をもつ形態構成上の創意のうち、元をただせば紀元前四世紀に発見されなかったものがまずひとつとしてなかったとは、刮目に値する事実である。「うずくまるヴィーナス」という美しいモティーフがその一例で、後にルーベンスや十八世紀のフランス芸術家は大いにこれを利用した。通例、碑文を根拠としてビチニア出身のドイダルソス(ママ)という後期ヘレニスティックの彫刻家がこれを創始したと言われ、たしかに彼はこのポーズで彫像を製作した。しかしながらこのモティーフは画家カミロスが絵付けをした前四世紀のアンフォラに現われていて、その人像はスコパスの彫刻から想を得ているようである。とすれば「うずくまるヴィーナス」の見事な構成もやはり、あの偉大な造形的エネルギーの時代に起源を遡る筈である。」
(クラーク、1971年[1980年版]、123頁)。
クラークは、「ミロのヴィーナス」の制作年代に関して、いち早くフルトヴェングラー説およびシャルボノー説に注目したので(120頁、482頁原註41)、後期ヘレニスティック時代とみていたことが、上記の文章よりわかる。
そして上記のように、「≪ミロのヴィーナス≫の生成は、後期ヘレニスティックの芸術家が創造の問題にどう取り組んで行ったかを明かしてくれる。彼らは偉大な発明の才に恵まれていなかったので、モティーフの組み合わせと発展に技巧の限りを尽した。」という。つまり「ミロのヴィーナス」などを制作した後期ヘレニスティックの芸術家たちは、偉大な発明の才に恵まれていなかったと捉え、その才能のないのをモティーフの組み合わせに意を注いだとする。
クラークのこの記述からもわかるように、後期ヘレニスティック時代の芸術家や彫刻について、さほど評価していない。これはこの時期を積極的に評価しようとするハヴロックとは対照的である。
そして、クラークは、こと女性裸体像に関して、紀元前4世紀という時代は形態構成上の創意の源を作り出した点で高く評価している。その一例として、「うずくまるヴィーナス」という美しいモティーフを挙げている。クラークによれば、このモティーフは画家カミロスが絵付けをした紀元前4世紀のアンフォラに現われていて、その人像はスコパスの彫刻から想を得ているとみている。そして、クラークは、「うずくまるヴィーナス」の見事な構成も、「あの偉大な造形的エネルギーの時代」=紀元前4世紀にその起源を遡っている。
ただ、通説では、碑文を根拠としてビテュニア出身のドイダルサスという後期ヘレニスティックの彫刻家がこれを創始したとされる(ハヴロックは、平面的な絵画的表現と、立体彫刻、三次元の構想とを区別して、「うずくまるヴィーナス(アフロディテ)」を後期ヘレニズム期の作とみている。ただし、ドイダルサス説には否定的である。ハヴロック、2002年、95頁~98頁参照のこと)。
後期古代の女性裸体像は、数が少ない上に、大部分が粗野であり、実質的に芸術の主題であることをやめていた。
クラークによれば、紀元2世紀以後の作とされる女性の単身裸体像はただの一点もないという。ヴィーナスは宗教から娯楽に、娯楽から装飾へと変転し、次いで消滅してしまった。
そして、再びヴィーナスが世に姿を現わしたとき、建物も思考体系も道徳も、姿を変えていたし、女体も変貌を遂げていた。
エヴァの肉体に、人類最初の不幸な母にふさわしい性格とゴシック装飾の尖頭アーチ的リズムと結合するため、新しい約束的手法(コンヴェンション)が発明されていた。イタリア・ルネサンスの初期の段階における芸術家たちの作品にも、こうしたコンヴェンションの意識が認められる。
14世紀半ば、1357年、シエナで、リュシッポスの署名入りの彫像(海豚に支えられていたというから、ヴィーナス像と推測されている)が発掘され、町の中央に据えられたが、異教の偶像崇拝にあたるとして、国家の布告によって取り外され、敵に悪運をもたらすようにと、フィレンツェの領内に埋められた。この話を彫刻家ギベルティは伝えている(この決定は、像が裸体のせいではなく、異教の偶像だったためであることにクラークは注意を促している)。
また、シエナからヴィーナスが追放されるより50年も前に、シエナ大聖堂の建築家ジョヴァンニ・ピサーノは、「貞潔のヴィーナス」(Venus Pudica)をほとんどそっくりに写した裸像をピサ大聖堂の説教壇上に「基本道徳像」のひとりとして含め入れていた。今日「節制」か「貞潔」の寓意像とみなさており、1300年から1310年の間の作品である(クラーク、1971年[1980年版]、127頁~128頁)。
ケネス・クラーク『ザ・ヌード』 (ちくま学芸文庫)はこちらから

ケネス・クラーク氏の『ザ・ヌード』 (ちくま学芸文庫)の購入はこちらから
【はじめに】
前回のブログでは、ハヴロック氏の著作を紹介して、「クニドスのアフロディテ(=ヴィーナス)」を中心とするヴィーナス像を検討してきた。「ミロのヴィーナス」を知るには、「クニドスのアフロディテ」を源流とする数多くのタイプのヴィーナス像にも目配りする必要がある。ハヴロック氏によれば、「ミロのヴィーナス」は、その中の1つのタイプに位置づけられるヴィーナス像であった。
さて、今回のブログでは、そのハヴロック氏が、その著作の中で高く評価していたイギリスの美術史家ケネス・クラーク氏のヴィーナス論を紹介してみたい。
繰り返しになるが、ハヴロック氏は、クラーク氏の業績を次のように賞賛していた。すなわち、
「オリジナルかコピーかという考古学的な問答の対象ではなく、美術作品として偏見なしにミロのヴィーナスを評価したのは、ケネス・クラークただ一人と言ってよいだろう。彼は、この彫刻を、「小麦畑に立つ楡の木」のようだと感じた」
(ハヴロック、2002年、113頁。「第4章 その後:クニディアに触発された諸作品」より)
ところで、クラーク氏のヴィーナス論を理解するには、氏の数ある著作の中で、大著『ザ・ヌード』に拠るのが最適かと思う。後述するように、この著作は名著の誉れが高く、美術史家が推奨する名著である。ハヴロック氏もその著作の中で参考文献として大いに利用ししているのみならず、ギリシャ美術史家の中村るい氏も絶賛している。そして、何より、この名著を翻訳して日本に紹介したのは、他ならぬ高階秀爾氏であった。
この大著は、幅広いテーマを扱っているが、今回のブログは、「ミロのヴィーナス」を主題としているから、クラーク氏がヴィーナスを対象として叙述した部分を中心に紹介することにする。
以前のブログで紹介したように、高階秀爾氏の著作『ミロのヴィーナスはなぜ傑作か?』(小学館、2014年)において、第2章以下第10章まで、ヴィーナス以外のヘラ、アテナ、レダ、ディアナなど、ギリシャ・ローマ神話の女神を解説していた。ただ、そこでは、ヴィーナス自体の名画を取り上げることが少なかったように思われる。
しかし、クラーク氏の大著は、ハヴロック氏が考察の対象とした、様々なタイプのヴィーナスを主題とする名画や彫刻を数多く解説している。
そこで、今回のブログでは、クラーク氏の「クニドスのヴィーナス」および「ミロのヴィーナス」に関する見解を紹介するとともに、名画・彫刻といった西洋美術に取り上げられたヴィーナス像も説明したい。
なお、字数制限の関係上、クラーク氏の著作を3回に分けて、紹介したい。
(以下、敬称省略)
執筆項目は次のようになる。
・【ケネス・クラークの名著『ザ・ヌード』の目次】
・【ケネス・クラークの名著に対する評価】
・【古代ギリシャの彫刻家について】
・【ケネス・クラークのヴィーナスについての理解】
・<「クニドスのヴィーナス」について>
・【「ミロのヴィーナス」と他のヴィーナス像】
ケネス・クラークと西洋の美術(名画と彫刻)
・【西洋美術の中のヴィーナス】
・<ボッティチェリの絵>
・<レオナルドと「レダと白鳥」>
・<ミケランジェロと「アポロン」像>
・<ヴィーナスの至上の巨匠としてのラファエロ>
・<「クニドスのヴィーナス」とジョルジョーネの絵>
・<「水から上るヴィーナス」とティツィアーノの絵>
・<ルーベンスの絵>
・<アングルの絵>
・<「クニドスのヴィーナス」のポーズとルノワールの絵>
・【もう一つの流れとしてのゴシック的裸体像(腹部の曲線に特徴的)】
・<ギリシャ的な女性観とゴシック的な女性観の対比>
・<「ベリー公のいとも豪華なる時祷書」に見えるエヴァ>
・<ドイツの画家によるゴシック的ヴィーナス像>
・<オランダのレンブラントの場合 >
・<ロダンの彫刻の場合>
・<「クニドスのヴィーナス」の対立物としてのルオーの絵>
・【まとめ】
・【補論 ウォルター・ペイター『ルネサンス』にみえるヴィーナス】
【ケネス・クラークの名著『ザ・ヌード』の目次】
ケネス・クラーク(高階秀爾・佐々木英也訳)『ザ・ヌード――裸体芸術論・理想的形態の研究』(美術出版社、1971年[1980年版])の目次は、先に紹介したように、次のようになっている。
「序」以外は次の9章からなる。
I はだかと裸体像
II アポロン
III ヴィーナスI
IV ヴィーナスII
V 力
VI 悲劇性
VII 陶酔
VIII もうひとつの流れ
XI 自己目的としての裸体像
「日本語版への序文」でも記しているように、クラークの「本書の基本的な議論は、人間の身体を幾何学的原理にもとづいたある種の構築に変貌させる裸体芸術というものは、紀元前五世紀のギリシャの流れを受けて」いるという前提がある。西洋の裸体芸術は、紀元前5世紀のギリシャの流れの影響があるといい、本書を通読すると、クラークの古代美術史への強い関心がうかがえる(ただ、「裸体芸術とは、ギリシャ人たちによって生み出された芸術形式だ」というクラークの主張は、エジプトの歴史を考慮に入れると、いささか言い過ぎであると自ら断っている)。
また、クラークは、1956年の出版当時、裸体像という主題をイタリア・ルネサンス芸術の研究者の眼で眺め、ギリシャ、ローマの芸術をラファエロやミケランジェロの眼で見ていたと告白している。ただ、1971年時点では、この点を特に強調しようとは思わないと断わっている。その理由は、本書で最も優れている部分は、ルーベンスを論じたところであると思うからという(4頁)。
目次をみてもわかるように、第2章の「アポロン」に続いて、第3章と第4章を「ヴィーナス」に当てていることから、ヴィーナスに対するクラークの関心の高さがうかがえる。章立てのタイトルとして、第5章から「力」「悲劇性」「陶酔」といった章名をつけている。
この点については、先の序文にも記している。「私が取り上げた主題は広大なものであり、それに秩序を与えるためには、「力」とか「悲劇性」とか「陶酔」といったような範疇で分類する以外に方法がありませんでした。この範疇は、今でも充分有効なものと思いますが、しかし、それが多少とも人為的なものであることは否定し得ません」という(3頁)。
取り上げた主題が広大なものであるから、「力」「悲劇性」「陶酔」といった範疇で分類する方法でそれに秩序を与えたと説明している。
【ケネス・クラークの名著に対する評価】
ケネス・クラーク氏の『ザ・ヌード』は名著の誉れが高い。「はじめに」において述べたように、ハヴロック氏はこの著作を高く評価していた。
他にも例えば、著名な美術史家の中山公男は、クラークの『ザ・ヌード』について、次のように評している。
「 力の表現、運動感の提示は、もちろん、これらの先史美術だけのものではなく、全美術史を通じて、ひとつのすばらしい系譜をなしている。ケネス・クラークは、その『ザ・ヌード』で、ギリシャの壺絵や彫刻の躍動的な人体表現からドガの≪スパルタの少女たち≫に至るまでの「力の表現」についてみごとな構成と分析を試みている。それらは、ほとんどすべて写実的な芸術ではあるが、しかし、ほとんどつねに、大なり小なり、人体のフォルムや姿勢に対して、なんらかの歪曲を強制している。ミケランジェロやシニョレルリの場合はもちろんのこと、ミュロンの彫刻ですら、人体に対してひそかな歪曲を行なっている。マニエリズムからバロックにかけての絵画や彫刻の試みたコントラ・ポスト、短縮法、きわめて特異な視点の採用などの諸要素は、すべて「表現」のためのデフォルマシヨンだと考えられる。たぶん、その歪曲が、写実性の基本的な諸要素とほとんど背馳しない限り、私たちはそれを歪曲とは受けとらないし、醜悪だとも考えない。」
(中山公男『レオナルドの沈黙―美の変貌―』小沢書店、1989年、100頁~101頁)。
このように、クラークはその著作で、古代ギリシャの壺絵や彫刻から、ドガの絵に至るまで、「力の表現」について、みごとな構成と分析を試みていると、中山は賞賛している。
また、古代ギリシャ美術史家の中村るいも、今回取り上げている著作『ギリシャ美術史入門』の「コラム9 古代ギリシャの衣装」において、
「美術史家ケネス・クラークは名著『ザ・ヌード』で、人間の肉体こそが、調和や力、陶酔、悲劇性など人間的経験を呼ぶ起こすと述べています。このような身体を演出するのが衣装であり、ギリシャ彫刻を理解する上で不可欠の要素です。」と述べている(中村、2017年[2018年版]、111頁)。
このように、名著の誉れが高い著作であるが、批判もないわけではない。例えば、先述したハヴロックは、その著作で、クラークの著作を批判している。ハヴロックは、「ヘレニズム期ギリシャ美術における女性裸体像という主題の歴史に、クラークが見たのはただ衰退のみだった」(ハヴロック、2002年、91頁)と批判している。
500ページをこえる大著であるが、西洋美術史に関心のある美術好きの人は、是非とも一読をお勧めしたい。
古代ギリシャの彫刻家について
ミュロンとポリュクレイトス
ミュロンは、競技者の活力の永遠の範例を創造した。その作品「円盤投げ」は、活動中の人体を幾何学的な完全性と融合させようとするあらゆる試みのうち最も名高いものである。この彫刻は、天才が人間の可能性の領域を開く際に示す飛躍のひとつであるとして、クラークは高く評価している。ミュロンは、束の間の移ろい易い瞬間の動作を取り上げ、完結性を与えた。
そしてミュロンとポリュクレイトスを比較して次のように述べる。
「ポリュクレイトスは動作にかからんとして静止している状態の人像を表現しようとしたし、ミュロンは動作をとりながら均衡を保っている人像を表現しようとした。彫刻家としてはミュロンの方がより困難な仕事に立ち向っていたと言えよう。なぜなら、動作を急に堰き止められた人像は、固体であるだけに、何か無理をして限界内に踏み留まっている感を与えがちだからである」と(クラーク、1971年[1980年版]、229頁)。
クラークによれば、静止状態の人像を表現したポリュクレイトスの「槍をもつ人」より、動作をとりながら均衡を保っている人像を表現した、ミュロンの「円盤投げ」の方がより困難な仕事であるとみている(ただし、中村は、自然に立つ姿は運動中より、難易度が高いポーズであるという。中村、2017年[2018年版]、150頁参照のこと)。
フェイディアスの「アポロン」像
古代の著述家たちは、ポリュクレイトスが完全に均衡のとれた男性像を創造したことを認めている。しかし、ポリュクレイトスは神の似姿を創造し得なかったと付言している。
それならば、これを為し遂げたのは誰か。古代の著述家たちは、それはフェイディアスであるという。紀元前480年から440年にかけて、一連の競技者像と並行して、一連の神像が見られたが、それはアポロンの幾つかのアポロン像に至って絶頂に達したとクラークは理解している。
これらのアポロン像は、ポリュクレイトスの形態自身の完成をさらに補足して、イメージの完成を表わしている。古典期に属した偉大なアポロンのイメージのひとつが、原作のまま今日に残っている。それは、オリュンピアの神殿の西正面破風に周囲の争闘を超越して立ち、ケンタウロスの激情に叱責を加えているアポロンである。
クラークによれば、晴朗、非情、また肉体美という力に寄せる無上の信頼など、初期ギリシャの理想とするものを、これほど完璧に具現した例はほかにない(ただ、このアポロンには神的な権威を高める意図から故意にアルカイックな性格が与えられており、肢体の方は造形的に平板で非現実的であるともいう)。
またフェイディアス様式を伝えるアポロン像として、「テヴェレのアポロン」(ローマ)がある。ブロンズ像からのコピーであるが、きわめて美しい大理石像である。ここではポリュクレイトス的競技者と、フェイディアス的神との相違が明瞭である。アポロンは、ポリュクレイトスのそれより丈が高く、より優美である。「テヴェレのアポロン」は、「神々の製作者」(古代の文献がフェイディアスについて述べる際に付された肩書)にふわわしいとする(クラーク、1971年[1980年版]、63頁~66頁)。
【ケネス・クラークのヴィーナスについての理解】
クラーク氏は、前述したように、第3章と第4章を「ヴィーナスⅠ」「ヴィーナスⅡ」として、ヴィーナス論を叙述している(97頁~219頁)。
クラーク氏は、ヴィーナス論をプラトンの『饗宴』の中に出てくる二種のヴィーナス、天界と俗世のヴィーナスの話から始めている。後世、「天上のヴィーナス」と「自然のヴィーナス」と呼ばれたが、中世とルネサンスの哲学では、それが根本命題となって、女性裸体の存在理由を正当化した。
古くから人間の非理性的本性は、イメージに形式を与え、それによって、ヴィーナスを低俗的なものから天上的なものへ高めることがヨーロッパ芸術の立ち還る目標のひとつとなってきたそうだ。
プラトンはふたりの女神を母と娘だとしたが、ルネサンスの哲学者はふたりが双生児であると認知した。
17世紀以後、女性裸体像は男性のそれよりも、ノーマルで魅惑的な主題のように考えられているが、本来はそうではなかった。ギリシアに紀元前6世紀作とされる女性裸体像はなく、紀元前5世紀にも、なお稀である(クラーク、1971年[1980年版]、99頁~100頁)。
<「クニドスのヴィーナス」について>
プラクシテレスの「クニドスのヴィーナス」は、彼がマウソレウムの建立に協力した直後、紀元前350年頃につくられたといわれる。東エーゲ海のコス島の人びとが着衣のヴィーナスを好んで、プラクシテレスの裸体のヴィーナスを受け容れなかったとプリニウスは伝えているが、真偽はともかく、ヴィーナス崇拝が長くつづいていた小アジアの南岸に程近いクニドスという島にヴィーナスはふさわしい存在であった。
ともあれ、「クニドスのヴィーナス」は、肉体の欲望を穏やかに甘美に形象化した像であった。そしてその美は、単にプラクシテレスの創造になるばかりでなく、すでにそのモデルでもあるフリュネーその人のなかに具現されていたとクラーク氏はみる(但し、ハヴロックはこの点に異を唱えている)。
プラクシテレスは美しい人体によってギリシャ世界を豊かにしたが、その功績の一端は彼女のものでもあったとみる(ただ、現存する49体の「クニドスのヴィーナス」の全身像レプリカのうち、原作の面影を幽かにでも伝えるものは皆無であるともいわれる。像の表面に微妙な色彩が施されていたため型取りが許されず、そのため模刻することは絶望的であったようだ)。
<「クニドスのヴィーナス」についてのケネス・クラークの原注>
偽ルキアノスの記述も含めて、この像に関して現在利用できるあらゆる文献資料は、C.S.Blinkenberg, Knidia, Copenhagen, 1933.に収められているという。
本文で挙げなかった主な事実をクラークは列挙している。
・われわれは「クニドスのヴィーナス」のポーズをローマ時代のクニドス島の貨幣から確認することができる。
・この像の成功に大いに寄与した彩色は、有名な画家ニキアス(Nikias)によってなされた。
・この原作の自由なコピーは明らかにブロンズで鋳造された。そしてヴァティカンにある第二のレプリカ、つまり「ベルヴェデーレのヴィーナス」はこのブロンズ・コピーをもとに大理石に刻んだものである。そしてこの大理石像が16世紀にピエール・ポンタンによって改めてブロンズに移し変えられ、こうして生まれた現在ルーヴル美術館所蔵のブロンズ像は、おそらく「クニドスのヴィーナス」の面影を最もよく伝えるものであろうとクラークはみている。
(クラーク、1971年[1980年版]、481頁原注37)
<中世における「クニドスのヴィーナス」の運命について>
テオドシウス帝によってコンスタンティノープルに運ばれたと伝えられるプラクシテレスの≪クニドスのヴィーナス≫は、十世紀に至っても皇帝コンスタンティヌス・ポルフィロゲニトゥスの讃美の的となっていた。原作か模刻か、いずれにせよ、十字軍によるコンスタンティノープル攻略の報告書のなかで、ロベール・ド・クラーリはこの像に言及している。その上、肉体自身は、ビザンツ人の眼にもなお、つねに興味の対象でありつづけた。その理由を人種的な連続に求めることもできよう。そして運動家たちは円形競走場(キルクス)で技を競っていたし、労働者たちは腰まではだかになってハギア・ソフィア大聖堂の建造に汗を流していた。
(クラーク、1971年[1980年版]、25頁~26頁)
クラークは原注において、次のようなことを記している。
中世における「クニドスのヴィーナス」の運命についての考察は、Blinkenberg, Knidia, 1933.
にみられる。また、ロベール・ド・クラーリの年代記を立論の根拠として、「クニドスのヴィーナス」は1203年にはまだコンスタンティノープルにあったと推定している。だが、ロベールが述べている像は「青銅づくり」であった。彼によれば、像は「優に20フィートの高さ」をもっていたという(他の点では正確な記述の中で寸法だけを誇張があったとしても、等身大を越える大きさのものであったろうとクラークはみている)。
彼の記述から、像が「貞潔のヴィーナス」だったことは明瞭であり、したがっておそらっく「クニドスのヴィーナス」のコピーか派生的作品であったとされる。
(クラーク、1971年[1980年版]、470頁原注8)
【「ミロのヴィーナス」と他のヴィーナス像】
ところで、19世紀に芸術の象徴のごとくみなされた白大理石の裸体像は、一般に「クニドスのヴィーナス」からではなくて、「カピトリーノのヴィーナス」と「メディチのヴィーナス」というヘレニスティック期の彫像から派生したものである。それらは基本的にはプラクシテレス的理念の翻案であるとはいえ、重大な相違点があるとクラークは考えている。
「クニドスのヴィーナス」はこれから入ろうとする儀式的水浴のことしか考えていないが、「カピトリーノのヴィーナス」は意識的にポーズをとっている。クニドスの右腕の所作がカピトリーノの場合左腕に与えられているが、カピトリーノの「自由な」側の右腕は衣をおさえる代わりに胴体の上方の、ちょうど乳房の下にまわされている。これは美術史上、「貞潔のヴィーナス(Venus Pudica)」の名で知られているポーズである。
「カピトリーノのヴィーナス」の方が、クニドスのそれよりも肉感的な写実に優れているが、あけっぴろげなプラクシテレスの「クニドスのヴィーナス」の裸体表現が世の憤激を買うような場合にも、このポーズをとったレプリカが後世に受け容れられた。ルネサンス以降の美術において「カピトリーノのヴィーナス」が非常な権威を獲得したその理由の大半が、ひとつの翻案的作品「メディチのヴィーナス」にもとづいていることは奇妙なことであるとクラーク氏はいう。後者は、全身をめぐるリズムが破綻しているようだ。その右腕は貞潔であろうとするために、あまりに鋭い角度をつくって曲がってしまい、軀幹をめぐる運動の流れを中断してしまった。そしてウフィツィ美術館の特別席に君臨していた「メディチのヴィーナス」には気取りとわざとらしさがある。ヴィンケルマンこのかた数多くの優れた鑑識家が「メディチのヴィーナス」をもって女性美の範例と見做しているが、それを理想美とする根拠は薄弱である。そして「メディチのヴィーナス」はだだっ広い応接間の飾りものの域を出ないとクラークはみなしている(クラーク、1971年[1980年版]、110頁~118頁)。
<「アルルのヴィーナス」>
ところで、「クニドスのヴィーナス」は、プラクシテレスの作になる唯一の有名なヴィーナスではなかった。プラクシテレスは、テスピアエの住民のためにも両脚が衣に包まれ胸乳を露わにした像「アルルのヴィーナス」(ルーヴル美術館)を作った。ルイ14世時代の彫刻家ジラルドンの補修前のブロンズ像を見ると、この像はひとつの優れた着想を具体化し、彫刻の主要課題のひとつを解決した。すなわち、トルソという完璧な造形的単位を紡錘状に先細りしてゆく支持脚の上に安定して載せなければならないという彫刻家の悩みの種となっていた問題を解決した。
プラクシテレスはただ脚に衣を巻きつけてトルソをむき出しにし、彫像の足場をきわめて堅固にすることに成功した。その結果、壺や柱や海豚といった支持体なしですまし、自由に両腕を演じさせることができるようになった。
ただ、「アルルのヴィーナス」がありきたりに見えるのは、その無表情な表面もさることながら、どちらかと言えば、動きの乏しい構成のせいであるようだ。とりわけ、身体の軸線が像の活力を削ぎとるほど平行に近い。
そして、この点では、後の彫刻家たちがプラクシテレスの創意をさらに発展させてゆくことができた。すでに紀元前4世紀に、膝で支えたマルスの楯を鏡にしてヴィーナスが自分の姿を眺めるというモティーフにこの創意が応用され、像ははっきり目立つ上昇的な対角線を基本にして組み立てられることとなった。ナポリにある「カプアのヴィーナス」がその主要なレプリカである(クラーク、1971年[1980年版]、118頁~120頁)。
<ケネス・クラークによる「うずくまるヴィーナス」への言及>
あるいは、女性裸体像から一例を引くなら、カタログや教科書ではドイダルソス(ママ)の作とされているが確実なところ前四世紀初頭の作と思われるあの≪うずくまるヴィーナス≫[281図]の像がある。洋梨のような彼女の身体の造形的な豊かさは、ティツィアーノ、ルーベンス、ルノワールなど、芸術に豊麗な実りをもたらした太陽たちをはじめとして、今日に至るまで、多くの人びとを喜ばせて来た。そして、この場合には、その理由を見出すのは容易である。というのは、それは豊かな実りの完璧な象徴であり、あたかも木になっている実のように大地の牽引力を感じながら、しかもその構造のなかに、官能的エネルギーの泉があることをも隠そうとしないからである。しかし、女性裸体像のその他のポーズの場合、われわれがそれに感ずる完全さは、ほとんど説明し得ない。例えば、そのような作品の一例として、ルネッサンス期の人びとをあれほどまで魅了した≪ポリクレトの寝台≫の名で知られる(今は失われた)ヘレニスティック期浮彫のあのプシュケーの像の輪郭線を挙げることができる。ちょうど、お祭の時にふと耳にした民謡が、ひとたび意識されるとつぎつぎと多くの作曲家たちの主題の素材として使われるように、このプシュケーの輪郭線はラファエルロ、ミケランジェロ、ティツィアーノ、プーサンなどの傑作に姿を現わし、歌のメロディーが最初の言葉から離れて独立した曲に育って行くように、われわれはそれによって裸体像が独立した存在を獲得するようになったと感じさせられる。
(クラーク、1971年[1980年版]、436頁~438頁)。
<「ミロのヴィーナス」>
このモティーフのもつ可能性は、それから200年ほどの間にさらに発展することになる。「カプアのヴィーナス」は像全体が浮彫のようにプロフィルで捉えられていたが、紀元前100年ごろ、ある天才的な彫刻家の手でこれが奥行きの次元で再構成されることになった。こうして生まれたのが、古代ギリシャの最後の偉大な作品である「ミロのヴィーナス」とクラーク氏は理解している。
1820年に発見されてから数年と経たぬ間で、「ミロのヴィーナス」はかつて「メディチのヴィーナス」が占めていた中枢的な地位を掌握していた。そして美術鑑賞家や考古学者の愛顧を失った今日でもなお、「ミロのヴィーナス」は「美」のシンボルとして確固たる地位を占めている(クラーク、1971年[1980年版]、118頁~120頁)。
<ケネス・クラークによる「ミロのヴィーナス」への言及>
シャトーブリアンとロダンが誤解していたのも、彼らの生きた時代を想えば、無理もない。クラークも、フルトヴェングラーが「ミロのヴィーナス」の制作年代を引き下げたことを評価して、次のように述べている。
「 ≪ミロのヴィーナス≫の名声の一端は、偶然の賜物であった。一八九三年にフルトヴェングラーがそれまでよりも厳密な分析を加えるまで、彼女は紀元前五世紀の原作と信じられており、首つきのさまという利点までそなえた、この偉大な世紀からの唯一の婦人単身立像と信じられていた。こうして彼女は熱烈な党派心のもとで、「エルギン・マーブルズ」が至高の芸術に祭り上げられた時代にめぐり合わせ、得をしたのである。「エルギン・マーブルズ」は堂々として自然であるため、また気取りや作為が見られないため、それまで称讃されてきたが、≪ミロのヴィーナス≫を冷たくとりすました古典主義の寵姫たちと対比させるときにも、同じ頌辞が使われたのである。古代の他の裸体のヴィーナス像に比べれば、彼女は遥かに頑健で多産型であるかもしれない。≪メディチのヴィーナス≫が温室を想わせるとすれば、≪ミロのヴィーナス≫は麦畑に立つ楡の木を想わせる。しかしながら、実のところ、彼女が古代の作品を通じて最も複雑かつ技巧的な産物のひとつであることを考慮に入れるなら、自然らしさを楯に弁護することにはある種のアイロニーがひそんでいる。この像の作者は、当時のさまざまな創意工夫を活用したばかりでなく、前五世紀作品の効果をも与えようと意識的に試みた。比例ひとつを取り上げただけでも、それを証明することができよう。つまりアルルやカプアのヴィーナスでは両乳間の距離が乳から臍までの距離よりも著しく短いのに対し、ミロのヴィーナスでは古い時代の等距離の形式が回復されている。彼女の身体の各面(プラン)は非常に広く穏やかであるため、一見するとひとつの面が次の面に移るときに通過する角が幾つあるのかわからない。建築に譬えて言えば、彼女は古典的な効果をもったバロック的構造物である。十九世紀に彼女がヘンデルの≪メサイア≫やレオナルド・ダ・ヴィンチの≪最後の晩餐≫と同じ美の範疇に加えられた理由も、この効果に求められよう。フェイディアスの英雄時代の作品ではなく、しかも「感受性」という近代的特質を幾分欠いているらしいことを承知されている今日でも、依然として彼女は最も輝かしい人間の肉体的理想のひとつであることに変りはなく、また芸術作品はそれが属する時代を表現せねばならぬという現代批評の合言葉に対する最も高尚な反駁となっている。」
(クラーク、1971年[1980年版]、120頁~122頁)。
このクラークの「ミロのヴィーナス」に関する叙述のポイントを箇条書きにして、まとめてみよう。
・「ミロのヴィーナス」の名声の一端は、偶然の賜物
・1893年のフルトヴェングラーの分析まで、「ミロのヴィーナス」は紀元前5世紀の原作と信じられていた
・「ミロのヴィーナス」は「エルギン・マーブルズ」とみなされていた時代にめぐり合わせ、得をした
・「ミロのヴィーナス」は、他のヴィーナス像に比べ、頑健で多産型
・「メディチのヴィーナス」が温室を想わせるとすれば、「ミロのヴィーナス」は麦畑に立つ楡の木を想わせる
・「ミロのヴィーナス」は、古代の作品を通じて最も複雑かつ技巧的な産物のひとつ
・「ミロのヴィーナス」像の作者は、前5世紀作品の効果をも与えようと試みた。例えば、比例で、古い時代の等距離の形式が回復されている(両乳間、乳から臍までの距離)
・建築に譬えて言えば、古典的な効果をもったバロック的構造物
・「ミロのヴィーナス」は、今日でも最も輝かしい人間の肉体的理想のひとつ
「ミロのヴィーナス」の作られたヘレニズム時代>
「ミロのヴィーナス」の作られた後期ヘレニズム時代について、クラークは次のように述べている。
「 ≪ミロのヴィーナス≫の生成は、後期ヘレニスティックの芸術家が創造の問題にどう取り組んで行ったかを明かしてくれる。彼らは偉大な発明の才に恵まれていなかったので、モティーフの組み合わせと発展に技巧の限りを尽した。芸術史を通観すればこれは異常なことでも不真面目なことでもない。例えば中国やエジプトではこれが通則であったし、ルネッサンス以後のヨーロッパ芸術の極度なめまぐるしさをそのまま優越のしるしと受け取ることはできないのである。ところで、こと女性裸体像に関して、およそ永続的な価値をもつ形態構成上の創意のうち、元をただせば紀元前四世紀に発見されなかったものがまずひとつとしてなかったとは、刮目に値する事実である。「うずくまるヴィーナス」という美しいモティーフがその一例で、後にルーベンスや十八世紀のフランス芸術家は大いにこれを利用した。通例、碑文を根拠としてビチニア出身のドイダルソス(ママ)という後期ヘレニスティックの彫刻家がこれを創始したと言われ、たしかに彼はこのポーズで彫像を製作した。しかしながらこのモティーフは画家カミロスが絵付けをした前四世紀のアンフォラに現われていて、その人像はスコパスの彫刻から想を得ているようである。とすれば「うずくまるヴィーナス」の見事な構成もやはり、あの偉大な造形的エネルギーの時代に起源を遡る筈である。」
(クラーク、1971年[1980年版]、123頁)。
クラークは、「ミロのヴィーナス」の制作年代に関して、いち早くフルトヴェングラー説およびシャルボノー説に注目したので(120頁、482頁原註41)、後期ヘレニスティック時代とみていたことが、上記の文章よりわかる。
そして上記のように、「≪ミロのヴィーナス≫の生成は、後期ヘレニスティックの芸術家が創造の問題にどう取り組んで行ったかを明かしてくれる。彼らは偉大な発明の才に恵まれていなかったので、モティーフの組み合わせと発展に技巧の限りを尽した。」という。つまり「ミロのヴィーナス」などを制作した後期ヘレニスティックの芸術家たちは、偉大な発明の才に恵まれていなかったと捉え、その才能のないのをモティーフの組み合わせに意を注いだとする。
クラークのこの記述からもわかるように、後期ヘレニスティック時代の芸術家や彫刻について、さほど評価していない。これはこの時期を積極的に評価しようとするハヴロックとは対照的である。
そして、クラークは、こと女性裸体像に関して、紀元前4世紀という時代は形態構成上の創意の源を作り出した点で高く評価している。その一例として、「うずくまるヴィーナス」という美しいモティーフを挙げている。クラークによれば、このモティーフは画家カミロスが絵付けをした紀元前4世紀のアンフォラに現われていて、その人像はスコパスの彫刻から想を得ているとみている。そして、クラークは、「うずくまるヴィーナス」の見事な構成も、「あの偉大な造形的エネルギーの時代」=紀元前4世紀にその起源を遡っている。
ただ、通説では、碑文を根拠としてビテュニア出身のドイダルサスという後期ヘレニスティックの彫刻家がこれを創始したとされる(ハヴロックは、平面的な絵画的表現と、立体彫刻、三次元の構想とを区別して、「うずくまるヴィーナス(アフロディテ)」を後期ヘレニズム期の作とみている。ただし、ドイダルサス説には否定的である。ハヴロック、2002年、95頁~98頁参照のこと)。
【補足 クラークのヴィーナス理解】
後期古代の女性裸体像は、数が少ない上に、大部分が粗野であり、実質的に芸術の主題であることをやめていた。
クラークによれば、紀元2世紀以後の作とされる女性の単身裸体像はただの一点もないという。ヴィーナスは宗教から娯楽に、娯楽から装飾へと変転し、次いで消滅してしまった。
そして、再びヴィーナスが世に姿を現わしたとき、建物も思考体系も道徳も、姿を変えていたし、女体も変貌を遂げていた。
エヴァの肉体に、人類最初の不幸な母にふさわしい性格とゴシック装飾の尖頭アーチ的リズムと結合するため、新しい約束的手法(コンヴェンション)が発明されていた。イタリア・ルネサンスの初期の段階における芸術家たちの作品にも、こうしたコンヴェンションの意識が認められる。
14世紀半ば、1357年、シエナで、リュシッポスの署名入りの彫像(海豚に支えられていたというから、ヴィーナス像と推測されている)が発掘され、町の中央に据えられたが、異教の偶像崇拝にあたるとして、国家の布告によって取り外され、敵に悪運をもたらすようにと、フィレンツェの領内に埋められた。この話を彫刻家ギベルティは伝えている(この決定は、像が裸体のせいではなく、異教の偶像だったためであることにクラークは注意を促している)。
また、シエナからヴィーナスが追放されるより50年も前に、シエナ大聖堂の建築家ジョヴァンニ・ピサーノは、「貞潔のヴィーナス」(Venus Pudica)をほとんどそっくりに写した裸像をピサ大聖堂の説教壇上に「基本道徳像」のひとりとして含め入れていた。今日「節制」か「貞潔」の寓意像とみなさており、1300年から1310年の間の作品である(クラーク、1971年[1980年版]、127頁~128頁)。
ケネス・クラーク『ザ・ヌード』 (ちくま学芸文庫)はこちらから












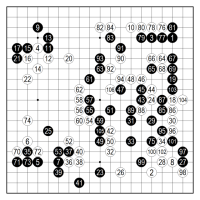
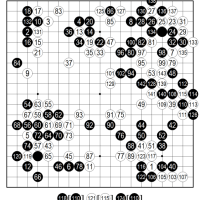
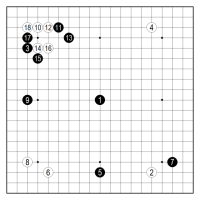
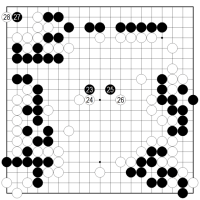
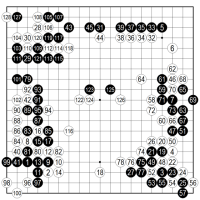
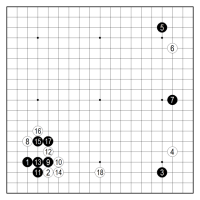
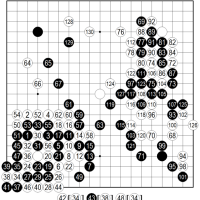
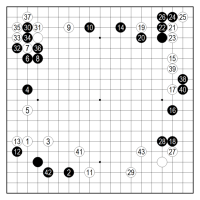
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます