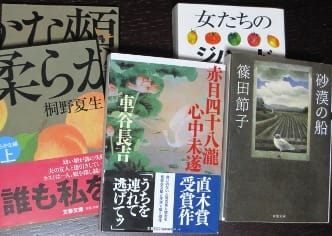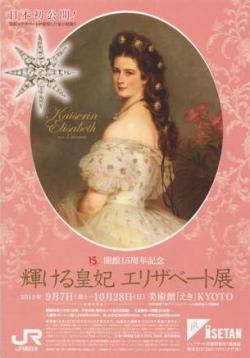実は、なんで日本人?と、見もしなかったパンフレット。開いてみたら、「←9/25 このキャストです」と丁寧に付箋が貼られていました。ウイーン版のキャストはガラ・コンサートのことだったのです。(トリプルキャストで、マテ・カマラスがトート役の日もありますが)
どこでどう思い込み違いをしたのやら!?ウイーン版で観劇だとばかり。開演するまで、思い込みは続きました。幕が上がり、エリザベートを暗殺するルキーニ役の高島政宏の登場に、!!!??? えっ?えっ?
暗闇の中で、私だけが舞台を見ながら違うことを考えていたのでしょう。そう、確かに劇場入り口には日本人のキャスティングで写真が…。「本日のキャスト」と小さな案内も目につくところに示されていました。この時に気付かなければおかしい。変だったのは、山口祐一郎の声だけではなかったのだ。
さらに、開場を待つ間にチケット代を清算し、渡されたチケットは3階! えーっ!! なんでこんな高くて遠いところから??? この席いくら!? と心ひそかに。

何もかもお任せでチケット予約をしてもらって、文句など言えようはずがありません。
「今度は本場だからね」と念を押されて、来月は「ロミオとジュリエット」です。チケット代の大半はこちらの舞台に注ぎ込まれたというわけです。彼女なりの配慮かもしれません、「高いからね」と。
【演劇界も不景気の風が吹いてなかなかチケットが売れない状況みたいです。閉鎖的な世の中だからこそいい舞台を見て元気になりたいですね~。いい舞台を支えるのは、確かな観客の目かもしれません。演劇界も「だからこそいい作品」しか興業しなくなってきています。選んで足を運ぶ私たちの期待を裏切らない作品にワクワク~。
今年後半、最も輝かしい作品の一つがフランス版「ロミオとジュリエット」だと信じてます。お楽しみに!! カレンダーには花丸マークをよろしくね。】
こんな友人の言葉をいただきながら、とんでもない勘違いの私。「確かな観客の目」などどこへやら、申し訳ないような…です。
昨日は山口祐一郎、子役の加藤清史郎クン、高島政宏さんたちで観てきました。三階という高所から、見下ろす役者の表情はわかりませんでした。それでも、しっかりおしゃべりして、時々観劇仲間として3人が顔をそろえられることを喜ばないわけにはいきません。