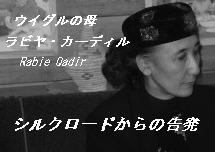(一昨日のつづき)
<iframe align="left" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=truthofsilkro-22&o=9&p=8&l=as1&asins=406280705X&fc1=000000&IS2=1&lt1=_blank&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" frameborder="0" scrolling="no" style="WIDTH: 120px; HEIGHT: 240px"> </iframe>「新疆」地区のトルコ系オアシス農民を中心としたイスラム教徒住民が自身の呼称を総称するのに1921年にソ連、アルマアタで「ウイグル」を採用したといわれている。それにどのくらいウイグル人自身がかかわったのかはまだ議論中であるという。しかし、そのソビエトにも勧められた民族呼称は当時の新疆省督弁、盛世才にも採用されることとなり、現在にいたっている。
森安先生が「偽」と言い切ってしまうのは、現在のギリシャがマケドニアの呼称を認めないと主張していることを連想してしまうが、古代に栄えた国家、民族等を拡大解釈したり、復活させたりすることは「タイ人」と「タイ族」や「タタール人」と「タタルスタン共和国」にもみられることであり私は問題があるとは思わない。たしかに古代ウイグルと現在のウイグル族をイコールとすることは歴史学的には疑問であるとしても、(現代)ウイグル人側から見ると誇りある民族集団が復活することに、また中国政府側からみれば中国北部遊牧地帯からの移住者たちということで大いに意義があったと思われるのである。
杉山正明氏は「ウイグル」について同じ趣旨で説明しているが、言葉は柔らかである。
http://blog.goo.ne.jp/kokkok2014/d/20050902
つまり、古代ウイグル学者森安先生は現代ウイグルをほとんど見据えていない。これは批判されることでなく、イスラム化以前の中央ユーラシア地域の歴史を語る本書では仕方がないことなのであるが。
現代ウイグルに対して関心が薄いわけはひとつ想像できる理由がある。
それは「シルクロード史観論争」を第2章で大きく取り上げていることである。
シルクロード史観論争についてはWikiやDivaneさんの以前のブログを参照していただければわかる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89
http://33365234.at.webry.info/200501/article_6.html
このシルクロード史観論争で脱シルクロード派に大反撃、森安先生は止めを刺したと思っていらっしゃるようで間野英二先生派の学者先生方にはぜひ、反論がほしい。大体のところを言えばソグド人、(古代)ウイグル人などはオアシス農業だけでなく通商業に多く従事していた、これは文献資料からも実証できる。シルクロードを単に東西、南北の関係で見るのではなくネットワークとしてみるべきである。等々。また、この論争で森安教授はイスラームの役割について脱シルクロード史観派は重要性を過剰に重んじているとしているのである。
そういうところが、現代ウイグルに対しての冷ややかさの理由と思われる。
しかしながら、北廷争奪戦やウイグル、チベット、唐三国会盟の話は現代に応用できそうでとても興味深い。こう言う歴史の新学説についてはとても興味深く、シルクロードに興味のある人はぜひともとっていただきたいと思う。
なお、森安教授は「あとがきに代えて」において今上陛下が「訪韓時に」朝鮮の祖先との関係を宣言された、と書いている、これは「百済の武寧王とゆかり」の談話のことであろうと思われるが、いまの天皇陛下は未だ韓国訪問は行っていない。それを指摘しておく。
ラビア・カーディル紹介サイト↓
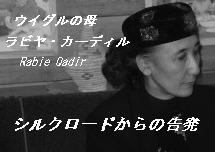
このブログに興味をいただけたらblogランキングへクリックお願いします。