|
第21章
今日も精神病患者が一人、ギャッヴィの発明したカミソリ式絞死刑台の餌食となり、両目に特大安全カミソリの刃を突き立てた生首が受け皿の上にキチンとキウィのデザートの様に置かれていました。 執行人でもあるギャッヴィの仕事熱心のおかげです。
又、患者をめっけてきたでぇ~。 こいつ、この寒いのに旅行中なんだとさ。 それに、この年で。」
ちょうどいい。今、こいつ(カミソリ式絞死刑台)がワシに腹減ったと催促しておってなぁ。 分身のワシ(ドッペルゲンシュタイナー)を喰わしてやろうかと思っていただよ。 ハハ。」
最上部にキラキラ輝く黒塗りの安全カミソリが、その不気味な箱の内側に向かってたくさん並んでいました。
寒かろぅ、早くこっち来てあったまんしゃい、茶でも飲んだらよかぁ。」
もちろんギャッヴィも瞳をエメラルドの様に光らせて。
キーホーはギャッヴィと市長さんと旅人が、のっそりと湯気のように現れると、彼らに向かって尋ねてみました。
キーホーが何を言って何をしても、三人は何も見えず何も聞こえない、という態度をとり始めたのです。
そして三人が直立不動のまま茶をすすり、話を始めるのを黙って聞いていました。
そこへ、うつろな目を光らせている死刑執行人のギャッヴィが話に加わりました。
いくらあなたが気狂いだからといっても、こちらだって慈悲の用意ぐらいはあるんだよ。 話によっちゃ情状酌量の余地もありうる。 ま、死刑はまぬがれんがね。ふふ。 死肉を赤犬に喰わしてやる事くらいは、してあげるよ。」
ギャッヴィは熱湯でジュージューと赤らんでいく顔を奇妙に歪ませ、フフフフフと笑って舌なめずりをしました。 市長さんは自ら、チンチンいっているお茶を頭からぶっかけて、湯気を立ち上らせながら、アッカンベーをしました。
もちろんですよ、キーホーは、もう心底震えちゃっていましたね。
KIPPLE |
|
第20章 音楽室三号の室内に入ったキーホーは、回りを灌木で囲われて何万年も前から埃が溜まっているような広場の真ん中に立っているのに気づきました。 ここも音楽室ではありませんでした。 しかし、キーホーが今し方入ってきた板戸の出口を振り返って探しましたところ何も無いのです。 出口は消え失せてしまったのです。
無 
↓ 出口は無し。仕方がないのでキーホーは広場の片隅に薄汚れた外套(マッキントッシュ)の様に建っている木造の納屋に入っていきました。 狭い納屋の奥にランプの燈し火が見えたのです。 キーホーは、ぼんやりとしてランプの燈された丸い傷だらけの机に腰掛けました。 そして待ちました。 だって、そこは待ち合い室だったのですから。 納屋の開かれた扉には、こう書かれていました。
その時のキーホーを軽く扱う眼差し。 過ぎた後、キーホーを襲った激しい羞恥。 キーホーは二度と、あんなミスは犯すまい、うんざりだと思って、死人の様に生きようと思いました。 誰もキーホーに目を向けさせない全く生気の無い、物の様な人間になろうとしました。 しかし、失敗でした。 だってキーホーは美男子だったんですもの。 比類無き・・・・・・・・・・・・・。
KIPPLE |
|
第19章
キーホーは、いつの間にか、さっきの一号室の板戸の前に立って、さっきと同じ様に室内の薄暗い円形劇場で、白い仮面を被った役者たちが繰り広げる奇妙なバカバカしい演劇を覗いているのでした。
彼は、竜巻のように斜めに回転しながら板戸口に向かって、すっ飛んで来ました。 そして、キーホーの顔に板戸口を境にぴったりと、笑い顔をくっつけますと、その役者は黄金色のフル・スペクトルを内部から輝かせて、言葉をこぼしました。 ご飯粒のようにです。 彼の仮面の奥で光る眼は、黒曜石のように重なってしんみりとしています。 笑い仮面がしゃべります。 パチッ。
私は若くなりたい。若くなりたい。若くなりたいんだ! 若くなって一杯冒険がしたい。パッションだ!情熱的な恋がしたい。 ああ、私の肉はもう若くないのだ。 肉体が老朽化すれば心も老朽化すると思うか!?。否! 貪欲な心は余計に若さを欲するのだ。」
だってキーホーは二号室の板戸を開けたはずでしたのに、一号室にはもう用はありませんし、それにその笑い仮面の役者の乾燥して今にも吹き飛びそうな悲鳴にもウンザリしてしまったのです。 ところが、どうしたことか、板戸は笑い仮面にぶち当たり、その白い陶器のような表面に無数の亀裂を走らせてしまいました。 笑い仮面の役者は、狼のように遠吠えをすると、体を真っ直ぐにしたまま背後に吸い込まれるように倒れてしまいました。
本物の顔は、おかしな皺(しわ)で一杯になっていました。 その皺は、まるでたくさんのデタラメな文字を何重にも重ねて書きなぐったようでした。
その間に年老いた笑い仮面の役者は死んでしまったようです。 すでに死後硬直が始まったらしく、ぎっしりと皮膚に刻まれていた様々な文字が空中にスポンスポンと飛び出していたからです。 文字は宙を羽の様に舞い、円形ドームを真っ白に包みました。
そして再び、キーホーは二号室の板戸の前に立ち、今度こそはと、注意深く、ゆっくりと二号室の板戸を開いたのです。
二号室の板戸を今、確かに開いたのですが、室内はやっぱり一号室だったのです。 まだ、文字たちが花びらみたいに舞っていました。
すると、やはりキーホーは二号室ではなく一号室の板戸の前に立っているのでありました。
彼はスタスタと二号室の前を通り過ぎると、三号室の板戸を開いたのです。 そして二号室にアッカンベーをすると、するんと三号室の中に体を滑り込ませていきました。 その後、二号室はガラス窓や板戸や壁をぷくっとふくらませて、知らんぷりされた事に腹を立てているのでした。
 音楽室二号が内部で核爆弾を爆発させ、自殺を遂げたのです。 理由は謎に包まれたままでした。 その後、ずっと。
デジャヴかな? 以前どこかで同じように注釈を入れたような気がする。 あなたは、そんな気はしませんか? どこかで・・ループしている。 そんな・・気が・・・。
KIPPLE |
|
第18章
何故ならば、そこは音楽室ではなく、円形劇場だったからです。 ずっと遠く、漆黒の闇の奥から青白い照明ライトが、舞台の上の白い仮面をガブッた役者たちを照らしていました。
KIPPLE |
|
第17章 向こうから今度は音楽教師が地球儀を、肩に担いでやってきました。 キーホーは喜び、ぴょんとはねると聞いてみました。 「あの。音楽室は?。」 音楽教師は、むっとした表情で黙って天井を指差しました。 キーホーは深々と御辞儀をし、チンチロリンと御礼を言うと、その音楽教師は、小さく頷いて、地球儀を軽やかに地平線の向こうまで蹴飛ばすと、爪先立ちになってクルクル舞いながら、つむじ風の様に去っていきました。
さっそく、キーホーはエスカレーターを逆さに駆け上がって上の階へ行きますと、音楽室を探し始めました。
あった。 ありました。
こちらから順番に、戸口に白いプラスティックボードに黒いマジックで、
KIPPLE |
||||||||||
|
第16章
 おじさんは黄色いガムテープを巻き付けた杖を振り回しながら一度、くしゃみをすると完全に消えてしまいました。  その後、おじさんは二度と、復元されませんでした。
キーホーは床で死んでるチョークを拾ってガラス戸に投げつけてやりました。 そうすると、割れたガラスの中から、涎をあやとりの箒のように垂らした猛犬が飛び出してきて、爽やかに笑うと、鳥の様に手足をハバタかせて大空へ滑空していきました。 目と口を大きく開いて見ていましたら後ろから数億のクラクション・ノイズの波が押し寄せてきましたのでキーホーは仕方なく前進する事にしました。 しかし、なかなか抜けられません。 犬が羨ましく思われ、誰か自分のザラ味のガラス戸を割ってくれはしないだろうかと、チラと考えましたが、ああ、なんて非現実的で可能性の無い、他愛無い、バカな事をと、又、女や猫に言われそうで、すぐに頭から、振り散らせて、正常にして、のろのろと再び動き始めたのです。
KIPPLE |
|
第15章  プチッ!。さて、キーホーは??。 ↓こっちよ!。 キーホーは、 『列車に乗って涼しい風を受けているうちに刻々と、林檎を囓り、子供を憎み、足を痺れさせ、隣人を殺したく思い、頭を抱え、皿を叩き割る映像を思い浮かべ、大きな口を開いて身体中の空気を吐き出し、外の世界を全部、自分から追放しようとしたけど涼しい風が吹き付けてきて、思わず、爽やかになってしまい、外を見ると大っきな山と畑が、延々とあって、何だか気抜けして、それチャンスだとばかり、煙草に火を点け煙を力無く吹き出し、自分対世界の人々を考えると再び皿が浮かび、涼しい風を発する窓に向かって飛び込んだら、引っ張られる様に列車から身体は引き離され、川原の尖った石にあたって粉微塵に砕けてしまいまして、その時、走り去る列車の窓に、ライターの火を凝視しているリリカルな少女の情景が映し出されまして、少女のまわりは薄闇でしたので、ランプが下がってるといいナ、と思いましたけど、自分の破片には早くも、さわ蟹が群がってまいりました。』 のを、どこだかわからない木造りの校舎の四階の窓から眺めていたのです。 ほら、蟹→
キーホーは、ミシリミシリと教室の床板を踏みしめながら戸口に向かって歩き出しました。
KIPPLE |
|
第14章 キーホーは呆れ果ててしまいました。 なんという、いい加減な小説でしょう。 キーホーは、かぁっ!として再びガリ版本から目を離し、小説家を税理士の忘れていったダンビラで切り刻んでやろうとしたところ、すでに小説家は、この前の駅で、声と共に降りてしまっていた事に気づくのでした。
キーホーは、おごそかに立ち上がり、 「ざけんじゃねぇよ!」 と、つぶやきますと、窓から本を投げ捨てました。 本は“じゃ、またね”と言ってパタパタと羽ばたいて森の中に、すっ飛んで行きました。
乃ち、目玉と口の位置が入れ替わる様な、ちょっとした崩壊が始まっていたようです。 
KIPPLE |
|
第13章 ほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほ
|
|
第12.3章 列車が止まり、あたりが一斉にばたつき始めましたので、キーホーがガリ版刷りから顔を上げますと、さっきの親戚を名乗る小説家は、すでに姿を消し、青いビロード張りの座席には小さな声が影のように這っているではありませんか。 声は波が月光にゆらめく様にするすると窓ガラスの底からプラットフォームに降りてゆきました。 こうです。 ど こ か で 偶 然 に 会 え る と い い ね 、 き っ と 会 え る さ 、 じ ゃ ぁ ね ・ ・ ・ ・
三十秒ほど過ぎると列車の中には、まるで砂浜に打ち上げられた巻き貝の内側にいる様な、吸い込まれる様な、透んだ静けさが立ちこめていました。 キーホーが再び、ガリ版刷りの小説に目を落とすと、列車は、前進しているのか?後退しているのか?それとも、動いているのか?動いていないのか?も、わからないくらいに、ソロソロゆっくりと揺れ始めました。
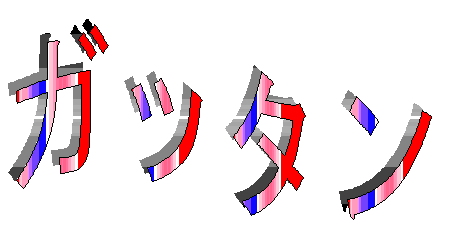
超宇宙的な、その美青年に引きつられて洞穴に入って行った僕は、この鍾乳洞の構造が極端に、上昇志向と下降志向のアンヴィヴァレンツな心理作用を与える事に気づいた。 登ったかと思うと、側面には、ぽっかりと深い口を開けた小さな穴が無数に下降している。 その中から針の先の様な光がチラチラと、と、とっ、とっとっとっと。 さぁて、これから奇型的美男子は、主人公の僕に、実は、この世、この宇宙は、卵の殻の表面の様なもので裏面の死界とピッタリ重なっているという事を説明し、裏側に迷い込んでしまったプロクシマ星系からやってきた宇宙一の美女、シャングリ星のリュィッテを助け出して行くのであるが、詳しくは、私の小説「クルベムゲイル・サガ」断片五十一の長編小説「遙か彼方のラブピース・ターボ」に描かれている。 続きと、断片五十一を読みたければ、この小説にノーベル塵芥川賞を与えたまえ。 与えるまで、この物語はここまでしか公開しない。 地下室の巨大な押入れの奥深くに眠らせる。 さよなら。
|














