日頃感じたこと、思ったこと事などを書きとめておきます。
野のアザミ
天草:吹割岩(ふきわりいわ)
2018-08-17 / 自然

天草ジオパークの一端に触れてみることにした。宮崎からは近くて遠い。九州自動車道を降りるまではいいが、それからが大変だ。天草への国道は込み合う。特に今回はお盆の時期だった。
一番最初に目指したのは、天草の玄関口・大矢野島にある吹割岩。大矢野島の北半分は約300万年前に活動した火山群だ。
だが、行くのに迷った。国道は、案の定、帰省客と観光客で車が数珠つなぎ。ガイドブックとナビで海岸の形を見比べながら、国道を右折したが、少し行き過ぎたため、数kmも過ぎた海辺をウロウロするはめに。再びガイドブックとナビが示す海岸の形を見比べ直し、どうにか目的地近くの海岸集落へ。ナビは地名を示してくれなかったが、海岸の形から場所を確信。集落を抜けたヘアピンカーブの先に、案内標識を見つけた。
駐車場はかなり広かったが、車は一台も姿無し。木陰に車を止めて、そこから少し遊歩道を下ると、暖かな海岸近くでよく見かける大きな暖竹の群落が迎えてくれた。遊歩道の下からは子供たちのにぎやかな声が聞こえ、向いの緑の山腹の中には別荘風の家が立ち並んでいた。目指す吹割岩はすぐのその先だったが、それまでとは全く違う雰囲気。草は伸び、最近はほとんど人が訪れていない様子。しかし、見上げれば、大岩をまっ二つに断ち切ったような崖が左右にからせまり、密議の場所にはもってこいのような広い空間が広がっていた。高さが15mほどはあるかと思える崖を写真におさめながら奥へと足を進めたが、何となく違う雰囲気も・・・。後で、入口にある説明板を読み直してみて納得。弘法大師の伝説を秘めた霊場でもあったのだ。奥にあるはずの洞窟は、柵がしてあり立入禁止。少し残念だが、目的の切り立つ吹割岩を見ることができただけでも良しとしたい。
下記は駐車場脇説明板に書かれていた由来。ただ、伝承の洞窟は、地下からマグマが上昇してドームをつくった後、冷えた時にできた割れ目と考えられているから、原城まで続いていたとの伝えは、単なる伝承のようだ。
あまり訪れる人が少ないようなので、一人で行くと怖いかも・・・。
天草四郎の洞窟(吹割岩)の由来
天草・島原の戦いの天草における蜂起の発端地は大矢野であり、総帥天草四郎時貞はここ大矢野町で小西牢人の大矢野松右衛門、千束善左衛門、大江源右衛門、森宗意軒、山善右衛門らと謀議をかさねていたが、キリシタン探索の目が厳しくなるとこの洞窟を絶好の隠場所として密議をこらしたという。
また万一にそなえて、この洞窟を島原の原城まで掘りぬかせていたともいわれ、原城落城のおり天草四郎は死んだことになっているが、実はこのトンネルを通ってこの洞窟にのがれて来たとの一説もある。
窟には大矢野八十八か所のひとつ、番外奥の院があり弘法大師の伝説を秘めた霊場としても多くの人の信仰をあつめている。
(昭和60年12月4日熊商大(現:熊本学園大学)探検部が洞内を探検調査したが落石等で埋まり奥を極めることができなかった)
熊本県(観)
天草・島原の戦いの天草における蜂起の発端地は大矢野であり、総帥天草四郎時貞はここ大矢野町で小西牢人の大矢野松右衛門、千束善左衛門、大江源右衛門、森宗意軒、山善右衛門らと謀議をかさねていたが、キリシタン探索の目が厳しくなるとこの洞窟を絶好の隠場所として密議をこらしたという。
また万一にそなえて、この洞窟を島原の原城まで掘りぬかせていたともいわれ、原城落城のおり天草四郎は死んだことになっているが、実はこのトンネルを通ってこの洞窟にのがれて来たとの一説もある。
窟には大矢野八十八か所のひとつ、番外奥の院があり弘法大師の伝説を秘めた霊場としても多くの人の信仰をあつめている。
(昭和60年12月4日熊商大(現:熊本学園大学)探検部が洞内を探検調査したが落石等で埋まり奥を極めることができなかった)
熊本県(観)



コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
コシアキトンボ
2018-08-09 / 自然



散歩中、ふと、足もとにトンボが落ちているのを見つけた。拾い上げてみると微かに動いた。瀕死の状態だ。たまに見かけることもあるトンボだ。調べてみると、背中に白い模様が特徴のコシアキトンボだ。これはメス。名前の由来は、腹部の白い部分が空いているように見えるからという。漢字では「腰空蜻蛉」だ。
瀕死の状態だから、道ばたの大きな葉っぱに乗せてやっても、じっとしたまま。こんな姿で葉っぱにとまっているトンボは見たことがないと思い、軍手にとまらせても、じっとしたまま。はて、どうしたことか・・・。
最初に見つけたのは、黒いアスファルト道路の上だ。時おり車も通るので、轢かれてしまえばそれまでだ。それでは忍びないので、最後だけでもと思い、トンボがよくとまっている姿を思いながら高く伸びた草にとまらせた。三枚目の写真は、最後の力を振絞り高く伸びた茎にしがみつき、ゆらゆらと揺れるトンボの姿だ。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
コミスジ
2018-08-08 / 自然

なかなかとまってくれない。ひらひらと舞いながら葉っぱから葉っぱへ。写真を撮ろうとするとまたひらり。1、2分そういうことをくり返しながら、こちらの希望を分かってくれたのか、翅を広げて「ハイどうぞ写真を撮って下さい!」と言うようにじっとしていたので、はいパチり。
たまに見かけるチョウではあるが、意識して写真におさめたのは初めて。調べてみると、コミスジ。小さなチョウで三本の白い線があるからこの名があるのだろう。漢字で書けば「小三條」だ。図鑑などには、クズのある低い山ならどこででも見ることができるとある。そういえば、近くの土手からは、散歩道をふさぐようにクズが蔓を伸ばしていた。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
ネズミモチとアオバセセリ
2018-06-27 / 自然

ネズミモチが花盛りだ。このネズミモチ、ギャラリー野の苑を開設して間もない頃、竹林から移植したものだ。30cmくらいのものだっただろうか、竹林の一角に水が湧く所があり、そのすぐ脇の日当りの悪い所に生えていたものだ。移植した所は、それまでと全く違う日当りのいい場所。そのためか、当初は育ちが悪くなかなか伸びてくれなかった。しかし、年を重ねるほどに、わが地を得たりとばかりに枝を伸ばし始め、ぐんぐんと成長してきた。
ネズミモチはどこでもありふれた木だが、落葉樹が多いギャラリーのまわりでは、ツバキ等とともに数少ない常緑広葉の照葉樹だ。ネズミモチの実は、色も大きさもネズミの糞に良く似ている。そして葉っぱは、モチノキに似ている。名前は、そこから来ているようだ。ネズミの糞に似ている実は、漢方薬にも使われているみたいで、薬効は「五臓も心も安らかにし、あらゆる病気を取り除く」という。ちょっと試してみる価値ありそうだ・・・・。
そのネズミモチの花は白くて小さい。しかし、いっぱい花が付く。その花のまわりでは、真っ黒なオナガアゲハやキアゲハなど、大きなアゲハ科のチョウが風に乗って舞う。そんな中、白い花から花に懸命に蜜を求めるチョウが数匹。セセリ科の仲間では、唯一青い翅を持つアオバセセリだ。翅の後ろに濃いオレンジ色がある美しいチョウだ。以前から、このネズミモチに来ていたのかもしれないが、今年初めて気がついた。
※チョウの仲間の数え方は専門的には「頭」、ここでは日常に使う「匹」にしています。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
ツバメ
2018-06-15 / 自然

梅雨時の晴れ間は貴重だ。昨日は朝から曇りで夕方から雨。今朝は未明まで雨が降っていた。玄関を開けると庭は湿ったまま。それでも時間が経つ毎に太陽が顔をのぞかせ始め、10時ともなると庭は乾いていた。
青空を背景にした庭木は、一段と緑を増しきれいだ。庭を横切る電線には巣立ちを終えた子ツバメが4羽。子ツバメと言ってももうすぐ独り立ちそうな大きさだ。1羽はちょっと離れて毛繕い。盛んに羽を広げたり嘴を羽に突っ込んだりして、太陽の光をうれしそうに浴びている。そこへ、親ツバメがスーッと飛んできてエサを与える。チチチチッツ・・・・。親ツバメが飛んでくるたびに鳴き声をくり返す。毎年くり返される光景だ。
青空に流れる白い雲と電線のツバメをずっと見上げていると、一瞬クラクラしそうになるが、なんだかうれしい。それにしても梅雨時の青空は、いつもよりきれいに見える。
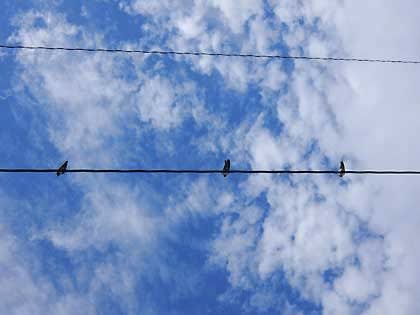

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
ニホンアマガエル
2018-06-06 / 自然

ズッキーニの葉っぱの上のニホンアマガエル
梅雨のしとしと雨が続く中で、今年はどこも梅が豊作。収穫されず、地面に落ちたままの梅も結構見かける。
畑ではズッキーニがぐんぐん成長し、毎朝大きな葉っぱの緑の中で、雄花と雌花の黄色が格別華やかだ。その葉っぱの上でじっとしているアマガエルを見つけた。単にアマガエルと思っていたが、正式な名は頭にニホンが付いている。ニホンアマガエルだ。捕まえようとするとピョンと飛んでまたじっとしている。カメラを構えるとまたピョン。
時々、風呂場にもいることがある。風呂ではなく風呂場。多分、窓を開けておいた時に入ってくるのだろうが、4、5日滞在するものもいる。こういうところでどうやって生きていくのだと思うが、小さなハエトリグモなどをエサにしているのか・・・?だとすれば、ハエトリグモもエサとするハエなどがいることになるが・・・。
ニホンアマガエル、環境によって色も変えるようだが、やはり緑色がいい。体の表面には毒があるそうだから、少し注意しなければならないが、それにしてもかわいい。パソコン画面の上に現れて、ポインタをおいかけたりするハエトリグモもかわいいが・・・。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
硫黄山(いおうやま)
2018-04-20 / 自然

韓国岳登山道より(2010.9)

硫黄山火口中心部(2014.7)

硫黄山案内板

硫黄山火口中心部(2014.7)

硫黄山案内板
霧島連山の硫黄山が4月19日噴火した。気象庁によれば江戸中期の1768年以来250年ぶりで、20日朝は熱水が土砂とともに吹き上がる現象も確認されたという。新燃岳のように高さ数千mというような噴煙ではないので、わが家からは見えない。しかし、新燃岳も活発な活動が続いているので今後が気にかかる。
この硫黄山、実は2014年7月に火口中心部に、足を踏み入れたことがある。企画するつもりだった「霧島ジオマーク」火山教室の下見だったが、それから間もなくして活動が活発になり、開催タイミングが合わず企画自体も延び延びになり今日に至っている。しかし、概要自体は頭に入れてきた。
当時撮影した説明板には次のようにあり、小さな火山ではあるが、改めて読むと自然の力・ダイナミックさを感じる。新燃岳や御鉢、あるいは桜島等含めて今後の推移を注視していきたい。
1768年(江戸時代)にできたと考えられている、霧島山の中では最も新しい火山です。山の高さは50m程度ですが、頂上には直径約100mの浅い火口があり、付近には最大10数mに達する火山弾があります。また、北側には溶岩じわや溶岩堤防など、溶岩流特有の地形が見られます。
1962年まで硫黄を採掘しており、当時の硫黄畑の石積みが火口内や周辺にたくさん残されています。
1962年まで硫黄を採掘しており、当時の硫黄畑の石積みが火口内や周辺にたくさん残されています。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
アカウミガメの守り神・小豆野次則さんのこと
2018-04-07 / 自然

帽子が小豆野さん
またひとり大切な人を亡くした。佐土原海岸のアカウミガメ調査第一人者だった小豆野次則さんが突然亡くなった。訃報を聞いたのは通夜の直前。あわてて駆けつけると、そこには海を背景にした小豆野さんの遺影。
佐土原海岸は、宮崎市の海岸のうち最も北寄りにある旧・佐土原町の海岸だ。地元ではさらに細かく、北より二ツ立(建)海岸、大炊田海岸、石崎(明神山)海岸と呼んでいる。地元言葉で書けば、「ふたったてんはま、おいだんはま、いしざきんはま」となる。その海岸のうち、小豆野さんが担当されていたのは石崎海岸だ。シーズン中は毎日の調査だ。朝、夜明け前のことだ。奥様と二人で出かけ、上陸や産卵を記録し、産卵していれば卵をふ化場に移しふ化を見届けられ、赤ちゃんガメを海に帰されていた。佐土原にとってなくてはならない人だった。
私は、その小豆野さんをガイド役として最近までアカウミガメ産卵観察会を行ってきた。観察場所は、一ツ瀬川と石崎川を挟んだ二ツ立海岸と大炊田海岸だった。産卵シーズンになると毎年4回の観察会だった。最後の2年ほどは小豆野さんの体調も考え年2回に減らしたが、上陸しそうな日を選び、参加者を募って産卵観察会を行うといういいとこ取りの企画だった。小豆野さんを先頭に、真っ暗な夜の砂浜を産卵のために上陸して来るアカウミガメを探してゆっくり歩くのだ。上陸するアカウミガメに出会えた確率は、3分の2ほどだっただろうか。しかし、野生動物だから全く出会えない日もあった。そういう日は、私も小豆野さんも平謝り。イチローが三振した時のような気分だった。そういう時でも上陸した足跡や産卵したあとは幾つもあったので、小豆野さんはそれらを前に話をされた。
話のひとつに、アカウミガメとの出会いがあった。夜の浜でひとりで詩吟をうなっていた時、海から上がってきたのだという。怪獣だと思ったそうだ。あるいは、参加者に「上がってくるのは全部メス。メスには尻尾がない。オスにはあるのになぜか?」と問いかけられた。夏の夜の浜での話は、ちょっと助平心が見えて楽しかった。また「自分はツルで有名な出水市の生まれ、カメに出会い『鶴は千年亀は万年』という実にめでたいことになった」と話をされた。
思い出は尽きない。暗闇の中に見つける一本の筋(上陸したばかりの足跡)、一晩に5頭も出会ったこと、じっと産卵を見守る親子、産卵を終え海に帰っていく姿、何回も産卵場所を探して動き回る姿、あるいは南の空のサソリ座、侵食が進み痛々しい砂浜等々・・・。
冥福を祈りたい。


コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
七ツ釜
2018-03-29 / 自然

七ツ釜

象の鼻

象の鼻
柱状節理を見ておこうと国の天然記念物になっている唐津市の七ツ釜に足を延ばした。天気は快晴。玄界灘に突き出た小半島から望む景観はまさに絶景。玄界灘の海の青さと玄武岩の柱状節理が雄大な景観をなしている。縦に斜めに自然が作り出す柱状節理は見ていて飽きない。海の青さは「玄海ブルー」と名付けたいほどだった。
柱状節理は、溶岩が冷えて固まる時にひび割れし、六角形などの柱状になったものだ。七ツ釜自体は、玄界灘の荒波で柱状節理が侵食されて出来た海蝕洞だ。七つある洞穴のうち最大のものは高さ3m、奥行き110mとある。地名から「屋形石の七ツ釜」として国指定天然記念物になっている。眼下では遊覧船が行ったり来たりしていた。
フリーダイバーのジャックマイヨールが10才の時、イルカに初めて出会った場所としても知られると聞く。どの辺りだったのだろうかと思いながら、「象の鼻」と名が付く場所辺りを見渡すと、その向こうのはるか下方の岩場で竿を出している釣り人が眼に入った。よく知られた釣り場でもあるようだ。大物が釣りあげられるか・・・。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
ムサシアブミ
2018-03-28 / 自然


葉っぱが出る前は、まるで筍が出てきたように地面からにょっきり。名前を漢字で書けば「武蔵鐙」。花を包む仏炎苞が鐙に似ている事から付いた名前だという。武蔵が頭に付くのは、武蔵の国の鐙が品質が良かったからという。
鐙というより、ヘビが頭をもたげたように思えてならない。仲間に茎の模様がマムシに似ているマムシグサや、花の先が釣り糸の様にヒモ状にのびるウラシマソウなどがある。とはいえ、どれもあまり好きにはなれない。筍状の時もヘビの模様のようだし、何となくヘビが出そうなところに生えるからかもしれない。ただ、仏炎苞の縞模様はとてもきれいだ。(佐賀県七ツ釜入口にて)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |




