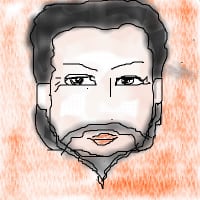はじめに
前回に谷川彰英の著書は、反日・左翼の戦後史学の仮説を史実として継承して利用した地名の解明であり、元から仮定の状況にある事を書いた。
先の本の難波の解説は、かいつまんで言えば、神武天皇が、西から攻めて来て、難波の地で「太陽を見て」名付けたということである。お粗末だ。
えらく、神々しく書いているが、古事記を知る人が読むと、この地は「ナガスネヒコ」によって、敗北した地であり、神武軍が付けたと云う太陽の輝かしい説明とは全く受け入れない。
詐欺師が無知な人をだますように、詐欺的論理だと私は思う。
なお、難波は大阪の繁華街で、地下鉄などでは、ナンバと読まれ、浪速(なにわ)区と区別される。このナンバ(難波)は、難・場でもあろう。
従来の浪速起源
ナニワは、試しに、「なにわ」で、転換すると難波と浪速・浪花が出てくる。浪速が出てくるように、従来は、「波の速い地」として名が付いた」とされている。
この件については、谷川著は「現在の大阪港のあたりは特に波が速いとは考えられない」と、早いうちに否定している。が、無知な否定である。
従来のナニワは、「波が速い」と云う、「なみはや」が語源とされてきた。これを否定したのだ。
宇摩説では、実際に、何故、波が速いのかと云う説明を具体的にができる。と云うのは、大阪港辺りの潮を云ったのではなく、古代の大阪は遠浅(海)だった。
大阪の地に、「波が速い」と付いたのは、この地が遠浅の海で高低差が少ない砂浜だった。だから、満ち潮が川の流れのように露出した砂浜を速く流れた(浸食)したのである。
つまり、従来説には、「何故か」の説明は無いが、宇摩説から見れば従来の説明は正しいのだ。
が、谷川氏は、天皇家が半島から渡来したという説のために、否定したのか、無知で簡単に否定したものか?良く解らないが、異常な地名解説である。
難波について
さて、ナニワに当てられた「難波」の方だが、ここにも、波がある。これは、今の大阪は陸地だが、古代には波が打ち寄せる地域、つまり、遠浅の地であった事を残すのであろう。
難波の漢字は、波が速いので「難がある波」との意味だ。また、処々にある暗礁や小島に因って、波が複雑に流れていた事、波に阿されて、暗礁などにぶつかる事などによるものだろう。
此の宇摩説を読んだ後で、先の本の言い回し(解説)を読むと、如何に詐欺的説明であるかが良く判る。話が飛ん所で、ドンドン確定化・既定事実化するのである。
この本は祥伝社の文庫本で税込600円だから、出来れば、実際の本で当られたい。ただ、このブログで書いているように、内容的にお粗末だから、勧めはしない。
以上のように、ナニワの起源は、「なみはや」で良く、大阪にあった細く長い遠浅の砂浜に潮流が早く押し寄せ、速く引いた事にっと生まれた地名ある。
また、暗礁や小島が多く、潮流は複雑に流れたから、ナンバとも呼ばれ、「難波」とも書いたが、「難・場」でもあったと云う事だ。
このように宇摩説で大阪地名を解いて行くと、大阪を「摂津」と云った意味も同様に判明した。これは、宇摩説の解明が正しい事を示すものだろう。
つまり、ナニワを解いて、同時に摂津の語源が「狭い津」の意味だったと判明した。このように、次々に、予定外の地の起源が判明し行くのだ。
次回は、「ナ」と、ナニワ、ナリの宇摩説の解説をする。
=================
二つの「ポチ」が、大きな励みになっています
*相場師ブログは、Gooの「株式投資と邪馬台国女王、卑弥呼」を登録しています。
皆さんのお陰で、順調に上がり、10位近くに来ています。
*ブログの殿堂は、ココログの「建国と今」を登録しています。
ここは、ニュースの「社会・経済」、金融資産の「株式。投資」、芸術の「歴史」に登録しています。
「建国と今」には写真のアルバムがあるので、記事の写真を見たい時は便利です。ランキングから訪問して下さい。
* また、ブログやランキングに妨害が入っています。