 | 7割は課長にさえなれません城 繁幸PHP研究所このアイテムの詳細を見る |
本日、新刊が発売になる。※
というわけで簡単に目次を紹介。
第一章 年齢で人の価値が決まってしまう国
第二章 優秀な若者が離れていく国
第三章 弱者が食い物にされる国
第四章 雇用問題の正しいとらえ方
第五章 日本をあきらめる前に
エピローグ
第一章:年功序列という世界で日本だけの奇妙なカルチャーが生み出す様々な弊害について
述べる。このカルチャーにおいては、20代前半に人生最大の勝負どころがやってくるため、
うかうか寄り道なんてしていられない。
といって、勉強しすぎても、レールから弾き出されることになる。
そして、卒業年度に求人が少なかった人たちは“一階部分”に押し込まれる。
第二章:日本の雇用法制では既得権の見直しが行なわれないため、人件費抑制は昇給抑制と
いう形で行なわれる。つまり賃金カーブは時間をかけてゆっくりと低下するわけだ。
これを予想した若手から流動化していくことになる。日本人の若手でさえそうなのだから、
まともな外国人はよりつかない。
高度人材から見て、日本の労働市場は世界44位という魅力しかない。
第三章:本来、安定した仕事よりもハイリスクな仕事の方が高時給であるべきだが、実際
にはそうなっていない。それは日本の労働市場が自由主義ではなく身分制度だからだ。
自由競争は社会に活力を生むが、規制は活力を削いでしまう。
日本型雇用を守り続けた結果、政府の債務残高以外は低迷し続けている日本を見れば、
それは明らかだろう。
第四章:従来の価値観は一度ゼロリセットする必要がある。
たとえば氷河期世代に対して「自己責任だ」という保守派も「資本階級が悪い」という共産党
も、どちらも日本型雇用主義者という点で変わらない。
テレビや新聞といった大手メディアも、この違いが理解できているとは言えない。
特にテレビ局に対しては、おススメの番組構成を提案してある。
第五章:本書を通じて主張していることの総括。
日本型雇用、つまり終身雇用というのは2階建てであり、一階部分の人間にとって維持する
メリットなど最初から無い。実は、我々は少数派ではなく多数派である。
問題は、このことに多くの人が気づいていないことだ。
本書は、2つの流れが同時並行で進む形となっている。
一つは、本ブログや過去2冊の新書と変わらないロジックの話。
そしてもう一つは、ある町のある一家を中心としたストーリーだ。
“エピローグ”というのは、多くの人が気付いたら・・・というifの話である。
それは確かに仮定の話に過ぎないが、理論的に不可能というわけではない。
少なくとも超国家主義や計画経済なんかよりは、ずっと身近なものである。
※でも店頭に並ぶのは大型店以外は来週かな。














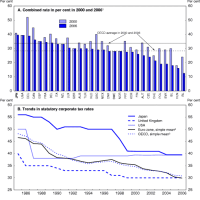





ところで、ダイヤモンド・オンラインの『格差社会の中心で友愛を叫ぶ』という連載が熱いです。
http://diamond.jp/series/yuuai/bn.html
私自身、2度の転職を経験しています。
転職そのものは、その会社その会社で新たな知識・スキルが身につくうえ、自分の得手不得手も体験できるので、いまの生活に大変プラスになっています。
ただ、「給料」となると話は別です。
実際、中途採用を受け入れる会社はベンチャーであったり、大手企業でも特定のキャリア・職種に限られています。
この本に書かれているとおり、給料を犠牲にしても新しいことを始めたい、と思っても年齢だけで門前払いされることも少なくありません。
城さんならご存知だと思いますが、「経験不問」で転職できる年齢はせいぜい35歳ですので、ちょうど35歳の私の職業はさらに限られることになります。
古い体質の会社に変化を求めるのは本当に難しいことだと思いますので、若い人たちが自ら会社を興していく行動が、これからは経済的にもインパクトを持ってくるはずです。
また、新卒を含む若い人たちが、古い体質の会社を選ばなくなったら、その会社自体が存続しなくなるので(年金制度と同じような話です)、若い人たちが今の社会に「NO」を突き付けるだけで面白いことが起こる気はしています。
まだ読破した訳ではありませんが、趣旨に感心したものとして、これを是非若い人に読んでもらいたいと思います。
具体的な当てがあるわけではないのですが、少しまとめ買いして若い人たちに読ませたいと思います。
これからのご活躍、益々期待しております。
50以下の人を中心にできるだけ多くの人に読んできただき、「問題の根本原因はいったい何なのか?」を多くの人が理解すれば問題は半分解決したも同然だとわかる本です(解決策は別に困難なものではないから)。
エピローグに出てきた、流動化はあるグループが唯一損をするだけ、というのはプロパガンダとしては○かなと思いますが、実際はもうちょっと摩擦が生じるでしょうね。でも、その摩擦を通り過ぎた日本は、現在の閉塞感に満ちた日本とは見違えるほどに、活力を持った社会です。
久々にハッピーエンドな話を読ませて頂きました。昭和から続く閉塞感にようやく天穴が空いたような爽快感がありましたよ。ドラマ化出来そうですね。(笑)
ドイツのように社員10人以下の企業は解雇自由にするなどの実験->検証を行ってみればよい。
(ア) 解雇制限緩和(解雇制限法の改正)
解雇制限対象となる企業の範囲を、従業員6人以上から11人以上に縮小し、 解雇事由も緩和した。
解雇制限法は、従業員6人以上の事業所の勤続6か月以上の労働者の解雇 について適用され、正当事由のない解雇を否定している。すなわち、
(1)緊急の経営上の必要性に基づかないもの、
(2)労働者を同一事業所
または同一企業の他の事業所で継続して雇用可能な場合、
(3)解雇対象者
の選定が不正な場合等は不当解雇となるとしてた。
こうした厳しい解雇制限があるため、一度雇用すれば雇用関係の終了が困難となることから、かえって事業主の新規雇用意欲がそがれ、結果として新規雇用創出がはかどらないという指摘がなされていた。そこで雇用に果たす中小企業の役割が大きいこと(全雇用の8割を中小企業が占める)から、中小企業を解雇制限対象から外すことによって、中小企業における新規雇用の促進を図ったものである。 また解雇に際しての人選基準も改正され、人選基準は、労働者の勤続年数、
年齢、扶養家族の3要素のみで足りるものとなった。なお、労働者の知識・技能等に基づく人選が正当な経営上の利益に合致する場合には上記の人選基準は適用しないとされた。(従前の法では、解雇対象者の人選に当たり、各種要素を考慮しなければならないとされていただけであった。) そして、労使間の事業所協定で解雇の人選基準を定めた場合、経営側に重大な瑕疵がない限り、裁判所は具体的人選の当不当を判断しないものとされた。
http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpyj199701/b0081.html
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091221/plc0912210131000-n1.htm
そうかね? 外国人労働者数や外国人登録者数は年々増加しているようだが?
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/1180.html
国籍別外国人登録者数の推移
サムスンやエイサーなどの価格破壊は大いに認めるけれども、安いという点を除けば、
自分にとってはどうしても手に入れたいと思わせるようなものには出会ってない。
VistaだのWindows7だのoffice2007だのi-phoneだのが欲しいとも思えない。
WindowsはXPで十分だし、officeソフトはフリーソフトのOpenOfficeで十分だし、
ガラパゴス携帯と呼ばれようがすぐ電源が切れるスマートフォンが羨ましいとは思えない。
確かに日本経済はもはや一流ではないが、殺人事件は少なく平均寿命も長く文化的には今も一流。
池田信夫氏や木村剛氏はインドや中国の経済成長をよく引き合いに出すが、あんな物騒な国はお断りだ。
太平洋戦争では負けたが日中戦争では勝ってた、だから大日本帝国だって捨てたものではない。
バイト先も解雇となり愚痴を垂れつつ親元でパラサイト生活する毎日・・・もしかして自堕落?
妹は1972年生まれですが、自分も大学卒業時に就職には苦労したはずなのに、財閥系大手上場企業を2年足らずで辞めて、専業主婦へ。義弟は某ITゼネコン傘下のシステム開発会社のSEで38歳。義弟の勤務する企業グループの社長が創業者から銀行出身者へ交替し、インドなどへの外注などコスト構造を徹底的に見直す、グループ会社間の統合を進めるなど新しい施策を表明しているのに、二人とも危機感ゼロ。そろそろ子供のためにも将来の財産形成のためにもマンションを買おうと、傍から見て大丈夫かなということを言っています。そして、甥には中学受験をさせると言い、最近、甥は塾に通い始めました。
城さんの雇用についての見方は決して社会に出ている人だけではなく、これから出ようとしている人、あるいは出ていく子供たちを教育したり育てる親や教育関係者も読むべきだと思います。若いころから「ラットレース」みたいなことをやっても報われるのか?本当に先行き不透明な時代を生きていく力とは何か?それを身につけさせるためにはどのように導いてやればよいのか、その一助となる本だと思います。
>2010年のナンバーワン!
まあまだ1月だしね(笑)
かなりいい本であると思うと同時に、暗澹たる気持ちになりました…。
今まで曖昧にして先送りにしてきた、「嫌な部分」だったかと思います。嫌な部分ですが、これに直視せざるを得ない事態になっているかと存じました。
若い人が、海外に出ていくのも必然なことかと思いました…。
お前は右翼か!