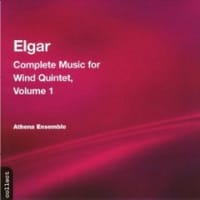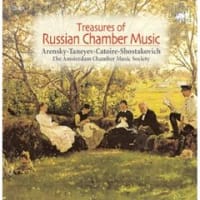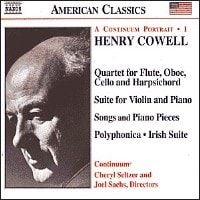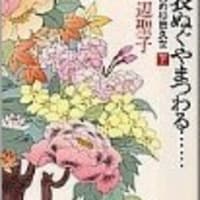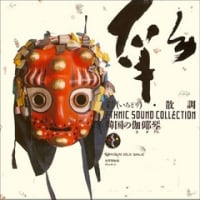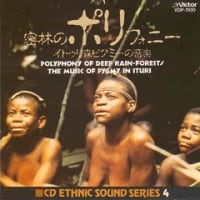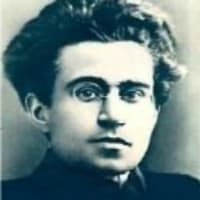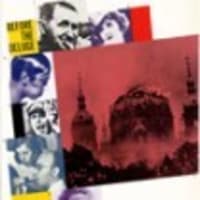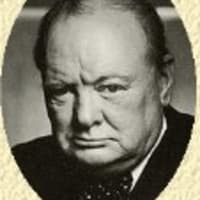冬は、やはり「鍋」でしょう、ということで、新聞にも2本ほど「鍋」に関する記事が載っていました(「朝日新聞」12月25日付夕刊)。
ということで、本欄も「鍋」についての雑考を。
料理名としての「鍋」は、多くがその主な具材を前に付けています。
「牡蛎鍋」「鮟鱇鍋」「泥鰌鍋」「鯨鍋」「ボタン(猪肉の別名)鍋」「サクラ(馬肉の別名)鍋」などなど。
また、「土手鍋」「寄せ鍋」など、料理のしかたを示すものや、謂れ因縁がありそうな「成吉思汗鍋」「石狩鍋」「柳川鍋」などもあります。
これらは料理名ですが、それ以外にもちろん、料理器具としての「鍋」の種類を表す単語もあるのね。
「石鍋」「土鍋」「中華鍋」「行平鍋」「寸胴鍋」などなどです。
ですから、新聞のコラムにあったようなお話もありうるのですな。
窪田聡作詞作曲の『かあさんの歌』について。
著者(五木寛之)が、この歌を口ずさんでいた。
こういう歌詞です。
「かあさんは よなべをして 手袋 編んでくれた……」
それを耳にした若いスタッフが、
「〈よなべ〉って、なんの鍋ですか」
と尋ねたそうです。
つまりは、「よなべ(夜鍋)」というのを、「牡蛎鍋」「鮟鱇鍋」あるいは「成吉思汗鍋」「石狩鍋」の一種と思った、というわけね(ちなみに「夜鍋」とは、徹夜作業のこと。「夜、鍋をかけ夜食をとりながら仕事をすることによる」そうです)。
これとは同日、「ちりとり鍋」の記事も載っていました。
小生、この名前は初めて目にしました。
文章を読むと、「牛赤身とホルモン、山盛りの野菜を一緒に煮る」鍋だそうで、命名の由来は、「ちりとりの形に似た底の浅い四角い鍋を使うこと」によるとのこと。
ですから、これは料理器具としての「鍋」の名称が、料理としての「鍋」の名前に転化したもの(大阪の鉄工所の経営者が、副業に始めたホルモン鍋の屋台から生まれた「鍋」ということも、関係あるのかもしれない)。
同様の例は、あるのでしょうか。小生は、今ちょっと思いつかない。
そういう意味では、興味深い名称の生まれ方になります。
しかし、「ちりとり」という汚れ物系の名前(語感は、三味線の音色のオノマトペ「ちりとてちん」に似て、汚くないんだけどね)を料理に付けるという即物性は、やはり関西系のような気がしますが、小生のような関東者の偏見でしょうか。
まあ、その内に、「浮世の塵芥(ちりあくた)を取り去る」なんていう語源伝説が生まれそうだけどね(こういうのもフォーク・エティモロジーと言うのでしょうか)。