■ボックス21/アンデシュ・ルースルンド&ベリエ・ヘルストレム 2022.1.10
アンデシュ・ルースルンド&ベリエ・ヘルストレムの 『 ボックス21 』 を、読みました。
今回は、東欧出身の女性の人身売買と強制売春のことがテーマとなっています。
この犯罪が、スウェーデンや北欧諸国で深刻な問題になっていることを指摘するばかりでなく、「もちろん、これはルポルタージュではなく小説なので、ルースルンド&ヘルストレム節とでも呼べそうな個性のあるドラマチックな文体や、心理描写もあわせて味わっていただきたい(訳者あとがき)。」と内容豊です。
エーヴェルトは唯一の友達ベングトの死に対して、あんなにも責任を感じる必要があったのだろうか。
ベングトの死を妻レーナに知らせることを躊躇する意味があったのかと思う。
それにしても、エーヴェルトとベングトが交わす友情の情景は、切なかった。
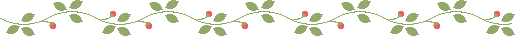
ずたずたに打ちのめされたグラヤウスカス。その担架が運び出されてから、鑑識官たちが到着するまでのあいだに、姿を消してしまったスリューサレワ。いまのところ分かっているのは、ふたりともバルト海の向こうからやってきた売春婦である、ということくらいだ。こうした売春婦には何人か会ったことがある。彼女たちの来し方は、いつも同じだ。バルト三国出身の、若く貧しい少女たちが、売春婦に変身させられる。まず、彼女たちの住む村に口のうまい人間がやってきて、仕事と豊かな生活を約束する。偽造パスポートを与える。そのパスポートを受け取るやいなや、彼女たちは希望に満ちたティーンエイジャーから、発情を装う女へと変身させられる。偽造パスポートは高価なので、それが彼女たちの借金となる。働いて返さなければならない。
大柄で、なにかと騒々しい、エーヴェルト・グレーンス警部。白髪混じりの髪は薄く、軽く足を引きずって歩き、以前に首を絞められたことがあるせいで首筋がこわばっている。気難しいこの警部については、だれもが噂を耳にしていたが、だれひとりとしていっしょに仕事をしたことはなく、見たことすらない者もいる。自分のオフィスに閉じこもり、シーヴ・マルムクヴィストを聞きながら、ひとりで捜査を進める、それが彼のやり方だ。彼のオフィスに入れてもらえる人間は、ほんの一握りしかいない。そもそも進んでそのオフィスのドアをノックしようと思う人間すらほとんどいない。それが周知の事実だ。
スヴェンは深く息を吸い込み、なんとか落ち着こうとした。まったく、エーヴェルト・グレーンスという人間は強烈だ。見ていて退屈することがない。
エーヴェルトはたくさんある窓をひとつひとつ探るように見つめた。どれにも高価そうなカーテンがかかっている。その向こうで、人々が生きている。生まれ、死んでいく。すぐ近くで進行しているにもかかわらず出会うことのない、いくつもの世界。だれもが隣人のことなどなにも知らずに生きている。
ふたりで何度も語り合ったものだった。
ベングトとは、取調室、居酒屋、ベングトの家の庭などで、ともに時を過ごしてきた。会話はしばしばひとつのテーマに収束した。そのテーマとは、真実。ある意味、すべては馬鹿らしいほど単純だ。真実と嘘。ふたつにひとつ。人がずっと抱えていられるのは、真実のほうだけである。
嘘をずっと抱えていることなどできない。
スヴェンはテレビの画面を、つい先ほどまでそこに映っていたものを叩いた。
「これは、きみ自身が耐えられなかったからだ。なぜなら、エーヴェルト、罪悪感は、他人になにかをしてしまったときに抱くものだ。自分に対してなにかをしてしまったとき、人は恥の意識を抱く。罪悪感には耐えられる。恥は耐えがたい」
エーヴェルトはなにも言わず、目の前で話しつづけている人間を見つめた。
「きみは、ベングト・ノルドヴァルを遺体安置所に送り込んで死なせたことで、罪の意識を感じていた。それは理解できる。罪悪感は分かる」
スヴェンは声のボリュームを上げた。力尽きつつあることを見せたくなかった。
「だが、恥は、エーヴェルト、恥のほうは理解できない! きみはベングトにだまされた自分を恥じた。ベングトの正体をレーナに知らせなければならない、そのことを恥じた」
さらに声を上げ、続ける。
「エーヴェルト、きみはレーナを守ろうとしたんじゃない。逃げようとしただけだ。きみ自身の恥から」
外は妙に肌寒かった。
『 ボックス21/アンデシュ・ルースルンド&ベリエ・ヘルストレム
/ヘレンハルメ美穂訳/ハヤカワ・ミステリ文庫 』
アンデシュ・ルースルンド&ベリエ・ヘルストレムの 『 ボックス21 』 を、読みました。
今回は、東欧出身の女性の人身売買と強制売春のことがテーマとなっています。
この犯罪が、スウェーデンや北欧諸国で深刻な問題になっていることを指摘するばかりでなく、「もちろん、これはルポルタージュではなく小説なので、ルースルンド&ヘルストレム節とでも呼べそうな個性のあるドラマチックな文体や、心理描写もあわせて味わっていただきたい(訳者あとがき)。」と内容豊です。
エーヴェルトは唯一の友達ベングトの死に対して、あんなにも責任を感じる必要があったのだろうか。
ベングトの死を妻レーナに知らせることを躊躇する意味があったのかと思う。
それにしても、エーヴェルトとベングトが交わす友情の情景は、切なかった。
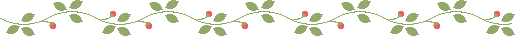
ずたずたに打ちのめされたグラヤウスカス。その担架が運び出されてから、鑑識官たちが到着するまでのあいだに、姿を消してしまったスリューサレワ。いまのところ分かっているのは、ふたりともバルト海の向こうからやってきた売春婦である、ということくらいだ。こうした売春婦には何人か会ったことがある。彼女たちの来し方は、いつも同じだ。バルト三国出身の、若く貧しい少女たちが、売春婦に変身させられる。まず、彼女たちの住む村に口のうまい人間がやってきて、仕事と豊かな生活を約束する。偽造パスポートを与える。そのパスポートを受け取るやいなや、彼女たちは希望に満ちたティーンエイジャーから、発情を装う女へと変身させられる。偽造パスポートは高価なので、それが彼女たちの借金となる。働いて返さなければならない。
大柄で、なにかと騒々しい、エーヴェルト・グレーンス警部。白髪混じりの髪は薄く、軽く足を引きずって歩き、以前に首を絞められたことがあるせいで首筋がこわばっている。気難しいこの警部については、だれもが噂を耳にしていたが、だれひとりとしていっしょに仕事をしたことはなく、見たことすらない者もいる。自分のオフィスに閉じこもり、シーヴ・マルムクヴィストを聞きながら、ひとりで捜査を進める、それが彼のやり方だ。彼のオフィスに入れてもらえる人間は、ほんの一握りしかいない。そもそも進んでそのオフィスのドアをノックしようと思う人間すらほとんどいない。それが周知の事実だ。
スヴェンは深く息を吸い込み、なんとか落ち着こうとした。まったく、エーヴェルト・グレーンスという人間は強烈だ。見ていて退屈することがない。
エーヴェルトはたくさんある窓をひとつひとつ探るように見つめた。どれにも高価そうなカーテンがかかっている。その向こうで、人々が生きている。生まれ、死んでいく。すぐ近くで進行しているにもかかわらず出会うことのない、いくつもの世界。だれもが隣人のことなどなにも知らずに生きている。
ふたりで何度も語り合ったものだった。
ベングトとは、取調室、居酒屋、ベングトの家の庭などで、ともに時を過ごしてきた。会話はしばしばひとつのテーマに収束した。そのテーマとは、真実。ある意味、すべては馬鹿らしいほど単純だ。真実と嘘。ふたつにひとつ。人がずっと抱えていられるのは、真実のほうだけである。
嘘をずっと抱えていることなどできない。
スヴェンはテレビの画面を、つい先ほどまでそこに映っていたものを叩いた。
「これは、きみ自身が耐えられなかったからだ。なぜなら、エーヴェルト、罪悪感は、他人になにかをしてしまったときに抱くものだ。自分に対してなにかをしてしまったとき、人は恥の意識を抱く。罪悪感には耐えられる。恥は耐えがたい」
エーヴェルトはなにも言わず、目の前で話しつづけている人間を見つめた。
「きみは、ベングト・ノルドヴァルを遺体安置所に送り込んで死なせたことで、罪の意識を感じていた。それは理解できる。罪悪感は分かる」
スヴェンは声のボリュームを上げた。力尽きつつあることを見せたくなかった。
「だが、恥は、エーヴェルト、恥のほうは理解できない! きみはベングトにだまされた自分を恥じた。ベングトの正体をレーナに知らせなければならない、そのことを恥じた」
さらに声を上げ、続ける。
「エーヴェルト、きみはレーナを守ろうとしたんじゃない。逃げようとしただけだ。きみ自身の恥から」
外は妙に肌寒かった。
『 ボックス21/アンデシュ・ルースルンド&ベリエ・ヘルストレム
/ヘレンハルメ美穂訳/ハヤカワ・ミステリ文庫 』














