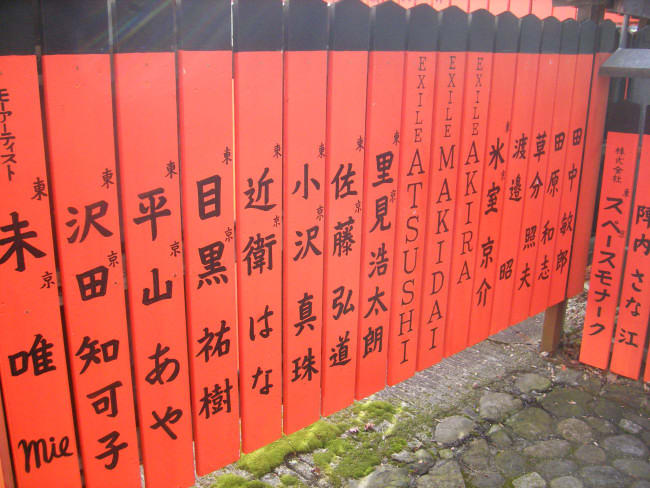昨日、先週末から行っていた海洋学習の代休となる小学5年の娘と
京都市北区玄琢にある「大宮交通公園」へお出かけしてきました。
仕事が午前中に終わった私。時間を節約する為、仕事服のままの登場です。
「大宮交通公園」は子供達が楽しみながら道路・交通ルールを学ぶために整備された市が運営する緑地公園です。
公園内を一つの‘まち’に見たてて、道路整備や信号機や横断歩道などを設置し
ミニチュア的な市街地整備されています。また、郊外地見たてた区域には緑いっぱいの公園となっていて散策したり、
お弁当などを持ってきたのんびりするのには最高のスペースでもあります。
土・日の休日には園路をゴーカート(子供のみ)で走行することができ、実践的な
交通マナーも学べるので、家族連れで遊びにいくのには最適な施設です。
この公園は昭和44年に整備された施設で、実は私も子供の頃、よくここに連れてきて貰い、ゴーカートを乗り回していた記憶があります。
残念ながら、この日はゴーカートの運行日(木・土・日のみ)でなく
「今日は10回以上、ゴーカート乗る!」と行く前から気合が入っていた子供は
運休と聞いてかなりががっかりしていましたが、自然がいっぱいで遊具もある
公園なので、すぐにあちらこちらで転がり、遊んでくれたので一安心。

園内には昔、京都市内を走っていた市電やチンチン電車、蒸気機関車も展示されたいます。
市電は私も子供の頃、いつも利用していた懐かしい車両です。
また、市電とチンチン電車の車両内はミニ図書館になっていて、車内外で読書にいそしむこともできます。
並んでいる本は子供の頃に読んだ記憶のある‘児童名作集’からドラえもんの漫画まで幅広いです。
漫画大好きな我が娘は「ドラえもん」や「コロコロコミック」を熟読。
日が暮れるまで読書タイム(?)となってしまいましたが・・・

ゴーカートコースとなるハイウエイの横には豊臣秀吉が造った「御土居」があります。
秀吉は京都の町並みを改造する為「御土居」と呼ばれる土盛の城壁で洛中と洛外の
線引きをして市街地と街外とを明確にした、その史跡です。
ここは「玄琢下」と呼ばれる「御土居」が残っています。
平日は近所のお子様連れで散策する主婦の方も多く見られましたが、本当にのんびりできて、
今の季節、お弁当をもって訪れるのには最高の癒しスポットと感じました。
しかし、地下足袋に作業ズボン、『船士魂』の文字が染められたTシャツは
周囲で、かなり浮いていたことは間違いないかも・・・
「京都市交通公園」
所在地:京都市北区大宮西脇台町
入園料:無料
駐車場: 無料(15台)
但しゴーカートは一回:2人乗り250円、1人乗り150円
開園時間 :9:00~16:30
休園日 :火曜日 12/29~1/3
備考 :園内、食堂等無し、自動販売機はあり