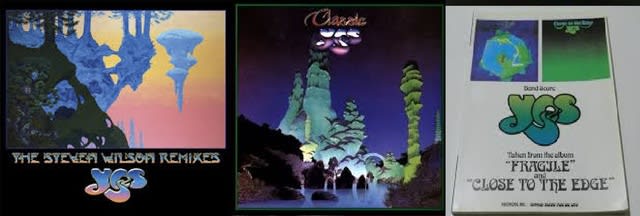
A.いまごろ「プログレ」入門するの?
こんどのテーマは、プログレ、とくにイエスである。なんで?といわれるとちょっと困るが、要するに何にも知らないから、というのが答えだ。ぼくは、プログレッシヴ・ロックもイエスも、全然知らない素人だから、このさい知ってみようということだ。 調べてみたら、バンド「イエス」のメンバーは、中心だったベーシスト、クリス・スクワイアとキーボードのリック・ウェイクマンが共に1948年ロンドン生まれ、ドラムのビル・ブルフォードとその後継者のアラン・ホワイトが1949年生まれというように、1949年生まれのぼくとは同世代になる。みんないまや70歳に達しようというジジイになっているが、ファーストアルバム「Yes」が出た1969年7月では、花の20歳前後だった。ロンドンと東京は遠いが、いわば同時代を生きていたことになる。でも、ぼくは高校時代に友人たちが夢中になったビートルズやローリングストーンズにはじまるロックに、あえて触れないように過ごしていた。
当時のぼくには、音楽はジャズやクラシックを聴くだけで満足していて、新興のロックはなんだか流行に飛びつく軽薄さと、大音量で騒ぎまくる野蛮で下品な感じがして敬遠していた。 あれから半世紀が経った。若者だったミュージシャンが年老いてあの世に行くのも近い。ロックも考えてみれば全盛期はせいぜい1980年代はじめまでで、CDの売上枚数を競った時代は過去のもの。いまの日本では、「洋楽ロック」などと一括されて中高年の懐メロ扱いされている。イエスのCDを探しに中古屋へ行ったら、プログレ4大陸(キング・クリムゾン、ELP、ピンク・フロイド、イエス)とまとめられた棚に「ロック・クラシック」と札がついていた。おお、もうクラシックになってしまったのか。
ま、それもそうだよな、今の大学生からみれば、生まれるずっと前に流行った「楽曲」なんて知らんもんね。ぼくらが昭和の初めの演歌聴くようなもんだな。 ともあれまずは「プログレ」の定義は?安易にWikipediaにはこう書いてある。
「プログレッシブ・ロック(英: Progressive rock)は、1960年代後半のイギリスに登場したロックのジャンルの1つ。進歩的、革新的なロックを意味する。世界ではプログ・ロック(progまたはprog rock)、日本での一般的な略称は「プログレ」。代表的なグループには、ピンク・フロイド、キング・クリムゾン、イエスなどがある(引用者註:なぜかELPほかは外れてる)。 プログレッシブ・ロックは、実験的・革新的なロックとして、それまでのシングル中心のロックから、より進歩的なアルバム志向のロックを目指した。1960年代後半に誕生し、全盛期は70年代前半である。当初の進歩的・前衛的なロック志向から、一部のクラシック音楽寄りな音楽性が、復古的で古色蒼然としていると見られ、1970年代半ばから後半にかけて衰退したとされている(引用者註:誰がそんな説を唱えたの?)。ピーター・バラカンはプログレッシブ・ロックの全盛期が短かかったことを指摘している。後年、マリリオン、アネクドテンなどの登場により、復活してきている。 プログレッシブ・ロックとは進歩的ロック、クラシック的ロック、アート・ロック、前衛ロック、実験的ロックなどの概念を包括したジャンルである。」
以下云々は飛ばして、要するにプログレの特徴を箇条書きすると…
◎一部のバンドはアルバム全体を一つの作品とする概念(コンセプト・アルバム)も制作した
◎大作・長尺主義傾向にある長時間の曲 ◎演奏技術重視で、インストゥルメンタルの楽曲も多い
◎技巧的で複雑に構成された楽曲(変拍子・転調などの多用)
◎クラシック音楽やジャズ、あるいは現代音楽との融合を試みたものも多く、演奏技術を必要とする
◎シンセサイザーやメロトロンなどといった、当時の最新テクノロジーを使用した楽器の積極的使用
◎イギリスのバンドの場合、中流階級出身者が多かった ということになる。
そこで、以下はもっと詳しい「洋楽」専門家らしき立川芳雄さんという人が書いた、「イエス入門」という要を得たありがたい文章があるので、まずこれを読ませていただく。
「プログレはブルースや黒人音楽からすごく離れた非常に白人的な音楽といえますが、イエスはその最右翼的なバンドです。僕は中学校時代から自分でギターを弾いたりしていたんですけれども、クラシックを勉強していない素人が、当時のプレイヤー系の雑誌なんかを見ながら自己流でやろうとすると、だいたい「コードを押さえて弾きましょう」というあたりから始まる。ソロは「ブルースのコードに合わせて弾いてみましょう」ということになるので、アマチュアでロック系のギターを弾く人間はどうしても最初ブルース、ロックンロール方向に行くんです。その時に、ピンク・フロイドは親和性が強い。フロイドはデイヴ・ギルモアがブルース・ギタリストですよね。キング・クリムゾンの場合、ロバート・フリップは意図的にブルースを拒否しようとしているところがありますけど、それ以外のプレイヤーには黒人音楽を引きずっているみたいなところがあるんです。だから素人の中学生でギターを弾いている人間はそっちに行きやすい。ところがイエスは、まずコピーしようと思っても何が何だかわからない。最初は特にそうです。たぶんこう感じた日本の音楽ファンは多いと思います。だからイエスは、ちょっと入口が狭いんですよね。
イエスの中心人物はヴォーカルのジョン・アンダーソンとベースのクリス・スクワイアだと思うんですけれども、この二人が最初にバンドを組んだ時、サイモン&ガーフィンケルが好きだというんで意気投合したというエピソードがあるんです。ですから非常にフォーク的なんだけれども、フォークといってもアメリカのカントリーから来るものではなくて、ヨーロッパの白人的なフォークです。イエスはすごくメロディ重視型なんです。メロディで聴く人にとってはイエスは「いいな」と思えるところがあると思います。でも、たとえばエリック・クラプトンやローリング・ストーンズあたりのファンは、イエスに対して「これは音楽なんだろうか」と思うくらい違和感を覚えるんじゃないかという気がします。ストーンズやクラプトンみたいにブルースが元になっている音楽は、たとえばヴォーカル一つ取っても、こぶしをきかせるというか、音符にできない部分が味わいということになるんです。しかしイエスはかっちり音符になるようなメロディが特徴で、非常にスクゥエアな感じがする。そのへんが好き嫌いのはっきり分かれるところだと思います。僕も最初はギターをやっていたこともあり「なんだ、こりゃ」と思ったんですけれども、聴いているうちにだんだん、そのスクゥエアな感じが良いと思えてきました。
音楽というのはいろいろ聴いているうちに自分の好みがはっきりしてきますよね。僕もだんだん、自分はソウルやR&Bよりは白人系の音楽の方が好みなんだとわかってきた。そうするとイエスを自覚的に聴けるようになりました。本当に異様なくらいブルースっぽくないのが特徴で、たとえば3拍子の曲が多いんです。三拍子のロックはあまりない。アルバムに一曲くらいデカダンな雰囲気のお芝居っぽい曲を入れようというんで三拍子を使うというのはよくありますけれど、代表曲に三拍子が多くて、しかもノリがいいというのはなかなかない。すごく不思議で、イエスの奇妙な特徴だと思います。
このバンドの強みって、楽曲中心主義にあると思うんです。70年代前半、いわゆる黄金期のイエスは、曲がめちゃくちゃいい。その曲のよさで生き残ったんでしょうね。同じプログレ・バンドで比べると、たとえばクリムゾンは、メンバーが替わると演奏する曲も変わる。唯一の例外が「21世紀の精神異常者」で、あれだけはバンドにとって特別な曲なんでしょう、メンバーを替えてもちょくちょく演っていますけれども、ただ基本的にあのバンドはメンバー間のインプロヴィゼーションで曲を作るという感じなので、メンバーが替わると音楽性もどんどん変わっていくんです。ところがイエスの場合は、70年代前半に『こわれもの』と『危機』という名作を作ってしまった。そして、そこに入っている代表曲が自分たちにとっての規範になってしまって、あとはそれを真似していくという感じで何十年もバンドを存続させている。メンバーは替わるんだけども、黄金期の曲は演奏し続ける。むしろメンバーのほうが曲に合わせていかなくてはいけない。新しいメンバーが入っても、変わるのは些末の部分で、基本的に音楽性は変わらないまま保たれていく。クリムゾンと対照的ですね。それからピンク・フロイドの場合は、メンバーが変わると音楽性が変わるとわかっているんでしょう。だからメンバーが減っていくんです。新しいメンバーは入れない。そしてメンバーが減れば減るほど売れていくという不思議なバンドです。イエスはどんどんメンバーが替わるけど曲が揺るがないから、結局、音楽性が変わらないまま何十年もやってこれてしまった。彼らも一時期、「ロンリー・ハート」のスマッシュ・ヒットがあって、あそこで音楽性を変えるかと見せかけたところがあったんですが、四十年という長いスパンで見てしまうと変わっていない。今はライブで「ロンリー・ハート」を演らず、むしろ70年代の曲でくる。だから結局、曲が良かったというのが彼らの強みなんですね。さっきも言ったように、イエスの曲というのはメロディ―中心型で、楽譜にきちっと書けるような曲です。メンバーの味で聴かせるということはない。新しく入ってメンバーが古い曲に対して「俺流の色に染めてやるぞ」と言っても、それができないくらい曲が完成されている。それで何十年も保って来たバンドですね。イエスはライヴも魅力的ですけれど、彼らは近年も、スタジオ作品で新しい曲を作る一方で、ライヴでは昔の名曲を演奏し続けている。僕はこれをダブル・スタンダード方式と呼んでいるんですけど、この方式を最初に始めたいくつかのバンドのうちの一つが、イエスだと思います。ステージでは、新作の曲もやるけれども、最後は必ず往年の名曲をやってファンを満足させる。それをけっこう以前からやっていたのがイエスです。ロック・バンドは変わっていくから、「俺たちは古い曲はやらないよ」という人たちが多いんですが、イエスは黄金期の曲が規範になっていることを自分たちで分っているので、そこは外さない。このダブル・スタンダード方式の成功が、イエスを長生きさせたんでしょう。
イエスは、プログレ好きでポップな曲も好きという人も満足させるんだけど、逆にシンフォニックな壮大な難しい世界が好きという人のことも満足させてくれる。『こわれもの』や『危機』はポップな面が強いと思うのですが、その後の『海洋地形学の物語』や『リレイヤー』は、普通の人には難解だと思わせるところがあって、しかしプログレのマニアにとってはむしろそれが嬉しい。70年代のイエスの作品にはポップな面と難解な面とが同居していて、いろんなファンを満足させるところがある。そのへんもこのバンドの魅力になっていると思います。
『海洋地形学の物語』はLP二枚組で全四曲という構成ですが……、イエスのもう一つの本質的な魅力として、LPレコード時代を象徴するバンドだということがあると思うんです。僕は、ポピュラー・ミュージックの聴かれ方には歴史性があると考えています。60年代後半までは、皆がLP盤ではなくシングルを聴いていた。ビートルズも中期まではシングルで聴かれていました。しかしビートルズが『サージェント・ペパーズ』を出したあたりから、LPはトータル・アートだという発想が出てきて、片面約20分を統一感をもって聴かせるということがロック界に広がった。それが60年代終わりから70年代までです。ところが80年頃からパンク、ニューウェイヴの時代になって、シングル盤の手軽さが再評価されるようになった。このあたりからLPの凋落が始まって、さらに90年代になると、今度はCDが主流になる。そうすると、CDって曲を飛ばしながら聴くことが簡単にできますから、アルバムを通して聴くという習慣が失われていった。さらに21世紀に入ると、音楽を配信で手に入れるようになるので、アルバムという形式自体が形骸化してしまいました。この本の読者の皆さんはどちらかというとLPやCDになじんだ人が多いと思いますけど、長いスパンで見てしまうと、LPやCDを一時間かけて集中して聴くという聴き方のほうがむしろ特殊なんですね。60年代末から70年代にLP、トータル・アルバム至上主義の時代があって、プログレというのはその時代を象徴するジャンルなんです。あと二十年くらい経って振り返ると、本当に変わった時代だったと評価されることになるかもしれませんね。メディアって、自分の身体と外部をつなぐものですから、人間は若い頃に慣れ親しんだメディアからなかなか離れられない。ですから、いま四十代以上の人たちはシングルよりもアルバムで聴くことになじんでいると思います。イエスをはじめとするプログレのトータル・アルバムは、そうした人たちを満足させるものだと思います。」立川芳雄「イエス入門」(文藝別冊『イエス プログレッシヴ・ロックの奇蹟』河出書房新社、2016)pp.46-50.
何も知らなかったぼくには、ふ~ん、そうなのかァ、なるほどね…、と感心するばかりなのだが、あのプログレ全盛の70年代、ぼくもクリムゾン、フロイド、ELP、そしてイエスの名前くらいは知っていたが当時のLPレコードを自分で購入して、針を落として20~30分聴くという対象とは思わず、ジャズやクラシックのLP盤しか聴かなかった。ただ、唯一記憶に残っているのは、音楽の中身ではなくレコードジャケットである。イエスの『リレイヤー』や『トポロジーの物語』のLPジャケットは、ロジャー・ディーンという人のイラストで、ぼくはこれだけは欲しかった。でも、レコードは買わなかったので、ロジャー・ディーン、ロジャー・ディーンとつぶやいてはレコード屋のロックの棚にそれがあるのを探しては眺めた記憶がある。そのうち『レコード・ジャケット・カタログ』という美術本が出たので、お値段は高かったが無理して買った。やっぱり、ロジャー・ディーンは個性的で気に入った。プログレもイエスも、当時のぼくにはロジャー・ディーンの付属物でしかなかったのだ。
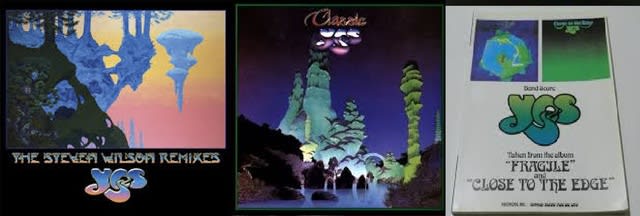
B.過ちをなかったことにしたい偉い人たち
誰でも自分の間違いを認めるのはつらい。それもその当時はなんの疑問も抱かず、世間も気がつかなかったことが、ずっと後になって大きく問題視されたような場合、いまさら間違っていたなんて言われても責任あんの?悪いのオレだけか?と口走ってしまう人はいるだろう。問題はそれが、民間人の過失ではなく、政府として公式に行った行政行為である場合、守るべきは被害者であって行政官僚の方ではない。しかし、どうもそうなっていないらしい。
「ハンセン病元患者の家族への賠償を命じられた熊本地裁判決で今月、控訴を断念した国。「首相談話」で謝罪しながら、「政府声明」で国の法的責任を否定した。この手法は、2001年に元患者に敗訴したときと同じだ。このとき国の責任をあいまいにしたことが、その後の施策や啓発に影を落とししてきたと、ハンセン病問題に詳しい藤野豊・敬和学園大教授(日本近現代史)は指摘する。 (安藤恭子、榊原崇仁) (中略) 元患者の判決から、家族の被害が認められるまで十八年。この間、患者の救済や生活保障を定めたハンセン病問題基本法(09年施行)ができたが、家族は対象とされなかった。
「元患者のみならず、その家族もまた『患者予備軍』として国に監視される立場にあった。同じ隔離政策の被害者だったゆえ、声を上げるのに時間がかかった」と藤野氏は指摘。ハンセン病を発症した父を恨み、結婚を恩に着せる夫からの暴力を受けた女性の話を聞いた経験に触れ、こう話す。 「当事者は人生そのものを奪われた。その苦難を思えば、自らの責任を認めない国の欺瞞は許されない」 藤野氏は、家族の被害実態の新たな検証と、首相談話が約束した立法など補償措置による速やかな救済がなされるか、市民の側が見届けることが必要とする。
「高齢化する原告の時間との闘いを考えれば、首相談話を当事者が歓迎するのはいいと思うが、国の反論や声明はなお検証されるべきだ。国は元患者らがいなくなることで、問題が自然消滅するのを待っている。人権問題として向き合わず、『気の毒だから救済する』という道場の論理で、終わらせてはいけない」 国策による人権侵害の「救済」が、すんなり進まない例は少なくない。
1950年代に日本政府の募集に応じてドミニカ共和国に移り住んだ人らが劣悪な生活を強いられたとして損害賠償を求めた訴訟では、2006年の一審判決で国の違法性が認められたものの、原告側が敗訴。政府は一人当たり最高二百万円の特別一時金で幕引きした。汚染された血液製剤を投与されてC型肝炎ウイルスに感染したとして患者らが国などを相手取った損害賠償訴訟は、和解に向けた基本合意書の調印まで提訴から五年余りを要した。
集団予防接種の注射器使い回しが原因で多くの人がB型肝炎ウイルスに感染した問題は、06年の最高裁判決で国の過失が認められながら、首相の謝罪に至ったのは11年。九州訴訟弁護団事務局長の武藤糾明弁護士は「被害者認定の条件を詰めるのに官僚側の抵抗があった」と語る。謝罪の前段で協議した際、「被害者側が提出しなければならない資料を多く求めてきた。少しでも認定のハードルを上げようとしているように感じた」と振り返る。
官僚が素直に被害者救済に動かないのはなぜか。明治大の西川伸一教授(官僚分析)は「明治以来、日本の発展をけん引してきたのは自分たち官僚だという、高い矜持がある。そんな自分たちが誤りを犯すことはないと考えている。一方で、先輩の官僚を否定するような振る舞いに出れば、いつかは自分たちが否定されるという恐れも抱いている」とみる。
さらに挙げるのが「余計なカネを出したくない」「仕事を増やしたくない」という考え方だ。「国の予算を使うとなれば、財務官僚を相手にしないといけない。彼らこそエリート中のエリートで、折衝は骨が折れると考えてしまうのだろう」。米国製兵器の爆買いの方がよっぽど「無駄」にも思えるが、「国民の意識と乖離した論理がまかり通っているのが現状だ」。 誰のための税金かという疑問が湧く中、千葉商科大の田中信一郎准教授(政治学)は「官僚の論理を抑え、国民の目線を取り込むべき人たちがいる。政治家たちだ」と説く。
しかし、長らく政権を担う自民党はこうした論理を追認してきたという。「支持者や仲間を徹底して重んじる。だからこそ、薬害をもたらした企業をかばい、政権を支える官僚組織を守る」。ハンセン病の件でも、「国民の目を恐れ、やむなく控訴を断念した」一方、「結局は政府声明で、守るべきものは守るという意思を明確にした」とみる。
最近、こうした姿勢が顕著になった例が、旧優生保護法下で障害者らに不妊手術が繰り返された問題だ。四月に議員立法で救済法が成立したが、盛り込まれた一時金は1人320万円にとどまり、訴訟で原告側が求める3千万円台後半と大きな開きがあった。田中氏は警鐘を鳴らす。
「官僚や政治家の姿勢が今のままなら、『いわれなき被害者』は軽んじられ続ける。ハンセン病の問題に限ったことではない」」東京新聞2019年7月17日朝刊24・25面こちら特報部。 以前、南米移民の研究をしていた時、ドミニカ移民の悲劇についていくつか文献があって、日本政府が募集して送り込まれた人たちが、事前の説明とは全く違う劣悪な条件下で苦しんだ話は聞いていた。それを国相手の賠償訴訟があったことまでは聞いたが、結果が納得のいくものでなかったというのは残念だった。裁判で実害があったことを認めながらも、それが官僚のしたことであれば権力を使って責任を最小限にとどめ、補償を軽くしたり曖昧にしようとする例は後を絶たない。それは長期政権ほど政官癒着は構造化するというわけかな。公正な政治とはほど遠い。

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます