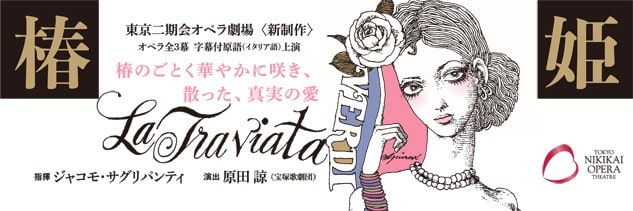日生劇場はいい劇場…今年は特に、射手座の季節にこの劇場に行くのが楽しみで、ビジューつきの替えの靴まで持って出かけてしまった。
自宅兼事務所から車で10分ほどの場所だが、近隣の帝国ホテルやペニンシュラを散歩したくて有楽町から歩いた。
日本語上演のオペレッタは発声もお芝居も大変だが、眞鍋卓嗣さんの演出はさらに芝居部分が多く、歌手陣は身体をフルに使ってコミカルな動き、お笑い芸人並みのボケとツッコミを披露していく。プレビュー公演のためか、冒頭の男性陣たちのお芝居には個々のテンションにギャップが感じられるふしもあったが、そこを屋台骨のように支えていたのがミルコ・ツェータ男爵役の三戸大久さんだった。膨大な台詞をこなし、ジュピター神のように舞台に君臨していい声を聴かせてくれた。
ヴァランシェンヌ箕浦綾乃さんはこの公演が二期会デビューとなるが、舞台初日はかなり緊張されていたように見えた。ヴァラシェンヌのパートは実はとても難しく書かれているのだ。不倫相手のカミーユ役の高田正人さんがよく支えていた。高田さんと箕浦さんは芝居の相性もよかったと思う。
ハンナ役の嘉目真木子さんが登場すると、すべてが一気に引き締まる。意外にもハンナは初役だという。どんな役も真剣に取り組まれる嘉目さんが、この未亡人役をシリアスに演じていたのがよかった。嘉目さんが舞台に現れた瞬間に、これからどんなドラマが展開されようと「右のものは右に、左のものは左に収まる」と思える。ヒロインが正義を握っている、と感じさせる真っ直ぐな存在感があるのだ。
ダニロ役は最初から泥酔している芝居で、与那城敬さんがいい味を出していた。眞鍋演出では、芝居と歌唱と台詞がめまぐるしく交差し、特にダニロ役の負担が多かったと思うが、与那城さんは誠実にこなしていて魅力にあふれていた。嘉目さんも与那城さんも真っ白な清潔感溢れるカップルなのだ。『メリー・ウィドー』は「大人になればなるほど恋は純粋になる」という話だと思っているので、お二人の演技には作品との本質的な相性の良さを感じた。ソーシャル・ディスタンス時代となって、密着した演技が出来なくなったことは、芸術にとってもひとつの「進化」だと考える。人と人とが直接触れ合うと、ある意味ただの物質になってしまう。触れるか触れないかの、静電気を感じるようなギリギリの距離感がむしろ男女の醍醐味だと思う。
ピットには期待の沖澤のどかさんが入り、東響を率いて期待以上のサウンドを聴かせた。弦の弱音の表現力、男性の感情の暴発を象徴するような打楽器、合奏の上品さ、どの場面にも指揮者の厳密な意図と美意識が行き届いていて、沖澤さんのオペラ指揮者としての適性を証明していた。6年前の『チャールダーシュ…』の三ツ橋敬子さんの指揮でも東響はいい音を聴かせてくれたが、若い女性指揮者に秘められている才能をきちんと汲み取って鳴らしてくれるのは有難い。音楽の未来を握っているのは沖澤さんや三ツ橋さんのような人たちなのだ。
レハールは歌手が歌う旋律と管楽器をシンクロさせ、弦楽器とシンクロさせたプッチーニと似たポップな大衆性がある。声量が控え目の歌手たちはオケの旋律線に歌がかき消されてしまう場面があったが、これは歌手が頑張るしかない。男性陣がバッカス神のように歌う「女、女、女のマーチ」では、指揮棒を振る沖澤さんが凄い笑顔で、思わずこちらも笑ってしまった。
オペラやオペレッタは、「感情的に腑に落ちる」ということがなければ、どうも観た感じがしない。「どうだ、凄いだろう」というものを見せられても、「情」が動かなければ何も残らない。日生劇場は凄い場所で、ここではエモーショナルな出来事が起こらないわけにはいかないのだ。『メリー・ウィドー』なら、上野の東京文化会館で観た2016年のウィーン・フォルクスオーパーのゴージャス極まる上演が忘れられないが、ある意味日生劇場は負けていない。とちらが凄くて、どちらが本物、などという議論はナンセンスだ。この2020年の東京で、ピットが宝石の音楽を奏で、日本語でレハールが上演されていることを俯瞰の目で見た時、狂おしく愛らしい至福の空間であると思った。
架空の国ポンテヴェドロ、という設定が既に、少女漫画『パタリロ!』の「常春の国マリネラ」に似ている。演劇・娯楽・オペレッタには「擬き(もどき)」の楽しさがあり、それは日本語上演のような「移し(写し)」の作法によってさらに大衆化する。大衆化しているから簡単、というのではない。与那城さんのダニロを、ヨーロッパの歌手は真似できないと思う。ラスト近くでの日本語での芝居と歌の高速切り替えの連続技は、最も高度な技術を要する。それを「楽しい!」と見ている自分はなんと幸せなのか…。
「ヴィリアの歌」は泣けて仕方がなかった。山の向こうから故郷が、先祖が、風のように語り掛けてくるメロディで、どの国でもその国の言葉で歌われるべきだと思った。満月はどの国から見ても満月。一休さんが水を張った桶に映し、将軍様のもとに運んだ月のように「みんなのもの」だった。
ダニロに「落とし物はないですか?」と問われる人妻たちを演じたシルヴィアーヌ内田智子さん、オルガ小野綾香さん、プラシコヴィア石井藍さんのコメディエンヌぶりも圧巻。マキシムの踊り子や官僚たちも熱演で、プリチッチュ役の志村文彦さんはもはや、日本のオペレッタの至宝だと認識した。
美術装置はシンプルだが、「ハンナの故郷を思わせる」緑に溢れたパーティの装飾は女心にぐっとくるものだった。大使館が舞台なので、なるほどどの国の大使館もああいう地下への階段や中庭があるよなぁ…と納得。特にあの階段はポーランド大使館そっくりだ。
二期会『メリー・ウィドー』は11/26.27.28.29にも日生劇場で上演される。