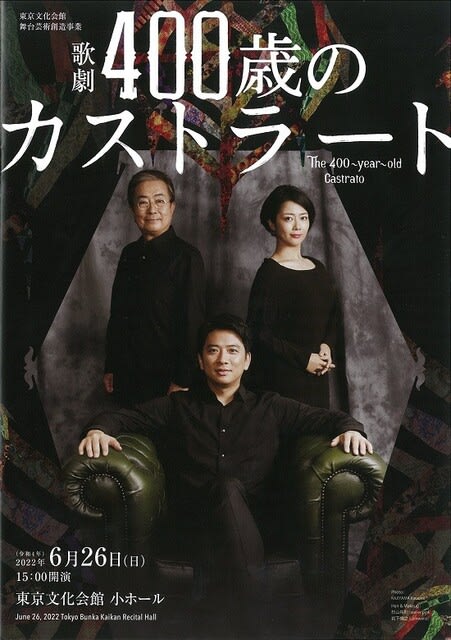深作健太さん演出のストレート・プレイ『ドン・カルロス』を新宿の紀伊國屋ホールで観劇(11/22)。このホールを訪れるのが初めてなら、深作さんの演劇を拝見するのも初めて。二期会の『ダナエの愛』(R・シュトラウス)の稽古見学で初めてお会いし、ワーグナー『ローエングリン』ベートーヴェン『フィデリオ』と深作オペラの素晴らしい上演を続けて観てきた。
紀伊國屋ホールは若い女性客が多く、この日はマチネとソワレの2公演だったが、恐らくリピートで鑑賞しているお客さんもおられるのだろう。演劇ファンとオペラファンは客層が違うが、批評精神旺盛なオペラファンより、演劇ファンの方が素敵だと思うことが最近は多い。
暗く殺風景な舞台を見て、2時間みっちり休憩なしの『ドン・カルロス』がどう演じられるのか想像できなかった。そして最終的には、ひどく心が搔き乱された。人の善良さ、純粋さ、平和と自由を求める理想精神が、勝利の一歩手前で、より一層深い闇(権力)によってかき消されるブロセスを見た。
役者たちがこんなに電撃的な存在であることに驚き、心臓が止まりそうだった。
登場人物全員が、皆どん詰まりの状況にある。シラーの戯曲は読んだことがないが、ヴェルディの『ドン・カルロ』は4幕版も5幕版も観たことがある。翻訳とドラマトゥルクを大川珠季さんが担当しているが、深作さんが演出となると、どうしてもオペラがチラつく。オペラが豪華客船だとすると、小劇場でのストレートプレイはモーターボート。スピードが違うし、自由度も違う。
カルロスは吃音で、片足が不自由で、引きこもりで自閉症の兆候もある。ナイーヴで壊れやすいこの役を、2004年生まれの北川拓実さんが情熱的に演じた。吃音で足が不自由という設定は、『金閣寺』の主人公・溝口と、内翻足の柏木を思わせる。二重の脆弱性を背負いつつ、カルロスはもっと重大な欠落も背負っている。「一度も父親のフェリペⅡ世に愛されたことがない」という愛情飢餓で、蓋をあければフェリペ本人もそれ以上の愛情飢餓を抱えている。みんながいびつで、癒しを必要とし、ボロボロの状態で言葉を剣のように交わしている。
その中でエリザベートは唯一冷静な存在で、愛原実花さんが女神のように美しく理性的な王妃を演じた。運命を引き受けているただ一人の女性で、このエリザベートはオペラのエリザベッタより性格に矛盾がない。カルロスを愛するのは彼が「最も弱い存在」だからで、オペラでエボリを断罪する場面でも、この王妃はまったく動じず「あなたもカルロスを愛していたのね」と慈愛の微笑みを浮かべる。
このプロジェクト自体が、ドイツのどこかの大劇場の近くの、オフ・ブロードウェイ的な場所で演じられるべきだと思った。ロックのライブのようでもあり、演劇の次元から突如マイクを持ち出して、歌い出すように台詞を語り出す。全員がそれをやる。アンダーグラウンド感覚が濃密で、ベルリンの壁を思わせる舞台の壁面に、カルロスもロドリーゴもエリザベートも、グラフィティアートのようなメッセージの単語をペンキで描く。
エーボリ公女を演じた七味まゆ味さんはご自身で劇団を主宰されている女優さんだが、この夜のブチ切れたエーボリは衝撃的だった。登場のシーンではヨガのポーズを取り(エリザベートも一緒にヨガをする)、カルロス誘惑のシーンでは蛸のような海の魔物となり、殴られ、倒れ込み、大声で叫ぶ…舞台は生き物だから、私が見た日は特に凄かったのかも知れない。目から黒い涙を流して演じていたという印象が残った。
17歳の北川さんがこの膨大な台詞を、苛酷な芝居とともに完走してみせたことは奇跡だ。そして深作さんが一筋縄ではいかないのは、全員から生身の人間としての、最も痛くて寂しい心を引き出してみせたことだ。一握の砂の中に、砂金や砂鉄があるように、すべての人間の深いところに同じ感情がある。不安、闇、愛されなかったという傷。ドン・カルロスもフェリペもエーボリも、全員現代人と同じ苦しみを抱えている。とどのつまりは「寂しくて、生きるのが苦しくて、もう限界だ」ということなのだ。
演劇の魔法の瞬間が惜しみなく繰り広げられる中で「深作さんはいつこの物語を諦めるのだろう」と目を凝らしていた。緞帳もなく、暗転も使わない。現代劇と歴史劇を思い切り奔放にミックスしている。それが回収不可能な瞬間があるのではないかと思った。演劇のプロはそんなヤワなものではなかった。凄い。最後まで白い十字架が舞台で事の成り行きを見守っていた。フェリペがロドリーゴに対して「私の初恋の男だった」と語る台詞は、シラーの原作にあっただろうか? 愛の飢餓感という主題は、容赦なく全体を貫く。
新国の「マイスタージンガー」を見たばかりだったので、「深作さんにも将来マイスタージンガーを演出して欲しいなぁ」とほのぼのとしたこと(?)を考えていたのだが、途中から「オペラがどうの」ということは、どうでもよくなった。この演劇で、深作さんの才能の巨大さを重ねて思った。オペラの世界は、あまりに狭量な聴衆が多い。深作さん演出の「ローエングリン」は最高だったではないか。私は大絶賛したが…中には酷いことを言う人もいた。オペラの演出に対する上から目線の論調は、あまりに閉鎖的だ。不自由すぎる。
「お前の死を犬死にしてやる!」とロドリーゴの亡骸に呪詛の言葉をかけるフェリペを、神農直隆さんが演じた。フェリペの重々しい存在感とナイーヴな内面は、最後は権力者としての残忍さに集約されていく。この心の成り行きは、現在の世界でも起こっていると思った。狂気じみた残忍さは、愛の欠落から成り立っている。ゆえに愛より強靭なのだ。
心の闇と向き合って、それを浄化したり問いかけたりする舞台は、役者たちにとっても過酷で、なおかつかけがえのない時間だったろう。千秋楽の前日で、役も成熟してきた時期だったはず。ドン。カルロスの時間から抜けて現実に戻ることは寂しいだろうし、日常でこれほど貴重な「自分自身の深淵」と向き合うこともないだろう。舞台は狂気を孕んでいるが、同時に癒しでもある。全員が綺麗な心をもっているドリーム・チームだった。
俳優たちの「自由!」 というシュプレヒコールが響いたこの舞台を見て、演出家の創造性にリミットを設けない演劇は、自由をどこまでも受け入れるジャンルだと実感した。オペラは、すべてがこんなふうに自由ではない。役者たちをとことん信頼し、自由にする深作さんの天才に驚愕し、少し心を落ち着けて、やはり深作さんの演出する「マイスタージンガー」も観たいと強く思った。オペラに必要なのは、この『ドン・カルロス』のような切っ先鋭い「自由」なのだ。