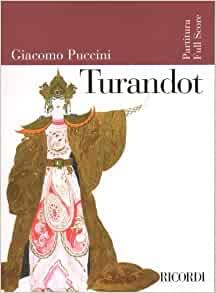プッチーニのオペラ『エドガール』(セミ・ステージ形式)をオーチャードホールで観る。二期会と指揮者のアンドレア・バッティストーニは、ヴェルディ『ナブッコ』以来共演を重ねているが、ヴェルディはバッティストーニと東フィル、プッチーニはルスティオーニと都響、という暗黙のローテーション(?)が、前回の『蝶々夫人』から変わってきていて、ヴェルディ担当(!)だったバッティストーニも、プッチーニを続けて振っている。2012年頃、バッティストーニに「本当はどっちの作曲家が好きなの?」と聞いたことがあり「プッチーニは昔から大好きで、ヴェルディは学びながら好きになってきている」という返事だった。今回の『エドガール』は指揮する姿から、心底プッチーニが好きなのだと実感した。
2008年にプッチーニのメモリアルイヤー(生誕150周年)を記念してリリースされたBOXでも、『エドガール』は音源だけではよく分からないところが多かった。出世作『マノン・レスコー』の4年前、30歳のときに完成している。フォンターナの台本はミュッセの詩劇をもとにしたもので、あらすじを読んでもわかりづらい。プッチーニは何度も改訂を繰り返し、3幕版が決定稿となったが、2008年にはトリノ王立歌劇場で初演4幕版がホセ・クーラ主演で初めて上演されている。イタリアでも上演機会が少ないので、日本ではバッティストーニとの縁がなければ聴くチャンスがなかったかも知れない。
始まってすぐ、先日の春祭のモランディ指揮・読響で聴いたばかりの『トゥーランドット』を思い出した。二つの作品の間には36年の開きがあるが、合唱とオーケストラの響きには既に『トゥーランドット』のすべての要素があり、音楽的には劣ったところがなかった。もしかしたら、プッチーニは遺作で先祖帰りをしたのかも知れない。『エドガール』は14世紀のフランドルが舞台で、既に異国の物語に素材を得ようとするプッチーニの姿勢が反映されている。ドニゼッティ=ヴェルディの流れを汲もうとする視点は一切なく、むしろ音楽の流れはビゼーを強く思い出させた。妖艶なメゾ・ソプラノが活躍するところなど、『カルメン』を意識しているのではないか。聖歌を思わせる荘厳な合唱から、突然エキゾティックなメゾの歌が始まる強烈さからも、『カルメン』を思い出さずにはいられなかった。『エドガール』の完成は1888年で、『カルメン』の初演が1875年。
誘惑に弱く、情動的に不安定な主人公エドガールを福井敬さんが演じた。酔いどれの役として登場するが、福井さんの誠実なオーラは隠しようもなく、それが表面的ではないエドガールの「魂」を表しているように感じられた。エドガールの清楚な恋人フィデーリアを髙橋絵理さんが演じ、プッチーニのライバルだったレオンカヴァッロの『道化師』で高橋さんが素晴らしいネッダを歌ったときから、10年が経っていることに気づき、光陰矢の如しと思った。どこまでも澄み切った美声で、全身から清らかな光を放っている。プッチーニは生涯、フィデーリアのような女性を理想としていたのではないか。一方で、実生活では清楚な小間使いの娘を自殺に追い込んだエルヴィーラを妻にしている。『エドガール』では、ムーア人の娘・ティグラーナが妖艶な悪女として登場し、中島郁子さんが圧倒的な歌唱と演技で魅了してきた。とても強い女性の役で、ティグラーナの音楽には平和を乱すような性格が感じられた。
東フィルはバッティストーニの歌心とプッチーニへの愛を汲み取り、粘り強くハイセンスな熱演を繰り広げた。エドガールは愛の矛先がコロコロ変わり、兵役に出て戦死したかと思うと実は生きていたりして、台本から一つらなりのドラマを感じようとするのは難しいところが多かったが、未完成なドラマの内側で、作曲家のマグマのようなパッションは猛威を揮っていた。バッティストーニも作曲家だから、プッチーニのフラストレーションがよくわかるのだ。『エドガール』の初演は、スカラ座で三回で打ち切りになった。以後プッチーニが台本のクオリティにこだわり、結果的に極端な寡作になってしまったのはこのオペラが原因だと推測する。『マノン・レスコー』はすべてがうまくいった。台本が良かったからだ(それでも極端な場面転換は多い)。
二期会合唱団とTOKYO FM合唱団が素晴らしかった。プッチーニは合唱に多くを語らせ、彼の家系が18世紀から続く宗教音楽家の一族であることを思い出させた。オルガンも効果的に使われ、見事なミサ曲に聴こえるくだりが多くあった。連綿と続く家系のDNAの突然変異として、ただ一人のオペラ作曲家となったプッチーニには、血族の宿命のままに宗教音楽の作曲家になる道もあったのだ。イタリアのカトリック権力に対する疑念は、『エドガール』での少年合唱団と同じ装束の合唱隊が登場する『トスカ』ではっきりと描かれている。
福井さんをはじめ歌手たちには、もしかしたらこの先上演機会がないかも知れない『エドガール』という作品への責任感もあったかも知れない。ティグラーナを愛するフランク役の清水勇麿さん、フィデーリアの父グァルティエーロ役の北川辰彦さんも真摯な歌唱と演技で舞台を特別なものにしていた。バッティストーニは貴重な「大使」であり、東フィルは見事な友情で応えた。物語のカタルシスは、リニアな時間軸の先にあるものではなく、あらゆる瞬間に、唐突に何度も訪れた。
演出面では、少年合唱がエドガールの(空の)棺にウクライナ国旗色の旗を掲げる場面があり、その「祈り」の部分はスライド映像とともに現在の世界の異様な状況を反映していた。歌手たちが演技をする空間には余裕があり、オーケストラはだいぶ後ろに引っ込んでいたように見えた。段差がなくオケは後方に退いているので、音響のバランスを取るのに試行錯誤したのではないか。
プッチーニに駄作なし…と強く思う。コンチェルタンテ形式での上演は冒険的な試みであり、貴重な時間を経験した。作曲家の宗教的な魂が、オペラという「毒」に飛び込んでいく、変身の瞬間の奇跡が詰め込まれていた。

1幕の冒頭の歌詞に現れる「アーモンドの木」
2008年にプッチーニのメモリアルイヤー(生誕150周年)を記念してリリースされたBOXでも、『エドガール』は音源だけではよく分からないところが多かった。出世作『マノン・レスコー』の4年前、30歳のときに完成している。フォンターナの台本はミュッセの詩劇をもとにしたもので、あらすじを読んでもわかりづらい。プッチーニは何度も改訂を繰り返し、3幕版が決定稿となったが、2008年にはトリノ王立歌劇場で初演4幕版がホセ・クーラ主演で初めて上演されている。イタリアでも上演機会が少ないので、日本ではバッティストーニとの縁がなければ聴くチャンスがなかったかも知れない。
始まってすぐ、先日の春祭のモランディ指揮・読響で聴いたばかりの『トゥーランドット』を思い出した。二つの作品の間には36年の開きがあるが、合唱とオーケストラの響きには既に『トゥーランドット』のすべての要素があり、音楽的には劣ったところがなかった。もしかしたら、プッチーニは遺作で先祖帰りをしたのかも知れない。『エドガール』は14世紀のフランドルが舞台で、既に異国の物語に素材を得ようとするプッチーニの姿勢が反映されている。ドニゼッティ=ヴェルディの流れを汲もうとする視点は一切なく、むしろ音楽の流れはビゼーを強く思い出させた。妖艶なメゾ・ソプラノが活躍するところなど、『カルメン』を意識しているのではないか。聖歌を思わせる荘厳な合唱から、突然エキゾティックなメゾの歌が始まる強烈さからも、『カルメン』を思い出さずにはいられなかった。『エドガール』の完成は1888年で、『カルメン』の初演が1875年。
誘惑に弱く、情動的に不安定な主人公エドガールを福井敬さんが演じた。酔いどれの役として登場するが、福井さんの誠実なオーラは隠しようもなく、それが表面的ではないエドガールの「魂」を表しているように感じられた。エドガールの清楚な恋人フィデーリアを髙橋絵理さんが演じ、プッチーニのライバルだったレオンカヴァッロの『道化師』で高橋さんが素晴らしいネッダを歌ったときから、10年が経っていることに気づき、光陰矢の如しと思った。どこまでも澄み切った美声で、全身から清らかな光を放っている。プッチーニは生涯、フィデーリアのような女性を理想としていたのではないか。一方で、実生活では清楚な小間使いの娘を自殺に追い込んだエルヴィーラを妻にしている。『エドガール』では、ムーア人の娘・ティグラーナが妖艶な悪女として登場し、中島郁子さんが圧倒的な歌唱と演技で魅了してきた。とても強い女性の役で、ティグラーナの音楽には平和を乱すような性格が感じられた。
東フィルはバッティストーニの歌心とプッチーニへの愛を汲み取り、粘り強くハイセンスな熱演を繰り広げた。エドガールは愛の矛先がコロコロ変わり、兵役に出て戦死したかと思うと実は生きていたりして、台本から一つらなりのドラマを感じようとするのは難しいところが多かったが、未完成なドラマの内側で、作曲家のマグマのようなパッションは猛威を揮っていた。バッティストーニも作曲家だから、プッチーニのフラストレーションがよくわかるのだ。『エドガール』の初演は、スカラ座で三回で打ち切りになった。以後プッチーニが台本のクオリティにこだわり、結果的に極端な寡作になってしまったのはこのオペラが原因だと推測する。『マノン・レスコー』はすべてがうまくいった。台本が良かったからだ(それでも極端な場面転換は多い)。
二期会合唱団とTOKYO FM合唱団が素晴らしかった。プッチーニは合唱に多くを語らせ、彼の家系が18世紀から続く宗教音楽家の一族であることを思い出させた。オルガンも効果的に使われ、見事なミサ曲に聴こえるくだりが多くあった。連綿と続く家系のDNAの突然変異として、ただ一人のオペラ作曲家となったプッチーニには、血族の宿命のままに宗教音楽の作曲家になる道もあったのだ。イタリアのカトリック権力に対する疑念は、『エドガール』での少年合唱団と同じ装束の合唱隊が登場する『トスカ』ではっきりと描かれている。
福井さんをはじめ歌手たちには、もしかしたらこの先上演機会がないかも知れない『エドガール』という作品への責任感もあったかも知れない。ティグラーナを愛するフランク役の清水勇麿さん、フィデーリアの父グァルティエーロ役の北川辰彦さんも真摯な歌唱と演技で舞台を特別なものにしていた。バッティストーニは貴重な「大使」であり、東フィルは見事な友情で応えた。物語のカタルシスは、リニアな時間軸の先にあるものではなく、あらゆる瞬間に、唐突に何度も訪れた。
演出面では、少年合唱がエドガールの(空の)棺にウクライナ国旗色の旗を掲げる場面があり、その「祈り」の部分はスライド映像とともに現在の世界の異様な状況を反映していた。歌手たちが演技をする空間には余裕があり、オーケストラはだいぶ後ろに引っ込んでいたように見えた。段差がなくオケは後方に退いているので、音響のバランスを取るのに試行錯誤したのではないか。
プッチーニに駄作なし…と強く思う。コンチェルタンテ形式での上演は冒険的な試みであり、貴重な時間を経験した。作曲家の宗教的な魂が、オペラという「毒」に飛び込んでいく、変身の瞬間の奇跡が詰め込まれていた。

1幕の冒頭の歌詞に現れる「アーモンドの木」