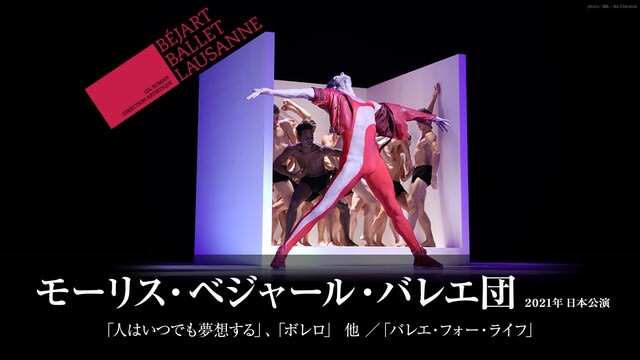日本フィル定期の二日目。開演と同時にラザレフ一人がにこやかに登場したので、舞台で何かを語り出すのかと思ったら、その後に楽員さんたち全員が続いて出て来られた。「指揮者は一番最初に舞台に出て、演奏会の主役たるプレイヤーを待つ。音楽が終わっても最後ま舞台にいて楽員を見送る」という愛に溢れた演出だと思い込んでいたが、コロナ感染予防対策だったのかも知れない。どのみちあの演出は、とても胸に沁みた。「みなさん舞台に出てきてください…わたしのために」とマエストロが語り掛けているようで…しかしリハーサルはいつもの鬼軍曹ぶりが健在だったに違いない。
ラザレフが振る日本フィルはいつも最高。この日はキュー出しも細かく、一人もらさず全員に指示を出していたように見えた。リムスキー=コルサコフ『歌劇《金鶏》組曲』は、この季節にぴったりの印象の曲だ。急に冷え込んだここ数日、秋を通り越して初冬の気配を感じていた。ロシアの人々は長い冬を劇場で楽しむ。子供も大人も劇場に詰め寄せ、赤い緞帳が開き、火の鳥や女奴隷や人形やスワンが踊り出す。『金鶏』もプーシキンが台本化したロシアの昔話・民話詩だ。リムスキー=コルサコフの純朴な童心が、オーケストラから溢れ出した。ランプから登場する巨人がナレーターを務めるような不可思議な物語の世界で、カラフルな音の絵巻が展開される。管弦楽版の組曲はバレエ音楽として構想されていたという説もあり、大変躍動的。リムスキー=コルサコフは貴族出身だったが、オペラの『金鶏』は反体制的の烙印を押され、初演は作曲家の死後に先送りされた。
管楽器のエキゾティックな節回し、弦の幻想的な響き、映画音楽を先取りしたドラマティックな大衆性が耳に快い。ラザレフはいつものように客席をしみじみと振り返りながら指揮をするが、まるで満開の桜か秋の紅葉を見るような表情でこちらを見る。あの仕草を観たくて演奏会に来るお客さんも少なくないという。
似たようなフレーズも、二度と同じ繰り返しはない。一度目は宗教的に、二度目はファンタジーのように、三度目はユーモアを交えて…たくさんの楽器が、マエストロの髪の毛の動きまでを音楽に変えていた。ロシアの魂みたいなものを感じたが、ラザレフ以外の指揮でこの感じを味わうことは難しいだろう。
『金鶏』だけでかなりのボリューム感だったが、すぐにピアノが舞台中央に移動し、リムスキー=コルサコフの『ピアノ協奏曲 嬰ハ短調op.30』が始まった。福間洸太郎さんが流麗なソロを披露。ピアノがかつて「洋琴」と呼ばれていたことを思い出した。一呼吸で継ぎ目のない長いフレーズを弾き切り、鍵盤から七色の色彩が溢れ出す。ソロは華麗で超絶技巧的だが、芯にあるものがひどく無垢で無欲な感じがする。福間さんの清潔感のあるタッチのせいもあるのだろう。メロディアスで優しく、作曲家の心の温かさを感じた。オクターヴの連打には強靭さを求められるが、演奏が洗練されているせいか、まったくごつごつした感じはなかった。音楽史的に何かやってやろうという、作曲家の野心のようなものは感じられない。ピアノの上を泳ぐ指は魔法のようで、15分間があっという間。空に浮かんだ虹を見るような心地で、もう一度まったく同じ曲を聴きたいという渇望感に駆られた。
曲が終わるか終わらぬかといううちに、ラザレフはくるりと向きなおって福間さんに拍手喝采を送り、曲が「成就した」ことに感謝した。そのあとの福間さんのアンコール(グリンカ「ひばり」バラキレフ編)が続いたが、指揮台に乗ったままのラザレフは、泣いているように見えた。後姿がそう見えた。
ラザレフは本当に日本フィルを家族だと思っているのだ。改めてそのことを嬉しく感じ、格別の真剣さでマエストロの愛情に応えているオーケストラを誇らしく思った。この数日、暖炉の前で家族に語り掛けるようなカヴァコスのブラームスに感動し、都響と本物の家族になった大野さんのR・シュトラウスに涙し、このラザレフの演奏会を迎えた。コンサートはますます祝祭となり、音楽家たちの愛の表現の場となっている。ラザレフの愛は毎回すごいが、今回は倍増しだった。
後半のショスタコーヴィチ『交響曲第10番』は、四方八方から壁が押し寄せてくるような密閉的な表現で、この曲の不気味さが骨身に沁みた。この数日間、体調も精神状態もぎりぎりで、肥大した心臓が身体から飛び出して死ぬ夢を見た。そのような状態だったので、ショスタコーヴィチは大変辛かったが、最後まで聴いた。この曲は本当に奇妙だ。こんこんと湧き出してくるものが、えんえんと「狂気」と「正気」のパラレルなのだ。囚人への拷問のひとつに、水を右から左の桶へ移し替えるだけの無意味な繰り返しがあるという。ショスタコーヴィチは、人の気がふれるようなことを左手でやりながら、右手では平然と正気を保っている。出口はない。閉所の表現。ラザレフはそこにも愛を込める。ショスタコーヴィチが伝えて来るメッセージは強烈だった。首根っこをつかまれて「自己憐憫など、意味はないぞ!」と言われたような気がした。
ショスタコーヴィチは超人で、これほど憔悴させる曲を、ユーモアで書いた。プロコフィエフは悲観から書いたが、ショスタコーヴィチは楽観から書いたのだ。根っこにあるのは紛れもない哄笑だ。最後の終わり方に、「本当のこと」が隠されているように思えた。