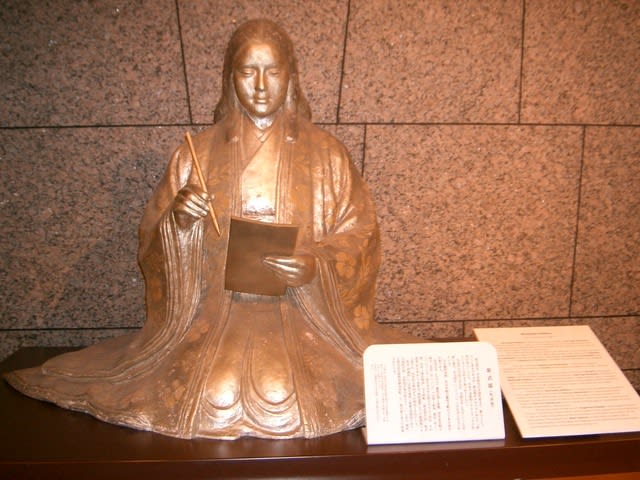梅雨に入って、いよいよ蒸し暑くなってきました。
早朝、FIFAワールドカップで、日本は勝ちました。
アウェイでは、はじめて。
眠いけれど、やはり日本人として嬉しいですね\(^o^)/
さて、梅雨といえば源氏物語ではやはり雨夜の品定め!
長雨の徒然に光源氏と男達のよもやま話が語られ、
その後、空蝉、夕顔への導入話となっています。
もしかしたら、藤壺との密会もこの頃だったりするのかもしれません(笑)
さて、
源氏物語featuring 大黒摩季「僕は十二単に恋をする」というミュージカルがこの秋、
東京天王洲の銀河劇場であるそうです。
http://www.gingeki.jp/performance/index.php?date=201010
出演者の中に
元宝塚トップスターの紫吹淳さんの名前があるので、
光源氏は彼女かもしれないし、
全く違う内容のミュージカルかもしれませんが、ご紹介まで。
そして本屋さんで、林望さんの源氏物語訳があるのを発見。
林真理子さんも出ています。
他にも古本屋さんに、
有名な武田宗俊さんのご本を見かけました。
いわゆる紫系と玉鬘系説の方です。
登場人物が光源氏を除き、両系列では
絶対にかぶらないという所が本当に不思議だと思います。
また、奈良にあるという写本大沢本や
他の写本の話を聞く機会があり、
果たして今普及している源氏物語の本文が
必ずしも正しいとも限らないという説にも納得しそうです。
現代の元になっている定家の青表紙本は本当に正しかったのか。
文面が写本によって違うという事。昔の研究書も違いがあるようです。
印刷が無かった時代、筆で写すのは間違いも多かったでしょう。
定家の鎌倉時代でさえ、様々な写本が伝わっているのですから、
本当の原文を推定していく事は、大変な作業ですね。

早朝、FIFAワールドカップで、日本は勝ちました。
アウェイでは、はじめて。
眠いけれど、やはり日本人として嬉しいですね\(^o^)/
さて、梅雨といえば源氏物語ではやはり雨夜の品定め!
長雨の徒然に光源氏と男達のよもやま話が語られ、
その後、空蝉、夕顔への導入話となっています。
もしかしたら、藤壺との密会もこの頃だったりするのかもしれません(笑)
さて、
源氏物語featuring 大黒摩季「僕は十二単に恋をする」というミュージカルがこの秋、
東京天王洲の銀河劇場であるそうです。
http://www.gingeki.jp/performance/index.php?date=201010
出演者の中に
元宝塚トップスターの紫吹淳さんの名前があるので、
光源氏は彼女かもしれないし、
全く違う内容のミュージカルかもしれませんが、ご紹介まで。
そして本屋さんで、林望さんの源氏物語訳があるのを発見。
林真理子さんも出ています。
他にも古本屋さんに、
有名な武田宗俊さんのご本を見かけました。
いわゆる紫系と玉鬘系説の方です。
登場人物が光源氏を除き、両系列では
絶対にかぶらないという所が本当に不思議だと思います。
また、奈良にあるという写本大沢本や
他の写本の話を聞く機会があり、
果たして今普及している源氏物語の本文が
必ずしも正しいとも限らないという説にも納得しそうです。
現代の元になっている定家の青表紙本は本当に正しかったのか。
文面が写本によって違うという事。昔の研究書も違いがあるようです。
印刷が無かった時代、筆で写すのは間違いも多かったでしょう。
定家の鎌倉時代でさえ、様々な写本が伝わっているのですから、
本当の原文を推定していく事は、大変な作業ですね。