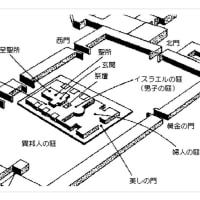おはようございます。パスターまことの聖書通読一日一章です。継続は力なり。聖書を日々手に取り、心の糧とするなら、自然に養われてくるものがあるものです。今日もぜひ聖書を開きながら読んでください。今日はマタイの福音書5章からです。
1.七福の教え
ガリラヤ湖の西岸、エ・タフガには、八角堂の「垂訓の教会」が建立されています。そこでイエスは、山上の説教(5-7章)を語ったと言われますが、マタイがここに記録した内容は、種々様々な機会に語られたものを一つにまとめたものと考えられています。繰り返される「幸いです」にちなんで、「七福の教え」と呼ばれて親しまれていますが、基本的に、4章の後半の続きで、イエスの弟子であることの意味を語っています。
文語訳では、「さいわいなるかな」と感嘆の響きのある訳になっており、その方がイエスの意図を忠実に再現しています。つまりイエスは、幸いになる方法や秘訣を語っているわけではなく、幸いな事実を指摘しているのです。荒野の誘惑の記録からもわかるように、イエスにとって神は現実の存在です。ですから、神以外に助けを求められない貧しさに卑屈になる必要はありません。助けはあるのです(3節)。嘆き悲しむ者も放っておかれることもありません(4節)、自分の分を弁え、神の公平なさばきに物事を委ねる者は、神が味方であることを知るでしょう(5節)。神の正義は求めるに値します(6節)。さて7節以降の後半は、より積極的な態度について語っています。あわれみ深く人に関わるなら、そのあわれみが帰ってきます(7節)、偽りのない透き通った心で人生を歩む者は、神を見るでしょう(8節)、平和を作り出そうとする者は、まさに神の子そのものです(9節)。そして10節、神のみこころに従って生きようとする人に戦いはつきもの、やり込められたとしてもそれで終わることはありません。神は生きておられるのです、12節「喜びなさい」と結ぶのです。
2.律法学者とパリサイ人に優る義
13節以降のポイントは20節、つまり、律法学者とパリサイ人に優る義にあります。それはまず、塩や(13節)、光のようなものだと言います(14-16節)。そして彼らが追及する律法、つまり神の教えを完全に全うするものだ、と言います(17-19節)。塩は、腐敗を防ぎ、光は闇を照らします。つまり、律法が律法として機能するのです。当時、パリサイ人にしても、律法学者にしても、彼らは聖書の研究に熱心でしたが、彼らの実践は上辺だけのことでした。しかしあなた方の義は、裏表のない、有言実行のまことの義、だから知の塩、世の光となって人々に影響を与えるのだ、と言うわけです。
ところで、律法学者は教育訓練を受けた律法の教師、パリサイ人は一般に指導者を除けば、敬虔な信徒集団のことを言いました。ですから大まかに、この後の5章は律法学者、6章はパリサイ人、そして7章はイエスの弟子たちの義を順に語っていくことになります。そこで5章の後半には「あなたがたは、律法学者にはこう教えられているだろうが、私の教えはこうである」と言うような特徴的な言い回しが出てくるのです。たとえば21節、「殺してはならない」と言う教えは、人を殺すという結果だけではなく、殺意そのものから問われなければならない、深く掘り下げて心を問う、それが私の教えだというわけです。外見ではなく、心を美しく磨く人生を求めたいものです。では今日もよき一日となるように祈ります。