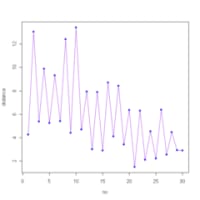・エゾマツの事業用種子のストックがいよいよ少なくなったので、将来的なエゾマツの採種園造成に向けて、採種園を構成する精英樹(?)候補木を選抜することになった。天然林からの選抜は、現実的になかなか難しい(接ぎ穂を取るのが困難、老齢なために活着が悪い)ということで、思い切って、造林係が調査している6つの古い造林地の中から候補木を選ぶことになった。

・古い造林地を選んだのには他にも理由があり、天然林ではあまりにも環境や年齢が不ぞろいなので、選抜した個体が本当に遺伝的に良質なのかどうか分かりにくいのだが、造林地ならば少なくとも年齢が一緒(しかも環境も類似)なので、成長の良い個体は遺伝的にも優れている可能性が高い(あくまで確率の問題だけど・・・)というわけ。さらに言えば、既に、富良野に植えられて数十年は経過していることから、一種の自然選択を受けた結果だとも考えられる。したがって、その次代も成林する確率は高い確率が高かろうと考えたわけである。


・今日は、関係者とともに何はともあれ現地を確認しようということに相成った。要領を確認しつつ、一次選抜と称して、ピンクテープを巻いていく。選抜の基準は、他と比べて成長が良いことと、通直性が特に高いこと、また、ヤニや傷などの欠点がないこと、である。考えてみると、育種を専門にしていながら、最も重要なステップである”選抜”という作業をまともにやったことがなかった(実に新鮮だった!)。最初は戸惑いながらの作業だったが、よく考えてみれば、当方の技術スタッフにとっては、日ごろの業務は一種の選抜作業である。一度、目が合ってくれば作業はとんとん進む。


・68林班の造林地では、モモンガの食痕があった。どうやらエゾマツの若枝をもぎり、その芽を”がじがじ”と食っているらしい。巣はどこにあるのかが分からなかったが、芽は贅沢に頂芽だけを食っている。なかなかのグルメである。そういえば、西の沢ではマカバの枝にオジロワシがじっと留まっており、動物相の豊かさを実感させられた。
・結局、3林分で30個体強を選抜。少々、林分によって選抜強度が弱い(甘い基準?)ところもありそうだが、採穂するときにもう一度確認しながら選定することにする。全体の目標から言っても、最初は少し緩めに選び、検定をしながら徐々に絞り込んでいくのがよさそうだ。とはいっても、採穂、接木、採種園造成まで、まだまだ手探り状態が続きそうである。

・古い造林地を選んだのには他にも理由があり、天然林ではあまりにも環境や年齢が不ぞろいなので、選抜した個体が本当に遺伝的に良質なのかどうか分かりにくいのだが、造林地ならば少なくとも年齢が一緒(しかも環境も類似)なので、成長の良い個体は遺伝的にも優れている可能性が高い(あくまで確率の問題だけど・・・)というわけ。さらに言えば、既に、富良野に植えられて数十年は経過していることから、一種の自然選択を受けた結果だとも考えられる。したがって、その次代も成林する確率は高い確率が高かろうと考えたわけである。


・今日は、関係者とともに何はともあれ現地を確認しようということに相成った。要領を確認しつつ、一次選抜と称して、ピンクテープを巻いていく。選抜の基準は、他と比べて成長が良いことと、通直性が特に高いこと、また、ヤニや傷などの欠点がないこと、である。考えてみると、育種を専門にしていながら、最も重要なステップである”選抜”という作業をまともにやったことがなかった(実に新鮮だった!)。最初は戸惑いながらの作業だったが、よく考えてみれば、当方の技術スタッフにとっては、日ごろの業務は一種の選抜作業である。一度、目が合ってくれば作業はとんとん進む。


・68林班の造林地では、モモンガの食痕があった。どうやらエゾマツの若枝をもぎり、その芽を”がじがじ”と食っているらしい。巣はどこにあるのかが分からなかったが、芽は贅沢に頂芽だけを食っている。なかなかのグルメである。そういえば、西の沢ではマカバの枝にオジロワシがじっと留まっており、動物相の豊かさを実感させられた。
・結局、3林分で30個体強を選抜。少々、林分によって選抜強度が弱い(甘い基準?)ところもありそうだが、採穂するときにもう一度確認しながら選定することにする。全体の目標から言っても、最初は少し緩めに選び、検定をしながら徐々に絞り込んでいくのがよさそうだ。とはいっても、採穂、接木、採種園造成まで、まだまだ手探り状態が続きそうである。