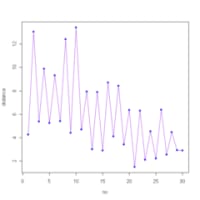・京都のSさんを迎えて久しぶりにカツラ論文について議論。改めて論文の売りについて考える。ジーンフロー系の論文は次から次へと出ているので、ちょっと前に考えたことが古くなっていたりする。これって、あまり健全とはいえない分野かもしれんなあ・・・。とは言うものの、結果と考察をもう一度見直しているうちに、何が結果なのかが改めて見えてきたようだ。
・Burczyk et al.(1996)(1996年のKnobcone pineのもの)を二人で読み直しながら、近隣モデルをSさんに説明する。自分にもいい復習になった。その後、カツラの散布モデルについて、久しぶりに鳴子のTくんと電話で議論。それにしても、花粉(あるいは種子)散布曲線というものは、点で考えるか一周させるかで違うので実は意外と簡単ではない。累積密度曲線がどうにも納得できなかったのだが、電話で話すうちに、事情(?)がようやく飲み込めてきた(今まで理解できていなかったことが発覚)。これをうまく活かすにはどうすればいいか、もう少し熟考すべき・・・。
・Mくんのエゾマツ造林原稿を郵送。コピーと回答書を3部ずつ送る。こうした作業は実は結構嫌いではなかったりするのだが、こうしたアナログ作業はいつまで残るのだろうか・・・。
・Burczyk et al.(1996)(1996年のKnobcone pineのもの)を二人で読み直しながら、近隣モデルをSさんに説明する。自分にもいい復習になった。その後、カツラの散布モデルについて、久しぶりに鳴子のTくんと電話で議論。それにしても、花粉(あるいは種子)散布曲線というものは、点で考えるか一周させるかで違うので実は意外と簡単ではない。累積密度曲線がどうにも納得できなかったのだが、電話で話すうちに、事情(?)がようやく飲み込めてきた(今まで理解できていなかったことが発覚)。これをうまく活かすにはどうすればいいか、もう少し熟考すべき・・・。
・Mくんのエゾマツ造林原稿を郵送。コピーと回答書を3部ずつ送る。こうした作業は実は結構嫌いではなかったりするのだが、こうしたアナログ作業はいつまで残るのだろうか・・・。